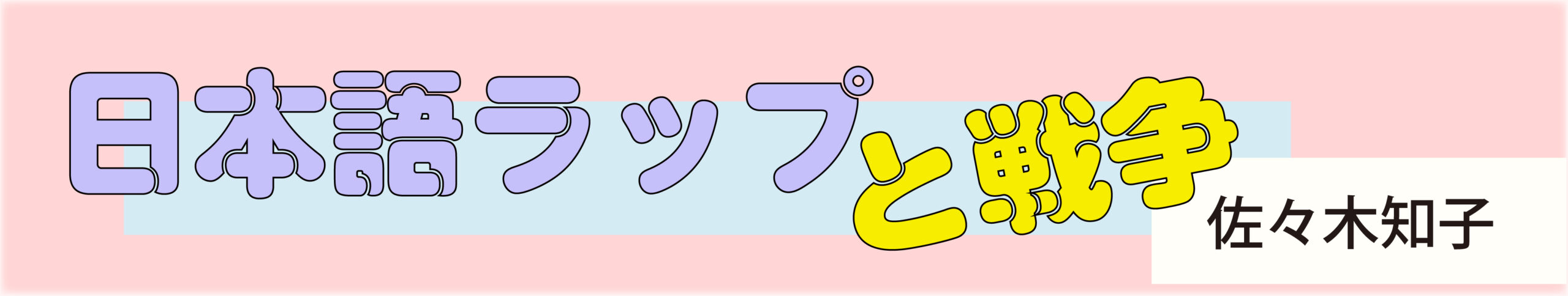Photo Tomoko Sasaki
1989年に結成されたヒップホップ・グループ「ライムスター」のMCとして活動を続ける宇多丸さんは、ラッパーとしてのキャリアに加えて、批評家、コラムニスト、ラジオパーソナリティとしても、多方面でヒップホップ1に関する発信を行ってきた。なかでも、長年にわたるラジオ番組2でのパーソナリティとしての活動を通じて、ラップシーンの実相やその文化的背景を、ヒップホップに馴染みのない世代や他ジャンルのファンに向けて明快な言葉で伝え、日本におけるラップ文化の定着に様々な影響を与えている。
宇多丸さんにお話を聞きたいと思ったきっかけは、以前、彼がラジオ番組で「戦争について話すことをためらう空気」に疑問を呈していたのを耳にしたことだった。彼は、自身の両親も戦争経験世代であることに触れつつ、戦争の直接体験者が亡くなっていく現在、そうした人々を知る世代の自分には、その記憶を継ぐ責任があるように思うと語っていた。また、「過去から目を背ける者 は、 過去から足を引っ張られ続ける」という言葉からは、過去として戦争を切り離すのではなく、いま現在と地続きの問題として捉えるべきだという問題意識が伝わってきた。
そうした姿勢は、これまで手がけてきた楽曲にも表れている。時代ごとに社会が直面した重大な出来事から、ライムスターは戦争をテーマとした作品も発表してきた。これらの制作を通じて、宇多丸さんは繰り返し、戦争や暴力の問題に対峙してきた。
ラップという表現で、戦争をどのように語ることができるのだろうか。その際、ライム(韻)、フロウ(流れ)、レペゼンなど、ラップ特有の表現技法はどのような効果をもたらすのか。 ラップやラジオといった複数のメディアを通じて、社会の矛盾や暴力の構造について発信してきただけでなく、ラップの技術やメディアとしての特性そのものについても言葉にしてきた宇多丸さんにお話を伺った。
イラク戦争と対テロ戦、ウクライナ侵攻ーーラップで表現した「戦争」
ライムスターがこれまでに発表してきた楽曲「911エブリデイ」(2003)と「いのちのねだん」DJ HAZIME feat. RHYMESTER(2004)ではイラク戦争や対テロ戦争を、「Open The Window」(2023)ではウクライナ侵攻をそれぞれ主題として扱っている。こうした楽曲が制作されるに至った背景には、どのような動機やきっかけがあったのだろう。
宇多丸:アルバムって文字通り、その時期の自分たちの気分や、思っていることのパッケージなんです。作っている時に「ないこと」にしづらいほどの大きな出来事、例えば戦争や紛争があって、自分の言葉として何か言う。それがヒップホップカルチャーとしてのラップなので、こういうトピックには触れざるを得ない。触れざるを得ないけれど、どれをどう触れるのか、それは考えあぐねるというか、非常に悩むところです。例えばイラク戦争とか、同時多発テロとか、今振り返るとまた別の見方もあると思いますが、あの時は「これから世界はどうなってしまうのか」「これを節目に、もう取り返しのつかない泥沼に行くんじゃないか」そんな予感がありました。
メンバー間で話し合う中でも、そして自分の中でも、やっぱり触れないわけにいかない。そう言うと後ろ向きな感じがしますけど。できれば本当は面白おかしいことばかり歌ってたいじゃないですか。でもやっぱり、個別の曲なりの作るモチベーションはあるんです。
例えば「911エブリデイ」だったら、同時多発テロはもちろん大変なことで、騒ぎになっているけど、暴力によって人が死んだりしている事態って、今突然に起きたことじゃないのにっていう違和感があったことだとか。メディアを通して我々が知るか、知らないかにも、例えば欧米なのかそうじゃないかといった差があることを感じたんです。そういう構造そのものを歌い、単なる反戦歌というよりも、戦争というものを我々がどう捉えているのかとか。そういう視点を入れたかったのだと思います。
説明ではなく、曲にすること
宇多丸:「いのちのねだん」はDJ HAZIMEさんという僕らの盟友からトラックをもらって依頼された曲です。最初のリリックは全然全然違う内容だったんです。でもHAZIMEちゃんから、こういうんじゃない、それこそ「911」みたいにストレートに言ってほしいと言われて書き直しました。なので、あれはHAZIMEちゃんのプロデュースあってこそと言えるかもしれない。そのサジェスチョンをしてもらったおかげで、自分たちだけでは破れなかった殻を破れたかもしれない。当時も今も、硬質な、ある種の「正しい」メッセージを表現に落とし込むことに僕自身惑いがあります。そのままを言うなら、そのまま語りかけた方が良くない?という。特に僕にはラジオという場があるので、ラジオで話した方が早いと思ってしまうところがある。だから「わざわざ曲にする意味ってなんだろう」とワンクッション入るんです。それが俺たちの腰が重いところというか。もちろんクオリティコントロールの意味もあるけれど、その腰の重さに対してケツを叩いてくれた曲なのかもしれません。
これはもちろん戦争のことを歌っているんだけど、僕のヴァースで重要なのは「この国がどっちに向かっているのか」という点だと思っています。死を、戦争を、世を憂いて語る人は、なんで君は為政者の側の視点で偉そうにしているんだと。俺たちは殺される側なんだよって。殺して殺される側なんだよっていう、その一人の人間じゃないかって。それを思い出せっていうようなことです。
でもそのメッセージだけを出すってよりはやっぱり、何らかの情緒的表現の中で言うってことが、歌という表現には大切なのだと思います。
「戦争」だけでなく、「しょうがない」に抗う
宇多丸:「Open The Window」は本当にもう、これぞ苦労しました。制作のきっかけはウクライナに対する侵略ですけど、そうこうするうちにパレスチナの事態が起こって。侵略とかそういう事態だけでなく、「#MeToo」のように、「今までしょうがないね」って言ってたことと、暴力的に「こういうもんだから」って言ってきたものとの戦い––戦いっていう言葉は使いたくないけど、今、問われていることを、なんとか曲にしたいと思ったんです。でもそれをコンパクトに音楽的な表現に落とし込むのはなかなか簡単にできなくて。とってもとっても時間がかかってしまいました。そしてこの曲をやる際のMCが「ちょっと説教くさいんじゃないかな」、「そんなこと聞きにきたわけじゃないのかな」とか思いつつ、それでも100人中、うざいと思う人が95人でも、5人が「うん」と思ってくれれば、その5人に伝われば……いやそれも問題か、とか色々やはり思うわけです。それでもやはり「ないことにもできない」。でも一緒に作ったJQ君(Nulbarich)とかは若い世代ですけど、そういう覚悟の部分を「すごくいいと思います」ってわかってくれた上でアレンジをものすごくエモーショナルにして返してくれたり。時間はかかっちゃいましたけど、最終的には然るべきものができたって思います。
ラップの表現形式と効果―ライム、フロウ、ビートが織りなす快楽
宇多丸さんは、ライムスター結成当初から音楽ライターとしても活動し、ヒップホップ文化の紹介に取り組んできた。ラッパーとしての実践と幅広い知識を併せ持つ宇多丸さんに、ラップという 表現の特徴と、その形式で戦争を語ることの特性について尋ねた。
宇多丸:一番簡単な答えを言えば、パブリック・エネミー3のチャックDが「ラップは黒人のCNNだ」って言ったような意味じゃないかと思います。本を読んだり、報道に触れる習慣がない人にも届くというのが、当時は大きかったと思う。あるいはECDが「そのままの言葉で語るよりも音楽なら聴いてもらえる」と言っていたことであるとか。あと詩的表現に一旦落とし込むことで、堅い部分が和らいで聴きやすくなったりということもありますよね。そして韻を踏むことで元の言葉とは「別のイメージ」が広がるというのは、ラップだからこその点かもしれません。韻を踏むために別の言葉を出してきたら、元の言葉との落差が面白いものになる。それは時に作者も意図してなかったところにまでイメージが広がっていくこともあります。
「911エブリデイ」では、Mummy-Dが「超えろ俺らのイマジネーション」とラップするように、私たちはテレビの向こう側にある戦争という現実に、徐々に想像を通じて近づいていく。しかし楽曲の最後で宇多丸さんが、「どこか遠い国で起こった大惨事 TVで眺めてる幸せな午後三時」と韻を踏むことで、再びその距離が強調される。ここには、私たちが一時的に感情移入し高揚することはあっても、それを持続することが難しいという構造が示されている。
宇多丸:まさに「どこか遠い国で起こった大惨事 TVで眺めてる幸せな午後三時」は、やっぱり韻で思いついた箇所です。「大惨事」に対して「午後三時」っておやつとか、穏やかな時間帯という印象ですよね。この一行が先に浮かんで、これはいつか使おうと。その時は、どういうタイミングで発表するかアイデアはなかったんです。でもその後に「911エブリデイ」で、確か僕が最初の8小節を書いたと思うけれど、あのイメージはこの韻が導き出したものです。最後にもう一回あの「どこか遠い国で起こった大惨事 TVで眺めてる幸せな午後三時」を置くことで、もう一度自分たちの現実に戻る。テレビを消した後の部屋のイメージで「さあ、どうする?」と問いかける感じにできるなと。
韻を踏むことには、イメージを飛躍させると同時に、リズムを生み出すという特性がある。それは、メッセージの伝達においてどのような効果を持つのだろうか。
宇多丸:ラップは「フロウ」と言うように、音に言葉を乗せて流していく。特にヒップホップはビートがあってグリッドが割とバシッとあって、つまり型があって、そこの上をすり抜けていったり、踊っていったり、曲芸をしてみせたりする、そういうイメージだと思います。その上でライミングという、近しい言葉の響きが繰り出される。同じような言葉の響きなのに、「おっとそうきたか」と思わせられる。その「おっとそうきたか」の瞬間にやっぱみんな「おぉ!」となる。繰り返しの中にあるジャンプのようなものが印象を強めるんです。だいたい4小節単位で展開していくとして、4小節目とか8小節目とか16小節目の最後に一番印象的な決めのラインが来ると。それがいわゆるパンチラインになるわけです。フリースタイルの後でみんなが歓声を上げるのなんかはそれですよね。音楽的でありながら、意味も読み取りながらのリアルタイムで、うまいことを言うスキルが物を言うわけですから。音楽という心地よく感じてしまうものに言葉を乗せることで、意表をつくパンチ、思わぬ角度からの効果的なパンチみたいなのが来ると、硬質なメッセージでも「はい、お説教ね」ではなく「おーそうきてこうきて、おーなるほどなるほど!」って耳に届く。メッセージを伝える力というのは、そういうところにもあると思います。
もちろん、今僕はとてもうまくいった場合の話をしていますが。でもラップを使って何か、例えば特定のメッセージを伝えたいと思っている人は、この効果を誰もが目指している。効果がより大きくなるように考えていると思います。
ラップの表現形式と効果―固有名詞がひらく歴史性
ラップの形式や内容には、どこか「決まりきった枠」に収まらない自由さがある。メロディの流れや曲の構成にとらわれず、語りたいことを言葉として詰め込んでいくことができる。その自由さは、何かを語るときにどのような広がりをもたらしているのだろうか。
宇多丸:ラップは言葉の数、つまり情報量が多いということもありますよね。一般的な歌のようにAメロBメロみたいな構造からも比較的自由で、1番と2番が全然違ってもいいし、1番しかなくてもいい。要は詰め込み放題です。今はもちろん、以前よりは音楽全般が自由になっているとは思いますが、特に日本語のポップミュージックではこういうことは歌わないとされること、つまりメッセージ性の強い内容も、ラップとフォークと土着民謡なら歌えるみたいな。例えば年号を入れながら歌うみたいなこと、つまり時系列にして歴史を語るみたいなこともしやすい。
過去の出来事を歌っているにもかかわらず、それが今聴いたときに、なぜか生々しく響いてくることがある。ラップは“過去と現在”、“彼方”とここ“をつなげて、歴史を身近に立ち上げていく。
宇多丸:そういう点においてラップ特有のものといえば、「固有名詞の多さ」じゃないでしょうか。その固有名詞が情報を想起させる。情報量が多くて、韻という、音楽的かつ文学的な仕掛けがあって、さらに固有名詞が想起させる文脈がある。そこには「歴史の地層」があると思うんです。ヒップホップカルチャーにおいてサンプリングの存在感が薄れてきた、とは言われていますが、それでもフリースタイルなら過去の楽曲の引用をするし、それまでの文脈をどう踏まえるかが重要ですよね。それこそバトルだったら相手が前に言ったことを踏まえる、これも過去じゃないですか。その文脈をうまく使ってレイヤーにして、またそれを武器にするというのかな。R-指定(Creepy Nuts)なんかはその力がめちゃくちゃ高い。そういう意味においては時間とか歴史っていうのものは当然ラップには含まれるんじゃないかと思います。
要するにヒップホップって、もともと同じ町内のお兄ちゃんたちがやってたことですから。靴にしたって「スニーカー」じゃなくて、「俺のアディダス」「俺のナイキ」なわけで、どんどん固有名詞によって具体的になっていくんです。あるいは過去のポップカルチャーの引用とか。トニー・モンタナがどうこうって言えば『スカーフェイス4』っていう共通のイメージを思い浮かべるとか。日本においては、『はだしのゲン』って言えばもうそれだけで何の話してるかがわかるというような。「はだしのゲンのように」っていうと喚起するイメージが圧倒的になるわけです。
ラップには、自分がどこから来たのか、何を代表しているのかを表現する「レぺゼン=represent」と呼ばれる側面が見受けられる。その土地や文化、個人的な背景を言葉に刻むことで、語り手の立ち位置がより明確に示される。
宇多丸:固有名詞は、その人がどういう文化圏にいるかを示すものでもあって。僕よりも下の世代だったら『ジョジョ』や『ワンピース』の引用の方が「わかるわかる」と近しく感じさせるでしょうし。固有名詞があって、情景が具体的であるほどヒップホップぽいということが言えるんです。
戦争を語るのもヒップホップ
戦争という重いテーマも、日常の語りの延長線上で扱う。そこには、戦争を語ること自体を特別な行為にしないというスタンスがある。宇多丸さんは、ラジオやラップといったメディアを通して、普段通りのテンションのまま、戦争や社会の問題に言葉を向ける。くだらない冗談も、真面目な話も、どちらも生活の一部として語られる。
宇多丸:戦争のことをラジオで話す時に思っているのは、「こんなことは普通に話すもんだ」ということなんです。映画の話をしたりくだらない冗談を言うのと全く同列に、戦争とか紛争の話をするのは当たり前だっていう感じ。例えばラップにしても、それを語りたいからこの形式を選んでいるというよりは、今これは「語る方が当たり前」だという思いがあって。「そういう話はまあちょっと」みたいなのは、もうそんな態度は古いというか、それはあまりかっこよくないと思う。かっこよくないうえに面白くもない。その感じにみんなが慣れてくれたらという思いがあります。それはある意味、ヒップホップがそうだからなんですよね。めちゃくちゃかっこよくて、踊れて、ふざけたこともやってるし、色っぽいことも歌う。同じように真面目な話もするっていう。だって生活がそうなんだから。食べるし、ラップするし、でも戦争とかももちろん暮らしの中の一部だし、という。それに世代的な問題もあって、僕は親が直接戦争を経験している世代だから、そこまで人ごととも思っていないんです。むしろめちゃくちゃ身近なものだと思ってる。親からも、実際いかにロクなもんじゃなかったか、叩き込まれてきていますし、いつでもそうなりうるということを知っている。あの状態になったらおしまいだから、その状態になる前に食い止めなきゃいけない。当事者になってからではもう何もできないから。
戦後80年の現在と戦争の記憶
終戦から80年が経過しようとしている。かつては遠い出来事として語られていた戦争が、いまではむしろ、生活と地続きのものとして若い世代に受け止められている――そんな感覚を、宇多丸さんは自身の世代と、現在の若者たちとの違いのなかに感じ取っている。
宇多丸:僕は80年代の子供ですけれども、同世代の人たちも別に戦争に関心が高いわけじゃない。だから今の若者が戦争に関心が低いとか言われると、むしろ今の賢い子たちは、情報も多いし80年代よりもずっとしっかり考えている気がします。だからそんなに、戦争の記憶が風化しているかというと、まあそういう部分もあるのかもしれませんとしか。でも僕は、ラジオでご一緒しているパートナー陣とか、若いリスナーのメールとか、なんかしっかりしてるな、ちゃんとしてるなって思います。それは多分、僕が若い頃よりも「戦争になるかもしれない」という感覚がもっとリアルなんじゃないかな。80年代の戦争話ってとにかく核戦争や終末戦争みたいものが流行っていて、今思えば非常に能天気な話だったのかもしれません。要するにドカーンって地球が滅びちゃって全部いなくなるみたいな。だからこそ、戦争を生活と地続きに感じられる今の子たちの方が、自分たちの問題として捉えるなりの切実さがある気がします。
おわりに
「本当は面白おかしいことばかり歌ってたい」。そう語る宇多丸さんだが、「ないことにしづらい」ほどの大きな出来事──イラク戦争、同時多発テロ、ウクライナ侵攻といった現実に向き合うなかで、ラッパーとして自らの言葉で語ろうという姿勢が、作品に結実してきた。
ラップは、形式に縛られない柔軟さと圧倒的な情報量を併せ持つ表現手法だ。小節や構成に明確な決まりがないからこそ、語り手は年号を織り込んで時系列に沿って歴史を語ることも、自身の経験と社会の出来事を重ねることもできる。韻やリズムが生む快楽は、意味を超えて聴き手の身体に届き、記憶に残る言葉を立ち上げる。そこに固有名詞が加わると、抽象的な出来事に具体的な輪郭が与えられていく。
サンプリングやレペゼンといったヒップホップの技法は、過去と現在を折り重ね、歴史を再構成する方法でもある。戦争のような重く複雑な主題も、ラップのリズムにのせて語ることで、遠くの出来事ではなく、「いま・ここ」に関わるものとして並べられる。
そしてヒップホップは、ユーモアや遊び心を含みながら、映画や冗談の話と同列に、社会問題も取り込む柔軟さを持っている。ビートの上で、あらゆる出来事がラッパー自身の物語に織り込まれ、生活の一部として立ち現れる。戦争もまた、遠くの抽象ではなく、日常と地続きにある現実として語ることができる。社会の矛盾や暴力の構造を特権的な立場から語るのではなく、日々の声から浮かび上がらせる。
宇多丸 PROFILE
1969年東京都生まれ。ヒップホップ・グループ「ライムスター」のラッパー。1989年、大学在学中にMummy-Dと出会い「ライムスター」を結成する。ヒップホップ文化がまだ根付いていない日本において、日本語ラップという表現方法を模索するとともに、雑誌ライターとしてヒップホップ文化を紹介することで支持層の拡大に尽力する。ラジオパーソナリティとしても活躍し、2009年には第46回ギャラクシー賞「DJパーソナリティ賞」を受賞。近作にライムスター・アルバム『Open The Window』(2023)、映像作品『King of Stage Vol. 15 at 日本武道館』(2024)、書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』(2025)などがある。
ディスコグラフィ
RHYMESTER、2003、「911エブリデイ」、アルバム『グレイゾーン』(2004)収録、Ki/oon Records.
DJ HAZIME feat. RHYMESTER 、2004、「いのちのねだん」、アルバム『AIN’T NO STOPPIN’THE DJ』、cutting edge.、アルバム『ベストバウト 〜16 ROUNDS FEATURING RHYMESTER〜』(2007)収録、ファイルレコード.
RHYMESTER、2023、「Open The Window feat.JQ from Nulbarich」、アルバム『Open The Window』(2023)収録、ビクターエンタテインメント.
- ヒップホップは、1970年代のニューヨーク・ブロンクスで行われたブロック・パーティーに端を発し、DJ、MC(ラップ)、ブレイクダンス、グラフィティの四大要素からなる文化である。近年の日本では音楽やファッションとして若者に親しまれているが、本来ヒップホップは、表現や共同体意識を含む包括的な文化を指す言葉である。
- 主な番組に「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」(2007-2018)「アフター6ジャンクション」(2018-2023)「アフター6ジャンクション2」(2023-)、(全てTBSラジオ)がある。
- 1987年にデビューしたニューヨーク・ロングアイランド出身のヒップホップ・グループ。社会や政治に対する批判的メッセージを込めた楽曲と独自のスタイルで知られている。
- ブライアン・デ・パルマ監督、アル・パチーノ主演のギャング映画(1983)。キューバからの移民である主人公、トニー・モンタナが、ドラッグビジネスで成り上がる姿を描く。