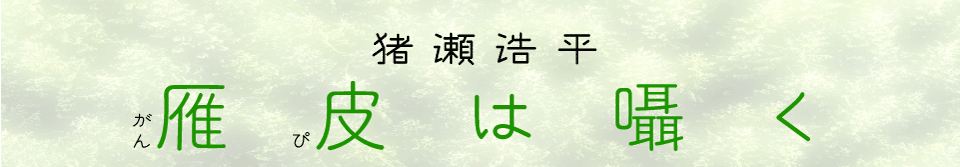技法から見た紙
2024年2月2日、成田山書道美術館に出かけた。
節分の前日の成田山は、豆まきの舞台の設営の最中だった。その舞台の脇を通り抜けながら境内を歩き、梅の花が咲く庭園を抜けて、美術館を目指した。
美術館につくと、「新春特別展 書の紙」とかかれた看板が立っていた。この美術館の学芸員をしているタムラさんに教えていただき、わたしは雁皮を使った展示を見に来た。送られてきた展覧会の案内は、以下のように書かれていた。
「漉く・染める・引く・摺る・撒く・散らす・描く・継ぐ・磨く・打つ」これらはすべて紙を加工するときに使われる言葉です。これらの多様な言葉が象徴するように、一枚の紙には様々な技法が込められています 1。
建物の中に入ると、吹き抜けになっており正面に唐の玄宗が皇帝に即位した際に記したとされる「紀泰山銘」の13メートルにおよぶ原拓が展示されていた。吹き抜けと、紀泰山銘を挟んで、左右の一階、二階の両方のスペースに、200ちかくの書が展示されていた。
全部で第一章から七章までの構成で、そのうち〈染紙〉に、〈雲紙と飛雲紙〉に、四万十町の雁皮の染めと、漉きの技法についての説明があった。そこで使われた雁皮は、ご成婚の森を中心にして、ハマダさんら、朝霧森林倶楽部の人びとが育てたものだ。
受付にもどり、タムラさんに会いたい旨を伝えた。
タムラさんとは、2023年の7月に福祉農園の仲間と、埼玉県のときがわ町を訪ねた時に出会っていた。
ときがわ町には紙を漉いているタニノさという和紙職人がいる。彼女はユネスコ無形文化遺産登録された細川紙の継承者であり、1995年からときがわに移住している。わたしは、ときがわ町にゆかりのある職場の先輩の縁でタニノさんと出会い、一緒に四万十町を旅したことがある。その旅のなかでタニノさんはシマオカさんと出会う。シマオカさんは和紙職人のタニノさんとの出会いの先に、御成婚の森に雁皮が生えているのを見つけた(第2回参照)。こうして、雁皮をめぐる物語がつむがれていった。
一方、タムラさんは高校時代にタニノさんに出会った。以来、趣味で紙漉きをする。大学では書道を学びながら、タニノさんのワークショップを手伝っていた。今回の展示に向けた実験を、タニノさんの工房でしていたときに、わたしが家族や仲間とともにどかどかとやってきた。それがタムラさんとわたしの出会いとなった。
タムラさんの問題意識は、「染紙」として一緒くたにする視点を再考し、色の来歴を探り、技法ごとに分類することである。そのために、タニノさんにも協力してもらって平安時代の染め方がいかなるものかを考えるために実験を行った。たとえば「漉き染め」は、漉き舟2の中に染料を入れて、和紙植物の繊維を染めてから紙を漉く。このとき、新たに異なる原料を加えることを「混ぜ漉き」という。「漉き返し」は、染めて漉かれた紙を、一晩水につけた後、叩いたり手でちぎったりしてほぐし、紙素の状態にもどす。それを十分に攪拌させたうえで、もう一度漉いて紙にする。「漉き掛け」は、白い紙の上に、色で染めたものを流して漉く方法で、水の動きによって波や雲のようなさまざまな模様が生まれる。漉き掛けの技法のなかには、雲紙や飛雲紙の技法が含まれる。「雲紙」は、染めていない紙素を白く漉き、その簀に、藍や紫に染められた紙素を舟からすこしずつ掬い入れ、簀桁を揺り動かしながら模様をつけることで生まれる。また、「飛雲紙」は、雲紙とは違い、白い紙の上に色のついた紙素をポイントで置いて乾かす技法であると考え、それぞれの方法を試した。実験には、埼玉の武蔵楮と、四万十の雁皮、そしてつなぎとして埼玉のトロロアオイが使われた3。
展覧会では、実際に漉き染めをつかった作品として、泉福寺焼経が展示されていた。泉福寺焼教は、金がほどこされた装飾経で、火事による焼損がそのまま残っている。この書も平安時代のものであり、紙は、染めのない雁皮の層を、藍で染められた楮の層で挟んだものになっている。藍の厚薄による濃淡があり、その風合いある表面に、金箔が散らされている。その涼やかな色と、焼かれて出来た茶色い滲みのコントラストが、生の最も美しい瞬間と、そして最も過酷な瞬間の両端を表し、そのふたつをつなぐグラデーションを表しているようである。
タムラさんが、タニノさんのもとで行っていたのは、白い紙の層に藍の繊維をかけた二層の紙の実験だった。次は、泉福寺焼経のような、藍の繊維の層を白い雁皮の層で挟む三層の技に挑戦したいという。「タニノ先生と次のステージに行きたい」とタムラさんは語った。
*成田山書道美術館の「特別展 書の紙」についての記述は、成田山美術館の田村彩華さんにご教示いただいたことが参考になっている。
参考文献
成田山書道美術館・田村彩華・高橋利郎編2024『書の紙』成田山書道美術館
- 以下は、引用した部分の続きである。いずれも成田山書道美術館のホームページ内のこの企画展の紹介を参照にしている。 「 紙を染料に浸けたり刷毛で引いたり、漉く段階で着色したりする染紙や版木を用いて文様を摺り出す唐紙、箔を撒いたり継ぎ合わせたり下絵を描いたりする様々な装飾、さらに滲みを止め、紙を平滑にする打紙などの加工方法があります。どれも紙を美しく書きやすくするための加工で、多くはこれらの技法を複合的に用いています。 本展は無地の紙から装飾を凝らした平安の古筆まで、多様な展示に渡ります。なかでも宮田三郎の唐紙制作、大柳久栄の染紙や打紙の加工に注目し、その技法にもクローズアップして紙作りの一部分を詳しく紹介するコーナーを設けます。書の紙がどのように作られ、どのように表現と関係しているのか、確認しながらご覧いただきたいと思います。」
- 漉き舟は、叩解した和和紙植物の繊維、ネリ(トロロアオイなど)、水をいれた舟。
- こちらの記述については、この展覧会の図版を参照(成田山書道美術館・田村・高橋編2024)。