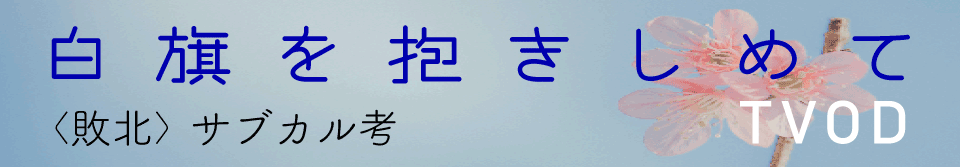かつて若者だった兵士たち
今年の8月は、吉田裕『兵士たちの戦後史』(岩波現代文庫)を読んでいました。
私の祖父母は戦争体験者にあたり、母方の祖父は1945年に召集され、本土上陸作戦に備えて九十九里浜にまで配属された時点で終戦を迎えてます。おそらく私くらいの世代が、子どもの頃に直接戦争の思い出などを聞ける最後に当たるかなと考えると、80年とは結構長い。しかし考えてみると、例えば日中戦争/太平洋戦争で兵士だった若者が40代だった時もあれば、60代だった時もあった。つまり、バリバリ働く会社員だったし、農家を営んでいたし、上司だったり先生だったりもしたわけです。山田太一のドラマ『男たちの旅路』がまさにそんな話で、上司が特攻隊上がりで、普段は寡黙なんだけど、ふとした瞬間にとてつもない暴力を発動させてしまう。いわゆる、そのようなトラウマがある人を抱え込んだ時期というのが、戦後数十年間続いていた。『兵士たちの戦後史』を読むと、彼らが戦後日本の中で社会を下支えしていたし、揺れ動く社会の中で記憶を閉じたり発散させたりしながら生きていたことがわかります。
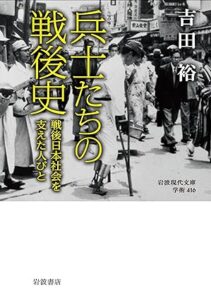
吉田 裕 著『兵士たちの戦後史
戦後日本社会を支えた人びと』 (岩波現代文庫)
戦争経験者、特に兵士だった人たちの多くは、軍隊時代が「若者」の期間だったわけです。例えば1970年代に彼らが1940年代を思い出す行為には、2025年のおじさんが1990年代に若者だった頃を思い出すのと同じ時間の距離が流れているわけですが、それが戦争であるかどうかというのはずいぶん違う。小津安二郎『お茶漬の味』で、佐分利信がパチンコを打ってたら、そこの店長(笠智衆)に「班長さん!」と呼ばれてそのまま家まで招待されるなんてエピソードが出てきます。昔は店の奥に経営者の住まいになっている建物がたくさんありました。かつての軍隊にいた2人がビールを飲んで、「現代」について語り合う、というのは、パチンコが爆発的に流行している1950年代です。笠智衆はパチンコ屋をやりながらも、「こんなもんが流行っとる間は、世の中はようならんです」と否定的。そして「あの時分は楽しかったですなあ。シンガポール」と、戦争の頃の話に持っていき、佐分利信は「ああ、でも戦争はもうごめんだね。やだね」と返す。そこから戦地の風景などについてポツリポツリと話し、沈黙が流れる。笠智衆は軍歌を歌い、佐分利信は黙っている。この沈黙が、というより、沈黙せざるを得なかったのが「兵士たちの戦後」なのかなあと思います。
佐分利信はパチンコについて「世の中の一切の煩わしさから、離れて、パチンてやるんだ。玉が自分だ。自分が玉だ。純粋の孤独だよ」とも語るわけですが、ここに当時における変化が表れています。総力戦体制とはとにかく「集団」でしか動けないような状態だったわけですが、戦後それが「自由」の名の下に個人になっていく。「戦後民主主義」と総称される諸々の中には、ひとりになる自由を求めていた側面もあったのではないでしょうか。おそらく「敗北」や「やせ我慢」といったキーワードは、このあたりに繋がっていくように私からは思えます。
いま個人的に近代日本の「若者」のあり方について色々と調べているのですが、重要なポイントとして、日本も欧米も、まず第二次世界大戦が深く突き刺さっており、そこの渦中にいた「元・若者」が、その後の「若者」を語る視線のようなものが存在します。欧米についてはここでは置きますが、日本の「若者語り」を見る限り、とにかく「戦中」を生きた世代(「戦中派」ほか)と、その後の若者を比較するような形式が支配的でした。これが1970年代あたりまでは持続しています。若者は「大人」にとって脅威で、理解しがたいものでもありつつ、戦争の記憶と照らし合わせるならば、そんな若者の「自由」なふるまいは尊重されなければいけないというような意識が並立しているように見えるのです。
そんな「自由」の極点として1960年代後期の全共闘運動などはあり、同時にそれが「戦後民主主義」への痛烈な否定を持っていったと考えるに、彼らが集団的であったのも頷けます。橋本治は「原っぱの論理」ーー戦後の都市空間の中にあった、「原っぱ」で夕方まで遊び続けたような子どもたちのエネルギーの延長ーーと言い、または遅れてきた世代、ないし戦争経験者を両親に持つ世代が、戦争をもう一度再現したと見るような言説もあります。それもまた表面的には「敗北」し、「敗北」した側からの視点での語りがさまざまな形で表現されていくーーこれが、私の考える「サブカル」の始まりです。
「サブカル」と「敗北」の系譜
以前も記した通り、1970年代の松岡正剛や片岡義男ら、もうちょっと時代を下って村上春樹などを加えても良いかもしれませんが、彼らによって追求されたさまざまな知的な体系のようなものは、一般的にはそれまでの「政治の季節」に対するアンチのようにも受け取られますが、むしろテーマを変化させた延長であると私は見ています。共通項としてはやはり個人的である、ってことでしょう。彼らはむしろそれまでになかった文脈を繋げ合わせることに長けていましたし、すごく単純に考えてしまうと「コミュ強」っぽいところがあると思うんです。ちょっと今回は乱暴に表現すると「おしゃれ」っぽいところがあるわけですね。それらが1980年代的な「ネアカ」「ネクラ」の対立構造を準備します。「ネクラ」の発生当時には、それらは四畳半フォークとか、戦後持続的に存在した「若い根っこの会」のような集団就職者のコミュニティ「的」なものに向けられていたわけですが、ただ具体的な闘争としての対象ではなく、なんとなく鈍臭くて、なおかつ「集団的」な特徴を備えていたものに向けられていました。「人生雑誌」のような、いわゆる学歴とか都市生活などといったものとは距離のある、「カルチャー的」ではない層にいた若者たちのコミュニティやメディアについては昨今研究が進んでいて、非常に興味深いのですが、1980年代あたりにはその流れが見えにくくなってしまうのですね。同時期に現れていたのが「おたく/オタク」ですが、やがて「ネクラ」的なカテゴライズはそっちに向かっていくようになります。そうなると「オタク」と「サブカル」みたいな図式ができてきます。
「オタクvsサブカル」とは2005年『ユリイカ』の特集名ですが、いまその構図を若い人にとうとうと説明しても「?」となってしまいそうです(実際、割とそうなります。)1990年代だったら「オタク」に割り振られていたようなコンテンツはすでに広範な層に受け止められており、例えば1997年に『もののけ姫』と『エヴァ』劇場版がほぼ同時に公開されていたみたいな出来事も、今では「サブカル」の正史ですが、当時だとそもそもアニメをサブカルっぽく語ることにすらちょっと緊張感があったような状況も思い出します。『スタジオ・ボイス』がエヴァ特集をやって「ぬおお」ってなるような感じです。加えて『パーフェクトブルー』も伝説的な古典として語られますが、それより当時は大友克洋が関わってた『スプリガン』の方が世間的には盛り上がってたなとか色々思い出しちゃいます(公開時期とかはあえて調べずに、私が持った印象と記憶で書いてます)。まあそれらは余談ですが、ではその後どう展開していったかといえば、かつての「ネアカ」「ネクラ」といった対立は、陽キャとか陰キャといったより広く、かつ特に所属するコミュニティや摂取しているコンテンツなどを通さない、極めて属人的なものとして書き換えられていき、現在に至っているのではないでしょうか。
くどくどと書いてみましたが、ここで、本連載のテーマとなっている「サブカル」と「敗北」の関係性と、その系譜を「私視点で」ざっくりとまとめてみました。連載当初はこのように時系列で追っていこうかなとも話してましたが、それを一旦外してお互い書いてみたら、むしろ回り道しつつ、それぞれのスタンスが見えてくるようなスリリングなやり取りになったような気がします。

『STUDIO VOICE』1997年3月号Vol.255
(INFASパブリケーションズ)
個人的に面白いと思ったのは、コメカ君が前回も「そもそもぼくはこの『ステイタス』による階級化という(避けがたい)プロセスそのものが、昔からとにかく苦痛なんです」と書いているように、ステイタスの問題にかなり拘っている点です。それは今回通史的にまとめた中では、「オタクvsサブカル」時代の領域でありつつ、取り急ぎ私は、ゼロ年代にあったそのような問題意識を延長させて考え続けたい意志として受け止めました。「ステイタスの廃絶」まで求めるとなると、かなり過激というか「結果現れるのは『共産主義』ではないか」と思いましたが……、それもまた興味深い意見です。
先述したように陽キャ/陰キャ、もしくはモテ/非モテみたいな構図が極めて即物的な形で存在し、SNSなんかを眺めれば主に性愛をめぐる論争のような形で現れている一方で、カルチャーっぽいステイタスはむしろ数値化された、バズってなんぼの世界に置き換えられてしまっているわけですね。特に、最近のコンテンツに関する議論を見ていると、対象を絶賛するか否定するかに関わらず、美的な(センスの)問題と倫理の問題と経済的な(マーケティングの、売上の)問題がごっちゃになっていて、語ってる本人の中でもそれぞれ切り分ける気がないのだなと思えることが増えました。古典的な実存の問題はSNSの呻きとかエモいポストの方に漂っていて、あとはコンテンツの内容を美的かつ倫理的に「考察」「整理」し、数値に還元するくらいしか残されていない、なんて言い方もできるかもしれません。
しかも、これは本連載中にどんどん進行している事態ではありますが、バズってなんぼの価値観は現実の政治や社会に反映されつつあります。これは結構困ったことで、既存の議会主義的なシステムはある種元から「数値化された」ものであり、バズっていこうとすればいかようにも適用できてしまうことがバレちゃったようなところがあります。かつ、SNSのような(擬似的な)直接民主主義性がそれを下支えしてしまったといえます。世界各地で起こっている状況ではありますが、それらに比べても日本はフィクション性が顕著というか、例えば迷惑ユーチューバーみたいな存在でもある程度の票を取って活躍して(社会問題になって)しまうような状況が現出していて、人気の背景には生活実感とか不満もあるのかもしれませんが、それより「ノリ」のようなものが突き動かしている側面があると私は見ています。
正直これをどうすればいいのかとパッと回答することなどはできないわけですが、コメカ君が前回記した「引きこもり」のようなキーワードは、実は結構鍵になるような気がします。バズがものを言う現在は、再び「集団」の時代に突入しているわけです。そこで個人に戻ること自体のラディカル性があるのではないか。そこでラディカル性を求めず、むしろ市井の「人間」に焦点を当てていくのがコメカ君の意図かと思われますが、それならこちらは「外こもり」でいこうかしら、なんて考えました。
「外こもり」ってゼロ年代にちょっとだけ流通したフレーズで、いわゆるバックパッカー的なライフスタイルの延長で、外国に出ていって個人的に何もしないで生活するみたいなニュアンスで使われていて、いや私はそんな生活がしたいわけではないので説明しますと、国内でも国外でも、知らない土地で交流もしつつフラフラと歩いているところから、社会や歴史や、まあこれまでよく取り上げていたカルチャーやら、自分の人生について考えることにハマってきたんですね。SNSに夢中になっていると何となく集団の中で連帯しているような気分になりがちなんですが、基本的にそれは「気分だけ」「見てるだけ」だし、それならどんどん個人的になっていこう、インターネットで見えないところで過ごそうと考えるようになったのです。これは、引きこもりに反しているようで、実は表裏一体のもので、かつ、結構ポジティブなのではないかと。「集団」から見たら、「敗北」のように見えそうだけど、むしろ「敗北」で良いのではないか。
なので、方法論の相違こそあれど、実は2人とも同じ方を向いているのではないか、と思った次第です。お互い、色々と試行錯誤していきたいですね。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。