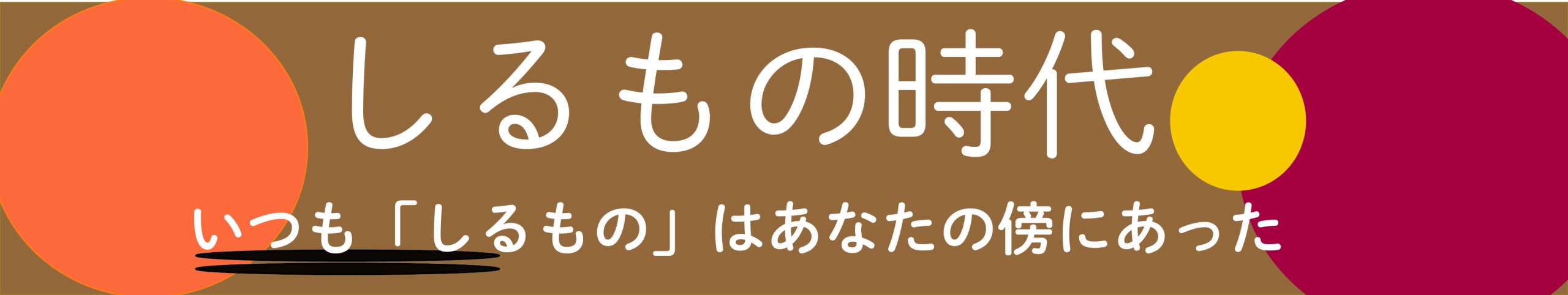短編小説:胡麻するとんかつ
打ち明け話を聞かされがちな舞台装置というものがある。ぼくにとっては、すりたての胡麻が香る場所だった。
ソースにすり胡麻を混ぜるたべかたを推奨するタイプのとんかつ屋に、お昼時、数人で連れ立って出向き、定食を注文し、揚がるのを待つ胡麻すりの時間に、ぼくは様々な話を聞いたものだ。
実は、と前置きされて、同棲中の彼女が一昨日から出て行って帰らないんだとか。この店の窓から見えるところにある病院のベッドの上に先月末まで2か月ばかり伏せっていたんだとか。まだ陽は高いのに、飲み会ではしごした2軒目の帰り道のような話題がぽろぽろこぼれ出てくる。
振り返ってみると、めでたい話はさっぱり聞かなかった。
とんかつ屋の名は「とんち」という。かつてぼくが3年ほど勤めていた職場の程近くにあった。今もきっとあるはずだ。よそから訪ねてきた人らと一緒に、とりあえずとんかつ、と、目指していくことがしばしばあった。同僚と出向くよりもそういうシチュエーションのほうが多かったかもしれない。
「とんち」は二車線の通りから一本入ったところにある一方通行の細い道に面していて、お昼時にはおもてにメニュー表が出ている。通りから入口まで、3つばかりある敷石を踏んでいく。入口は引き戸で、L字型のカウンターと、小上がりがあった。カウンターはひとり客優先の趣あり、ぼくらは靴を脱いで小上がりの席に陣取ることが主だった。お手洗いのドアの横には階段があって、2階にも席もあるんだな、そうわかっていたものの、上がってみたことはない。
「とんち」のとんかつはおいしかった。お肉がいきいきしている、と、誰かが評していたのを思い出す。ついでにいうと、お米も粒が立っていて、おいしかった。
勤めていた3年間イコール「とんち」に通っていたことになる。そのあいだ、ぼくは誰かに自分の胸中を打ち明けることはなくて、聞き役に徹していた。「とんち」か、胡麻か、どちらかが持っていた、みんなの口を開かせる力はぼくには作用しなかった。ぼくが頑ななわけではきっとない、そう思いたい。
そもそも、とんかつにはすり胡麻とソースを合わせてつけてたべるというスタイルは、古典というかスタンダードなのか、あるいは一昔前に前衛的なものとして提示されたのか、ぼくは知らない。どこのとんかつ屋でも用意されてるわけじゃないことは知っている。だからこそ不思議ではある。そのたべかたがベストなのか、と、問われたら、返答に困ってしまうのはほんとうだ。郷に入れば郷に従え、そう受け取っているにすぎない、ぼくは。
あるとき、仕事とは切り離したところでの女友達の、ヒノにそう話すと、検索すればわかるでしょう、と、やにわにiPhoneを撫ではじめたので、いや、そこまでして知りたいわけじゃないから、と、制止した。ヒノはちょっと不服そうにした。
こないだヒノとふと入ったとんかつ屋も、胡麻すり系だった。それと知って入ったわけではなかった。その店の名は、そういえば「とんち」にて打ち明け話をしたある人の名字と同じだった、と、今になってふと思い出す。そう、離職にまつわるもちろん明るくない話だった。
ヒノとぼくはお昼のサービス定食を注文した。メニューにある惹句によると、ロースカツ定食がお昼時には200円安くなるイコール、サービス、ということ。
暖簾をくぐって引き戸を開けてからの店内の造作は「とんち」とはけっこう異なっていたものの、小体なすり鉢と白木のすりこぎは「とんち」で使っていたものと瓜二つだった。
これ、うちにあったら便利じゃない?
胡麻をすっているとき誰かがそう言うのをぼくは何遍も聞いたものだ。というよりむしろ、ぼくもふとそう思って口に出したことがある。
でも、胡麻をするにはちょうどいいけど、汎用性がないようにも思う。思う、というだけで、実際に手元に置いてみたことはないからほんとうのところはわからない。とんかつをたべきってしまえば、これ、うちにあったらいい、そんな空想自体もとんかつと一緒に消えてしまうもので。
小ぶりのすり鉢とすりこぎを使って卓上で胡麻を擂るのには両手を使う。集中しないとすり鉢がぐらぐらする。とはいえ、刃物を使うような調理とは違って、少しばかり頭の中に、暇というか、空き地のようなものがあっても許される。というよりむしろ、できてしまう。それだから、世の人は、胡麻をするときなにかしら不穏なことを口に出しがちなのか。ぼく以外は。
定食といえばね、ここは豚汁だよ、と、ヒノが言った。ヒノは前にもこの店に来たことがあったのか。ぼくが勝手に、ふたりで初めて入る店だと思い込んでいたのだったか。なあんだ。やや拍子抜けするも、自分の手元から鳴る、ぱちぱち、という音の心地よさに宥められる。この胡麻が砕ける音、存外、ぼくは好きだなあ、と、はじめて思った。
とんかつに豚汁っていう組み合わせは王道なんだよ。
ヒノはそう言って、すり鉢の中をしげしげと覗き込んでみてから顔を上げ、ぼくのほうを見て、それからまた俯いて、続けた。
でも、前に、そのふたつが一緒に食卓にあるのは許せないっていう人に会ったことがあるもんで。
「へえー、豚汁の具の種類にうるさい人ってたまにいるけどね」との、ぼくの返しは的外れだったかもしれない。
それはそうと、ヒノはまだすりこぎを手に取っていなかった。
「胡麻きらい?」 うーん、とヒノはどっちつかずに唸って、要る? とぼくに訊ねる。快諾した。ヒノは自分の鉢からぼくの鉢に、さらさら、と胡麻を移してから、お冷やを一口飲むと、こう言った。
女も三十路を越えたならいわゆるおっさんみたいな保守性がないといけない、ってずいぶん前に言われたなあって。
「ほ? 保守性?」
ぼくが聞き返すと、ヒノは、まあそれは置いといて、と、打ち切って、ぼくのすり鉢の中を覗き込み、白胡麻と黒胡麻が混ざってるんだよね、そう言った。
ヒノの視線を感じながら胡麻をすっている。ヒノがぼくの手元から視線を離さずにいるもので、ぱちぱちいう音がやんでもぼくはすりこぎを手放せずにいた。ずっとこうやってすっていてもいいかもなどという心地に誘われる。なるほど、こういう心境から打ち明け話を切り出したくなるのかもしれない、と、合点がいった。
サービス定食が運ばれてきた。ごはんと漬物と、豚汁が先に卓上に並べられ、後からロースカツを載せたお皿がうやうやしく置かれる。ぼくがすり鉢にヒノはいそいそと、割り箸を袋から出して、まず、豚汁をすすっていた。そこではじめて、「とんち」の定食に付いていたのも豚汁だった、と、思い出すことができた。「とんち」に通っていた頃のぼくは、自分ではあまり汁物をこしらえはせず、もっと漫然とお椀に向かっていたものだった。ヒノの言葉どおりならば「とんち」も王道だったのか。
ここの豚汁には、にんじんの明るいオレンジ色が浮き沈みしている。
「とんち」の豚汁にはどんな具が入っていたか、脂っこかったか、ちっとも思い出せない。
生野菜を好まないヒノは、ロースカツの隣に盛られたキャベツに手をつけていない。胡麻にとどまらずそれまでもをぼくのお皿に引き取るのは、なんとはなしに憚られた。
(了)
エッセイ:家庭料理人にとっての豚肉
いっとき、「家庭料理」と「自炊」とを包括することのできる言葉を探していた。しかし、これぞ! という気の利いた言葉がいっこうに浮かんでこないまま時間が過ぎていった。
そのうち、自分以外の誰かのぶんも一緒につくるときと、ひとりぶんとでは、台所に向かう気持ちはどうしても違うものになるから、あえて分けて言い表してもよいのでは、との結論に辿り着いてしまった。
人間関係が料理の腕を磨き、あるいは鈍らせもする。たとえば、やさしくできない人のためにはごはんはつくれない。そう思ってしまう私はあくまでも家庭内料理人にすぎない。
気持ちの置きどころが違えば、たとえ自分以外にはそれとわからなくとも、着地点は違ってくる。
そんな私が、ひとりぶんでもふたりぶんでも、変わらない心持ちで、同じやりかたでつくっている唯一の料理がある。
スープ、味噌汁、それは汁物。
汁物をこしらえるときには虚心坦懐でいられる。不思議と。
しばらくのあいだ、ベーコンと野菜のスープと、豚汁を、交互につくり続けていた。新しいレシピに挑戦しようという機運があまり高まらない時期であったことは否めない。とはいえ、料理したくないよ、と、しょげているわけではない。手がなにもレシピをおぼえていないヤングな頃だったら、こういう心理状態だったら、なにもつくらなかったか、即席麺に豆腐を浮かべたりしていたはず。
ベーコンのスープ、豚汁、つくりかたはほぼ同じ。汁の味のベースとなるベーコン、あるいは豚肉を炒めるところからはじめる。続けて、具となる野菜を入れて蓋をし、全体がしっとりと汗をかいたら日本酒少しと水を沢山足して煮込む。仕上げの段階で、ベーコンのスープは、溶け出した塩味との兼ね合いで塩を足したりし、豚汁ならば味噌を溶く。その手前まで同じようにつくってきても、色も味わいも別物としてお椀の中に着地することに毎度感心させられる。
肉を炒めるところをスタート地点とする汁物としては、豚汁ならぬ鶏汁を長らくつくっていたのだけれど、きゅっと締まっておいしい親鶏の肉が安価に手に入る街でいっとき過ごした後は、そんじょそこらの若鶏を前にしても、つくりたい欲が起こらなくなってしまった。それをきっかけに豚汁に軸足を移したのだった。これは外れだなあという豚肉もないではないが、ぼやけた若鶏ほどこちらを落胆させはしない。牛肉よりも安いのはもちろんのこと。ついでにいうと、私はあまり牛の味に執着がなくて、おでんに入っている牛すじ串をたまにたべるくらいで、だからスーパーマーケットでも肉屋でも、きれいな牛肉の棚の前に立っても、自分の手で料理しようという欲がたいして湧かない。
以前つくっていた鶏汁には、いりことか鰹節とか、なんらかの出汁を加えていたけれど、親鶏の場合は使わなくても納得いくような仕上がりだった。そのやりかたを踏襲して豚汁にも出汁は足さない。とはいえ、白色の脂身がたっぷり付いている豚肉の場合は、汁が重たくなり過ぎないように、出汁を足すべきかなあと迷うときもある。でも、具の種類を増やすとか、その中でも豆腐を入れるとか、あるいは酒粕を入れるとかすれば迷いは消える。
お財布的にも、よくあるお徳用の豚小間を刻んで使うのがしっくりくるかなというところにいったん落ち着いている豚汁であっても、スーパーマーケットにて、豚汁用、と明記されて粗挽き肉が並んでいるのが目にとまると、いつもはっとして、手を伸ばしている。白色のトレイに溶け込むような色の脂がたっぷりして、重たい豚汁になる未来が約束されているのに。豚汁用粗挽き肉は、どこのスーパーマーケットにも常備されているわけではない、からかもしれない。せっかく、それがあるところまで来たのだから、という、旅先でお土産を余計に買うような衝動にも似た心理。まあ、豚汁用、そう記されているからといって、豚汁に使わなければいけないってこともないし、ピーマンを粗めに刻んで一緒に炒めてごはんに載せたりするのもよさそうだし、と、かごに入れた肉のパックを見やるも、帰宅してみればやっぱり豚汁をこしらえていた。
豚汁用の肉を選んでいるとき、私は豚肉が好きだなあとしみじみしてしまう。そのわりに、豚汁はそれほど頻繁につくっていなかったのは、汁物以外の料理に豚肉を使うことが多かったもので、汁物までも豚だと過剰かなあと、気持ちを抑えていた。
ここでひとつ、汁物から離れて、生姜焼きの話を。
豚の生姜焼きって、前もって調味液に浸しておくレシピが多いように思うけど、パックから取り出したばかりのなにも下味をつけない薄切り肉を油を引いたフライパンで焼いて、両面ほぼ火が通ってから、醤油・みりん・日本酒とおろし生姜を絡める、というのが私的ベスト・オブ・生姜焼き。
なぜかというと、お肉に火が通るのと、醤油が焦げついてしまうのとどっちが早いかというところに気を揉む必要がないから。お肉の肌のちょっとした焦げ目においしくたれが絡んでいるのが好きだから。
ベーコンをベースにした野菜のスープは、振り返ればもう15年近くつくっている。そういえば、ベーコンは豚肉だから、豚汁との距離も近いのだと今更気付く。
以前はベーコンと一緒にクミンも炒めるところからスタートしていたけれど、クミンを切らしてからは中断している。その代わり、煮込むときにローリエを入れたりする。入れないときもある。つい引き算しがちになっている。もしかしたら、ミニマルなレシピがかっこよく提示される今日この頃の世間の波に流されているのかもしれない。