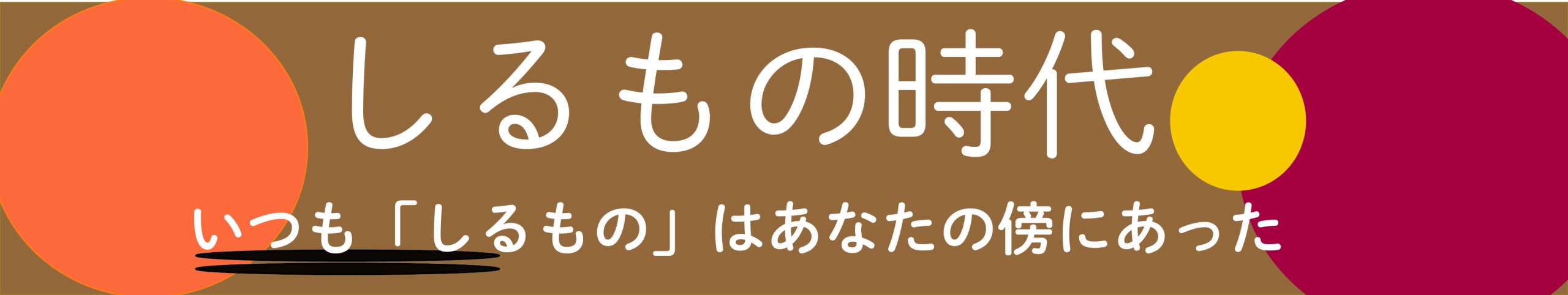第10回は公開終了いたしました。
木村衣有子(きむら・ゆうこ)
文筆と編集。主な守備範囲は食文化、書評、東北。1975年北関東生まれ。1994年から2001年まで京都在住、『恵文社一乗寺店』『喫茶ソワレ』でアルバイトしながら、フリーペーパー『nounous』、リトルプレス『marie=madeleine』を発行する。2002年より東京の東側に住みつつ、東北に通い続けて今に至る。主な著書に『家庭料理の窓』(平凡社)、『味見したい本』(ちくま文庫オリジナル)、『BOOKSのんべえ』(文藝春秋)、『生活は物語である 雑誌「クウネル」を振り返る』(BOOKNERD)などがある。リトルプレス『私的コーヒーAtoZ』『ピロシキビリヤニ』『底にタッチするまでが私の時間 よりぬきベルク通信 1号から150号まで』も好評発売中です。
Instagram @hanjiro1002
Instagram @hanjiro1002
- 第1回豚汁
- 第2回コーンポタージュ※公開終了
- 第3回トマトのしるもの※公開終了
- 第4回キャンベルスープ缶※公開終了
- 第5回めんつゆ※公開終了
- 第6回果汁※公開終了
- 第7回コーヒー※公開終了
- 第8回味噌汁※公開終了
- 第9回味噌汁の具※公開終了
- 第10回ラーメンスープ※公開終了
- 第11回シチュー
- 第12回冷や汁/読む料理本
- 第13回【最終回】チャイ