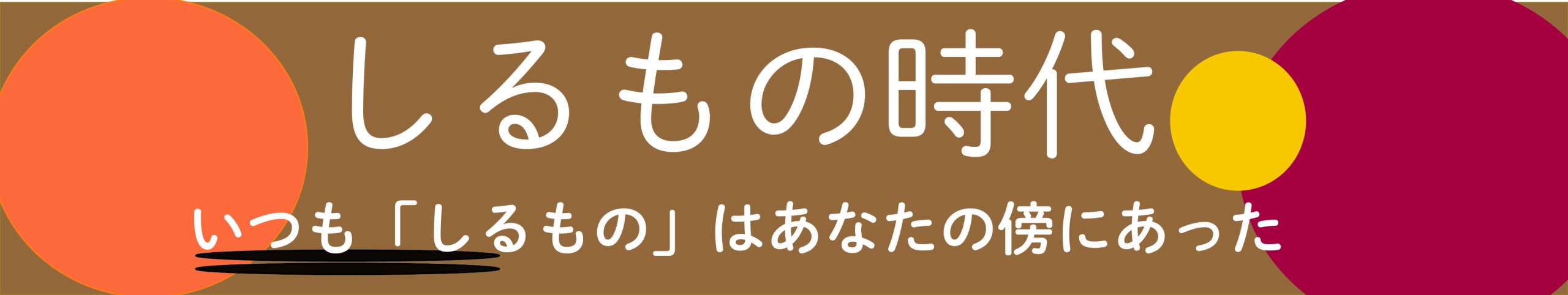短編小説:器
ぼくの勤め先の店にある水色のマグはふたつだけだが、以前は沢山あったそうだ。古株のスタッフがいつぞや話してくれた。立て続けに縁や把手が欠けた一時期があり、どんどん減っていって、ふたつが残された。
「それっていつ頃のことですか?」
たしか一昨年のことだという。
それから不思議と、割れずにふたつは残っているのだという。
店にやってきて鍵を開けるとき、明かりを消して店を出るとき、ふたつだけある水色のマグを視界の端にとらえて、あ、あるある、と、確認する。すると、ほっとする。毛布を両足に挟めばよく眠れる、というのと似ているかもしれない。いや、違うかも。
とある休み明け、水色のマグの定位置に目をやったとき。
マグは増殖していた。
10個まで数えてみて、やめた。まだある。20個はないかもしれない。
置かれていた他の器はどこへしまわれたのか、とにかく沢山のマグが存在感を放っている。ぼくがいつも見ていたふたつはその中のどれなのだか、ぱっと見にはわからなかった。ひとつひとつひっくり返したりしてみれば、わかるのかもしれなかったけれど、常々丁寧に漂白をしていたし、そもそもつるりとしていて、使い込んでいくだけそのしるしを表面に刻むような質の食器ではなかった。
その日は、久々にA店長と顔を合わせた。
というのも、梅雨明け後のあまりの気温上昇に、A店長とのウォーキングはいったんやめにしていた。ぼくから言い出したことだった。贔屓のプロ野球チームの選手が立て続けにふたりも熱中症になったことに恐れをなしていたA店長も同意した。
時を同じくして、系列店のあいだでの配置換えもあり、A店長と顔を合わせる機会がほぼなくなったまま、季節は秋めいてきていた。このまま、ウォーキングの時間はなくなるのかもしれないな、と、ちらっと思った。そう想像してみたとき、たいしてさみしくならなかったことにぼくは驚いていた。日常のいろいろな局面で、これってA店長に話したいなと思ったりしていたのはほんとうなのにな。
そうはいっても、その日はぼくは、マグについて、息せき切るように、訊ねた。
A店長曰く、オーナーである彼女の姉がこのマグを気に入っていたところ、前の週に、合羽橋で、お店のおもてに出された特売ワゴンで同じものが売られているのを見つけて、ありったけ買ってきたのだという。全く同じ輪郭、同じ水色のマグを。
やっぱりこれくらい揃っていると落ち着く、と、A店長は言った。彼女らは、水色だらけの光景のほうを見慣れていたのだった。
A店長の、カラスの濡れ羽色の髪がずいぶん短くなっているのに気付いた。前髪を斜めに留めてある金色のヘアピンがきらりと光って、誇らしげだった。
そもそもマグの一件に思い入れがあるでもなさそうなA店長は、タバコ屋の立ち飲み屋がつぶけたよ、と、言った。A店長は、あれほどの炎天下であっても、ちょいちょい、帽子をかぶってひとりでいつものコースを歩き、気になる物件を見回っていたらしい。
「無限の体力」
ぼくはつい、そう口走っていた。
A店長は、有限だよ、と、真面目に返してくる。
そういえば、A店長が気にしていた元おにぎり屋の跡はというと、改装工事がえらくのろのろとしか進まないと聞かされていたっきり、それっきりになっていたのだけれど、結果的に、コーヒースタンドになったという。
あの物件がコーヒースタンドの器なのかわからないけど、と、A店長は言った。
その次の日は遅番だったこともあり、ぼくは日中、A店長と一緒に歩いていた道程を久々に辿ってみた。ひとりで。道すがらに見る風物はA店長が昨日話していたとおりに変わっていたり、変わっていなかったりした。どちらともつかないのはもうおぼえていないということなのだろう。
それはさておき、A店長とぼくとは、環境の交友、なんだろうな。
偶然会わなければ話さない。あえて連絡を取ったり約束してまで会う人じゃない。
環境の交友、という言葉をよく使うのはヒノだった。ヒノはそういう人付き合いを続けていくのが不得手だという自負があるという。出会ってすぐ、ぐぐっと仲良くなって、社交辞令ではなく連絡先を交換し、約束して会う。そういうような関係しか長続きしない。とはいえそこまで仲良くできる相手なんてそうそう出会うもんじゃない。ヒノにとっては、ぼくもそのひとりなのだった。
道中、ぼくは目にした。自販機の前にいる、セーラー服の女子高校生の後ろ姿を。
肩を覆う横長の長方形の襟。セーラーカラーを見るとぼくはいつも、便箋のようだなあと思う。ヒノの言っていた近頃の傾向どおり、ズボンを履いていて、靴の踵すれすれくらいの長い丈。
海上自衛隊の制服みたいじゃないか、という感想が第一に頭の中に浮かぶ。セーラー服のおおもとである軍服っぽさが際立つ。スカートとの組み合わせじゃないと全く印象が違ってくる。
襟とプリーツスカートの直線的な折り目正しさが、女の子の活きている身体に沿うとひらひらしてみえる。そういう、ひらひら、揺らぎの似合うような性別、年頃のためにあるような制服だ、セーラー服は。ズボンになるととたんに揺らがなくなる。正直言って、むしろ、目のやり場がない。
ぼくは、自分が存外セーラー服に対して夢や希望をもっていることに、今になって、この年になって気付かされたのだった。だって、いつものぼくに似合わず、服ばっかり見ている。
振り返ってみると、まだ自販機の前にいるセーラー服の女の子の髪の毛はショートカットだった。やせてもふとってもおらず、背は高くも低くなかった。
そもそもぼく自身に選択肢がないのは自明のこととして、こう思うのだった。短いスカートを履いている女の人はそのひらひらと一緒に緊張感もまとっている。ぼくの身近には、のんびりとした印象を与える女の人ばかりなのだ、今は。両脚や脇をきゅっと閉じざるを得ない服装より、遠慮なくぐぐっと広げて伸ばせる力強さのほうに手を伸ばす人ばかりなのだ。服を選ぶ側が決めることなのだ。繰り返しになるけれど、ぼくが選べるものなんてなにもない。
服というのはいれものにすぎないのかな、たとえば、マグカップみたいなものなのか?
ぼくらが、たとえばチャイだったなら、器なしにその場にはいられない。こぼれていってしまう。
(了)
エッセイ:紅茶の入口
私にとっての紅茶の入口はチャイだった。
入口とは、自分で、紅茶が飲みたいなとはっきり思って立ち上がったとき、そういうイメージ。
古めかしいビルの地下の飲食店街の一角を成す紅茶専門店だった。店内は広く、明るくはなく、雑然としていた。地下鉄の駅直結だったか、そうでなくとも駅が近かったので、近隣のホワイトカラーの男性客が目立って、私はその後ろに隠れるようにしてチャイをのんでいた。22歳になる年の春に入学した専門学校に馴染めず、ひとりさぼって学校の傍にあったそのお店に逃げ込んでいた。ひとりでチェーン店でないお店で、過度に周りを気にかけずに過ごせるようになったのもそこだった。まだ自分自身が喫茶店で働き始める前だったのもある。
そのお店は、数年後、近隣にある真新しいビルの上階に移転した。行ってみると、窓が大きくて壁は白く、明るい。逃げおおせた、と、やれやれと息をつけるような明るくない隙間がない。よいお店ではあるはずだけれど、雰囲気はずいぶん違うものになっていた。それから数年後、また別の街に移ったはずで、そこには足を運べていない。
同じ頃、紅茶の茶葉を買ってうちで淹れることもたまにあったはずだけれど、味わいについて思い巡らすわけでもなく、習い性で淹れていた。牛乳で割ってもいなかった。
うちの外でチャイをのむのははじめてではなかったけれど、味は別格だった。もちろん、スパイスの効かせかたも好みだったのだと思う。その香りと味と場の雰囲気とが相まって、しっくりきたのかもしれない。
チャイだから、牛乳とスパイスと合わさってこその味わいではあったのだけれど、紅茶をストレートで飲むことが惰性でなく少し楽しくなったきっかけはチャイにある。
時間をさかのぼって女子高生の頃、当時たしかに一世を風靡していた「アフタヌーンティールーム」に行くのがうれしかったのはおぼえていても「ティー」そのものを享受していたわけではなかった。それに、のみものとして選んでいたのはカフェオレだったような、理由も、カフェオレボウルを目の前にしたかっただけだったような気がする。
やっぱり、チャイだと思う。
これと決めずにいろいろな茶葉を渡り歩いていて、今もその途上にある。近くに信頼できる紅茶専門店がなければとりあえず「リプトンの青缶」を買っておけ、という、とある本で知ったアドバイスに従っていたときもあったし、ティーバッグも使っているけれども、ティーポットというか急須で淹れるほうが、味がどうというよりもやりかたとして馴染みがあってそうしている。
うちでコーヒーを淹れずによそで飲むことにしていた一時期も、紅茶の茶葉は常備していた。たいていの人は淹れられるからというのもある。ちょっと淹れといて、と、たのんでも、豆から挽くコーヒーだと、できないよと尻込みされる場合もあるから。
30歳になるかならないかの頃、かっこいいなと思っていたのは、サリーをまとった女の人が売り場に立っている「新宿タカノインディアティーセンター」だった。このところしばらくは、蔵前の「アンビカ」でよく買っているのも、近所だからもあるし、インドっぽさがあるところで茶葉を手に取りたいという気持ちがある。ついでにいうと、年に一度くらい行く名古屋の紅茶専門店の押しも押されぬパイオニア「えいこく屋」も、すぐ隣にインド料理のお店が肩を並べている風景がとてもしっくりきている。
コーヒー豆については、豆そのものを見ていても、紅茶となると、雰囲気だけをいつまでも飲んでいる。それも、世間一般の紅茶のイメージとはちょっと違った角度の、仄暗い地下の、そして行ったことのないインドの。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。