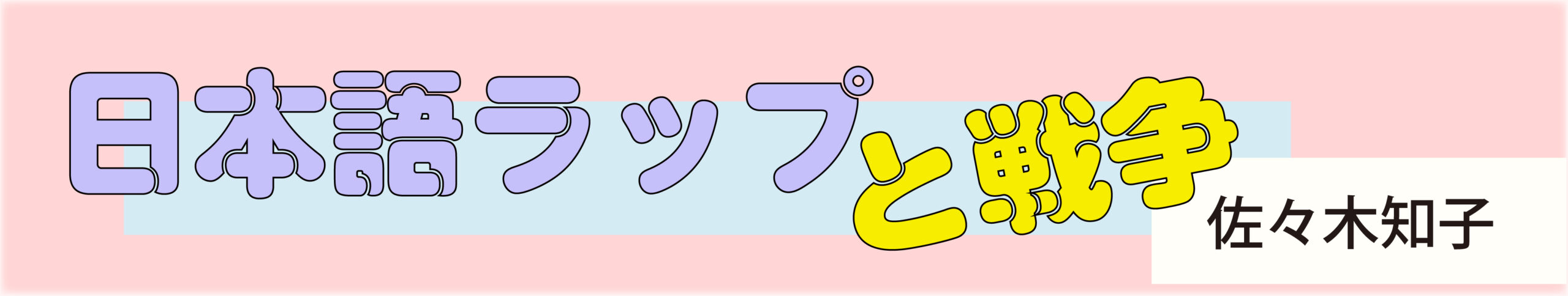911 エブリデイ 驚くようなことは別にねぇ
ミサイル 弾丸 雨降りで もうできりゃ全て目ぇつぶりてぇ
どこか遠い国で起こった大惨事 TVで眺めてる幸せな午後三時
( RHYMESTER「 911 エブリデイ」 2003 )
誰の戦争?誰のリアル?
戦争なんていやだ。戦争はよくないものだし、あってはならないという認識は、多くの人が共有している。誰もがそう言うし、それに対して「もちろん、それはわかる」と応じるのもまた、決まり文句のようなものだ。
けれど、そうした「了解」があるにもかかわらず、私たちはなぜ、戦争について誰かと日常的に語ることに、どこか躊躇いや抵抗を感じてしまうのだろうか。それはおそらく、戦争が、国際政治や歴史的な対立、宗教やイデオロギーといった、自分たちの生活からは遠く感じられることによって起こる問題だから、具体的な感情として共有したり、語ったりすることが難しくなっているからかもしれない。つまり、どこかで「自分とは関係ないこと」と感じてしまっているのだ。
RHYMESTERの「911エブリデイ」(2003)は、2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件をモチーフに、そうした戦争と私たちのあいだに横たわる距離を、逆撫でするように突きつけてくる。この楽曲の批判の矛先は、イラク戦争、それを対テロという名目で遂行したアメリカ、そしてそれを容認する国際社会、さらにはその構造に加担するメディア報道のあり方にまで向けられている。一方で、そうした批判を投げかける自分たちもまた、戦争をメディア越しにしか捉えられない立場にある。そこでの葛藤や複雑な感情もまた、この曲には刻まれている。
「ミサイル 弾丸 雨降りで もうできりゃ全て目ぇつぶりてぇ」というリリック(歌詞)は、世界のどこかでいま、まさに起きている暴力や死の氾濫を前に、何もできないとか、目を逸らしたいと感じてしまうその無力感や逃避の心理を、あまりに正直に、だからこそ痛烈に表現している。「どこか遠い国で起こった大惨事 TVで眺めてる幸せな午後三時」という一節では、戦争やテロの外にいる私たちが、メディアを通じて「安全な場所」から災厄を傍観している構図を巧みに描写し、他者の死が「画面越しの出来事」として消費されてしまうことへの皮肉が込められているのだ。
この楽曲では、語りにくくて重苦しいとされる戦争という主題を、散弾銃や爆撃音のサンプリングを織り交ぜたダークでアイロニカルなビートの上で軽妙に、しかし核心を突く言葉で描き出している。「ラップ」という形式がもつリズム、韻、時にユーモアを交えた語り口は、私たちが無意識のうちに避けてきた問題を再び目前に立ち上げる。そしてそれは、有り体に言ってしまえば、とても「リアル」に響いてくるのだ。
戦争が遠くなっていく
日本は2025年の今年、太平洋戦争の終戦から80年という節目の年を迎える。この「節目」とは、戦争体験者の高齢化と死去が進行するなかで、戦時下の出来事と現代を生きる私たちのあいだに、いっそうの時間的な隔たりが生まれてきていることを意味している。
戦争は、いまや私たちの日常生活のなかで語られる機会を失いつつある。かつては身近に存在していた戦争体験者による語りの場や、歴史を共有する空間も、次第に姿を消している。私たちは現在、そうした歴史的転換点のただなかに立っているのだ。
同時に、2020年代の世界情勢は、かつてないほど不安定な様相を呈している。2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻、2023年以降に激化したパレスチナ・ガザ地区の紛争、さらにはスーダンやミャンマーなど各地で続く武力衝突は、戦争がもはや過去の出来事ではなく、依然として現在進行形の現実であることを突きつけている。
そこでラップです
こうした状況のなかで、戦争の現実と向き合うためのひとつの手がかりとして〈戦争1〉を個人の視点から捉え直し、「わたしたち」の感情や共感をかきたてるような表現形式であるラップに注目したい。
近年、日本のラップシーンは目覚ましい発展を遂げ、文化的・社会的な影響力を拡大している2。若年層を中心にリスナーが広がり、バトルイベントやYouTube、ストリーミング配信を通じて日常的にラップが聴取され、共有される環境が整ってきた。アメリカでは、ブラック・ライブズ・マター運動やトランプ政権への批判など政治的、社会的な問題に対する応答として、ポリティカル・ラップ3が重要なメッセージ・メディアとして機能してきた。たとえば、ケンドリック・ラマーやドーチといったアーティストは、警察による暴力や人種差別などの構造的な問題に対してラップを通じて抗議の声を上げ、社会の中で議論を生み出すきっかけとなっている。
日本語ラップ4においても、同様に社会的な問いや現実の問題に向き合おうとする作品は、これまでも少なからず存在してきた。冒頭で挙げたRHYMESTERの「911エブリデイ」はその一例であり、エンターテインメントとしての魅力を保ちながら、同時に「遠くの戦争」を取り巻く現実やそれに向き合う私たちの姿勢に対して、鋭く言葉を投げかけている。
ラップはフリースタイルに代表されるように、その場その瞬間の出来事や心情を、言葉にして表すことができる。こうした言葉は、抽象的な理念ではなく、自らの実感や身体の経験に強く根ざしている。何を見て、何を感じ、どのような場所で生きているのか。そうした手触りを帯びた語りだからこそ、その言葉には耳ざわりがいいだけのきれいごとではない、特有の説得力や緊張感が宿る。
ラップには、歴史や社会的出来事を、時間や場所の距離を超えて現在に引き寄せ、過去と〈いま・ここ〉をつなぎ直す力がある。ラップは、自身の言葉で過去を現在に「呼び戻す」行為であり、同時にそれを他者に響かせる装置でもある。つまり、ラップは「過去」と「現在」、そして「わたし」と「社会」をつなぐ、「記憶の現在化メディア」としての可能性を秘めているのではないか。そうしたラップの力は、「戦争」という主題に対して、どのように切り込み、どのような言葉で私たちに語りかけるのだろうか。
本連載について
本連載では、実際にリリックの中で戦争について言及してきたラッパーたち、そしてその表現と表現の場に精通する音楽ジャーナリスト、さらに戦争、記憶、音楽表現に関する研究を行ってきた専門家へのインタビューを通じて、ラップで戦争を表現する社会的な意味や、その背後にある思考を深く掘り下げていく。
なぜいま、ラップで戦争を語るのか。そしてそこにはどのような可能性が含まれているのか。そうした問いについて、表現者であるラッパーをはじめ、さまざまな立場の方々からお話を伺い、それぞれの視点を交差させながら、ラップという表現が社会において持ちうる意味の広がりについても検討していきたいと考えている。

佐々木知子「稲佐山から爆心地を臨む」(シリーズ『Ground』より 20195)
参考文献
大和田俊之・磯部涼・吉田雅史、2017、『ラップは何を映しているのかーー「日本語ラップ」から「トランプ後の世界」まで』、毎日新聞出版.
佐々木知子、2019、『Ground』、tento.
ディスコグラフィ
RHYMESTER、2003、「911エブリデイ」、アルバム『グレイゾーン』(2004)収録、Ki/oon Records.
- 戦争という言葉で表現され、想起されるのは、必ずしも銃弾が飛び交うような戦闘だけではない。日常の中に潜む、比喩的な〈戦争〉もある。たとえば、暴力や破壊のように目に見えるかたちでは現れなくても、社会の中で「正しさ」とされる価値・規範が、人びとの意識や行動に無自覚のうちに影響を及ぼし、権力の偏りや制度のあり方が、人間の可能性を制限するような状況もまた、ある種の〈戦争〉と呼べるのではないか。
- 現在、ラップシーンの一部において排外主義的な言説が、想像以上の広がりを見せている。こうした状況において「戦争」というテーマをラップで表現することは、歴史修正主義的な語りを助長する可能性があることも否定できない。しかし、本連載においてラップにおける戦争表現を考察することで、そうした歴史修正主義的傾向を逆照射し、批判的に捉える視点を獲得することが可能になるのではないかと考える。ラップで戦争をどう語るかを問うことは、記憶を誰が・どのように語るかという構造を可視化し、修正主義的な語りがなぜ・どのように生まれるかという問いに接近する手がかりともなり得る。
- 政治的・社会的なテーマを扱うラップのスタイル。
- 磯部涼(2017)は、「日本語ラップ」という用語は、「『さんぴんCAMP』(1996)で確立されるハードコア・ラップ史観に基づいた言葉」であり、「そもそも、00年代以降はバイリンガルやトリリンガルのスタイルで、『日本語』による『ラップ』という形式にこだわっていないものも多い」ことから慎重に用いている。本連載ではこうした磯部の視点に多くを負いつつ、日本語を中心としながらも多言語的・多文化的な背景や表現を含みうる、より広い意味合いをもって「日本語ラップ」という呼称を採用する。
- 筆者の作品、『Ground』は、長崎の爆心地周縁の風景を撮影したものだ。戦争を表現することへの関心はこの作品制作が起点となっている。