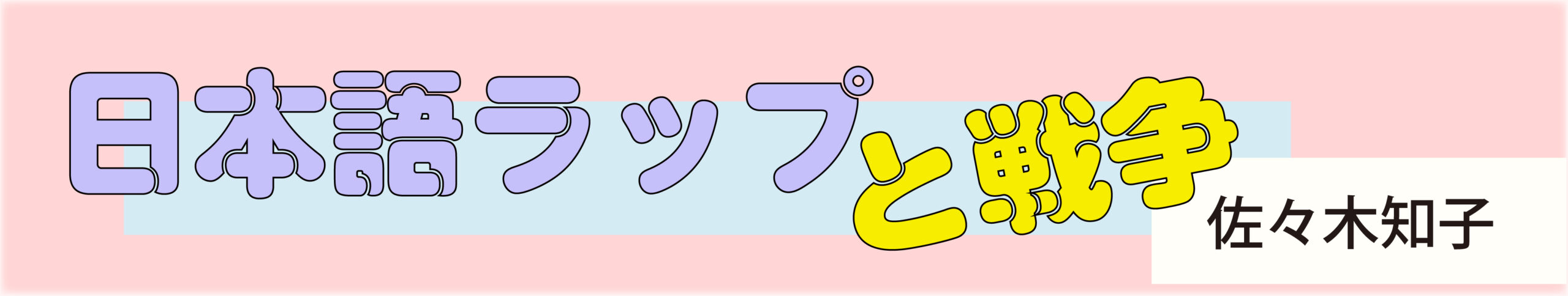Photo Tomoko Sasaki
針は変えたんだろうな?
電車の走行音とアナウンスが混じる中、THA BLUE HERBのファーストアルバム『STILLING,STILL DREAMING』(1998)の1曲目「THIS ’98」は、突き刺すようなこの言葉から始まる。チューニングは済んでいるのか。この曲を受ける準備はできているのか。短く放たれた問いは、挑発というより宣告に近い。音が動き出した時には、逃げる余地はない。大声でも激情でもない。ただ鋭利で乾いた刃のような言葉が、聴き手の身動きを封じて切りつけるのだ。
1DJと1MCで構成されるTHA BLUE HERBは、1997年の結成以来、自身のレーベルを軸に、一貫して北海道札幌市を拠点に活動を行ってきた。全曲のリリックを手がけ、ラップするのはILL-BOSSTINO(イル・ボスティーノ、以下BOSS)である。BOSSのリリックは、自身の置かれた環境、ヒップホップの現状、この社会の状況や歪み、そしてそれに対して自分がどう立つかを、熱を内に抱えて研ぎすました言葉で刻んできた。結成から現在まで、その言葉は後続のラッパーとリスナーに影響を与え、注目を集め続けてきた。
BOSSがこれまでラップしてきた数あるテーマの中でも、「戦争」は重要な位置を占めている。2019年にリリースされた「REQUIEM」は、「飛行機ごと体当たりして死ねと」という特攻隊を想起させる一行から始まり、「祖父」の戦争体験の記憶、日本兵士の加害性、さらには戦後の日本社会の在り方まで、過去と現在を行き来しながら戦争を直接的に表現している。また、2023年の「64 Bars of Mind」では、「パーティーの朝方 空から降りてきたゲリラ そこから続いているあの爆撃は 重い事実を突き付けてきた この不条理は俺達の無関心のせいさ 俺達は出来ない 刻々と進む虐殺を止める事が出来ない 年寄りの権力者の横暴な振る舞い1つ正す事すらも出来やしない」とスピットし、日常の描写から、その延長にあるガザ地区への空爆に触れ、現在進行形の暴力を自身の生活感覚と接続している。
日本の戦争体験の記憶から、いま、世界で起きている出来事へと視線を開いて現在進行形の戦争まで言及し、自身の心情をリリックに刻む。BOSSの表現を見ていると、日常から他国の戦争までがひとつながりの出来事として扱われ、ラップの表現はここまで射程を広げ、踏み込めるのかと驚かされる。
今回はこれらの楽曲を手がかりに、戦争をラップすることはどのような意味をもつのか、その際に何を見据え、いかにして言葉を紡いでいるのか、また、BOSS自身がラップという表現をどのように捉えているのかについて話を聞いた。
「64 Bars of Mind」――事象を反射するラップ
BOSS:「64 Bars of Mind」はレッドブルの「64 Bars」1 の企画で、オファーをもらったのが2023年の10月頃。ちょうどそのタイミング(10月27日)でガザ侵攻があって、だから最初から戦争を描こうとしたわけではなくて、公開までの2ヶ月のマインド、それをそのまま表現したらああいう内容になったんです。
ラッパーってやってるのは音楽なんだけどただのラブソングじゃなくて、基本的にはある事象があってそれを反射、投影する存在でもあって、俺は街の書記官って呼んでるんだけど、そこがラップの面白いところのひとつだと思う。熟慮に熟慮を重ねて何かを描くという側面ももちろんあるんだけれど、「64 Bars」関しては普通に、起こっていること、そこから感じる想いをそのまま書いたし、その中には僕の戦争に対する気持ちも、もちろん入っている。
けど、フリースタイル的にこういった事象に触れるのは危うさもある。言葉ってとても危ういものだから、その危うさを知れば知るほど慎重にもなるけど、それでも事象に対して反射的に何かを思うっていうのは自然なこと。こうしてる今も、ニュースひとつ見れば、誰かがそれに対して反対だの賛成だのを思っている。その思いを反射的にラップとして外の世界に出すということは、やはり大事だなと思う。
「REQUIEM」――熟慮と時間を要するラップ
BOSS:「REQUIEM」に関しては、本当にずっと残るものを作りたかった。だからこそ熟慮に熟慮を重ねて作りました。同じ戦争を扱ったものでも、「64 Bars of Mind」と「REQUIEM」は制作のプロセスは似て非なるものです。
「REQUIEM」は昔、鹿児島でライブした時に知覧の特攻隊の人たちに関する資料館(知覧特攻平和会館)に行って、彼らの「最後の手紙」を読んだんです。そこからずっと自分の中に蓄積していった気持ちを3年、4年、5年、6年、それぐらいかけて一曲にしていったもの。だからこの2曲は、かけた時間が全く違うんですよね。
〈答え〉ではなく、〈喚起〉させるもの
「REQUIEM」は、THA BLUE HERBがその名を冠したアルバム『THA BLUE HERB』(2019)に収録され、終戦記念日である8月15日にミュージックビデオが公開された。動画のコメント欄には、現在(2025年11月)までに258件の書き込みが寄せられており、その内容は幅広いものとなっている。
自分の祖父母や親類から聞いた戦争体験の記憶を呼び起こされたという声もあれば、戦没者を「愛国者」「英霊」と称える書き込みも見られる。一方で、ドイツがナチスの経験を踏まえて行ってきた歴史教育を引き合いに、日本の平和教育が形骸化しているのではないかと懸念を示したものや、いまこそ戦争に向き合いたいと語るコメントもある。
この曲は、英霊祭祀のような「戦争体験の神話」(G. Mosse 1990=2002)を想起させる反応から、むしろその神話化に距離を取り、批判的に向き合おうとする姿勢まで、相反する立場を同時に引き寄せるものとなっている。そこには、戦争をめぐる現代日本の記憶の複雑さが、そのまま凝縮されているようにも見える。
そして興味深いのは、こうした政治的・歴史的な位置取りの違いが見られる場であるにもかかわらず、「右か左どころか、ヒップホップのど真ん中だろこれは」というコメントが存在している点だ。戦争という重いテーマを扱っていても、BOSSのラップが「思想の対立」ではなく、「自分の立っている場所をどう語りうるか」というヒップホップの根本的な問いへとつながるものだと受け止められているのだ。
BOSS:YouTubeのコメント欄がああいう感じになったのは、俺自身もコントロールが及ばないところだし、サプライズでもあった。題材が題材だから、皆も文章で書くのはハードルも高かったと思う。それを超えて、それぞれに思うことをああやって文章にしてくれたのだし、書かれたことに対して、俺もものすごく気持ちが揺さぶられた。そういう場になったということは、率直に嬉しいです。
俺自身は、特攻隊の人たちの手紙を読んで、彼らを「死を強制された人たち」として感じたし、俺の歴史観はやはりそっちなんだけど、別の考え方をする人たちがいるのもわかる。とにかくいろんな文章、いろんな意見を交わす場所になった。右だろうが左だろうが、両方ある。その通りなんだよね。ラップってやっぱり、喚起させるものだと思う。何か決定的に答えを出して、そこに決着をつけるものではないっていうか。
自分の人生に関しては決着をつけられるけど、個人の主張ではどうにもならないものってやっぱりいっぱいあって、戦争もそうだし、この国の貧困のこともそうだし、人種差別もそう。自分ひとりの一曲で、世の中が直接変わることはないと思ってる。ただ変わっていくための足しには、プロセスのひとつにはなり得る。
ジョン・レノンの「イマジン」だって、あの一曲で人類の争いを止めるために何か決定的な答えが出たかというとそうじゃない。でもあの一曲があったから俺も自分自身の答えに向かっていくきっかけにはやはりなった。やっぱりラップに限らず歌っていうのは、喚起させるもの、人を刺激するもので、最終的に何かをするのはそれを聞いた人だから。そして追い追い変化を形作っていくのはその人その人の集合体だから。
俺、「BOSSが言ってくれてるから」って言われるのがいちばん嫌いなんですよ。俺が何かを言ったとしても、できるのは喚起するところまでで、考えるのも、答えを出すのも自分だろって。そうじゃなきゃどうにもならないだろって、常に言い続けてる。
俺が政治的にどういう思想を持っているかっていうのは、あの曲を聞けば一発で分かると思うんですよ。でも抑制をきかせて、言い過ぎないようにもしている。そうすることで特攻隊の人達へ意識が向いて、誰もが何かしら喚起されて、自分の意見を言えるようになっている。それはすごく、自分でもよかったって思います。
SNSでも、誰かがひとつのものを言うと、それに対してコメントがいっぱいついて、すごいことになるじゃないですか。簡単に言えば分断で、もうとても折り合えないような文章がそこにたくさんぶつかっている。それは何か新しいものを生むというよりは、相手を説き伏せるどころの話でもない、もっとレベルの低い言葉が行き交っている。でも幸運にも、あそこの場(コメント欄)ではそこまで極端な、ヒステリックな物言いはないですよね。どんな意見であれ、皆の死者に対する感情に抑制が効いているというか。そこにはちゃんと共通点がある。突き詰めていけば共通点はあるんです。
日常会話に近づくラップ
SNSをはじめ、感情の衝突が分断を深めやすい現在の社会状況において、BOSSは表現の場にあえて静けさや抑制を持ち込むことで、思考のためのスペースを確保しようとしている。特攻隊をどう捉えるかという問題でも、結論を固定せず、多様な意見が喚起される余地を残している。
だが、この抑制は同時に、どのように語るかを選択する難しさにもつながるのではないか。慎重に向き合おうとするほど、言葉の置きどころが容易には定まらないという側面もあるのではないか。そのなかでラップという形式で表現することは、どのような意味を持つのか。
BOSS:ラップに日常的会話以上の力があるんじゃないかと思うのは、やり始めの頃の感覚なんじゃないかな。俺にとっては、限りなく日常会話に近づいていく方が正解なんだよね。日常会話から離れて、必要以上に虚勢や怒気を含んだりっていうのは、ビギナーの頃の振る舞いだったと思ってる。できるだけ自然になって、こうやって喋っている時と、ラップしている時の境がなくなっていくのが、俺としては理想だね。
俺のキャリアの最初の頃なんてそれこそ虚勢に満ちてたし、怒気に溢れていたし。でも、長く続けていく中で、どんどん「自分」に戻っていっている。そういう感覚が強いですね。
ラップの始まりは、アメリカの差別されている側、つまり少数派の黒人やプエルトリカンや有色人種たちが、自分たちの生活を、このパーティーを楽しもうぜというところから始まっている。パーティーを楽しもうという出発点は政治的じゃないと言う人もいるけど、十分政治的だと俺は思う。十分悲しいじゃないですか。決して「ただ楽しい」だけじゃない。持たざる側の人間が、どういう状況で、どういう生活で、どういう苦しみの中にいたのか。その中で「楽しもうぜ」と言う、動機、その選択の中に含まれている強さや、悲しみや、希望や、絶望。いろいろな意味が想起されてくるものだと思う。
ジャマイカのレゲエもそうだし、同じアメリカでいえばジャズもそうだし、世の中の抑圧された側から立ち上がる音楽だからこそ、俺はやってみようと思ったんです。アメリカから遠く離れた島国で、名誉白人の末席みたいな、俺みたいなやつでも、やっぱりひっくり返したいものがある。そこに力を与えてくれる音楽だから好きになったし、ヒップホップはそういうもんだって思ってます。
抑圧された側のヒップホップだから書けること
BOSS:特攻隊の人たちの手紙を読んだ時にも、やっぱりただの愛国心とは思えなかったし、ただかわいそうな十代の話とも受け取ることができなかった。そこにはいろんなものがあると思った。俺は日本が超好きだし、愛してるけど、同時に憎んでもいて、そのいちばん嫌いなドロドロしたものがチラッと見えて、だから書けるなと思った。「お前ら、この手紙以外に言いたいこと、絶対あったっしょ」って、全ての手紙の行間からすごく感じられた。特攻隊について書くことはすごく勇気がいったけれど、書かせてもらった。
戦争の問題に触れること自体が、どうしても政治性を帯びざるをえない。特に特攻隊は、戦没者を称揚する語りから国家の物語に回収されるものまで、さまざまな立場が衝突する領域だ。手紙の背景にある「言えなかった声」を拾おうとするBOSSの表現は、特攻隊をめぐる議論がしばしばナショナリズムの象徴として扱われる現状とは、別の角度からこの問題に触れようとする態度でもある。
BOSS:俺自身は、とても小さなパーティーをやっている人間で、たまたま知ってくれている人はいるかもしれないけど、世の中を震撼させるような事を大層な立場から言ってるつもりはない。
そんなことよりも、あそこで死んでいったあの人達の無念とどうやって向き合うか、ただそれだけでしかないんですよ。人と人、個と個、時空を超えた対話なんです。とてもシンプルに、供養で、慰霊で、鎮魂なんです。それでしかないですよ。本当に、俺は泣けるほどにかわいそうだと思ったもん。
しかし、他国の側から見れば、その行為によって命を奪われた人びとの視点も当然存在する。特攻隊の「悲劇」だけで完結させず、その背後にある加害の事実や、異なる立場からの記憶へも視線を向ける必要がある。それを考え始めると、戦争を語ることは単純に“かわいそうな若者の物語”では済まなくなり、どこまで踏み込むのか、どの視点を選ぶのかという意味で、困難な領域に踏み込むことになる。
「REQUIEM」はきわめて複雑で多層的な表現になっている。特攻隊の話と、祖父の戦争体験2が語られるこの曲には、個人史だけでなく、戦争の被害と加害の双方が折り重なるかたちで織り込まれている。日本社会が長く抱えてきた歴史的な問題を背景にしながら、「いろはうた」と現在を行き来する構成によって、過去と現在が絶えず往還するような時間の層がつくられている。そして物語は最終的に現在の“俺”へと収束し、個人の視点が歴史の積層に接続される。
BOSS:曲の最初は割と語り部的というか、少し外から見ている感じですよね。もし「大和魂見せろ」なんて言われたら、自分だったらどうするか。「僕と彼ら」という視点から始まって、それがどんどんストーリーになって、現代に近づいてくる。「田中角栄と周恩来」のところなんかは、ほぼ僕らの両親の世代のタイムラインで、もちろん僕はその次の世代なんだけど、昭和の時代であり、自分も何も考えていない子供だったとはいえ確かにそこにいた。当事者としての意識が高まっていって、最後は自分の問いに俺はうまく伝えられているだろうかと自身に問いかける。歴史が近づいてくると同時に、出来事が自分のものになっていくんです。
パーティーと「鎮魂」
BOSS:僕らのライブは、やっぱりパーティーです。そこでは、楽しければ楽しいほど、この楽しい時がその時にもゆっくりとだが失われていってるという悲しみ、哀しみも感じている。俺はそこにロマンを感じるし、それをどう今この時への没入として表現するかをがんばってもいるんです。そのライブの中で、特攻隊の死の描写がある「REQUIEM」をどこに入れるか、どういう心理状態であの曲にみんなを連れていくか、一音目のビートが入ってくるまでの間合いをどれくらい広げて、最後の「静ちゃんがんばれ」って言った後の静けさをどれくらいのものにするか、その後にどんな音を挟んできて、どんなメッセージを積み重ねて、どうやって終わるか、パーティーを楽しむという目的からはあまりに異質なこの曲をどうはめ込むかに苦心もしてる。
ライブで演奏されるとき、曲は場の空気や観客の状態とともに立ち上がる。どのタイミングに曲を置き、どのような流れのなかで受け渡すのか。その一つひとつをBOSSは、細心の注意を払って設計している。 こうして構築されたライブという生の場で、「REQUIEM」ではBOSSと観客が相互にどう交わり、どのような反応を呼び起こすのか。
BOSS:「REQUIEM」の時は、相互という意識はほぼないですね。他の曲に関しては、全部あると言っても過言じゃないんだけど。みんなが今どう思ってるかも大いに求めるし、レスポンスで僕自身も勇気をもらって、「よし」なんて言ってる。だからそこはとても大事にしてはいるんだけど、「REQUIEM」に関してだけは、ない。そこに自分の感情を挟むような、無粋なお客はいないですね。これはみんなで静かに聞くというか、俺ですら聞くという意識かもしれない。この曲は、タイトルのとおり鎮魂なのだから。
そういうことを大切にしてくれる、そういう理解のあるお客に出合えているのは、とてもありがたいことだと思っています。
体験者不在の時代――語られたこと、語られなかったこと
BOSSが語ったように、戦争について自身がそのとき感じたことや、日々の暮らしの中で触れた出来事を手がかりに言葉を紡いでいく姿勢は、戦争の直接体験者がいなくなりつつある時代において、表現が取りうるひとつの重要なかたちになっている。
BOSS:いよいよ戦争体験者がいなくなると言われ始めてから10年ぐらい経って、本当にその時が近づいてるなっていうのは色濃く感じてもいる。俺は昭和46年の戦後生まれで、「REQUIEM」の2番のような人生を観察しながら生きてきたから、昭和に対するノスタルジーはもちろんめちゃくちゃある。でも、人ってのは順にいなくなるし、それが時間の流れなんだから仕方のないことだとも思う。
「REQUIEM」を書いたのは、特攻隊のこともそうだけど、裏の大きなテーマは「黙って逃げ切った人に対する告発」でもあるんだよね。喋らないまま死んだ、でもやったことは自分で覚えてて、ずっと苦しんでた人達。あまりにもひどいことをやったから、自分の可愛い孫には言えない。ドン引きされるから。自分ひとりでその苦しみを背負って、死んでいった。
でも、自分のことを語ってくれた人たちもたくさんいた。勇気があった人達はいてくれた。新聞の投書ひとつでもそうだし、本でもそうだし、膨大に彼らの声が残されているから、資料としては十分なんだよ。もう大丈夫だよ。そこは生き残った人たちの中で、帰ってきた人たちの中で、自分たちのやったことや、自分たちの感じたことを残す役割は、もうあの世代は十分やった。だから、「うん、もういいよ」って思う。もう十分あるから、もう思い出さないでゆっくり休みなよって思う。
俺らの世代の読解力というのはまた別の話で、残されたものをどうするのかというのは考えていかなきゃいけない。でもあの人たちは、やるべきことはもうやったと思う。
楽曲を変容させるライブの時空間
戦争体験者不在の時代に向かうなかで、残された声や資料のアーカイブは確かに充実している。体験者の世代が残した膨大な記録を受け継ぎ、それをどう読み、どう現在に接続するのか。その読解を担うのは、戦争の非体験者である私たちの側だ。しかし、教科書や記念館に代表される「大文字の歴史」は、かつてあった出来事として時間的・空間的な距離を伴った理解へと収まりやすい側面がある。一方で、パフォーマーと観客が時間と空間を共有し、〈いま・ここ〉で表現が立ち上がるライブには、記録を読むのとはまた異なるかたちで、出来事を想起する瞬間がある。
BOSS:録音物はさ、その曲が作詞されて、作曲されて、レコーディングされた最初のテイクなんだよね。いちばん最初の完成品が永遠なものになってしまうところに、録音物の面白さや妙がある。でもライブっていうのはその曲をさ、練習やリハーサルも含めたら「REQUIEM」だけでも、もう100回も200回も歌ってるわけ。むしろそれは少ないほうで、「未来は俺等の手の中」ならもう多分何千回にもなるよね。いちばん最初の産声も最高なんだけど、楽曲として成長することで生まれるエネルギーもある。
だからライブのパフォーマンスと、レコーディングのものとは全然違うよね。録音物に対して「今だったらもっとうまくできるのに」って思うことって、誰にでもあると思う。でもそれはもうできない。基本やり直しはできない。ライブはライブで制約はあるんだけど、楽曲が成長していくという面白さがそこにはあると思う。
楽曲自体のことだけじゃなくて、時代にも関係してくるしね。「未来は俺等の手の中」というメッセージひとつとったって、上がっていく時の国と下がっていく時の国には全然違うわけだし。それは一人ひとり、人にもそれぞれ毎日あるじゃないですか。だからこそ、ライブというものは面白いんだと思ってる。
おわりに
BOSSへのインタビューでは、「64 Bars of Mind」と「REQUIEM」という二つの楽曲を手がかりに、ラップという形式でBOSSが戦争をどのように表現してきたのかを話してもらった。前者では、ガザ侵攻という出来事に対して、日常の延長線上から反射的に言葉が立ち上がっていた。後者では、特攻隊の手紙や数多くの戦争体験の話を長い時間をかけて熟慮し、被害と加害、個人史と社会の歴史を折り重ねるように編み上げていく。いずれにおいてもBOSSは、「決定的な答え」を見せるのではなく、聴き手それぞれの思考と感情を喚起するものとして、会話の感覚に沿うようにラップしている。
戦争体験者が去りゆく現在、BOSSが言うように、証言や記録という意味ではすでに膨大な資料が残されている。問題は、それらをどう読み、どのように〈いま・ここ〉の自分たちの現実に接続し直すのかという点に移りつつある。「世の中の抑圧された側から立ち上がる音楽」としてのヒップホップに身を置き、表現の土壌とするBOSSは、特攻隊の手紙に「名誉ある死」ではない別の声を聞き取り、その行間に潜む言えなかった思いを汲み上げようとする。そこには、国家の物語のなかで整理されてしまいがちな戦争を、ひとりの人間の問題、供養と鎮魂の問題として引き寄せ直すまなざしがある。
そして、楽曲はライブの時空間のなかで変容していく。「パーティー」であるはずのライブの流れの中に、「REQUIEM」という鎮魂の曲をどのタイミングで置き、どのような間合いで静けさを引き寄せるのか。BOSSはそれを慎重に設計しつつ、「REQUIEM」に限っては観客との相互行為をあえて切り離す、鎮魂の場として成立させている。そこには、教科書や記念式典とは異なる仕方で、死者へのまなざしと戦争の記憶が共有される、現代の「追悼」の形が見えてくる。
戦争の歌をめぐる議論はしばしば、「どの立場からのメッセージか」「どこまで政治的に踏み込むか」といった対立の構図に回収されやすい。けれどBOSSのラップが示しているのは、そうした大きな枠組みからは零れ落ちる、戦中の感情の揺らぎや逡巡、言いよどみや抑制のような微細な動きを、そのまま言葉として差し出すことの力だ。そこでは、戦争は特別なときだけ語られる遠い出来事ではなく、パーティーの一瞬や日々の生活の中で、不意にこちら側へせり出してくる。 日本語ラップが開くのは、ラッパーの身体を通してこうした「ふとした想起」が共有されて、各々が自分の言葉で考え続けるための場所なんじゃないか。
「64 Bars of Mind」に登場する、
「北じゃ秋を迎える度に全て見違える 秋に死んだあいつの思い出が生き返る」
「パーティーの朝方 空から降りてきたゲリラ」
といった一節は、一瞬の風景から個人的な記憶が甦る描写と戦争の記憶が地続きになり、日常の感覚と現在進行形の戦争が、ひとつの地平で結びつく瞬間を表している。直接体験していない戦争が、生活の中でふと姿を現す。このような想起のあり方こそ、「日本語ラップと戦争」が持ちうる可能性のひとつなのだと思う。
ILL-BOSSTINO(イル・ボスティーノ)PROFILE
1971年北海道生まれのヒップホップMC。1997年にトラックメイカーのO.N.Oと「THA BLUE HERB」を結成し、1998年に1stアルバム『STILLING, STILL DREAMING』を発表。自身のレーベル「THA BLUE HERB RECORDINGS」を運営し、THA BLUE HERBとして精力的な活動を続けるとともに、グループ、ソロでさまざまなプロジェクトを展開。2015年にはソロ・プロジェクト“tha BOSS”としてアルバム『IN THE NAME OF HIPHOP』を発表。2023年に『IN THE NAME OF HIPHOP II』をリリース。
文献
Mosse, George, 1990, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford University Press.(= 宮武実智子訳、2002『英霊――創られた世界大戦の記憶』柏書房)
ディスコグラフィ
THA BLUE HERB 、1998、「THIS ’98」、アルバム『STILLING, STILL DREAMING』収録、THA BLUE HERB RECORDINGS.
tha BOSS、2023、「64 Bars of Mind」、THA BLUE HERB RECORDINGS.
THA BLUE HERB 、2019、「REQUIEM」、アルバム『THA BLUE HERB』収録、THA BLUE HERB RECORDINGS.
- Red Bullが開設したジャパニーズ・ヒップホップ専門のYouTubeチャンネル「レッドブルマイク」で展開されているシリーズ。毎回一人のラッパーが登場し、一発撮りで64小節をラップする企画である。
- BOSSによると、この楽曲に登場する「祖父の戦争体験」は、BOSSが実際に祖父から話を聞いたわけではなく、これまでの人生のなかで触れてきた新聞の投書やさまざまな証言、社会に蓄積された語りの断片が積み重なり、その総体として立ち上がった“イマジネーションとしての祖父”が、あの物語の源になっているという。