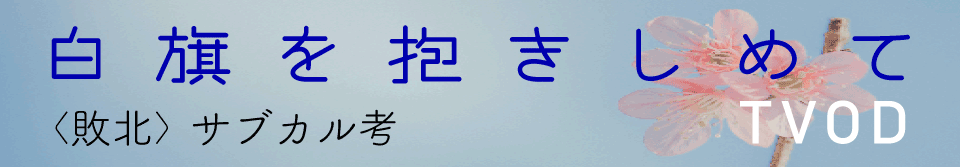勝ち組を夢見ない
こんにちは。12月に入り、いよいよ寒くなりましたね。今年は延々と長く続いた暑さから突然冬に急降下するような気候で、秋の日をほとんど味わえなかったのがとても残念です……。
さて、今回は「白旗を抱きしめて」と銘打って、サブカルチャーと「敗北」という問題について、ぼくたちなりに考えようとしています。何故いま現在2023年において、わざわざ「敗北」というテーマについて、それもサブカルチャーを通して考えるのか。そしてそもそもぼくとパンスくんふたりの間で、「敗北」というものの捉え方や考え方について、恐らくかなりの距離・違いがあるでしょう。これからこうして手紙をやりとりするような形でこのテーマを話していければと思うのですが、まずはぼくが「敗北」について考えていることを、書いてみます。
2000年代に入る頃から、「勝ち組・負け組」という言葉をよく聞くようになった記憶があります。ぼくもパンス君も同じ1984年生まれですが、ぼくらが大学生になった2000年代中頃には既に、この言葉は世間に溢れかえっていたように思います。もともとは第二次世界大戦終結時、海外在住日系人のなかで日本の敗戦を信じない人を「勝ち組」、信じる人を「負け組」と呼称したことがこの言葉の起源だそうですが、2000年代当時は単純に、格差社会化が進行するなかでの経済的強者が「勝ち組」、弱者が「負け組」と呼ばれていました。
また少しニュアンスは異なりますが、2003年には酒井順子『負け犬の遠吠え』がベストセラーになりました。どんなに美人で仕事ができても、30代以上・未婚・子ナシは「女の負け犬」である、とするこの本は、その「負け犬」当事者である著者が、現代女性の生き方をユーモアを込めて批評的に描いたエッセイでした。そして文庫版の解説で林真理子が指摘しているように、酒井が描写する「負け犬」そして「勝ち犬」(「普通に結婚して子供を産んでいる人達のこと」とされています)はどちらも、「都会のごく一部の恵まれた層」の人々に限られることが特徴です。いわば、「勝ち組」として生きる女性たちのなかにある立場や生き方、生態の違いを観察したのが、『負け犬の遠吠え』だったと思います。何にせよ、この時期に「勝ち負け」みたいな言葉がそれまで以上に世間に流通しがちになった印象が、自分にはやはりあります。

『負け犬の遠吠え』酒井順子、講談社文庫。単行本は2003年発売
では当時の自分が「勝ち負け」についてどう考えていたかを思い返すと、「勝つ」ということに重要性を感じることができない、正直そこに興味を持てていなかったような気がします。高校生の頃、友人が「とりあえずどこか有名企業に入社できれば、人生安泰なのにな」と言っているのを聞いたとき、「そういう『勝ち組』的な人生を目指すのは、つまらないから嫌だな……」と思ったことをよく憶えています。そしてそれをその友人に直接言えなかったことも、よく憶えています。黙ってなんとなくやり過ごしてしまいました。
その頃にはぼくは既にさまざまなサブカルチャーに夢中になっていて(なかでもそのとき自分が一番思い入れていたのは、中古レコード屋で掘り返していたP-MODELや有頂天等の、80年代の日本のテクノポップバンドたちの音楽でした。有頂天のボーカル・KERAは、自ら主宰していたナゴムレコードがリリースしていた諸バンドの音楽は、弱者のための表現としてあったと思う、という趣旨の発言をしています)、それらの表現や作品たちが、金や仕事や結婚で「勝ち組」になることよりももっと大事なもの、もっと面白いものが世界にはあると言っているように、自分には思えていました。そこには「勝ち負け」みたいな土俵に乗らない世界観の提示だったり、また「負けること」そのものを深くとらえてみようとするような表現だったり、そういった諸々の試行錯誤があるように感じていました。もちろん、いわゆる中流家庭で育ち貧困を知らなかったからこそ、そういう風に甘っちょろくあれこれ考えながら学生時代を過ごせていたということでもあります。有名企業で人生安泰、という選択を切実に望まざるを得ない事情というのも、世のなかにはあります。
オルタナティブの模索と、「買う」という行為
しかしとりあえず、2000年代に入る頃の自分にとってサブカルチャーは、「勝つ」こととは違う世界の可能性を開いてくれるものだったわけです。
そしてここで少し話を迂回して、参照してみたい本があります。1997年に発行された『オルタカルチャー日本版』です。当時のオルタナティブな文化事象を羅列したこの本の編集後記で編集者の穂原俊二は、「原稿が集まって、俯瞰して読んでみると、やはりある動向が見えてきます。特にエッセイを書いていただいた方々の原稿は、特にお互い打ち合わせしたわけでないにもかかわらず、不思議とどれもどこか通底したものがあります。それは、あえて言葉にはしませんが、ひとつだけいえば、当たり前ですが、もう80年代じゃない、ということでしょうか」と書いています。

『オルタカルチャー日本版』メディアワークス
97年の本の編集後記に、「もう80年代じゃない」と書かれている。本書では、70年代日本におけるアメリカン・サブカルチャーの直輸入作業が「イデオロギーとしてあった左翼=資本主義否定に対するさわやかなカウンター、つまり都市生活や商品世界を享受することを肯定してもいいじゃないか」というようなムーブメントとして機能し、しかしそれが80年代の大消費時代に至って消費=「買う」という行為ばかりに短絡・閉塞していったことが指摘されています。そしてその象徴として挙げられているのは、「より良く面白く生きるために『使う』情報を提供していたはずの『全都市カタログ』が、なぜか『買う』情報一色の『ポパイ』のような雑誌になっていったこと」、です(『全都市カタログ』とは、1968年に創刊されたヒッピー向けの雑誌『ホール・アース・カタログ』を模して1976年に発行された、『別冊宝島』第1号のこと)。

『全都市カタログ』宝島社
「イデオロギーとしてあった左翼=資本主義否定」においては、資本主義社会において経済的な「勝ち組」になること自体が否定されます(当たり前ですが)。しかしそういう教条的かつ抑圧的な左翼の硬直性を解体するため「都市生活や商品世界を享受することを肯定」しようとした70年代が、消費=「買う」ことだけに短絡される80年代を準備してしまう。「より良く面白く生きる」ことのために資本主義にすら可能性を見出そうとしていた態度=サブカルチャーが、結果的に資本主義の全面化を後押しするアイテムや構造そのものになってしまう。先述したように、「『勝ち組』になることよりももっと大事なもの、もっと面白いものが世界にはある」とサブカルチャーが言っているように若かった自分には思えていましたが、しかし80年代以降のサブカルチャーの世界というのは、「買う」力=「勝ち組」的な経済力を持つ人間こそが謳歌できる世界としての側面を強く持ってもいたのでした。
『オルタカルチャー日本版』は、そうした「消費」に閉塞した文化状況に対して、当時普及し始めていたインターネットによる環境変化も含めて、ようやく顕在化し始めた更にオルタナティヴな何かを模索しようとした本だったと思います(「もう80年代じゃない」)。しかしこの後IT時代の寵児として堀江貴文のような存在が頭角を顕し、更に「勝ち組・負け組」的な世界観が世間において前景化していったことに、皮肉な歴史を感じたりもします。
「多様性」の水面下にあるもの
こうしたプロセスを踏まえて辿り着いたいま現在2023年の状況を考えてみると、少なくとも文化的には、2000年代のころよりは(あくまで、そのころよりは)一定の多様化が進んだようには感じます。恋愛市場・結婚市場で「勝ち組」になれない/ならないのを恥ずかしいこととするような社会的プレッシャーは、相対的には減じている。「誰もが必ず異性間恋愛に基づいた人生設計をしなければならない」というようなロマンティック・ラブ・イデオロギーの専制機能は、かつてよりは恐らく一応衰弱している。サブカルチャーにおいても80年代的な消費主義=差異やブランドに価値を持たせるカタログ文化的な構造は、過去のものになりました。ネットの発展によって中央集権的な情報環境はどんどん分散化され、例えば音楽ひとつとっても、かつては中古レコード屋が密集する都市部に住んでいなければ難しかったような視聴体験が、ウェブを通して多くの人に、安価かつ手軽な形で開かれました。コミュニケーションや文化体験の水位では、自分が勝っているのか負けているのかを意識させるようなメッセージやプレッシャーが、表面的には減っているかもしれません。2000年代当時よりも、「勝ち組・負け組」という表現を聞く機会そのものが少なくなったような気もします。
ただ自分には、そうした状況の後ろ側で、「勝ち組・負け組」的な世界観・世界像というものが実は再強化され続けているのではないか、という疑問があります。格差社会というものが当たり前の前提となって久しく、消費やコミュニケーションに対する考え方の多様化自体は少しずつ進む一方で、自分が生まれ持った経済環境や制限・事情をひっくり返すような自由の可能性を信じることは、この社会では以前よりもむしろ難しくなっているように思います。モノを「買う」力や恋愛市場における資本力を持たない「負け組」であることを、変えようのない所与のものとして受け入れざるを得ない層が、増え続けているように感じます。サブカルチャーにおけるカタログ主義の消失にも、情報環境や生産体制の変化と同じぐらいに、ユーザー側の経済力の衰弱というものもそれなりに大きく作用しているはずです。
ただ、ぼくは今ここで、「だから『勝つ』ことを改めて意識するべきだ」という話をしたいわけではありません。そういうレベルの問題においては、自分だけが金やコミュニケーションにおける強者になることを目指すより、格差社会構造そのものを変えられるよう、社会や政治に対するコミットを自分なりに少しずつ続けて行くしかないように思います。ぼくがいま考えたいのは、サブカルチャーには「勝ち負け」の構造そのものを解体するような思考を広く届けたり、「敗北」することそのものを深く捉えていくような力があったのではないか、そのことをもう一度理解することで、変えようの無い格差構造の上で消費選択肢やエスケープ先ばかりが増えていく現状での思考とは異なる、何か別の形での捉え直し作業ができるのではないか、ということです。「負ける」ことを甘美に捉えたり、勝ち目がなくともともかくファイティング・ポーズをとっていればいいんだ、というような敗北主義的な思考を称揚したりしたいわけではなく、人生や社会には「負ける」場面というのはやはりあり、そしてそもそも「勝ち負け」という基準そのものを取っ払うような思考が必要な場面というものもやはりあるという当たり前のことを、「多様化」という言葉の水面下から引っ張り出して考え直してみたい、という気持ちが、自分にはあります。
ということで、初回はこのあたりで筆をおきたいと思います。お返事楽しみにしています。では!
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。