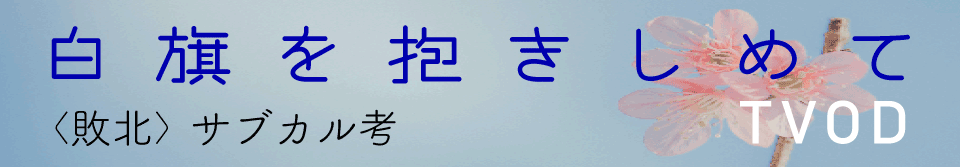第7回は公開終了いたしました。
TVOD(TVOD)
コメカ(早春書店店主 @comecaML)とパンス(@panparth)による批評ユニット。 「サブカルチャーと社会・政治を同時に語る」活動を、様々な媒体にて展開中。著書に『ポスト・サブカル焼け跡派』(百万年書房)、『政治家失言クロニクル』(Pヴァイン)がある。
- 第1回「敗北」について──コメカより
- 第2回「敗北」表現の源泉――パンスより※公開終了
- 第3回錯綜する世界のなかで「負ける」こと――コメカより※公開終了
- 第4回政治から遠く離れて、カウンターカルチャーを考える――パンスより※公開終了
- 第5回「やせ我慢」の精神――コメカより※公開終了
- 第6回ちいさなラディカリズムーーパンスより※公開終了
- 第7回「かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう」を再検討するーーコメカより※公開終了
- 第8回負けから始まるーーパンスより※公開終了
- 第9回ベランダ立って胸をはれーーコメカより※公開終了
- 第10回戦後という「デカい話」――パンスより※公開終了
- 第11回九条という「やせ我慢」――コメカより
- 第12回バズをあきらめて2025――パンスより