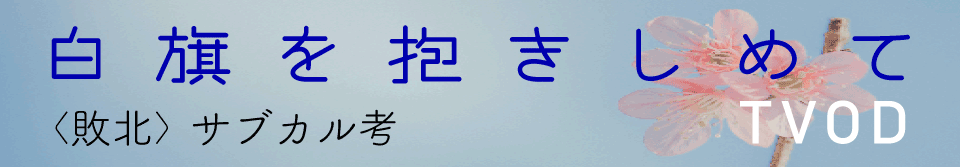SNSの現在地
私が書いた前回の原稿の日付を確認してみたら、9月でした。それから現在にかけて、世界情勢があまりにも変わっていて、自分の中でいろいろと仕切り直したいような気分になっています。
いや、より正直に言うならば、何を書いたら良いのかよくわからなくなっています。これはこの原稿に限らず、SNSでちょっと呟く程度の行為においても同様です。日々流れてくる情報の量に追いつけないし、追いつけないなりに思考をめぐらせているのですが、どれも的を外しているような気がしてうまくアウトプットできません。さらに、何を書いても、意見が変にハレーションを起こしてしまうのではないかと不安になって、尻込みしてしまいます。
いや、私のような弱小アカウントが何を書こうが、炎上したり批判がバンバン飛んできたりするようなことはないので、元来臆病な性格ゆえのしょうもない心配であることは百も承知なのですが……。
と弱音を吐きつつ、どうにか書き進めていくことにします。思いついたことからどんどん書いていきます。
まず、最近の悩みについてです。第二次トランプ政権開始以降、ツイッターを開くと「バンスは最悪」「バンスの発言は許せない」などといった文言をちょくちょく見かけて、そのたびに、パンスの悪口が書かれていると見間違えて動揺してしまいます。冗談半分で人に話すのですが、実際少しダメージを受けるのでつらいです。いまだに慣れません。できれば「ヴァンス」表記にしてもらえるとありがたいですね……。
我ながらどれだけ臆病な性格なのかとあきれますが、実際めちゃくちゃ名指しで攻撃を受けまくりながら対抗している人って強すぎると思います。とてつもない金や権力を持っている人なら平気なのかもしれませんが、現状の自分には絶対無理です。対抗して勝つ気にもなれないし、対決する気力もない。
そんな私ですが、SNS上における「勝ち/負け」について改めて考えています。日々多くのレスバが流れてきますが、レスバにおいて明確な「勝ち/負け」という概念は存在しません。だいたいどちら側も勝利宣言して、それぞれの仲間が「うちの仲間が勝っているな」と認識して終わることが多いです。これは、勝ってはいないけど負けてもいない、ということなのでしょう。
SNS上においては仲間という概念も大きいと思います。例えば政治家が対立する政治家にちょっとありえないようなレスをすることは日常茶飯事ですが、それは自分を応援してくれる仲間の存在を認識しているからでしょう。「徒党を組んでいる」という意識があるのです。政治家としてその発言はアウトだろうという職業倫理をたやすく超えてしまうのは、長期的に見たらリスクでしかないので、結果的にそれは「勝ち」とは言えませんが、その場でのパフォーマンスの方が優先されてしまいます。
「勝つ」というよりは「勝ち馬に乗る」という感覚も普及しています。ある問題が起こったら、その時点で大勢を占めている側に乗っかると、より多くの共感を得やすいです。そういった事象が毎日のように現れるので、乗っかっている人を眺めていると、「いや、それ前に乗っていた意見と矛盾しているのでは?」と思うこともありますが、もうそんな一貫性などはどうでも良いのかもしれません。かつてなく集団性が高まっているように感じますし、その上には理念のようなものが備え付けられていますが、割と付け替え可能なようです。
サブカル以降の「敗北」
このような時代において「敗北」を意識することはとても難しいです。かつては「敗北の美学」のようなものがありましたが、現在はそもそも負けるきっかけが希薄になっています。
ここで「やせ我慢」の話につなげたいのですが、実は、かなり返答に悩んでいます。
「敗北」については太平洋戦争の「敗北」という歴史的事実なので理解できますが、「やせ我慢」についてはよくわからない。「敗北と『やせ我慢』をその中心に抱え込んでいたはずの戦後民主主義的感性」とあるのですが、それは一体どういうものなのでしょうか。かなり私の歴史認識と異なっているので、私が理解できないだけなのかもしれないのですが……。
また、「『乗れない奴は遅れている』という勝負に負けること=遅れていくこと自体を含みこんだ戦後民主主義的感性」という定義もあり、これも具体的にはどのようなものを指しているのかが気になります。
「ぼく自身のなかにもおそらく、殺される前に殺せ、というような感性がある。それを如何に『やせ我慢』するか」とあるので、「我慢」しているのは、暴力衝動のようなものでしょうか。戦後という歴史に当てはめるならば、敗戦によって一旦徹底的に排除が試みられた、帝国主義的な拡張志向、封建的な制度、好戦的な感性があり、それらを捨て去って丸腰の状態で「やせ我慢」しなければならない状態に置くことこそが、戦後民主主義なのだということでしょうか。
「九条」というテーマが出てきているので、私の認識について、ざっと書いてみます。
戦後の政治体制における「九条」との距離感で大雑把に分けると、左派が「非武装中立」を目指す路線で、右派が「日米安保」を遵守するって構図になっていて、現実的には日米安保を保持しながら理想論として非武装中立があるみたいな状態でした。ただ、特にゼロ年代以降に改憲論の勢いがついてきて、非武装中立の立場は悪くなってくる。そんな中、確か大塚英志が『新現実』などでリバイバルを唱えていたような記憶があります。「九条の会」もこの頃だし、中沢新一と太田光の『憲法九条を世界遺産に』って本もありました。
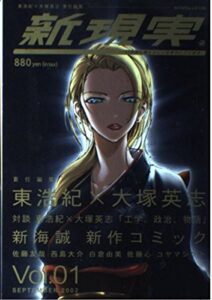
『新現実 Vol.1』 (カドカワムック 156)角川書店

太田 光・中沢 新一『憲法九条を世界遺産に』 集英社新書
ゼロ年代に展開されていた上記のような議論を参照すると、九条を「やせ我慢」のように捉えることもできなくはないかな、と思いますが、「世界遺産」などに比べるとかなり後ろ向きな表現になっているのは興味深いです。トランプ政権はこの2ヶ月くらいで日米安保すら危うくしているので、そのような(戦後体制から見れば)危機的状況においては後ろ向きになるのも無理はないですが……。
そんなわけで悩んでいたのですが、ここに「アメリカ」って存在を入れれば、少し見通しが良くなるかもしれません。
先日、川村湊『戦後文学を問う』を読み返していましたが、本書の中でも「アメリカ」は重要な位置を占めています。敗戦後、アメリカは日本文化に対しても大きな影響を及ぼしていましたが、その後数十年間、その受容は緊張感の中にありました。自国を占領してきた憎しみの対象でありながら、魅力的なコンテンツを大量生産する国であったわけです。
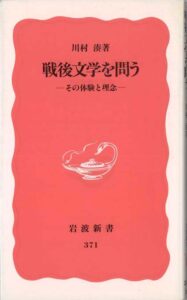
川村湊『戦後文学を問う:その体験と理念』岩波新書
それから30年ほど経ち、最近では反米を訴えるとロシア派や陰謀論者のように扱われるようになってしまいました。そして、特に21世紀以降、アメリカは何となくリベラルで、正義を行使する国であって、見習わなければいけない対象として捉えられるようになりました(アメリカのリバイバルとでも言うべきでしょうか)。
しかしアメリカのトップがトランプになり、権威主義国家の仲間入りをしようとしている今、事態はさらにややこしくなっています。
「サブカル」以降の「敗北」とはどんなものだったか、明確にしていくのが良さそうです。ここでSNSの風景に戻って、国内で盛んな対立に目を向けてみると、話題になるのは主に、男女の対立、世代間闘争、都市と地方の格差などが挙げられます。ここに「勝ち/負け」を見出して論争が繰り広げられているわけですが、前回のコメカ君の原稿を読むと、「B’z論争」を挙げるなど、すでに決着が付いていそうな「センス」の対立にこだわっているのが見受けられ、興味深いです。コメカ君のスタンス的にはすでに「勝って」いるにも関わらず、違和感を持ち続けている。
それは要するに、権威主義についてはまだ残存しているじゃないか、って指摘だと思うのですが、では、その権威は解除できるのか。「自由に至るための道筋」とは何なのか。この辺りについて、より詳しく伺ってみたいですね。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。