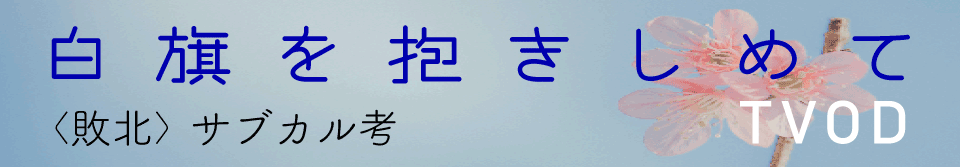「ステイタス」競争から逃げ出したい
前回パンス君が書いてくれたように、カルチャーにおける「センス」の問題、そして権威主義の問題について、たしかにぼくはやたら固執しているところがあります。『STATUS AND CULTURE』でデーヴィッド・マークスは、美的判断の基準=「センス」について、現代の「みんな違ってみんないい」的なオムニヴォリズムが、いわゆる「良いセンス」を否定する、としています。しかし、かつての時代の「良いセンス」が否定されたとて、「社会における各個人の重要度を示す非公式な指標」=「ステイタス」による人々の階級化までもが解消されるわけではない。「ステイタス」の完全廃絶はそもそも不可能であり、オムニヴォリズム以降の世界では結果的に、文化資本よりも経済資本ばかりが「ステイタス」階級について力を持つ(かつては品の無いものとして見られていたような過度の衒示的消費ばかりが現代の「良いセンス」として機能し、「ステイタス」に作用する)現状が出来上がってしまった、というのが彼の見方です。その上で、社会的に「ステイタス」が公平に配分されるようにすること・複雑な記号性を持つカルチャー創造を促進すること、が彼が提示する解決案であるわけですが、そもそもぼくはこの「ステイタス」による階級化という(避けがたい)プロセスそのものが、昔からとにかく苦痛なんです。
マークスによれば、文化体験そのものが「ステイタス」という概念抜きには成立し得ないものであり、恐らくその通りだろうという実感は自分にもあります。ただ、文化を「個人的」に体験したい・「ステイタス」競争から逃げ出したいという気持ちが、ぼくにはどうしてもあるわけです。マークスが「オムニヴォア的センスは超個人主義の先駆けでもある」と言うように、階級化プロセスから離れ、「個人的」に文化に触れようとするような態度と、現在のオムニヴォリズム的状況はたしかに一見相性が良い。しかしパンス君が言うように、ぼくが「権威主義についてはまだ残存しているじゃないかって指摘」にいまだにこだわっているのは、自分は(マークスによれば不可能であるはずの)「ステイタス」の完全廃絶までをも欲望してしまっている、ということなんだろうと思います。スタイルウォーズの勝ち組が文化的権威を誇っていた20世紀末より、経済資本を見せびらかす下品な勝ち組が権威として君臨する現在の「文化的多元化」状況の方が、正直言って自分にとっては更に不愉快なわけで、権威主義という観点から言えば状況は悪化しているとすら思う。「ステイタス」階級における権威性、ひいてはそれを生み出す勝ち負けのゲームそのものから抜け出したい。がしかし、ぼくは革命によってそういうゲームや体制をひっくり返そうとしているわけでもない。言ってしまえばこれは脱社会的というか引きこもり的な欲望で、ある種の「おたく」性であると言えるのかもしれない。「やせ我慢」みたいなことを言いつつ、実は脱社会的な欲望も自分のなかにはある。カルチャー周りの諸々に対するぼくの権威主義嫌悪・批判というのは、社会に対する引きこもり的感性とどこかで繋がっている気がするわけです。いかなる権威も「ステイタス」階級も存在しない社会というのは、それはもう社会とは言えないのかもしれない……というか、言えないでしょう。私たちはどうしても、権威や階級が、それらが呼び起こす「勝ち負け」のゲームが存在する社会のなかを、生身で生きていかざるを得ない。
自らの「渡世」を生きる
ところで先日、賈樟柯の『長江哀歌』(2006)を観ました。この映画では、国家プロジェクトとしての三峡ダム建設のために移住を余儀なくされる人々と、山西省から来た一人の男・一人の女についての物語が語られるわけですが、登場人物たちは皆、歴史の流れ、経済的苦境、そして政治権力・権威の強大さに対して、表向きにはなすすべがない不自由な状況にあります。しかしそのなかに見え隠れする、人びとの生活のなかにある逞しさ・力強さ、そして風が通り抜けるような一瞬(だけ)の解放の感覚が、この映画の魅力だと自分は思います。苦しい日常生活のなかをどうにか生き抜く人々が、それでも人間としての尊厳を持ち続けようとする姿を描くという点で、本連載でぼくが取り上げた山田太一の作家性にも近いところが、賈の作品世界にはあるようにも感じます。
ちなみに彼は著書のなかで、こんなことを語っています。
「九〇年代以後、中国に突然思想の多元化、価値の多元化の時代がやって来ました。この時代の中で、かれら(引用者註:中国第五世代の映画監督たち)の創作は迷走を始めました。かれらは外側にある主流の価値から何かを探し出し頼みとすることができなかった。なぜなら、主流の価値はもとより分裂し矛盾しているものであり、パラドキシカルなものであったから。そこへ一つの主流の価値が出現しました。すなわち商業、そして商業は英雄へと変じました。社会全体が経済活動に邁進し、経済生活が中国人の唯一の生活、最重要の生活になりました。国家から個人まで、経済活動が天下を束ね、文化活動、思想活動は完全に周縁化されました」(『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』)

賈樟柯 著、丸川哲史・佐藤賢 訳『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』 (以文社)
中国第六世代の監督として、第五世代の監督たちの多くが「商業論理の奴隷」に、しかも行政と結託する形でなってしまったことを批判した発言ですが、思想・価値基準の多元化(1990年代中国のそのような多元化、そして「社会主義市場体制」には、もちろん固有の・独特の事情があったわけですが)の先に、結果的に経済力の専制状況が来るという流れにおいて、『STATUS AND CULTURE』で語られていたことと構図が似ています。賈樟柯はそのような「商業論理の奴隷」になることを否定し、「映画は自由を探し求める方法であり、また中国人が自由を探し求める方法でもあります」(『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』)と語りますが、しかし賈の映画作品そのものは、はっきりとわかりやすく自由や解放を描いているわけではない。むしろ、彼の言葉でいう「渡世」=社会のなかで生活し、働き、他人との関係性のなかで生きていくことの嫌さ・辛さや、そこにある人間の一生懸命さを、賈樟柯の映画は独特のグルーヴ感で描いていく。そこには現代中国の政治的な制約・限界の問題以上に、何か自由というものの本質的な問題に絡んでいく側面があるように、自分には感じられます。そのような「渡世」に、大きな時代の流れのなかに、政治権力の圧力のなかに、内在して生きるしかない私たちの限界の生活(そこでは、「やせ我慢」をするしかない場面も多々あるでしょう)の奥底にこそむしろ、何か本当の意味での自由へのきっかけが眠っているのではないか。権威主義体制の圧力に対して、利己主義ではなく個人主義的な在り方=「ひとり」としての在り方を、自分のどこかに保持し続けるためのきっかけが、眠っているのではないか。賈樟柯の作品を観ていると、そのような気持ちが自分のなかに湧いてきます。
また彼は、こんなことも書いています。
「わたしは、映画の中の人物を人間関係の中だけではなく、社会の外、あるいは自然に置くようになりました。服は人間のある種内心の表情であるだけではなく、我々の皮膚にはりついている膜でもあり、人間の階層の標識でもあります。しかし、我々は裸になった時、階級の区別などない、ただ人間の美しさと肉体の平等があるだけです」(『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』)
ステイタスによる階級化というプロセスを苦痛に感じてきた自分には、この感覚が非常によくわかる気がする。脱社会的なレベルでの、「ただそこにある」ような人間を、身体を、描くこと(それは映画という表現メディアこそができることだと思います)。賈樟柯の作品では、人間が「渡世」を生きる姿と「社会の外」にある人間身体そのものの姿と、そのどちらもが描かれているように感じられて、ぼくはそこに強く惹かれます。前者は「負け」も含みこんだ「嫌な生活」の在り様として、後者は「社会の外」(それは勝ち負けのゲームの外側でもあります)に置かれた「人間の美しさと肉体の平等」として。我々人間の生の現実というものは、まさにそのような両面から成り立っているのではないかという気がしてくる。権威や「ステイタス」階級のなかでしか生きようがない「生活」と、その外側にある「人間の美しさと肉体の平等」。その両面を描くことで、「ひとり」の人間の在り様が、まざまざと立ち現れてくる。そこにこそ「自由を探し求める方法」があるのではないかと思えてくる。権威も階級も無い「社会の外」へ思いを馳せながら、しかし現実の「嫌な生活」を「やせ我慢」しつつ内在的に生きること。そのプロセスのなかで、「自由を探し求める方法」を模索し続けること。
浦部法穂は「「すべて国民は、個人として尊重される」とする憲法13条に示された「個人の尊重」原理こそ日本国憲法の最も根底にある原理だということは、これまで私は折に触れ言ってきた」(憲法の言葉シリーズ⑤「個人」 | 発信記事 | 法学館憲法研究所)と語っていますが、この13条に顕わされた個人の尊重や、九条の武力放棄などは、この憲法が生まれた経緯にさまざまな事情があったにせよ、その言葉そのものを正面から読めば、やはり現実に対して「やせ我慢」してでも理想を掲げる意志を感じさせるものであるように、自分には思えます。そして、現実の「嫌な生活」のなかを生きるとき、「ひとり」であることを諦めないために、13条の個人の尊重や、九条の武力放棄のような志向を、じぶんの生活の実践のなかに織り込んでいきたいとぼくは思っているんです。それは「殺される前に殺せ」というような感性からではない生き方を試みてみようということでもあるつもりです。そこで「我慢」するのは、暴力衝動のようなものももちろんそうですが、相手を「論破」しようとするようなマウンティング感覚だったり、よりメタレベルを確保しようとするような卓越競争の感覚だったり、自らのプライドや自負に強く固執することだったり、そういう諸々も含めてです。現代における「勝ち」とは、そのように相手を言い負かし、「論破」する感覚に依拠している部分も非常に大きくあるはずです。
賈樟柯が言うように、どんな時代のどんな国の人間も、それぞれに自らの「渡世」を生きるしかない。しかし彼がまた言うように、「どんな状況においても、人は尊厳を保持し、また生き延びるためのポジティブな力を保持しようとする」(『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』)。ぼくにとってはこの「尊厳を保持し、また生き延びるためのポジティブな力を保持しようとする」ことを、どんな状況下においても諦めないようにすることが、「自由に至るための道筋」です。権威は解除できない。現実の「渡世」(大抵の人間はそこで「負け」てしまう)からは逃げられない。しかしそのなかで人間の尊厳や生き延びるためのポジティブな力を保持しようと努力し続けることはできる。そして、「階級の区別などない、ただ人間の美しさと肉体の平等があるだけ」の、「社会の外」に思いを馳せ続けることもできる。そうした意志は、「勝ち」を志向することではなく、むしろ「負け」のなかにある生を「やせ我慢」しながら見つめることから生まれてくるはずだ。『長江哀歌』はぼくにとってそのようなことを改めて実感させてくれる作品だったわけですが、自分が「敗北」という観点からサブカルチャー表現に求めているのは、つまりこのようなことです。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。