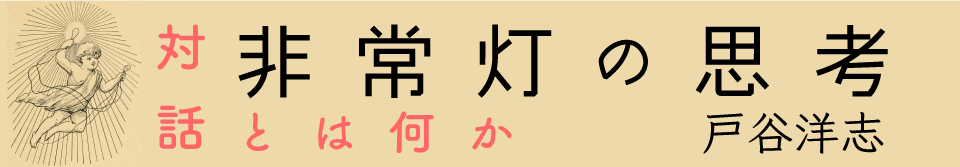私たちは普通、何を話すかを考えてから、それについて対話すると思っている。思考は対話に先行する。対話は思考を必要とするが、思考は対話を必要としない──それが対話と思考に関する常識的な理解だ。
しかし、アーレントはこの順序を逆転させる。彼女によれば、むしろ、思考こそが対話を必要とする。私たちは、対話をした後で初めて思考する。対話が可能ではないときに思考を開始することもまた不可能である。そのように考えた点に、彼女の思想の独自性がある。
ただし、前回、私たちが検討したように、彼女は主著『人間の条件』のなかで、十分に理論化された形では提示していない。むしろ、対話と思考をめぐる彼女の思想は、その理論の体系性を崩すものですらある。
それでも、彼女に対話と思考について考えさせたのは、自らが直面した全体主義の脅威であったに違いない。前々回、私たちはアイヒマンに対する彼女の分析から、責任をめぐる問題の中で、その思想に着手したのだった。彼女はそこに「悪の陳腐さ」という新たな悪の形態を洞察した。しかし、興味深いことに、そうした悪のあり方を、アイヒマンという個人にだけ帰属させるのではなく、もっと広く、当時の支配体制を支えたすべての人々にまで拡大させている。
今回は、そうした全体主義的な支配体制において、思考と対話がどのように影響され、そして掘り崩されていったのかを、眺めてみよう。
ナチスドイツはおよそ六〇〇万人のユダヤ人を虐殺した。前々回述べた通り、それを可能にしたのは、極めて合理的かつ効率的に設計された輸送網である。その責任者がアイヒマンだった。しかし、それだけでこのような途方もない規模の虐殺が可能になったわけではない。それ以上に重要だったのは、ユダヤ人を現場で強制連行するための組織化された警察機構である。
そうした機能を担っていたのは、ゲシュタポと呼ばれる秘密警察だった。ただし、いわゆる「ユダヤ人問題の最終的解決」を遂行するためには、ゲシュタポのリソースには量的にも質的にも限界があった。そのため、ゲシュタポは独力でユダヤ人を強制連行するのではなく、広く住民からの密告に頼ることにした。つまり、「あそこにユダヤ人が住んでいる」「あの人はユダヤ人と友達である」といった通報によって、強制連行していったのである。
つまり、住民もまた警察的な機能を果たし、ユダヤ人の強制連行に参画したのである。当然のことながら、密告に頼るということは、いわば住民を共犯者へと仕立て上げることを意味する。このようにして、住民は政府の暴力へと組み込まれていった。
アーレントの考えでは、密告によって虐殺に加担することは、政府から強制的に服従させられたことを意味するわけではないし、だから加担した住民が免責されるということもない。なぜなら、いかなる権力も、服従し、支持する者がいなければ存在しえないからだ。ナチスドイツに服従するということは、すなわちその支配体制の存在を支持する、ということを意味する。だからこそ、住民はそのように虐殺へと加担したことに責任を負わなければならない──いささか強硬にも思えるが、彼女はそう主張する。
彼女が、ナチスドイツへの服従を、その支配体制への支持として捉えるのは、当時の国内には抵抗した人々も存在したからだ。人々は暴力への加担を拒否することもできた。だからこそ、加担した行為に対しては責任が問われなければならない。
ただし──ここが重要な点だが──ナチスドイツに服従し、それを支持した人々は、必ずしもナチスドイツのイデオロギーを信奉し、それを自分の信念としていた、ということを意味するわけではない。ただ、周囲に同調し、自分で考えることを放棄していたのだ。それに対して、ナチスドイツへの加担に抵抗した人々は、自ら思考し、何が正しい行為であるかを判断していた。言い換えるなら、ナチスドイツの暴力に加担した人々は、自分では何も思考せず、ただなんとなく、暴力に加わったのである。加担した人と加担しなかった人を隔てているのは、ナチスドイツのイデオロギーに賛同したか反対したか、ということではない。思考を放棄したのか、あくまで思考したのか、ということなのだ。彼女は次のように述べる。
新しい秩序に協調した人々は、革命的な人だったり、叛乱を好む人だったりするわけではありません。ナチスと「協調」したのは圧倒的な多数者だったのです。道徳的な崩壊は、疑問をいだくこともなく、叛乱のスローガンを掲げることもない社会的な集団のうちで起きた屈服だったのです。1
アーレントはここに、ナチスドイツにおける虐殺の特異性を洞察する。すなわちそれは、人々の悪意によって引き起こされたのではなく、人々が何も考えないことによって引き起こされたのだ。
それでは、なぜ、周囲に同調し、自分で思考することをやめ、結果的に権力を支持することになってしまったのか。彼女はその鍵を、密告という手法そのもののうちに洞察している。
住民に密告させること、同時に密告された人々を見せしめ的に弾圧することは、当然のことながら、人々を疑心暗鬼にする。常に、誰かにいわれのない密告をされるのではないか、という不安に苛まれるようになる。そしてそれは、それまで培われてきた親密な人間関係を、根本的に破壊するよう機能するのである。アーレントは次のように述べる。
誰かが告発されるや否や、彼の友人は一夜にして最も激烈で危険な彼の敵とならざるを得ない。彼の罪を密告し警察と検察側の調書にたっぷり中味を盛り込むことに協力することで、われとわが身の安全を守ることができるからである。一般に告発はありもしない犯罪について行なわれるのだから、間接証拠をでっち上げるためにはまさにこの友人たちが必要とされる。粛清の大波が荒れ狂っている間は人々が自分自身の信頼性を証明する手段はただ一つしかない。自分の友人を密告すること、これである。そしてこれは、全体的支配および全体主義運動の成員から見ればまことに正しい尺度であって、ここでは事実、友人を裏切る用意のある者のみが信頼に足る人間である。疑わしいのは、友情その他一切の人間的な紐帯なのだ。2
たとえば「私」の街にユダヤ人の友達が住んでいるとしよう。同時に、ゲシュタポがその街の住民に密告を奨励するとしよう。この場合、その街に住んでいること自体が、「私」にとっては重大なリスクである。もしも他の住民から、「私」がユダヤ人と友達だということを密告されたら、「私」はゲシュタポに逮捕され、厳しい取り調べに遭うかも知れない。場合によっては、政治思想犯として強制収容所に送られてしまうかも知れない。
こうした状況において、もっとも合理的な行動は、自分からその友達を密告することである。たとえ「私」がしなくても、他の誰かがるかも知れない。しかし、それより先に自分が密告されれば、「私」は窮地に立たされる。だからこそ、まだ誰よりも先に、自分から密告することが必要なのだ。それこそが自分の身の安全を確保するために、唯一、合理的な戦略である。
同時に、このとき、友達に(それが何人であっても)自分の状況を話すことは危険である。うっかり、プライベートな事情や、本音を口にした結果、それを密告されて逮捕されるかも知れない。したがって「私」は誰にも私的な話をすることができなくなる。友達であっても、自分のことを話さず、うわべだけの付き合いをしなければならなくなる。「私」は誰とも親密な関係になれなくなる。親密さそれ自体が、身を危うくするかもしれないものになる。
このように、密告に基づくユダヤ人の強制連行は、住民が他者と親密な関係を築くことを妨害する。そのとき、他者と友情を交わすこと自体が困難になってしまうのだ。「友情」を含む「人間的な紐帯」は断ち切られてしまうのである。
密告による支配は人々から友情を奪う。アーレントによれは、それは「複数性の破壊」3 を意味する。複数性とは、言い換えるなら、この世界に存在するのは「私」一人ではないということ、「私」以外の人からはこの世界が違った仕方で見えていると確信できる、という性質である。そうした複数性が破壊されることを、彼女は「見捨てられた」状態と呼ぶ。全体主義において人々は見捨てられた状態に陥る。そしてそれは、人間にとって危機的な孤独を意味している。彼女は次のように述べる。
見捨てられていることの中で人々は真にひとりになる。すなわち他の人々と世界から見捨てられているだけではなく、自己──これはまた同時に孤独の中での〈各人〉でもあり得る──からも見捨てられている。だから彼らは孤独の分裂を実感することはできるが、他人によってもはや確認されない自己のアイデンティティを自分と一緒に維持することはできない。この見捨てられている状態の中では、自己と世界、──ということはつまり真の思考能力と真の経験能力はともになくなってしまう。4
アーレントによれば、自分が他者から見捨てられる、という感覚は、同時に自分自身から見捨てられることである。そしてそれは、私たちから「真の思考能力」を奪う。人間は自分自身が置かれた状況について思考できなくなり、盲目的に体制に服従してしまう。したがって、ナチスドイツの全体主義的体制において、大多数の人々は権力を支持し、暴力に加担してしまったのだ。
この引用文を理解するためには、対話と思考をめぐるアーレントの思想を今一度思い起こしておく必要があるだろう。彼女によれば、思考とは自分自身との対話である。私たちは、たとえ一人でいるときであっても、思考するとき、もう一人の自分と出会っている。言い換えるなら、もう一人の自分と対話できなければ、思考することもまたできない、ということだ。それに対して密告による支配体制は、自分で自分自身を見捨てさせ、それによって思考の条件そのものを破壊するのだ。
しかし、ここで次のような疑問が生じたとしても不思議ではない。なぜ、他者から見捨てられることが、自分自身からも見捨てられることを意味するのか。
たしかに、密告による支配体制は人々を疑心暗鬼にし、それによって友情を維持することが困難になることは想像できる。そして、それが他者から見捨てられているという感情を催すこともまた、理解できる。しかし、なぜ、自分自身からも見捨てられることになるのだろうか。
そのような主張が真であるのは、そこに次のような前提が置かれているときだけだろう。すなわち、自分自身との対話は、友達と対話できることをその条件とする、という前提である。しかし、それほどまでに友達との対話に重要な機能を認める議論は、少なくとも『人間の条件』では見られないものだった。彼女はこの前提を、どのように正当化しているのだろうか。
『人間の条件』の刊行と同じ年に行われた講演「暗い時代の人々」のなかで、アーレントは、友情のもつ政治的な意味について考察している。人間が交わしうる様々な人間関係のなかで、友情はある特権的な地位を占めている。「周知のように、古代人は友人を人間生活に不可欠なものと考え、実際友人を持たない人生は真に生きるに値しないと考えていました」5 。彼女が政治や公共性について語るとき、その範例となっているのは、古代ギリシアである。それゆえ、アーレントにとって友情が特別に重要な概念であるとしても、不思議ではない。
ただし、古代における友情は、現代のそれとはやや異なる事柄を含意していた。現代において友情とは、あくまでも親密圏における人間関係を指すと考えられている。アーレントの概念に基づくなら、それは私的領域に属する関係性であり、「顔つき合わせた出会いという親密さ」である。一方、古代における友情の概念には、これとは根本的に異なる「政治的妥当性」が含意されていた。
では、友情の政治的機能とはいったい何なのか。アーレントによれば、それは対話である。彼女は次のように述べる。
ギリシア人にとって友情の本質は対話のなかにありました。かれらは絶えざる議論の交換だけがポリスの市民を結合すると考えました。対話のなかで、友情の政治的重要性とそれに固有な人間らしさとが明らかにされます。こうした会話は(各個人が自分自身について語る親密なおしゃべりに比べて)、それがたとえ友人がいるという喜びに満たされていたとしても、共通の世界に関心を寄せるのであり、共通の世界は、それが絶えず人々に語られるのでなければ、まさに文字通り「非人間的」のままにとどまります。6
アーレントはここで、対話を「共通の世界に関心を寄せるもの」と位置づけ、「自分自身について語る親密なおしゃべり」とは区別している。
ただし、ここでいう「共通の世界」に関する対話とは、決して、同じ世界について同じように語る、ということではない。そうではなく、同じ世界を違った視点から語るということこそが、対話の本質的な営みなのである。前述の通り、友情は「私」の視点に複数性を与えるものである。「私」は、友達と対話することによって、「私」が目の前にしている世界を、友達が違った仕方で眺めていることを知る。それが、私たちの生きる共通の世界にリアリティを感じさせるのだ。
ここにアーレントの議論の特徴的な点がある。世界がリアルなもの、つまり人間的なものであるためには、自分が目の前にしている世界を、自分とは違った仕方で眺める他者との関係が必要なのである。同じ意見ではなく、異なる意見と出会うこと──それがアーレントにとっての対話の条件であり、友情の営みなのだ。彼女は次のようにも述べている。
人間によって作られているからといって世界は人間的になるわけではなく、またそのなかに人間の声が聞かれるからこそ人間的とならないというわけではなく、ただ世界が人間的となるのはそれが語りあいの対象となった場合に限ります。われわれが世界の物事にどれほど影響されようと、それがどれほど強くわれわれを感動させかつ刺激しようと、仲間とそれについて討論することができる場合にのみ、そうしたことはわれわれにとって人間的なものとなるのです。7
世界は、友達と語り合われることによってのみ、人間的になる。それは言い換えるなら、世界について友達と対話できないとき、その世界は私たちにとって非人間的なものとして立ち現れる、ということだ。
ここから、なぜ、自分自身と対話できるための条件として、友達との対話を念頭に置いていたのかを説明することができる。友達と共通の世界について対話できるからこそ、私たちはその世界を人間的なものとして、リアリティを持ったものとして感じることができるのだ。
たとえば──卑近な例になるが──あなたが恋愛をしていて、恋人からひどい罵声を浴びたとしよう。あなたはその罵声がひどい暴力のように思うかも知れないが、同時に、それは恋人なりの愛情表現なのかも知れないとも思う。そしてどちらの理解が正しいのか分からなくなってしまう。それに対して、あなたの友達が「いや、それは暴力だよ、愛情ではないよ」と言ってくれれば、あなたは自分にされたことが単なる暴力であったということを、確信するに違いない。このように、友達と対話するとき、あなたは自分の身に起きたことをリアルなものとして、人間的なものとして確信することができるのだ。
そうであるとしたら、友達との対話が奪われるとき、私たちは自分が帰属している世界を人間的なものだと感じることができない。それは、あたかも自分が本来帰属するべきではない場所であるかのように、ここにいるべきではない人間のように、感じてしまう。そのとき人間は、その世界に生きているはずのもう一人の自分も見失ってしまうのだ。
あるいはその感覚は、次のように表現することもできるかも知れない。友情を破壊されるとき、私たちは、自分がまるで間違った世界に迷い込んだような気分になるのだ。目の前で繰り広げられる暴力の連鎖を、まるで映画でも観ているかのように、おとぎ話を聴いているかのように、感じてしまうのだ。このような状況では、その世界に生きるもう一人の「私」など、出現しようがない。そんなものは嘘だ、本当は存在しない、というわけである。
この講演におけるアーレントの主張は、極めて明瞭に、他者との対話が自分自身との対話に先行する、という立場を取っている。友達と関わることができなければ、私たちは自分自身と出会うことすらもできない。だからこそ、友達を作れない環境に人間を置くこと、人間から友情を築く可能性を奪うことは、危険であり、許されえない状況でもあるのだ。
さて、私たちはこれまで、対話をめぐるアーレントの思索を検討してきた。最後に、そこから明らかになったことを、指摘しておこう。
アーレントの対話の概念は、常識的なそれと、根本的に異なっている。私たちは普通、対話を、対話をする前に考えられたことを語り合う行為だと思っている。それはいわば、それぞれがすでに財として持ち合わせている意見を、披露しあうような営みであり、インプットとアウトプットの相互交換である、と言えるだろう。
しかしアーレントは、そうは考えない。思考が先立つのであれば、対話があろうとなかろうと関係なく可能だということになるが、それはちがうと彼女は言う。私たちが思考するために、他者との対話を必要とするのだ。私たちは対話しながら思考するのである。
そうである以上、対話において語られることは、決してすでに完成されたものではない。それらはレディ・メイドではない。そうした言葉は、その対話がなければ決して生まれなかったであろうものであり、その対話が「私」に考えさせたことなのだ。
なぜそう言えるのか。それは、対話とは「私」の思考に複数性をもたらすものであるからだ。物事を複数の視点から吟味する営みこそ、思考なのである。
だから、対話のなかで語られることは、常に試作品であり、プロトタイピングであり、未完成である。それはまだ自分のものになっていない言葉、十分に鍛えられていない言葉なのだ。そうでしかありえないのであり、そうであっても構わない。私たちは対話のなかで、しばしば、言葉に詰まったり、うまく話せなくなったりする。しかしそれは決して悪いことではない。そうしたことを、「コミュニケーション能力が低い」などと言って非難することは、人間を対話から遠ざけものになるだろう。
反対に、あたかもすでに完成されているかのような言葉を対話のなかで語られたら、この人は本当に対話しているのだろうか?と私たちは疑うのではないだろうか。たとえばやり手の営業マンの話を聞いているとき、こういう印象を覚えることがある。相手のなかですでに完成された言葉のフレームワークがあって、会話がそこに落とし込まれていて、実際には相手は自分の言葉など聞いていない、と感じるのではないだろうか(おそらく、本当に熟練した営業マンなら、そうした印象すら抱かせないのだろうが)。
もう一つ、興味深いのは、アーレントが思考に先立つ対話を、主として友達との対話として説明していることである。彼女にとって対話は何よりもまず友情をモデルとしたものだった。ナチスドイツにおいて、密告による支配は友情を破壊することで人間から対話を奪った。また自己と対話することは、自分自身に友達として接することに譬えられた。明らかに、彼女にとって友情は、他の関係性にはない特別な意味を持っている。
その意味とはいったい何なのだろうか。彼女はそれを、必ずしも明瞭に論じているわけではない。しかし、おそらく、他の人間関係になくて、友情にしかない特徴とは、一緒にいて心地よい、ということだろう。
彼女は良心について論じるとき、自分が自分自身と一致することの道徳的な重要性を指摘していた。それは、自分と一緒にいることに耐えられること、居心地が悪くないこととして説明される。この意味において、自分自身との一致は、決して論理的な整合性を意味するのではない。
私たちが思考できるためには、一緒にいて居心地のよい他者との対話がなければならない。あるいは、そこで求められる対話は、あくまでも居心地のよいものでなければならない。そうした居心地のよさは、おそらく、対話がロジカルに展開していくときのスリルとは違う素晴らしさがある、と理解するべきだ。ロジカルな対話だけが優れた対話だと思ってしまうと、私たちは、この事実を見逃してしまうのである。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。
- ハンナ・アレント『責任と判断』ジェローム・コーン編、中山元訳、ちくま学芸文庫、二〇一六年、二五七頁
- ハンナ・アーレント『全体主義の起源 3 全体主義』大久保和郎・大島かおり訳、みすず書房、二〇一七年、三九頁
- 前掲書、三一八頁
- 前掲書、三二一頁
- ハンナ・アレント『暗い時代の人々』阿部齊訳、ちくま学芸文庫、二〇〇五年、四五頁
- 前掲書、四五-四六頁
- 前掲書、四六頁