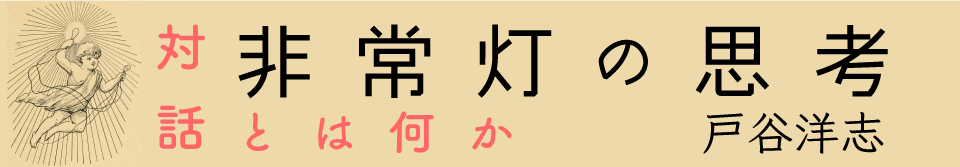本連載ではこれまで、対話に関する様々な哲学者の思想を検討してきた。最終回となる今回は、これまでの議論を踏まえた上で、筆者が提示すべきと考える対話観を示す。ただし、結論から言えば、未完成である。まだ十分に洗練されていないし、曖昧な点を多く抱えているだろう。それでもここでそれを提示するのは、無意味なことではないだろう。高度に複雑化し、いたるところに分断を生じさせている現代社会において、対話の営みを見つめ直すことは喫緊の課題に違いないからだ。
打算的対話
私たちは他者と対話するとき、実際には何をしているのだろうか。
具体的な行動だけを抽出すれば、対話とは、話すことと聞くことによって構成されている。まずはそう考えることができる。「私」が話し、他者がそれを聞く。それに対して、他者が何かを話し、「私」がそれを聞く。そのやり取りを、まるでテニスのラリーのように繰り返すことが、対話において私たちが行っていることだ。
この行為が、問いと答えとして理解されるなら、対話は相互に情報を取得しようとする営みである、ということになるだろう。一方が質問し、他方が回答する。対話は役割を入れ替えながらそれを繰り返すことである──その場合、目的は情報を取得することであり、対話はその手段である、ということになる。
しかし、情報を取得する手段として、対話それ自体が望まれているわけではない。なぜなら、情報を取得する手段は一つではないし、そもそも対話は相当に効率が悪いからである。対話をした結果、思ったような情報は得られないかも知れない。欲しかった情報に辿り着くまでに、割に合わないようなコストがかかるかも知れない。それだったら、ネットで検索したり、本を読んだりした方が、はるかに割安だろう。
このように、情報の取得を目的にした対話は、必然的に、コストパフォーマンスを基準にして評価されるようになる。つまり、コスパが優れている対話が「よい対話」であり、そうでない対話は「悪い対話」として評価されるのだ。このとき、私たちが理想とするのは、できるだけ短い時間で、大量の、あるいは高品質の情報を取得できるような対話だろう。
そうであるとしたら、対話は短ければ短いほどよい、ということになってしまう。ゼロに近づけば近づくほど、価値は上がる。このことは、交通手段に対する評価とよく似ている。ある場所に到着することが目的なら、辿り着くための時間は、短ければ短いほどいい。その時間はゼロであることが理想である。もしも、瞬間移動することが技術的に可能になれば、それがもっとも理想的な交通手段になるだろう。同じことが対話にも当てはまる。無ければ無いほどよいもの、できれば無しで済ませるべきものになってしまうのだ。
この意味において、情報の取得を目的にした対話は、自分自身を否定することになる。私たちにとって、対話は本質的に余計なもの、排除されるべきものとして捉えられることになる。本書では、こうしたあり方を、「打算的対話」と呼ぶことにしよう。
対話がこのようなものとして理解されていることは、確かにあるだろう。たとえばジャーナリズムにおける取材や、ビジネスにおける情報交換のために行われる対話は、多分にそうした色彩を帯びている。しかし、日常生活において「よい対話」と呼ばれている事象には、それに留まらない意味があるように思える。
たとえば、「私」が友達とカフェで対話し、その友達と別れて一人で帰る道すがら、「ああ今日はよい対話だった」と思い返すとき、それは、決して「コスパのよい対話」を意味するわけではないだろう。では、その価値はいったいどのように評価されるものなのだろうか。
制作的対話
おそらく、私たちは、内容だけで、日常において繰り広げられる対話の価値を決定しているわけではない。たとえば、思い返してみたら本当に下らないことしか話していないのに、その対話が素晴らしいものであるように感じられることはあるだろう。同じ内容であっても、対話の仕方が違っていれば、味気なく感じられることもあるだろう。もちろん内容は重要だ。しかし「よい対話」とは、「よい内容の対話」と完全に重なるわけではない。
「よい対話」はまた、私たちにとって快楽を誘う対話であるとも限らない。たとえば、爆笑を誘う対話や、愛する人との親密な対話は、きっと「よい対話」だろう。しかし、そうではなくとも、そこに「よい対話」が成立することはある。たとえば、悲しみや怒りを共有する対話も、あるいは、互いが語りにくいものを抱え、沈黙が支配するなかでほんのわずかな言葉が交わされた対話も、「よい対話」になりえる。
それでは「よい対話」とはいったい何だろうか。筆者の考えでは、それは充実感を抱かせる対話である。そしてその充実感とは、二人が過ごしたその時間の中で、「ともに対話を作り上げた」という感覚ではないだろうか。
私たちは対話をしているときに、実際にその対話をともに作り上げていると言える。つまり、対話において私たちが互いに交わし合う言葉は、単なる情報の交換ではなく、それによって対話を完成させるための寄与なのである。
それはあたかも、二人でひとつの作品を作る営みのようなものだ。もちろん、対話の結果として、そこになにかの物質的な成果物が残るわけではない。それでも、よい対話をしたあと、私たちはなにかが完成したような気持ちになる。そうした充実感を抱けるか否かが、対話への評価の根拠になっているのではないだろうか。
物質的な成果物が残るわけではない以上、ここでいう「作る」という行為は、ある種の擬似的なもの、空想的なものである。しかし、そのような制作活動は、必ずしも私たちにとって奇異なものではない。たとえば、スポーツで相手と対戦しているときにも、そこに空想的な制作活動が展開されることがある。それが対戦である以上、プレーの目的はさしあたり勝利することである。しかし、いつのまにかその目的が曖昧になり、むしろ相手とプレーを競い合うなかで、「よい試合」を演じることを、プレーヤーが目指すようになる場合がある。
しかし、これは決して、「よい試合」のためにプレーヤーたちが非本来的なプレーをするようになる、ということではない。プレーヤーは、あくまでも勝利を目的に全力を出す。その結果として、「よい試合」を作り上げていくのである。この意味において、勝利を目指すプレーと、「よい試合」を目指すプレーは、両立する。むしろ、後者は前者を包摂するのである。
本書では、このように、ともに作り上げられるものとして捉えられる対話を、「制作的対話」と呼ぶことにする。制作的対話において、私たちはともに「よい対話」を作り上げようとする。それは、「よい対話」のために、本来だったら言いたくないことを言ったり、興味がないことを聞いたりすることを意味しない。スポーツにおける「よい試合」が、自らの勝利のために全力を発揮することを要求するように、「よい対話」においても、「私」は自分の興味があること、面白いと思えることを、楽しみながら話す。それは打算的対話とは本質的に異なる行為なのである。
「よい試合」とは何か
制作的対話とは何か。それを掘り下げて考えるために、もう少し、スポーツのメタファーで考えてみよう。
「よい試合」は、対戦するプレーヤー同士が全力を出し合う試合である。それに対して、「悪い試合」があるとしたら、それはどんなものだろうか。
おそらく、大きく分けて三つある。まず、プレーヤーがあえて本気を出さず、最初から明らかに手加減している場合である。このような試合は、たとえ得点などによって伯仲していたとしても、「よい試合」とは見なされない。なぜなら、優位に立つプレーヤーは、対戦相手の実力を低く評価していることが、明らかになってしまうからだ。つまり、すでに対戦相手の実力を知ってしまっており、相手に合わせたプレーをしているに過ぎないのである。
次に、プレーヤーが最初から勝負を捨てている場合である。たとえば、その試合の直後にもっと大きくて重要な大会への出場を決めているプレーヤーが、怪我や疲労を抱え込まないようにするために、最初から本気を出さず、それどころか「別に負けても構わない」という態度でのぞんでいる場合だ。この場合も、得点が伯仲していても、「よい試合」にはならない。それは、プレーヤーがその試合に集中せず、別の試合の方を重視しているからである。言い換えるなら、プレー内容を、別の試合でのプレーを意識して決定しているのだ。
最後に、プレーヤーがルールを無視する場合である。ここで言うルールには、明文化されたものとそうではないものがある。明文化されたルールの無視は、反則行為となる。一方で、明文化されていないルールとしては、スポーツマンシップなどの倫理があるが、それに違反する行為は、たとえ反則ではなかったとしても、「汚い」プレーとして、すなわちダーティプレーと呼ばれて批判される。互いに反則行為を繰り返し、何でもありになってしまった試合は、やはりどれほど得点が伯仲していたとしても、「よい試合」には到底なりえない。
「よい試合」を阻むこの三つの条件は、それぞれ次のように言い換えることができるだろう。
第一に、相手を見下すことである。これは、自己を基準として相手の能力を評価し、それに自分が合わせようとすることである。このような関係は、「私」と他者の対等な関係を毀損する。なぜなら、「私」は相手に合わせてあげているのに対して、相手は「私」に合わせてもらっているからだ。
第二に、相手との関係を超越することである。「私」が相手と関わっているとき、その関係を超越するとき、「私」はやはり、相手と対等な立場にはいない。なぜならそのとき、「私」は相手と向かい合うのではなく、「私」と相手が対峙している場面を、いわば垂直的に見下ろしているからである。「私」は、相手から決して見返されない地点から、相手の視界の外から、相手を眺めることになる。
第三に、規範を逸脱することである。他者との関わり方を条件づけている規範を破ることは、「私」と他者の関係を著しく不安定にする。なぜなら、その規範への信頼が、両者の関係に安定性を与えているからだ。規範からの逸脱は、「私」と他者の関係から持続可能性を奪い、関わり続けることを困難にする。
制作的対話の条件
筆者の考えでは、制作的対話を成り立たせるための条件にも、以上の三つが該当する。
まず、私たちは「よい対話」をするために、相手を見下すべきではない。つまり、相手の理解力や知識量を決めつけ、それに合わせて話をするべきではない。このような態度が、決して充実した対話を形成することはない。見下すことが、相手に対する不当な評価になるから、というだけではない。たとえ相手に対する「私」の評価が完全に正しかったとしても、こうした対話は望ましくない。なぜなら、そのとき「私」は「相手に合わせてあげる」ことになり、対等な関係が維持できなくなるからだ。
また、相手との関係を超越するべきではない。言い換えるなら、相手との対話をその外側から眺め、別の目的のために対話を利用するべきではない。たとえば、相手に何かをさせようとして、その手段として対話をすることが、これに該当する。そのとき「私」は相手をある特定の方向へと誘導することになる。
そして最後に、規範を逸脱するべきではない。対話しているとき、「私」と相手の間には、暗黙の裡に対話においてするべきことと、するべきではないことが、共有されている。その規範が守られている、ということが、対話における「私」と相手の関係を安定的なものにし、また、ある種の安全性をもたらす。そうした規範が破られるなら、それは対話の持続可能性を毀損することになる。
この考えをそのまま進めると、こうした対話において私たちが何をするべきか、あるいは何を要求されているのか、ということが見えてくる。
第一に、相手と対等な立場に立つ、ということである。これは相手と同じレベルになる、ということではない。そうした対応をするためには、「私」は相手のレベルを知ることができなければならない。しかし、相手のレベルを知ることができる、と思い込むこと自体が、相手に対する不当な評価なのである。相手と対等であろうとするなら、相手のレベルがまったく分からない、ということを前提にしなければならない。
第二に、あくまでもその対話に内在するということである。私たちは、その対話のためだけに対話するべきである。その対話が終わった後のことを考えながら、対話をするべきではない。あくまでも対話に集中するべきである。もちろん、対話のなかで何かを学んだり、自分が抱えている悩みへのヒントを求めることはあるだろう。重要なのは、そうした対話の外部へ意識を向けるつもりがないのに話題がそれてしまう場合でも、対話が成立するようにしなければならない、ということだ。対話は自立するものでなくてはならないのである。
そして第三に、規範に基づいて対話するということである。そこには様々な規範があるだろう。不確かな情報を確認せずに言うべきではないし、嘘をついてもいけないだろう。たとえ意見が対立しても、相手の人格を否定してはいけないだろう。相手が恋人や家族の愚痴を語ったとしても、そうした人たちを貶めるようなことを言うべきでもない。
制作的対話における連帯
ところで、ここまで読んで、「よい対話」の不可欠な条件として、意見の一致は必要ないのか?と思うかもしれない。
私たちはしばしば、対話が合意形成のために必要である、と考える。実際、それは一面では事実だろう。しかし対話はそのためだけに存在するわけではない。
対話は、意見の不一致を解消するために、行われることがある。つまり別の立場にある二人を、対話をとおして合意を形成することによって、同じ立場に置き直すことができる。合意形成を目的にした対話にはそうした役割が期待される。
しかし、たとえ最終的に合意に達することができなかったとしても、「私」がその対話を「よい対話」だったと感じることは、十分に起こりえる。むしろ、日常的に経験する「よい対話」に、そうした合意形成の機能はほとんどの場合において期待されていないのではないか。
そうであるとしたら、「私」は対話において、自分とは異なる立場にある他者と関わり合っていることになる。対話のなかで「私」と他者は、その意見においては、対立している。意見の対立は、普通に考えれば、二人が分断されていることを意味するはずである。分断を解消しない対話に何の意味があるのだろうかと思うかもしれないが、これに対して、私たちの日常的な感覚をもって回答するなら、それもまた対話だ、ということになる。対話において、たとえ「私」と相手が異なる立場にあるのだとしても、必ずしも分断されているわけではない、と。
たとえば「私」が、旅行で重視するべきなのは風景である、と考えているのに対して、相手は食事である、と考えているとしよう。「私」と相手は、旅行について対話する。その結果、お互いに自分の意見を譲らず、結果的に両者とも自分の立場を変更することなく、対話が終了する。決して合意形成には至っていない。しかし、二人はその対話に充実感を抱き、それが「よい対話」だったと感じるとする。そうしたことは普通に起こりうる。このとき、二人は分断されているのだろうか。もちろんそんなことはない。異なる立場にありながら、ある意味では通じ合っているのであり、ある意味では対話によって何かを共有しているはずだ。では、そのとき二人の間にある共同性は、いったい何に根差しているのだろうか。
その共同性は、決して、二人の立場の同一性に基づくものではない。立場は明らかに異なっている。したがってその共同性は、二人がもともと立脚している立場を超えたものであり、そうした立場から二人を自由にする。だからこそその共同性の根拠が問われるのである。
その根拠は、次のように説明されるだろう。すなわち、対話の参加者を結びつける共同性は、ともに対話を作っているという点に根差している。つまり、あたかも一つの作品を共同で制作する人々が、共同制作者としての共同性を持つように、一つの「よい対話」を作ろうとしているという点で、繋がっているのだ。だからこそ人々は、たとえそれぞれがもともと異なる立場にあるのだとしても、連帯するのである。
対話において「私」が他者と連帯するのは、「私」と他者が同じ立場にあるからではない。「私」と他者がともに対話を作っているからである。こう言い換えることもできるだろう。「私」は、他者とともに「よい対話」を作ろうとすれば、どんなに立場が異なる相手であっても連帯することができる。この意味において、制作的対話は、対話の参加者の立場を超えた連帯を可能にする。
対話の目的
しかし、おそらくここにおいて、制作的対話という概念は一つの厄介な反論に直面しうる。制作行為には常に目的が伴う。しかし対話において「私」は予見不可能な他者と関わる。他者が「私」と同じ目的を共有しているという保証は、どこにもない。そもそも、目的が共有されていると信じること自体が、他者の他者性に対する暴力だろう。したがって、制作的対話は、対話における他者性の尊重と整合しない。こうした反論である。
制作行為が目的を伴うことは、ほとんどの場合、真実だろう。そして、日常的な制作において、そうした目的は明確なイメージを伴う。たとえば「私」が木材から椅子を制作するとき、「私」は完成品の椅子のイメージを明瞭に意識する。設計図を描く場合は、それを頭のなかで再構成し、自由自在にイメージを回転させたり、拡大・縮小させたりすることができなければならない。制作は多くの場合そうした心像によって導かれる。
しかし、当然のことながら、心像は「私」の頭のなかにあるものである。仮に対話が制作されうるものだとしたら、「私」がどんな対話をその完成形としているのか、ということは、他者には知りえない。そして、同時に「私」も、他者がどのような完成形をイメージしているのかを、知ることはできない。だから、「私」と相手は同じように対話を完成へと向かわせようとしながら、その完成形はまったく違っている可能性がある。そうであるにもかかわらず、どちらか一方が抱いている対話の完成形の心像を絶対視することは、前述の通り、他者の他者性の否定になりかねない。
たとえば「私」は、久しぶりに会った友達とカフェで対話しているとき、「仕事のことを忘れてリラックスできる時間を過ごしたい」と思っているとする。それが「私」にとっての対話の完成形だ。しかし、相手はそうは考えておらず、「普段は職場で話せない、仕事の本質に関わることについて、意見交換したい」と思っているかも知れない。このとき、「私」と相手はその対話の完成形を共有していない。
このとき、「私は今日は仕事の話なんかしたくないんだから、相手はそんな話をするべきではない」という態度を取ることは、暴力である。なぜなら、事前に約束でもしていない限り──もちろん、たとえ約束していたとしても、当日になって想定外のやり取りをすることはありうる──相手がその対話をどうしたいのか、ということについて、「私」と相手は対等だからだ。
では、完成形を事前に共有できないことは、対話の共同制作を脅かすだろうか。合意形成を目的とした対話においては、おそらくそうだろう。だからこそそうした状況では、対話の開始時点において、目的が確認される必要がある。しかし、そうではない対話においては、必ずしも完成形の共有は必要ではない。むしろ私たちは、事前に決まっていないからこそ、「よい対話」の形成を楽しむことができるのではないか。
もしも、あらかじめ決定された完成形があり、対話がただその完成形を目指して進行するプロセスに過ぎないなら、そのとき対話は、すでに存在する行程を辿る行為にとどまる。対話のなかでのやり取りは、その大部分が、悪い意味での「作業」になる。そして、そうした作業へと堕落した対話は、最初に述べたような、打算的対話以外の何物でもなくなるだろう。
したがって、私たちはこう考えるべきである。制作的対話において、対話の完成形は共有されていないし、明確にイメージされているわけでもない。イメージは実際に相手と対話していくなかで、柔軟に変化し、訂正される。「私」と相手は、それぞれの心のなかで、対話の時間をどんなものにしたいのかを、朧気ながら理解している。しかしそのイメージは、実際の対話のなかで覆され、まったく予期していない展開が生じたり、盛り上がりが生まれたりすることもある。それはそれで、対話は完成されたのである。
この意味において、対話の制作は、即興的であると言える。つまりそれは本質的に「戯れ」なのである。
***
制作的対話という概念には、なお、多くの反論が寄せられうるだろう。それらを一つ一つ検討することは、本連載を費やしても到底力が及ばない。しかし、それでも筆者はこのアイデアが、憎悪によって引き裂かれた現代社会を乗り越えるための、一つの手がかりになると信じている。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。