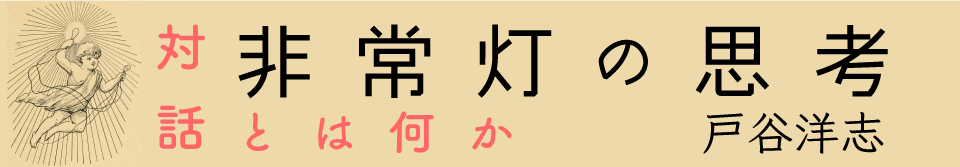本連載はこれまで、対話に関するハイデガーとアーレントの思想を概観してきた。両者は、対話をまったく違ったものとして捉えていた。改めて、その違いを簡単に整理すれば、次のようになるだろう。
ハイデガーは対話をある種の雑談として捉えていた。それは、人間に対して空気を読むことを要求するものであり、いつの間にか人間を周囲に同調させるものである。彼の哲学の枠組みのなかで、それは自分の本来のあり方を忘れること、つまり非本来性に陥ることを意味する。それに対して、本来性の回復としての先駆的決意性は、他者との繋がりを絶った孤独のなかで発揮されなければならない。総じてハイデガーは対話について消極的な評価を下している。
一方、アーレントは、そうしたハイデガーの哲学における孤独の賞揚が、ナチスドイツの全体主義を下支えしていた、と指摘する。彼女にとって対話とは、決して人間を周囲に同調させるものではなく、むしろそうした同調に抗う複数性を持った思考を可能にするものである。思考は対話に基づいているのであり、もしも対話の機会が奪われれば、人間の思考もまた停止する。そして、彼女の考える対話とは、あくまでも友情に根差したものに他ならない。このことから、彼女は人間の存在にとっての対話の価値を、高く評価している、と言えるだろう。
ある種の対話は、同調圧力を生み出す。これは、一面において事実であると思える。しかし、また別の仕方で行われる対話は、そうした同調圧力を克服する可能性を、人間に開くものでもある。ではその違いはどこにあるのだろうか。私たちは、どんな風に他者と対話すると同調圧力を生じさせ、どんな風に対話するとそれを乗り越えられるのだろうか。
この問題を考えるために、今回から数回にわたって、近代ドイツの哲学者イマヌエル・カントの思想を検討しよう。
カントは、人間が十分に思考できるようになるためには、他者との対話が必要である、と考える。この点においてカントの発想はアーレントに似ている。では、そもそも彼にとって、思考するということはどのような営みなのだろうか。
カントは『判断力批判』のなかで、思考を次のような三つの段階に区別して説明している。
1 じぶんで考えること
2 他のあらゆるひとの立場で考えること
3 つねにじぶん自身と一致した考えであること1
順に見ていこう。
第一の段階、「じぶんで考えること」は、「偏見から自由な思考様式」2を指している。私たちは、世間で言われていること、親や教師など、権威を持つ者から教えられたことを、鵜呑みにしてしまう傾向がある。しかし、その内容が正しいかどうかを自分で検証していないなら、そうした知識はただの偏見である。そして、偏見に留まる限り、他者から与えられた知識に支配されるため、受動的な状態に置かれることになる。
しかし、権威を持つ者から教えられたことの正しさを、自分の力で検証するなら、そのようにして得られた知識は偏見ではない。また、そうやって知識に向かい合うとき、私たちは能動的な態度を取ることになる。これが、カントの考える「じぶんで考えること」である。
これに対して第二の段階「他のあらゆるひとの立場で考えること」は、言うなれば視野狭窄から自由な思考様式である。たしかに、「私」は物事を自分で考えることができる。しかし、それが「私」一人の視野から生まれた思考であれば、その思考は依然として限定されている。もちろん、思考が制限されているということは、それが不合理であることを意味するわけではない。自分で思考できるなら、そこから合理的な答えを見つけ出すことはできるだろう。とはいえ、合理性が一つしかないわけではない。ある物事に対する合理的な考え方には、複数のパターンがありえるのだ。
自分の立場からしか思考しない人は、そのように複数ありえる合理的な答えのうち、一つしか知ることができない。それ以外の答えの可能性には、辿り着くことができない。しかし、そのように自分の立場から導き出された答えが、様々な答えの可能性のうち、もっとも適切なものであるという保証はない。それに対して、もっとも適切な答えに到達するためには、自分以外の立場からも物事を考えることができなければならないのだ。
カントは、このように、他者の立場を取り入れた思考の仕方を、「拡張された思考様式」と呼ぶ。それは、「判断の主観的な個人的条件を抜け出すことができ、普遍的立場(この立場を、その者がかろうじて定めることができるのは、他者たちの立場に身を置き入れることによってである)にもとづいて、じぶん自身の判断をめぐって反省する」3ような、思考に他ならない。言い換えるなら、「他のあらゆるひとの立場で考えること」とは、自分が思考したことを、他者の立場から見つめて反省すること、再び思考し直すことである、と考えられる。
第三の段階、すなわち「つねにじぶん自身と一致した考えであること」は、「じぶんで考えること」と「他のあらゆるひとの立場で考えること」の結合によって実現する思考のあり方である。そのため、それは「達成するのにもっとも困難な準則」4である。カントは、この第三の思考様式について、あまり多くを説明していないが、さしあたり、その内実は次のように解釈することができるだろう。
私たちは、自分自身と不一致の状態で物事を考えることがありえる。それは、前に言ったことと、後で言ったことが、違うということである。つまり、ある状況と、別の状況で、考え方が一貫していない、ということだ。しかし、私たちはどのような状況においても、ある一つの首尾一貫した思考に基づいて、物事を考えることができなければならない。この意味において、この第三の思考様式は、時間的な性格を帯びている。
カントによれば、この思考様式は、「前二者の思考様式を結合することによってのみ、またそのふたつの思考様式に熟達するまで繰り返し遵守したのちに、はじめて到達しうるもの」5である。つまりそれは、様々な立場から自分自身で思考することによって獲得されるものなのだ。様々な立場から考えるということは、その度ごとに別の立場から考えることもできてしまう、ということである。それぞれの状況において最適な考え方を選択していけば、そのような状態に陥りうることは容易に想像できる。しかしそれは、時間的に俯瞰すれば、場当たり的で首尾一貫していない思考とも言える。
第三の思考様式は、このような事態に抵抗するものである。すなわち、様々な立場から物事を考えることができるのに、そこに一つの首尾一貫性を与えることができる、という思考の仕方なのだ。
カントの思考概念の基礎は、思考を偏見からの自由として捉える、という点にあるだろう。偏見とは、与えられた知識への依存である。それを自らの力で吟味することを重視する彼は、思考の特徴をその能動性と自律性のうちに見ていた。こうした傾向は、カントの他の著作においても一貫している。
たとえば『啓蒙とは何か』のなかで、カントは「啓蒙」を次のように定義している。
啓蒙とは何か。それは人間が、みずから招いた未成年の状態から抜けでることだ。未成年の状態とは、他人の指示を仰がなければ自分の理性を使うことができないということである。人間が未成年の状態にあるのは、理性がないからではなく、他人の指示を仰がないと、自分の理性を使う決意も勇気ももてないからなのだ。だから人間はみずからの責任において、未成年の状態にとどまっていることになる。6
カントによれば、啓蒙とは「未成年の状態」を脱出することだ。未成年の状態とは、すなわち、自分で物事を考えることができず、思考を他者に委ねることである。自分の代わりに誰かに考えてもらう状態と言ってもいいだろう。なぜ、未成年状態の人は、思考を他者に委ねるのだろうか。思考する力をそもそも持たないからだろうか。カントによれば、そうではない。なぜなら人間は誰でも思考する力を、つまり「理性」を持っているからだ。むしろ、未成年状態の人は、自分で思考する「勇気」を持てないのである。したがって、未成年状態の人を啓蒙するということは、そうした人に思考する勇気を抱かせる、そしてその勇気を発揮させる、ということを意味するのである。
ここには、すべての人間には思考する力が備わっている、というカントの基本的な信念が示されている。しかし、ここで疑問がわきあがる。現在、思考する力を発揮できていない人は、どのようにすれば、思考できるようになるのか、という問題だ。
極めて素朴に考えれば、いま思考する力を発揮していない人は、そもそもその必要を感じていない。そうした人には、思考することの必要性を説いたり、あるいは思考することを強制したりすればよいのだろうか。しかし、強制されて思考することは、結局はそのように強制してくる他者がいなければ思考しない、ということであり、啓蒙の条件である自律的な思考とは呼び難い。思考を強制されることは、依然として、他者に依存した状態にあるのであり、厳密に言えばそれは思考していることにはならないのだ。
たとえば、子どもに思考力を身に着けさせようとするとき、教師が直面する矛盾を想像すれば明らかだ。教師は、生徒の思考の主体性を育てたいと思っている。したがって、自分からものを考える生徒に高い評価を与え、高成績をつける。すると、生徒たちは高い成績を取るという目的のために、思考するようになる。一見すると、生徒たちは主体的に思考するようになったかのように見える。しかし、実際には、強制力が働いて、高い成績を取らなければならないと思った結果、生徒はそのように変化したのだ。生徒は、依然として教師の持つ非対称的な権力に依存しているのである。
では、現在思考する力を発揮していない人は、その力をただ潜在的に有しているだけで、結局はずっと発揮できないのだろうか。もちろん、カントはそうではないと考える。ではいったいどのようにすれば、もともと思考する必要性を感じていない人が、自ら思考するようになるのだろうか。
カントが提案するのは、人間が自ら思考したいと思うような状況を、意図的に設計することである。彼は、『実践理性批判』のなかで、「人間の理性には、提示された実践的な問題に、きわめて微細な吟味を加えることを好む性向がある」7と指摘し、それを未成年状態にある人の教育に活用するべきである、と主張する。人間は、ある種の状況に置かれれば、自ら「思考したい」という欲求を抱くようになる。この欲求に駆られて思考が始まるなら、それはあくまでも自律的な営みであり、真に思考と呼ぶに値するものだろう。
では、人間が自ら思考したいと思えるような状況とは、いったい何なのだろうか。カントによれば、それは議論の場である。彼は次のように述べる。
あらゆる議論の中でも、ふつうならどんな理屈にもすぐに飽きてしまう人でも参加したくなり、その場にある種の生気が生まれるような議論がある。それは、ある人の性格を決めてしまうあれこれの行為の道徳的な価値についての議論である。8
ふつうは理論的な問題についての緻密で思索的な議論は、無味乾燥で面倒だと考えるような人でも、語られた善行や悪行の道徳的な内容を詮索するような議論には、すぐに仲間入りしてくるものである。そしてそうした行為の意図の純粋さやその意図における徳の高さを低めたり、疑わしくしたりするような事柄をさまざまに考えだして、思弁のほかの客体〔話題〕でふだんは期待できないほどに厳密で、思索的で、微細な議論を展開するものである。9
カントによれば、人々は「行為の道徳的な価値」に関して他者と対話するとき、「ふだんは期待できないほどに厳密で、思索的で、細微な議論」を展開する。この意味において、道徳的な問題をめぐる議論は、これまでにない深い思考を可能にする。
このとき、重要なことは、人々はこのような議論に自ら参加し、そのなかで思考したいという欲求を持つ、ということだ。すなわち、議論に参加して深く思考する人は、決して、そうすることを誰かに強制されているわけではない。議論に参加すれば報酬があるわけではないし、参加しなければ罰が与えられるわけではない。まるで美しい景色に心惹かれるように、あるいは美味しい料理に食指が伸びるように、私たちは自然と議論に加わりたいと思うのだ。だからこそ、その思考はあくまでも自律的なもの、真に思考と呼ばれるに値するものなのである。
そもそもカントは、この洞察を、市井の人々が交わす議論を観察することによって得ている。おそらく彼は、カフェやサロンに赴き、その様子をしげしげと眺め、そこで展開される熱の籠った議論に心を打たれたのだろう。それは、人間は誰もが理性的な存在である、という彼の信念を確信的なものにしたに違いない。
私たちは、考えなければならないから、考えるのではない。考えたいから、考えるのだ。そして、「考えたい」という意志を触発するものこそ、他者との対話に他ならない。それが、思考と対話の関係をめぐる、カントの基本的な考え方である。
人間には、思考したいという欲求がある。そしてその欲求は議論の場において開花する。それなら、話は簡単だ。人々に無限に議論させればよい。気が済むまで対話させればよい。それで人間はどんどん思慮深くなり、どこまでも啓蒙されていく。ここまでの考察を総合すれば、そうした結論が見えてくる。
ところが、カントはそのように楽観的ではない。
カントによれば、「人間には、集まって社会を形成しようとする傾向が備わっている」。そうした傾向が、議論への参加を動機づけ、対話したいという気持ちを促すのだろう。そのように「社会を形成してこそ、自分が人間であることを、そして自分の自然な素質が発展していくことを感じる」10ことができる。この意味において人間はその本質において社交的である、と言える。
しかし、人間にはこれと相反する性質もまた備わっている。すなわちそれは、「一人になろうとする傾向」であり、「孤立しようとする傾向」であって、「すべてを自分の意のままに処分しようとする非社交的な傾向」に他ならない11。カントは、人間に備わるこの相反する性質を、「非社交的な社交性」12 と呼ぶ。
カントは、この矛盾を、ありのままに肯定する。彼は、社交性も、非社交性も、人間の生には必要であると考えるのだ。
社交性は、人間が他者と関わり、社会を形成するために必要である。人間はそこで、「牧歌的な牧羊生活」を送ることになり、「仲間のうちで完全な協調と満足と相互の愛」を謳歌することになる 13。しかし、そうした居心地のよい領域に留まり続けていれば、成長することはない。新しい挑戦をすることはない。
それに対して、非社交性は、そうした他者との関係性から距離を取らせ、周りよりも優れた存在であろうとすることへと、人間を促す。カントによれば、こうした非社交性こそが、「人間にそなわるすべての力を覚醒させ、怠惰に陥ろうとする傾向を克服させ、名誉欲や支配欲や所有欲などにかられて、仲間のうちでひとかどの地位を獲得するようにさせる」14 。つまり非社交性は、ただ仲間と協調するだけではなく、仲間と切磋琢磨すること、それによって自らに新しい可能性を開いたり、自らを成長させたりするのである。
だからといって、非社交性だけがあればよい、ということではない。もしそうなれば、人間はただ敵対し、争い合うだけになってしまう。それどころか、前述の通り、人間が社会のなかで、言い換えるなら仲間によって認められた居場所のなかで、はじめて自己を実現できる存在である以上、やはり人間には社交性が必要なのだ。
したがって、非社交的社交性は、社交性と非社交性という、相反する性質の適正なバランスを要求する。どちらが欠けても、私たちは人間らしい生活を営むことができない。私たちは、仲間と協調しようとしながらも、同時にその仲間よりも優れた存在でありたいと思う。それは人間が、仲間との関係性のなかで自己実現しながら、同時に仲間と切磋琢磨することで自らを成長させるからだ。
対話に関するカントの思想は、こうした人間の相反する性質を前提として展開される。すなわち人間は、一方において、他者との対話を自ら求める。しかし、他方で、対話することを忌避しもする。彼にとって、対話は楽しいものであると同時に、苦痛でもあるのだ。
カントは人間が非社交的な社交性を持つ生き物であると考える。そしてこのことは、思考と対話をめぐる彼の思想を、いっそう複雑なものに変えていく。
前述の通り、彼は、あらゆる人間が理性的な存在であり、思考する力を持つと考えていた。しかし、その潜在的な思考を開花させるためには、本人が自分から思考したいと思えるような状況を準備する必要がある。たとえば道徳的な問題をめぐる議論や、他者との対話のなかで人間は思考したいという意志を抱く。人間が一面で社交的な存在であるから、つまり他者と関わることを望む存在であるがゆえである。
しかし、他方において、人間には他者と関わることを忌避する側面もある。そうした傾向は、議論を前にしても発露するに違いない。すなわち私たちは、議論や対話を嫌いもするのだ。
他者と議論したり対話したりすることが面倒だ、と感じることがあっても、まったく不思議ではないし、むしろそんな経験はいくらでもあるのではないだろうか。自分の言ったことに対して、誰かが反論してきたり、問い直したりしてくる。その結果、前言を撤回したり、自分の理解が浅かったことを認めなければならなくなったりする。場合によっては、論破されたり、批判されたりすることもある。そんなことが楽しいはずがない。
また、こうした非社交性は、下らない競争を引き起こしもする。対話は、しばしば、知識のひけらかし合いになる。あるいは、直接的であれ、間接的であれ、ただの自慢の応酬にもなりうる。そうなると、対話はもはや意味をなさなくなる。知識のひけらかしや自慢をする人は、相手の話を聞かず、自分が相手よりも優れていることを認めさせようとしているだけだからだ。
前述の通り、カントは思考を、自分の立場を逃れ、他者の立場から物事を考えることと捉えていた。しかし、知識のひけらかしや自慢合戦に陥った対話は、思考を自分の立場へと固着させ、他者の立場への視野を閉ざすことになる。それはむしろ思考を妨げる。人間の非社交性は思考を閉塞させるのだ。
そうであるとしたら、私たちは、人間には思考することを望む意志が備わっている、などという楽観的な洞察に居座るべきではないだろう。たとえそれが真実だとしても、人間には思考することを拒否し、知識をひけらかしたり自慢したりすることで、対話を破壊しようとする傾向も備わっている、ということも言わなければならないだろう。人間にはその両面が存在するのだ。
カントは、人間の非社交的な社交性を肯定する。同時に、人間はあくまでも啓蒙されるべきであり、自律的に思考するべきである。そうである以上、たとえ人間の非社交性を認めざるをえないのであったとしても、知識のひけらかしや自慢によって対話を破壊することは、避けるべきなのだ。そしてその上、人間から非社交性が解消されることはないだろうし、それはむしろ人間にとって有害ですらある。
このように考えるとき、思考と対話の望ましい関係を作り上げるために、残されている可能性は一つである。それは、非社交性と両立するような形で、対話の場を設計することだ。人間が、他者と議論したり対話したりすることを面倒に感じ、隙あらば知識をひけらかしたり自慢したりする存在であることを前提にしながら、それでも健全に機能する対話のスタイルを、考案することだ。それが、人間を啓蒙し、自律的な思考を促進するためには求められるのである。
では、そうした対話のスタイルとは、いったいどのようなものだろうか。カントはどんな対話の設計を提案するのだろうか。それを、次回のテーマにしていこう。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。
- イマヌエル・カント『判断力批判』熊野純彦訳、作品社、二〇一五年、二五七頁。
- 前掲書、二五七頁。
- 前掲書、二五八頁。
- 前掲書、二五八頁。
- 前掲書、二五八頁。
- イマヌエル・カント『永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編』中山元訳、光文社、二〇一三年、一〇頁。
- イマヌエル・カント『実践理性批判2』中山元訳、光文社、二〇一五年、二二三頁。
- 前掲書、二二〇−二二一頁。
- 前掲書、二二一頁。
- イマヌエル・カント『永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編』中山元訳、光文社、二〇一三年、四〇頁。
- 前掲書、四〇頁。
- 前掲書、四〇頁。
- 前掲書、四二頁。
- 前掲書、四一頁。