東京・恵比寿にある、「写真集食堂めぐたま」では、美味しい料理や飲み物を愉しみながら、僕が集めた古今東西の写真集の蔵書、5000冊余りを自由に閲覧することができる。家の中でどんどん増殖して、本棚からはみ出し、床にまで溢れ出てきていた写真集の置き場所と、旧知の料理人、おかどめぐみこさんが腕を振るうことができる食堂という一石二鳥のアイディアを実現できるスペースとして、2014年にオープンした。以来、コロナ禍でお店が開けない時期もあったが、現在はようやくほぼ通常通りの営業ができるようになった。
その「写真集食堂めぐたま」のメニューに「亡命ロシア風鶏の煮込み」と称する鶏肉のシチューがある。実はこのメニューの誕生については、僕も多少かかわりがある。

めぐたま食堂の「亡命ロシア風鶏の煮込み」
ある日、例によって本屋さんで「書棚のきのこ狩り」をしていると、ピョートル・ワイリ/アレクサンドル・ゲニス著、沼野充義/北川和美/守屋愛訳の『亡命ロシア料理』(未知谷、1996年)という本が目についた。そのタイトルを見た瞬間、何かひらめくものがあった。リアルなきのこ狩りでも、「書棚のきのこ狩り」でも、大事なのは「きのこ目」である。つまり、落ち葉や草むらに隠れてはっきりとは見えないきのこを判別し、探り当てる能力のことだ。きのこ狩りを繰り返していると、だんだん「きのこ目」が育ってきて、たとえば本のタイトルや装丁をぱっと見ただけでも、そこにきのこが生えているかどうか判別できるようになってくるのだ。
『亡命ロシア料理』の場合は、何といっても「ロシア」が決め手になる。前回の「日々のきのこ」にも書いたように、ロシア人は世界に冠たる「きのこ民族」である。当然、ロシア料理にもきのこはふんだんに使われている。ということは、この本の中にもきのこを使ったメニューが紹介されているに違いないと踏んで、ページをパラパラとめくってみたら、まさに思った通りの大当たりだった。同書の第16章は「キノコの形而上学」と題されていて、二人のロシア人の著者たち(ワイリはラトヴィアの出身だが)のきのこ愛が、たっぷりと綴られていたのだ。

『亡命ロシア料理』P・ワイリ/A・ゲニス
その内容について述べる前に、著者たちがなぜこの本を書くに至ったかを記しておこう。1949年、ラトヴィアのリガ生まれワイリと、1953年、ロシア中部のリャザン生まれのゲニスは、リガでジャーナリストとして活動していた。ところが旧ソ連時代の社会体制の息苦しさに耐えられなくなり、ともに1977年にアメリカに亡命する。以後、ニューヨークを拠点として、現代ロシア文学を紹介する二人組の文芸評論家として広く知られるようになった。
二人にとって、「自由の国」アメリカでの生活は満足すべきものだったが、ただ一つ我慢ならないものがあった。アメリカの食べものの不味さである。その彼らが「アメリカの不味いジャンクフードを罵倒しながら、故郷の味を懐かしみ、本物のロシア料理の作り方を読者に伝授すると同時に、ロシアとアメリカの両者を視野に入れた文明批評を行なった本」(「誰も知らない、とても美味しいロシア――亡命ロシア料理の『詩学』に向けて(訳者あとがき)」、それが本書なのだ。ということは、当然ながらこの本には彼らにとっての「魂」の発露というべき数々のロシア料理のメニューがたっぷり詰まっている。その中に、むろんきのこ料理も含まれていることはいうまでもない。
『亡命ロシア料理』の第16章「キノコの形而上学」は、次のように書き出されている。
キノコは、われわれの何人かの知人と同様、植物と動物の間で中間の立場をとっている。学者たちはいまだに、キノコには魂があるか、という問題を解決していない。しかし、森でヤマドリタケを見つけたことのある人なら誰でも、魂があることを絶対に信じて疑わないだろう。ヤマドリタケはずんぐりして善良な魂をもっているし、アンズタケはコケティッシュでせっかちな魂を、アミガサタケ はしわくちゃな魂を、カラハツタケはスラヴ派の魂をもっている。[中略]魂なしで生えているのはマッシュルームだけである。なぜなら、マッシュルームは畝で栽培されているのだから。
この書き出しからして、ワイリとゲニスが筋金入りのマイコフィリア(きのこ愛好家)であることがわかるだろう。その彼らは、苦労して「ポーランド産かイタリア産の干しヤマドリタケ」などの材料を手に入れ、ディル(ハーブの一種)やサワークリームで味つけした「キノコ・スープ」、干しヤマドリタケを煮てみじん切りにし、サワークリーム、バター、卵、胡椒、タマネギ、パン粉を加えて球状に丸めて揚げた「キノコのミートボール」、マッシュルームを縦に薄切りにしてレモン汁で薄めたサワークリームを注いだ「マッシュルームの反=料理的食べ方」などを次々に紹介している。どれも美味しそうだし、レシピもシンプルなので誰にでもすぐ作ることができそうでもある。
だが、「写真集食堂めぐたま」で出している「亡命ロシア風鶏の煮込み」は、実はこの「キノコの形而上学」の章で紹介されている料理ではない。おかどめぐみこさんが、まだ「写真集食堂」をオープンする前にうちに遊びにきたとき、たまたま本棚で『亡命ロシア料理』を見つけ、その内容に興味を持って、自分でも注文して購入した。おかどさんが最も引きつけられたのは、その第5章「帰れ、鶏肉へ!」で紹介されていた鶏肉のシチューだった。それは、こんなレシピのメニューである。
鶏肉の大きなかたまりと乱切りにしたタマネギを用意する(鶏肉四〇〇グラムにつきタマネギ中二個)。鍋の底にバターの小さなかけら、月桂樹の葉、粒胡椒、鶏肉、タマネギを入れる。水は一滴もいらない! 塩を振り、弱火にかけて、その場を離れる。
掃除なり、愛なり、独学なりに精を出せばいい。台所にいなくったってすべてはうまくいくのだから。一時間半程たてば、汁の滴る素晴らしい料理ができあがる。それにはどんな付け合わせでも結構。ゆでたジャガイモでも、ライスでも、マカロニでも。
あまりにも簡単すぎると思われる方もいるかもしれない。でも、何もしないで1時間半ほど放っておけば、本当に「汁の滴る素晴らしい料理」ができあがっている。水を1滴も入れないというのが最大のポイントで、タマネギと鶏肉の水分だけで充分なのだ。火から下ろす5分前にサワークリームとニンニク、ハーブ類などを加えて味つけをする。やはり、サワークリームが入っていないとロシア料理という感じがしない。
『亡命ロシア料理』の著者たちは、きのこのことも忘れてはいない。「オニオン・ソースの鶏肉のいいところは、添えるもので変化をつければ、しょっちゅう作れるということだ。たとえば、鍋に干しキノコをすぐに、二、三個入れてもいい」とも書いている。おかどさんは、このレシピを応用して、「亡命ロシア風鶏の煮込み」にきのこを入れるようにした。本当なら香り高いヤマドリタケ(ポルチーニ)がいいのだろうが、手に入れるのがむずかしいので、八百屋さんで売っているような栽培種のきのこを何種類か入れる。鶏肉は「大山鶏」という名品を使っている。そうやって、開店後すぐに「写真集食堂めぐたま」に登場した「亡命ロシア風鶏の煮込み」は、大好評で、いまも人気メニューの一つになっている。
料理の分野におけるロシア人のきのこ愛の強さ、深さがわかるのは、『亡命ロシア料理』だけではない。同書の共訳者の一人、沼野充義さんの妻でロシア文学者の沼野恭子さんの著書『ロシア文学の食卓』(NHKブックス、2009年)には、ロシア文学の中に登場するさまざまな料理が、「前菜」「スープ」「メイン料理」「サイドディッシュ」「デザート」「飲み物」という章立てで順番に紹介されている。そのあちこちに、きのこを材料にした料理が出てくるのはいうまでもない。
たとえば、アントン・チェーホフの「海の精」(1887年)という短編小説にも、きのこ料理が紹介されている。ある会議の後で、議長が意見書を書き換えている間に、会議のメンバーの間できのこ談義に花が咲くのだ。
(……)それから生のカブに塩をかけて食べ、それから、もう一度ニシンですね。でも、何よりも美味しいのは、あなた、塩漬けのカラハツタケですよ。細かく刻んでイクラのようにして、そうですね、タマネギとオリーブ油を混ぜる……絶品です! でも、カワメンタイの肝となったら、これはもう悲劇としかいいようがない!」
「ふむ」名誉調停判事が、眉をひそめて賛同した。「前菜には、それから……ほら、ヤマドリタケがいいですよ」
「まったく、まったく、まったくそのとおりです……タマネギと、月桂樹の葉と、いろんな香辛料を入れてね。鍋を開けると、湯気がたって、キノコの香りがする……涙が出てきます! (……)
この件の後半部分に出てくるヤマドリタケの鍋料理は、どうやら「亡命ロシア風鶏の煮込み」に近いもののようだ。
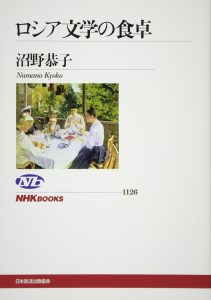
『ロシア文学の食卓』沼野恭子
もちろん、チェーホフだけではなく、多くの文学者たちが、きのことその料理を作品の中に登場させている。『ロシア文学の食卓』に入っている主な作家と作品は以下の通りである。ゴーゴリ『死せる魂[第一部]』(1842年)、イリヤ・イリフ&エヴゲーニィ・ペトロフ『十二の椅子』(1928年)、ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』(1929~40年)、ゴンチャロフ『オブローモフ』(1859年)、プーシキン『エヴゲーニィ・オネーギン』(1825~1832年)。こうしてみると、実に錚々たるロシア文学の巨匠たちが、そのきのこ愛の賜物とでもいうべき作品を執筆していることがわかるだろう。
沼野恭子さんの訳による、彼らの小説や詩の抜粋を読んでいるだけで、きのこの香りがそこら中に漂っているような気がしてくる。生唾が湧いてくる。今夜は写真集食堂めぐたまで、「亡命ロシア風煮込み」を注文することにしよう。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。



