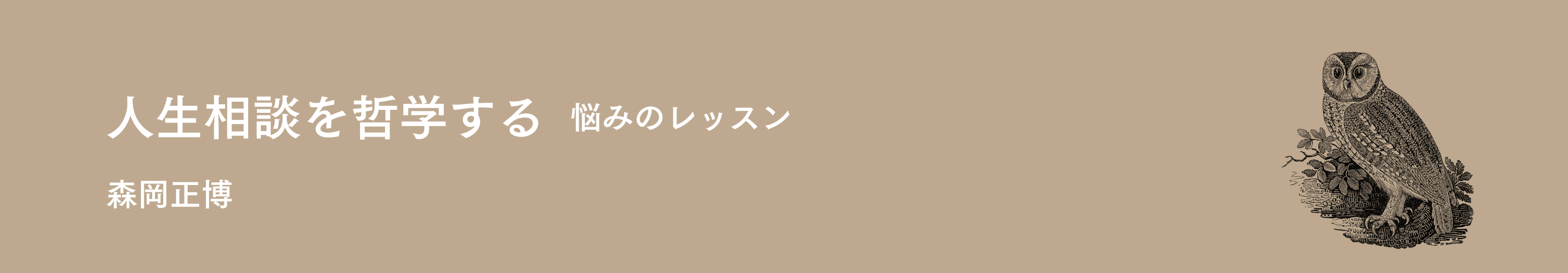Q7:私は哲学が好きですが、哲学者の肩書きに定義はあるのでしょうか。哲学者の苦悩や喜びはどんなものでしょう? (中学生 女性 14歳)
A7: 哲学者の肩書きに、定義はありません。自分とは何か、時間はなぜ流れるのか、生と死の意味は何かといった問題に、徹底して自分の頭で考え続けていくことができれば、あなたはもう哲学者です。医師や弁護士になるためには、難しい国家試験に受からなくてはいけませんが、哲学者になるためには何の資格も不要です。
極端な話、「私は哲学者である」と宣言しさえすれば、誰でも哲学者になることができます。その人がどんな職業に就いているかも、ぜんぜん関係ありません。たとえば古代ローマの哲学者マルクス・アウレリウスは、ローマ帝国の皇帝でした。かと思えば、古代ギリシアの哲学者ディオゲネスは、いまで言えばホームレスの生活をしていました。
哲学の愛すべきところは、世間の価値観からまったく自由になって、ものごとを突き詰めて考えることができる点です。たとえば、私たちは過去・現在・未来と時間が流れると思っていますが、それを疑う哲学者もいます。存在するのは「いま」だけで、その他はすべてまぼろしだと言うこともできるのです。
また、私が死んだらすべてが無になるのだとしたら、私はどうして自分の人生を必死で生きる必要があるのでしょう。それを考え抜くのも哲学の仕事です。
自分自身の生にとってもっとも大切な問題を、狂気のように追求せざるを得ないのが哲学者の苦悩であり、また喜びなのです。
質問の背景
質問者は中学生の女性です。哲学が好きで、自分とは何者なのか、生きることや死ぬことの意味などについてよく考えるとのことでした。自分は職業として哲学をしたいというわけではないけれども、どうすれば哲学者の肩書きを名乗れるのか、大学に入って論文を書いて認められたら哲学者なのか、それとも自分で哲学者だと思ったら哲学者なのか、とても気になると質問してこられました。
このような疑問を持っている方は多いでしょう。私は、自分で宣言すれば誰でも哲学者になることができると回答しました。哲学者とはそもそも職業ではなくて、存在や生死の根本問題を、世間の価値観から自由になって、とことん突き詰めて考える人のことを指しているからです。
この点について、さらに書いてみることにしましょう。
ふたたびあなたへ
あなたがおっしゃるように、どうしたら哲学者と呼ばれるようになるのか、とても不思議ですよね。私もよく質問されます。私は自分のことを哲学者と称していますが、それは単に自分でそう宣言しているだけであって、どこかの団体や学会などから認められているわけではありません。逆に、自分のことを哲学者と称していると、哲学研究の専門家たちから冷たい視線で見られることもあります。どうしてそんなふうになってしまったのでしょうか。
哲学の歴史を振り返ってみましょう。古い時代では、ローマ皇帝であっても、ホームレスであっても、哲学的な思索を深く掘り下げた人物は哲学者と呼ばれました。かならずしも彼らが生きている同時代に哲学者と呼ばれたわけではありませんが、後の時代から振り返って、「ああ、あの人はたしかに哲学者だった」と言われてきたのです。ブッダも同じで、ブッダは自分を哲学者だとは思っていませんでしたが、ブッダの思索したことを後の時代の研究者たちが学問的に整理してみると、「ああ、この人も哲学者じゃないか」と気がついたのです。
その後、19世紀になって学問の細分化が起き、哲学もまた専門分化した学問として位置づけられるようになりました。20世紀になるとその流れはさらに進み、今日では哲学の内部で非常に細かい専門分化が起きています。たとえば、ある人はカントの哲学の中にある美学という部分について研究をずっと続けていますし、また別の人は、立派な人間とはどういう人なのかを考える徳倫理学という分野の研究を続けています。これらの人たちは、自分の専門領域を狭く絞って、緻密に研究しているのです。彼らのことを、「哲学研究者」と呼んでおきましょう。哲学研究者になるためには、大学院に進学して博士号を取得しなければなりません。実は20年ほど前まではそんなこともなくて、博士号を持たなくても大学教員になることはできました。私が大阪府立大学の教授になったとき、私は博士号を持っていませんでした。しかしその後、博士号を持たずに大学で教えるのは良くないという風潮が強くなり、私も2015年に博士号を取得しました。博士になるためには、何かの専門家でなくてはならないので、私は「脳死の哲学」という専門分野で博士論文を書きました。
ですから、もし哲学研究者という肩書きを名乗るのでしたら、博士号を持っていることが大事というのが、いまの流れだと思います。実際に、大学の哲学の教員を募集するときには、博士号の取得を条件とすることがとても多くなっています。もちろん、博士号を持たず、大学に所属せずに、立派な哲学研究をしている人たちはたくさんいます。しかし博士号を持って大学に所属している研究者たちの中には、そのような市民研究者のことを「素人」と呼んで馬鹿にする人がいるというのも事実なのです。
悩み相談からずれますが、もう少しこのまま書いていきますね。
では、哲学者と哲学研究者は違うのでしょうか。これはなかなか難しい問題で、専門家の意見が一致するクリアーな答えがあるわけではありません。私は次のように考えています。哲学者というのは、世界があるとは何か、人が生きるとは何か、正しさとは何かといった、どんな人でも一度は直面するであろう根本問題について、それを首尾一貫して説明できるような考え方を作り上げようとしている人のことです。そして同じような問題を考えてきた過去の先人たちや、同時代の先輩たちの思索からヒントを得つつ、その根本問題を自分の頭で考え、その答えを自分の言葉で表現しようとしている人のことです。
このように考えてみると、哲学者であるためには、かならずしも哲学研究者である必要はないということになります。それらの根本問題を、先人たちの力を借りながら自分の頭と言葉で考えて表現していくことさえできれば、その人は哲学者と呼ばれるべきであり、カントの専門家とか生命倫理の専門家として博士号を持っている必要はないのです。あなたのような中学生であっても、哲学者になることはできるのです。これとは逆のことも言えます。哲学研究者だからと言って、かならずしも哲学者であるわけではありません。たとえば、ある哲学研究者は、カントの生い立ちや、彼のすべての作品や、その時代の学問状況などを詳しく調べて、カントの哲学がどのようなプロセスを経て作り上げられたのかを一生かけて研究しています。立派な哲学研究者なのですが、しかしながら、その研究者自身が、存在とか、時間とか、正しさとかについて自分の頭と言葉で考えてきたのかと言えば、そういうものはとくに発表していません。このような場合、この人は哲学研究者ではあっても、哲学者とは呼べません。もちろん、一流の哲学研究者でありかつ哲学者である人もたくさんいます。『存在と時間』という本を書いたハイデガーは、そのような人でしょう。
ですから、哲学者は大学の内側にもいますし、外側にもいます。博士号を持っている場合もありますし、持っていない場合もあります。社会的地位の高い人もいますし、どん底の階層の人もいます。同時代ですでに名声を博している人もいますし、まったく無名にとどまる人もいます。というのも、哲学者であるかどうかというのは、その人の社会的な地位や活動によって決まるのではなくて、その人がどのような思索をしてそれを表現しようとしているかによって決まるからです。
では、そもそも「哲学」とは何でしょうか。私がさきほど哲学者について述べたときの文章を用いると、哲学とは、「世界があるとは何か、人が生きるとは何か、正しさとは何かといった、どんな人でも一度は直面するであろう根本問題について、それを首尾一貫して説明できるような考え方を作り上げようとすること」であると私は考えています。しかし、これはけっして哲学界のコンセンサスではありません。私に賛成してくれる人も多いでしょうが、私のように考えない人もたくさんいるのです。たとえば、過去の偉い哲学者の書いたものに対して、緻密な注釈と解釈をほどこしていくことこそが哲学の王道だと考えている人もいます。またそれとは異なって、みんなで輪になって哲学的な問いについて自由に対話をし、気づきを得ていくことが哲学だと考えている人もいます。つまり、「哲学とは何か?」という問いに対して、哲学者たちのあいだには意見の一致はありません。そればかりか、哲学の営みのなかには、「哲学とは何か」について考えることそれ自体が組み込まれているのです。これは古い時代から現代に至るまでずっとそうでした。つまり「哲学とは何か」という問いにひとつの答えはなく、哲学をする人がそれぞれ自分の答えを見つけなければならないのです。
「哲学とは何か」についてひとつの答えがないのですから、「哲学をしている人すなわち哲学者とはどういう人か」という問いに対しても、ひとつの答えはないはずです。その答えは各自が考えていくしかありません。ですから、ある人が、哲学者とはどういう人なのかについてきちんと考えたうえで、「私は哲学者だ!」と宣言したとしたら、私たちはそれを尊重しなくてはなりません。「『私は哲学者である』と宣言しさえすれば、誰でも哲学者になる」と私が回答で書いたのは、こういう意味だったのです。
ところで、哲学者というと、ソクラテスやカントの名前が出てきます。なぜ彼らが哲学者の代表のように言われるかというと、彼らはそれまでの哲学のものの考え方を大きくひっくり返して、新しいものの考え方を打ち立てたからです。その新しいものの考え方が非常に魅力的だったので、その後の人たちは、もう彼らを無視しては哲学できなくなったのです。彼らはいわゆるオリジナルな哲学者だと言えます。そのような哲学は後世に残っていきます。
では、さほどオリジナリティのない哲学しか生み出せなかった人たちや、そもそもオリジナルなものを生み出せなかった人たちは哲学者と呼べるのでしょうか。私は哲学者と呼ぶべきだと思います。もしその人たちが、「世界があるとは何か、人が生きるとは何か、正しさとは何かといった、どんな人でも一度は直面するであろう根本問題について、それを首尾一貫して説明できるような考え方を作り上げよう」としていたならば、たとえその結果としてオリジナルなものを生み出せなかったとしても、その人たちは立派な哲学者なのです。なぜなら、哲学の神髄はそのような根本問題に対して正面から答えようとするところにあるからであり、答えた結果が人々にどう受け取られるかということはあくまで二次的なものにすぎないからです。哲学のいとなみの中心にあるのは、自分のために考えるということです。極端な言い方をすれば、これらの問いについて徹底的に考えて、何かの答えを出さないかぎり私は死んでも死にきれない、という気持ちによって哲学者が突き動かされているという面があると私は思います。これについては異論があるかもしれないので、つけ加えておくと、私はそういう気持ちに突き動かされてこれまで哲学をしてきました。ですから、私はまさに自分自身のために哲学をしているのだし、私はそのようなタイプの哲学者なのです。
オリジナルな哲学を生み出せる哲学者もいるし、そうでない哲学者もいる。そしてどちらも本物の哲学者である。これが私の考え方です。オリジナルな哲学者になるためには運も必要です。デカルトは「我思うゆえに我あり」という根本原理を打ち立てました。彼は『方法序説』という本で、この世でほんとうに正しく確実なものはいったい何だろう、と考えました。目の前に見えている風景は、ひょっとしたら単なる錯覚かもしれないから、ほんとうに正しく確実なものとは言えません。数学の定理でさえも、我々は間違った推論をたびたびするので、確実なものとは言えません。自分の頭の中にあるいろいろな考えも、やはり間違っている可能性があるので、確実なものではありません。ではいったい何がほんとうに正しく、確実なものと言えるのでしょうか。デカルトは次のように書いています。
しかしそのすぐ後で、次のことに気がついた。すなわち、このようにすべてを偽と考えようとする間も、そう考えているこのわたしは必然的に何ものかでなければならない、と。(谷川多佳子訳『方法序説』岩波文庫、1997年、46頁)。
すなわち、世界の中のすべてのものごとは間違っている可能性があるのですが、しかしそんななかで、けっして疑うことのできないもの、ほんとうに正しく確実なものがひとつだけあるのです。それは何かというと、「私がいま考えている」ということです。「私がいま考えている」ということがいまここで起きている。それを、私はけっして疑うことができません。デカルトはこのようにして、すべての学問の根本で支えることのできる絶対的な真理、すなわち「私がいま考えているということがいまここで起きている」ということの絶対的な正しさを発見したのです。デカルトはこれを「我思う故に我あり」と表現しました。
デカルトの発見は、その後の西洋哲学の歴史を大きく変えていくきっかけとなりました。これはヨーロッパの中世哲学から近代哲学への曲がり角で起きた出来事であり、まさにその時期であったからこそ巨大なインパクトを持ち得たという面があります。実際、デカルト以前にもこのような考え方は存在しており、またデカルト以降に自力でこの命題を発想した人もきっとたくさんいたことでしょう。デカルトはたまたまあの時期にヨーロッパにいたという運があったおかげで、「我思うゆえに我あり」は西洋哲学において決定的な役割を果たすことができたのだと私は思います。哲学者にとって、運もまた大事なのです。と同時に、もしデカルトの書物が発売直後に焚書になって地上から消えていたとしても、デカルト自身はみずからの思索によって「我思うゆえに我あり」を脳内に生み出したことで大きな哲学的な達成感を味わっていたはずです。「我思うゆえに我あり」が世に知られることがなかったとしても、デカルトはきっと哲学者として幸福だったでしょう。
私は、自分自身のために答えを見つけたいと思っていると同時に、自分にしかできないオリジナルな哲学的な思索を作り上げたいとも思っています。それに向かって進んでいくことが、私の生きる意味になっています。このような生き方をすることの苦悩は、過去の著名な哲学者たちの偉業があまりにも素晴らしすぎて、とてもそれに匹敵するようなものは作れないのではないかという絶望に陥って抜け出せなくなることです。現代人は長命になったので私にはまだ充分に時間が残されているはずなのですが、それでも苦しみと焦りはつのります。哲学をすることの喜びは、思索の果てに新しいアイデアやイメージが思い浮かび、それを自分の哲学の構築物の中に美しく取り込むことができたときに感じます。それは大きな達成感であり、哲学をやってきてよかったと思う瞬間です。そのとき、私は哲学者でよかったと心から思います。
哲学は、ものの考え方の根本のところを問いなおします。たとえば、私以外の人間は実はよくできたロボットだと考えることのどこがおかしいのかとか、眠りに落ちたときに私は死ぬのであり、次の日に起きたときの私は、前日までの記憶をもって生まれてきたまったく別の人間なのだと考えてもいいではないかとか、そのようなことを突き詰めて考えます。つまり哲学者は、私たちの多くが「当然そうに決まっている」と信じている常識や価値観をその根本から疑ってみるのです。これは哲学者がもっとも得意とする知的な作業なのですが、あまりそれをやりすぎると危ない領域に入ってしまうことがあります。たとえばニーチェは、19世紀のヨーロッパで、当時の西洋世界の基本的な価値観を支えていたキリスト教を徹底的に批判します。そして「神は死んだ」と宣言するのです。そして神に代わる新たな価値の原理を探そうとしますが、その試みの途中で精神に異変を生じ、最後は精神病院で一生を終えることになってしまいました。21世紀の現在の視点からニーチェの思索を読み直すと、ニーチェの発想はたいへん面白いし、共感できるのです。しかしニーチェが生きていた時代では、彼に共感してくれる人はさほど多くはありませんでした。このように、哲学者が自分の思索に忠実になって、本気で筋を押し通そうとすると、それは一般社会からは狂気とみなされる世界へと突っ込んでしまうことになる危険性があります。みずからのオリジナリティを大事にする哲学者は、いつも狂気の世界と隣り合わせだと言えるのかもしれません。これは哲学がかかえこんでしまうダークサイド(暗黒面)です。ニーチェの死後、その哲学にヒトラーが惹きつけられたのは有名な話です。
ずいぶん遠いところまで話を進めてしまいました。
こういう話を聞くと、哲学はなんか難しそうで、ちょっと怖いなと思われたかもしれませんね。でもこれは哲学の一側面にすぎません。哲学には、もっと楽しくて、私たちの頭脳を柔らかくしてくれる機能があります。小学校・中学校・高校で、「哲学対話」とか「哲学カフェ」という名の授業をする学校が少しずつ現われてきました。これからはもっと増えていくでしょう。これは、私たちがよく考えることのある疑問、たとえば「友情とは何か」とか「美しいとはどういうことか」などの問いについて、みんなで気楽に話し合いながら、その本質に迫っていこうとする試みです。これらの問いには、けっしてひとつの正解があるわけではありませんから、みんなで議論をしているうちに、「ああ、そういうふうに考えることもできるのか」とか、「そういう見方をすると世界が違って見えてくるなあ」などの気づきを得ることができます。もしあなたの学校にそのような授業がなかったら、議論好きの友だちと「哲学対話」のグループを作ってみてはどうでしょうか。以前の回答でも述べましたが、「哲学対話」では、自分の頭を使って考え、自分の言葉でそれを表現し、そして他人の意見を一方的に否定しないことがとても大切です。実はこれは哲学を行なっていくときの基本的なルールでもあるのです。知識を持っている人が偉いわけではない(ソクラテスはこれを「無知の知」と言いました)というのも、大事なことです。
もしあなたが哲学についてもっと興味を持ってきたら、私が本書のいくつかの章で紹介した哲学の本を少しずつ読んでみてはどうでしょうか。分からないところはどんどん飛ばしていっていいですから、楽な気持ちで斜め読みをしていきましょう。すると、どこかで、心に響く文章に出会うかもしれません。その文章を何度も眺めながら、自分の想像力をいっぱい広げていってみましょう。私も中学生の頃には、そのようにして哲学の本を読んでいました。哲学を好きな人が増えるのは、私にとって、とてもうれしいことです。哲学への関心をぜひ持ち続けていってください。
ご愛読ありがとうございました。本連載を加筆訂正し、書下ろしを加え、書籍化する予定です。詳細は後日、SNSなどでお知らせいたします。
*本連載のご感想、質問をぜひお寄せください。また、本連載をもとに哲学カフェや読書会、学校での授業などを開催される際もお知らせくださいますと幸いです。「連載・人生相談を哲学する」という件名で、ikinobirubooks@moshbooks.jpにメールをお願いいたします。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。