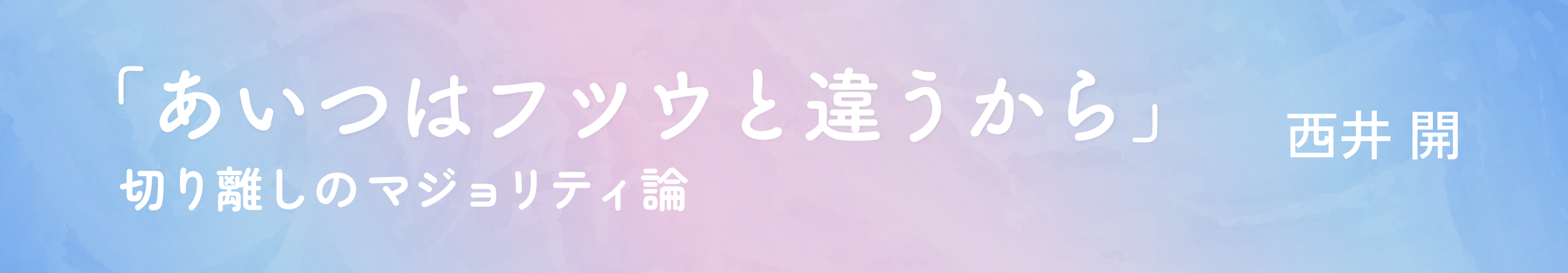第3回は公開終了いたしました。
西井開(にしい・かい)
1989年大阪府生まれ。立命館大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。現在日本学術振興会特別研究員。臨床心理士。公認心理師。専攻は臨床社会学、男性・マジョリティ研究。一般社団法人UNLEARN(DV加害者更生カウンセリング)所属。モテないことに悩む男性たちの語り合いグループ「ぼくらの非モテ研究会」発起人。著書に『「非モテ」からはじめる男性学』(集英社新書)がある。
- 第1回「そういう男性っていますよね」?
- 第2回「からかい」を掘り下げる※公開終了
- 第3回教師の暴力をたどる※公開終了
- 第4回趣味をめぐる接点と切断※公開終了
- 第5回境界の向こう側に追いやること、追いやられること※公開終了
- 第6回ホモフォビアを吸い込む※公開終了
- 第7回加害性を剥ぎ取る※公開終了
- 第8回笑う支援者の危うさ
- 第9回〈切り離し〉とは何か?