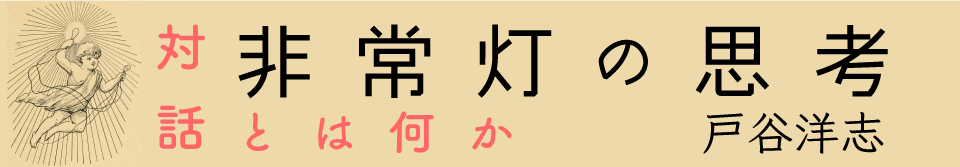第6回は公開終了いたしました。
戸谷洋志(とや・ひろし)
1988年東京生まれ。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科文化形態論専攻博士課程修了。現在、立命館大学大学院 先端総合学術研究科准教授。博士(文学)。専攻は哲学。現代ドイツ思想を中心にしながら、テクノロジーと社会の関係を研究すると同時に「哲学カフェ」を始めとした哲学の社会的実践にも取り組んでいる。著書に『Jポップで考える哲学』(講談社文庫)、『原子力の哲学』(集英社新書)、『スマートな悪』(講談社)、『ハンス・ヨナス 未来への責任』(慶應義塾大学出版会)、『未来倫理』(集英社新書)、『友情を哲学する』(光文社新書)、『SNSの哲学』(創元社)、『恋愛の哲学』(晶文社)、『悪いことはなぜ楽しいのか』(ちくまプリマー新書)、『生きることは頼ること』(講談社現代新書)、『メタバースの哲学』(講談社)などがある。
- 第1回破局と哲学的思考──あるいはストレッチの必要性について
- 第2回哲学対話とは何か──あるいは風呂場のタイルを動かしてみることについて※公開終了
- 第3回否定性を肯定するということ※公開終了
- 第4回発話に先行する対話──あるいは立食パーティーでの生存戦略について※公開終了
- 第5回対話の共同性──なぜ人は空気を読むのか?※公開終了
- 第6回「私」が「私」であるために必要なことは何か?※公開終了
- 第7回他者に自分を見ること、自分の中に他者を見ること※公開終了
- 第8回『人間の条件』における思考※公開終了
- 第9回この世界に自分を繋ぎとめる、もう一人の自分と出会う
- 第10回人間の社交性と非社交性
- 第11回楽しくなければ意味がない──内在的視線と外在的視線が交錯するとき
- 第12回(最終回) 対話を共同制作する