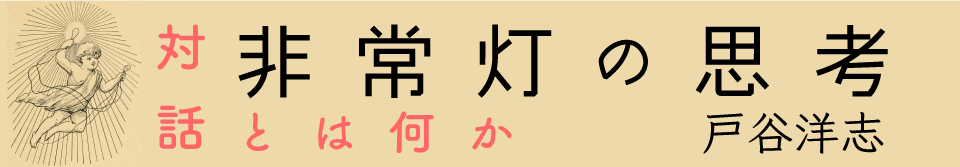私たちは、前回、社交性をめぐるカントの両義的な態度を検討した。人間は、一方において他者と対話することを好む。対話することを楽しいと思う。そして、対話のなかで思考することに喜びを感じる。人間は対話のなかで思考したいと思うのであり、そうした対話が、自律的な思考を育んでいく。しかし、その一方で、対話することを不愉快だと思う。相手と話を一致させることをうっとうしく思い、相手を出し抜いたり、論破したりしようとする。思考を触発する対話は、同時に面倒くさくもあり、疲労を催させもする。
しかし、対話にはメリットもデメリットもあるのだから、対話したい人はすればいいし、したくない人はしなくていい──そうした、一見中立的に見える相対的な立場を、カントは取らない。なぜなら、彼にとって人間は啓蒙されるべき存在であり、自らの理性を開花させ、自律的に思考できるようになるのは、望ましいことであるからだ。そして、そうした思考を育むために、他者との対話は絶好の舞台なのである。そうである以上、私たちは、たとえ対話が時として不愉快なのだとしても、他者と対話するべきである。
ただしそれは、本当は対話したくない人間に強制するものであってはならない。強制された瞬間に、対話の参加者は他律的になるからだ。対話の参加者は、あくまでも、思考することの楽しさに導かれるようにして、他者と対話するのでなくてはならない。
カントは、対話が不愉快なものになりうることに、極めて自覚的だった。たぶん、彼自身、たくさんの不愉快な対話を経験したことがあるのだろう。しかし、それでも、人間の理性にとって対話が重要な役割を果たすことを、信じて疑わなかった。
したがって彼は、対話がどうあるべきかを考えるとき、いかにしてそれを不愉快なものに陥らせないようにするか、という点を重視する。今回は、そのために彼が提案するいくつかの具体的なアドバイスを手がかりにしながら、その対話論の核心に迫っていこう。
対話を不愉快なものにしないためには、対話のなかでどのように振る舞うか、とは別に、どのような状況で対話するか、ということが重要である。どのような場所で、どれくらいの人数で対話をするのか──そうしたことは、よい対話を行う上で、決して軽視されるべき事柄ではない。むしろ、適切な状況を設定することは、対話にとって本質的な重要性を持っている。カントはそのように考える。
彼が望ましい対話の典型的な状況として挙げるのは、食事会である。みんなでテーブルを囲み、料理をつつきながら話を交わす──そうした状況を作ることで、人々は自然と気軽に会話することができる。ただし、食事会と言っても、ただ集まって食事をすれば、それでよいわけではない。彼は『人間学』において、よい対話を交わすための適切な食事会のあり方を、次のように分析している。
まず、対話を楽しむためにもっとも適した食事会とは、「男ばかりからなる趣味の深い(美芸に関して一致した)者同士による昼食会」1である。たとえば、芸術を好きな者同士が、最近観た作品に対する解釈を交換し合い、自由に語り合うような会合だろう。このように、人々が何らかの趣味を共有して語り合うことが、対話をより楽しいものにする。
ただちに注釈しなければならないが、ここにはカントの偏ったジェンダー観が表れているのは事実である。昼食会に参加できるのは男性だけであり、女性をそこから排除していた。したがってこの発想を額面通りに受け取って正当化することはできない。ただ、現代において彼を読む私たちとしては、その点を批判的に修正したとしても、その哲学から学ぶところはあるように思える。すなわち、趣味を共有した者同士の昼食会であれば、そこにどんな性別の人々が参加するのだとしても、問題はない。
興味深いのは、こうした昼食会について、カントが次のように述べていることだ。すなわち「こうした小ぢんまりとした昼食会は胃袋上の満喫というよりも──これは各人がそれぞれ単独で味わうことができる、──むしろ社交上の喜びを期待してきているのであって、胃袋上の満喫は本人たちにはただそこに至るまでの便宜手段にすぎないと映っているに違いない」。2 カントによれば、人々は自分の趣味について語りたいと思って、その食事会に集まってくる。しかし、「趣味について語ろう」と呼び掛けて、対話が始まるのではない。「ちょっと一緒にご飯でも食べよう」と言って、対話は始まるのである。そして、当然のことながら、その呼びかけによって集まってくる人々は、昼食ではなく、対話することを目的にくるのである。
対話を始めよう、と呼び掛けても、対話は始まらない。それには何らかの「便宜手段」が必要である。それはなぜなのだろうか。おそらくその理由の一つは、カントが洞察している通り、人間は非社交的な側面があるから、つまり対話を嫌悪する側面を抱えてもいるからだ。たしかに人間は一面において他者との対話を好む。しかし他方において、そうした対話を嫌悪し、他者を不快に感じることもある。だから「対話しよう」と言われると、興味をそそられる反面、警戒もする。対話ではない何かが目的であるかのように、対話を呼びかけなければならないのだ。
もしも「一緒にご飯でも食べよう」と呼びかけ、実際に食事から対話が発展し、その後で、対話によって不快な思いをすることがあれば、食事に集中すればいい。食べたものに関する感想をあれこれ言えばいい。そうやって対話を関係のない方向へと逃がしてやることができる。食事を「便宜手段」とすることは、保険的な機能も備えているように思える。そして、こうした便宜手段は他にもありえる。たとえば現代においては、お茶、たばこ、ゴルフ、ゲーム、一緒に帰ることなども、そうした手段になりえるだろう。
カントによれば、こうした食事会において重要なのは、すべての人が対話に参加できる、ということである。言い換えるなら、その目的が達成できるように、対話の場は設計されるべきなのだ。カントは、そうした観点に鑑みて不適切な食事会として、大人数による「豪華な夜会(どんちゃん騒ぎと大御馳走)」3を挙げている。なぜなら、大人数で宴会が行われると、どうしても「会話が滞ったり、あるいは逆に隣同士が勝手に固まって会話が小グループに分裂したり」4するという事態を避けられないからである。このような状況は、その場に対話に参加できない人を生み出す。そうした事態を回避するために、対話の場では「いつでも誰か一人が(ただ隣席の者とだけでなく)全員に向かって語りかけるという洗練さを備えていなければならない」。5 そのために適正な食事会の規模は、四人から一〇人である、とカントは述べる。
それでは、適正な呼びかけのもとで、適正な規模の食事会が開始されたとして、そこで交わされる対話はどのようなものになるのだろうか。対話なのだから、語りたい人が自由に語ればよいようにも思える。しかし、カントはそう考えない。食事会における対話は、あくまでも、厳密なルールに基づいて進行されなければならない。
彼はまず、そうした対話は三つの段階を経て進行していくべきである、と指摘する。第一の段階は、「世間話をする」6という段階である。そこでは、「その土地についての、ついでよその土地についての、私信や新聞で知ったそのニュース」7が交換される。したがって、会食に臨む人々は、そうしたニュースについて一定の知識を仕入れ、話せるように準備をしておくことが必要になるだろう。そして、世間話をしている間に、食事は大方終えてしまうのが望ましいという。この見解から、世間話にはかなりの時間を割かなければならないとカントが考えていたことがわかる。
第二に、「まじめに議論する」。8 議論が開始されるタイミングは、最初の食欲が満たされ、その場が盛り上がりを見せ始めたころである。世間話から議論へと切り替わるのは、単なる情報の交換に過ぎなかった行為について、誰かが「理屈」9を言い出したときである。それによって、人々はそれぞれが理屈について考えはじめ、自分の考えを語り始める。もちろん、そうなれば意見は対立する。しかしそれが対話をさらに盛り上げるのだ。カントは次のように述べる。
こうして最初の食欲が満たされると、座は早くもぐっと盛り上がってくる。というのは誰かが理屈をいい出すと、話題にされている同一の問題に関する判断が人によって食い違うことが避け難いし、しかも各人は自分の判断について一家言持っているから、そこに一大論争が巻き起こってそれが料理への食欲やワインボトルへの渇望を大いに刺激し、それが基となって論争がいっそう盛り上がるにつれて、かつ論争の輪が広がるにつれて人々の飲み食いはばくばくぐいぐいと進むからである。10
ただし、対話は議論で終わってはいけない。議論することは「一種の労働」であり、やがて「この力わざも面倒くさくなって」くる。したがって、対話は第三の段階として、「たわいのない機知のたわむれ」に移行する。それは、言い換えるなら、ただひたすら冗談を披露し合う、ということだ。カントはそこで相手を笑わせることができるなら、下ネタを利用することすら有効であると指摘している。
よい対話は、この三つの段階を踏まえて進行するのであり、それによって対話の参加者は満足して家路に就くことができる。言い換えるなら、対話が最初から最後まで議論で占められてしまったら、それはよい対話にはならない。あるいは、世間話で終始しても、冗談で終始しても、同じである。対話は、あくまでもこの三つの段階に沿って進行しなければならないのだ。
カントはさらに、対話において参加者が配慮するべき、次のような五つの規則を提案している。
第一に、「歓談の素材を選ぶこと」11である。前述の通り、カントが重視するのは、その場にいるすべての人が対話に参加している、ということである。そのためには、「参会者全員から興味を持たれ、誰もがいつでも何か当意即妙に話に加わる機会を与えられているようなもの」12が、話題として選ばれなければならない。反対に、その場にいる一部の人だけが理解できる話題は、その話題を知らない参加者を対話から排除することになるため、望ましくない。
第二に、「歓談の途中でほんのひととき間を置く」13ことである。つまり、ずっと話し続けるのではなく、時折、間を挟み込むのだ。「死のような沈黙」14であってはいけない。
第三に、「必要もないのに話題を変えたり、こっちの素材からあっちの話題へと飛んだりしないこと」15である。もちろん、多様な話題について語ることは、それ自体として悪いことではない。ただし、カントはあくまでも対話において話の統一性が求める。したがって話題が飛躍するときには、新しい話題が前の話題とどのように関係しているのかが明確である必要がある。
第四に、「自説に拘ること」16を慎重に回避する、ということだ。なぜなら、「こうした歓談は真面目な仕事でなくただの遊びにすぎない」17からである。そしてこのことは、自分自身に対して戒めるだけでは不十分である。他者が自説に拘り始めることに対しても、私たちは抑制的でなくてはならない。したがって、「誰かがそのように本気に走ったときは巧みに洒落でも飛ばして気を逸らすといい」18とカントは指摘する。
第五に、「それでも真剣な論争が避けられなくなったら、注意深く節度を守ることによって自分を見失うことなく興奮を抑制し、常にお互いが相手に尊敬と好意を抱いていることが誰の目にも明らかでなければならない」。19 たとえ、対話の参加者が自分の考えをぶつけあう事態に発展するのだとしても、それは互いに対する尊敬を前提にしたものでなければならないし、そしてその尊敬ははっきりと表明されなければならない。それに対して、相手を論破しようとしたり、論理的に詰めたりしようとする態度は、対話を破壊する行為である。
こうした一連の規則から明らかになることは、カントが理想とする対話において、参加者がその対話以前にどのような考えを持っているかは、まったく重要ではない、ということだ。むしろ、対話のなかで、様々な話題に意識を引きずられ、笑い話に巻き込まれていくなかで、普段とは違った仕方で物事を考えられるようになることにこそ、価値があるのである。
そうであるとしたら対話は、普段の自分の考えに揺さぶりをかけ、それをかき乱すように作用するものであると言える。それなのに人はそうした対話に参加することを、なぜ動機付けられるのだろうか。自分の考えが乱されるのなら、そんな場所に参加しない方がよいのではないだろうか。
カントは、人間が対話に参加することの動機を、まったく別の角度から説明する。すなわちそれは、健康の促進である。彼は『判断力批判』のなかで、私たちが議論において、思考を戯れさせることの価値について、次のように述べる。
ひたすらさまざまな表象の交代に基づく判断力において発現する。このたわむれによって、なんらかの関心を随伴する思考が生みだされることはないのはたしかであるとはいえ、それでもこころにはやはり生気が与えられるのである。20
私たちは対話のなかで、その対話に参加しなければ考えなかったであろう、様々なことを考える。そのように「表象」を「交代」させることによって、私たちの身体には「生気」が生まれてくる、と彼は考える。言い換えるなら、自分の考えに固執し、常に同じ意見を取り続けていると、生気は枯渇していき、息苦しい状態へと陥っていくのだ。
ここでただちに想起しておくべきことは、カントが思考のあり方の諸段階を、「自分で考えること」「他のあらゆるひとの立場で考えること」「つねにじぶん自身と一致した考えであること」という、三つの観点から説明していたことである。カントにとって思考とは、あくまでも他者の立場から物事を考えることができることを、含んだものである。対話における役割の交代は、私たちがそうした普遍的な思考に到達するために、欠かすことができないものなのだ。
ただし、重要なのは、人々が対話に参加するのは、それが私たちを啓蒙させるから、理性的な思考を可能にするからではない。楽しいからである。カントにとってその楽しさはあくまでも身体的なレベルにある。そこには、啓蒙に求められる普遍的な思考力とは別の基準が設定されている。
あるいは、こう言い換えてもいいかも知れない。対話は、人間の普遍的な思考の発展過程と、私たちが身体的に楽しさを感じる様々な事象とをつなぐ、交錯点に位置づけられるのである。だからこそ彼は、楽しく、立場を交換しながら、対話することを重視するのだ。ただ真剣に議論をするのではなく、かと言って冗談を交わすだけで笑って終わるのでもない、その中間にある対話こそが、彼にとってもっとも人間的な対話なのである。
対話は、私たちが楽しみながら自分の考えを豊かにすることができる場でもある。自分の考えを豊かにすることは、言い換えるなら、それまでの自分の考えの狭さを認め、それを相対化することだ。多くの人にとって、それは特に楽しくはないことだし、とりわけ自分の意見に自信を持っている人にとっては、耐えがたい苦痛でさえあるだろう。しかし対話は、参加者を楽しくさせてしまうことによって、それを成し遂げてしまうのである。
対話をしているとき、私たちは、自分が普段なら考えないようなことを考えたり、言わないことを言ったりする。そしてそれを楽しいと思う。しかし、そうした自己変容を楽しいと思わせてしまう点にこそ、対話の持つ偉大な力が示されている。そして、対話を楽しくしなければならないからこそ、カントは、それが成立するための形式的な条件に、こだわりを示していたのである。
よい対話を判定する基準は、対話の内容や、その過程や、結論に依存するのではない。その対話が私たちによい生気をもたらしたのか、私たちを健康的な状態にしたのか、要するに楽しかったのか、という観点から判定される。そして、対話の楽しさを保証するために、カントは厳密な形式性を要求するのだ。そうした形式なしに自由に対話をしようとすれば、対話に参加できない人が現れたり、ずっと同じ人が話し続けたり、全員が自分のもともと持っている思想にこだわり続け、深刻な意見の対立に陥ったり、またあまりにも議論が過熱しすぎるために疲労するだろう。そうした事態を回避するために、カントは様々な対話のルールを提案しているのである。
そのほとんどは、現代においても通用するものだし、あるいは見方を変えるなら、教育やビジネスなどでコミュニケーションデザインを生業にしている者であれば、知らず知らずのうちに実践しているものかも知れない。しかし、私たちにとって重要なのは、その背後にある対話をめぐるカントの思想である。
カントは、人間が啓蒙されるためには対話が必要だと考えた。しかし、人間には対話を好む傾向も嫌う傾向も内在している。だから、ただ好き勝手に対話をさせるだけでは、人々は場合によっては軋轢を起こし、啓蒙される可能性そのものを奪われるかも知れない。だからこそ、対話を楽しくするための工夫が、一つの倫理的な要請として求められる。そのとき私たちは、「どうやったらこの対話が楽しくなるか」を考えながら、傾聴し、また発言することになる。
ここには対話をめぐる内在的な視線と外在的な視線が交錯している。「私」は、他者が語った内容に定位し、それに対する応答として、相応しい内容を語る。そのとき対話の内容は、それまでに「私」と他者が何を語ったのかによって左右されるのであり、言い換えるならその内容に内在している。しかし、その一方で、「私」は、そのように対話している「私」と他者を俯瞰し、どうやったらこの対話が楽しくなるか、次にどのように展開していくべきかを、思案しもする。このとき「私」は対話の内容をその外側から眺めていることになる。そして、この外在的な視線が、対話のなかで何を語るかということにも影響を与えるのだ。
棋士の糸谷哲郎によれば、プロの棋士のなかには、「美しい棋譜を残すことにこだわる人」というのがいて、自分が敗北を読み切ったとき、「棋譜を汚していけないみたいな感じで投げ」るのだという。21 そうした棋士は、目の前の相手と勝負をしながらも、同時にその勝負を外側から眺める視点を持ち合わせてもいる。そしてその外在的な視線が、どのような一手を打つかという、勝負に内在する選択にも影響を与える。カントが考える対話、すなわち内在的な視線と外在的な視線を交錯させる対話は、あるいはそのようなものだと言えるかも知れない。
美しい棋譜を残そうとする棋士にとって、将棋は、決して勝負を目的にしたものではない。自分の一手一手が、棋譜となって未来に残ることを意識しているのであり、いわば「美しい棋譜を作っている」のである。それと同様に、優れた対話ができる人もまた、「楽しい対話を作っている」のではないか。すなわち、対話をするということは、相手とともに対話を制作することなのではないか。
カントの対話論から見えてくること、それは、対話は制作的な行為としての一面を備えている、ということである。そして筆者は、対話をこのような観点から捉えることによって、現代社会における対話が直面している困難を乗り越える、重要な手がかりを得られると考えている。
制作的な行為としての対話、すなわち、制作的対話とは何か──最終回となる次回は、それを冒険的に構想してみたい。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。
- カント『カント全集 15』渋谷治美・高橋克也訳、岩波書店、二〇〇三年、二四五頁
- 同書、二四六頁
- 同書、二四六頁
- 同書、二四六頁
- 同書、二四六頁
- 同書、二四九頁
- 同書、二四九頁
- 同書、二四九頁
- 同書、二四九頁
- 同書、二四九頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇頁
- 同書、二五〇-二五一頁
- 同書、二五一頁
- 同書、二五一頁
- カント『判断力批判』熊野純彦、作品社、二〇一五年、三一八頁
- 戸谷洋志・糸谷哲郎『棋士と哲学者 僕らの哲学的対話』イースト・プレス、二〇一八年、四二頁