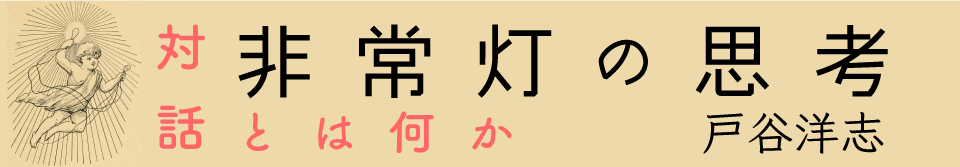私は子どもの頃から空手を習っていた。何度か引っ越しをした都合で、途中で流派は変わった。伝統派空手からフルコンタクト空手に変わったりもした。それでも、空手自体は大学生になるまで続けることになった。
あまり知られていないが、空手は流派によって稽古の内容がまったく違う。私が最初に習った流派では、基本的な突きや蹴りの動きを行った後で、型の練習をする。型というのは、一人で決められた順番で技を表現する、演武だ。一方で、高校生になって始めた流派では、キックボクシングのような構えで、突きや蹴りのコンビネーションを学ぶことになる。それからサンドバックやキックミットを使って、実際に相手に技を当てる練習をする。大学生になってから始めた流派では、相手の突きや蹴りに合わせて、相手を投げ飛ばす「捌き」という技術があり、二人一組で捌きをかけあう練習をする。
しかし、稽古の前に必ずストレッチをするという点では、どの流派も共通していた。身体が柔らかいことは、技を出すためだけではなく、怪我を防止するためにも、絶対に必須だった。実際、どの流派であっても、師範たちはタコのように身体が柔らかかった。
大学院に進学してから、私は一念発起してブレイクダンスを習うことにした。ブレイクダンスというのは、ストリートダンスの一種で、背中や頭で回転したり、片手で逆立ちしたりするスタイルのダンスだ。「バトル」と言って、一対一で向かい合って互いの技を表現し合い、技術を競うパフォーマンスも特徴的である。
空手とブレイクダンスはまったくの別世界だった。空手では礼節が厳格に重んじられていた。武道だから当然のことだ。私は誰に対しても常に敬語を使っていた。しかし、ブレイクダンスの世界にそうした礼節はなかった。私の先生は、私よりも少しだけ年上だったが、私が敬語を使うことを禁じた。堅苦しい雰囲気はいらない。ここでは自由に踊ろう。それがブレイクダンスの教室のルールだった。しかしそれは、そこに礼節がない、ということを意味するわけではない。前述の通り、ブレイクダンスにはバトルがある。バトルにおいて、私たちは相手に敵意を示しながらも、当時に相手をリスペクトする。相手が素晴らしいダンサーだと認めているからこそ、全力で相手を煽るし、挑発する。それがブレイクダンスにおける「礼節」なのである。
しかし、別世界のように見えた空手とブレイクダンスの間にも、共通点があった。それは、練習において必ずストレッチをするということだ。ブレイクダンスの技の多くは股関節の柔軟性を必要とする。たとえば、片手で逆立ちして静止する「マックス」や、足を振り回して背中で回る「ウィンドミル」という技は、足を開かないと形にならない。
空手の師範も、ブレイクダンスの先生も、私にこう言った。
「戸谷君、特に男性は成人になると身体が硬くなる。一度硬くなってしまった身体は、そう簡単には柔らかくならない。だから毎日ストレッチをしておかないといけない。そうでないと、自分が思った動きができなくなるし、ちょっとした拍子に大怪我をしてしまう。場合によっては、その怪我によってもう練習できなくなってしまうかも知れない。そうなってからでは遅いんだ」。
実際に、私はストレッチを怠ったせいで、肉離れを起こしたことがある。そのとき私は思い知った。どんなに身体を鍛えても、鋼のような筋肉を手に入れても、身体が柔らかくなければ、思うように動くことはできない。もちろん、日常生活を送っている分には、そこまでの柔軟性は必要ないのかも知れない。私たちは、学校に通うとき、スーパーで買い物をするとき、上段回し蹴りをしないし、片手で逆立ちをしたりもしない。極めて限定された範囲で運動していれば生きていける。しかし、その日々のなかで、私たちの身体は刻一刻と硬くなり、その可動域は狭くなっている。そして、いざ動かなければならなくなったとき、自分の身体を思うように動かすことはできなくなっている。
このような考えが、幼いころから根付いているからかは分からないが、哲学的な思考の意義について考えるとき、私はよく、ストレッチのことを思い起こす。
哲学の研究者は、誰であっても、「哲学が何の役に立つんですか?」という問いに一度は遭遇する。私のように運の悪い研究者なら、月に一回は尋ねられる。そしてそれに対して、みんなそれぞれに自分なりの回答を持っているものだ。ある人はとても冷ややかに答えるだろうし、ある人はまるでビジネスマンのように答えるだろう。もちろん私にも自分の答えがある。それはだいたい次のようなものだ。
哲学とは「当たり前」を問い直す学問だ。私たちの生活は、多くの「当たり前」によって成り立っている。それは、常識とか、偏見とか、先入観といった言葉にも置き換えることができる。
「当たり前」は道路標識のようなものだ。私たちは、それを信じるからこそ、安心して道の上を歩くことができる。もしも道路標識がなくなったら、自分がいまどこにいるのか、この道の先に危険なものがあるかどうか、分からない。私たちは不安になり、前に進むことができなくなってしまう。同様に、「当たり前」がなくなってしまったら、私たちは日常を生きることができなくなる。安心して一日を過ごすことができなくなってしまう。
だから、日常を生きる上では、哲学はあまり必要ではない。しかし、とても残念なことに、私たちの人生には何回か「当たり前」が崩壊する瞬間が訪れる。つまり、それまでの常識が通用しなくなり、それまでの日常が一変し、考え方を根本的に刷新しなければならないときがやってくる。
どんなときだろうか。それは人によって違うだろう。しかし、いくつか典型例を挙げることはできる。たとえば、両親が死んだとき、大きな病気を患ったとき、恋人と別れたとき、仕事を失ったとき、あるいは、恐ろしい災害に見舞われたとき、戦争に巻き込まれたとき、余命を告げられたとき、などだ。そうした瞬間は誰にでも訪れる。そして人生において一回ではなく、少なくとも何回か、忘れた頃にやってくるのだ。
こうした、「当たり前」が崩壊する瞬間を、「破局」と呼ぶことにしよう。
破局は私たちにとって大きな危機である。それまで私たちが頼ってきた「当たり前」が、もう役に立たなくなってしまうからだ。破局が起きたとき、道路標識は、まるで魔法が解けたように、するすると透明になり、消えてしまう。何も目印のない道の真ん中に取り残される。そのとき私たちは、道路標識なしに、今まですがってきた「当たり前」を頼ることなしに、次の一歩を踏み出さなければならない。それができなければ、どこにも行けないまま日が暮れて、不安と虚しさに見舞われる冷たい夜に飲み込まれてしまう。
破局に遭遇した後、私たちは手探りで一歩一歩前に進みながら、新しい「当たり前」を作り上げていく。破局は私たちに常識の更新を迫る。「当たり前」がバラバラに砕け散ってしまうからこそ、私たちはその破片を拾い集め、それを一つ一つ組み立て直さなければならない。しかし、それはもう前と同じ形にはならない。私たちは、破局の後を生きるために、それによって自分が再び前に進んでいけるような、そうした「当たり前」を再編しなければならないのだ。
だがそれは決して簡単な仕事ではない。何の練習もなしに、一人でやすやすとできるものではない。では、そのためにはどんな力が必要なのだろうか。おそらくそれは、「当たり前」を問い直す力だ。言い換えるなら、今まで信じてきた「当たり前」が唯一の答えではないということを受け入れる力であり、その外側に、別の答えを模索する力だ。道路標識とは別の方向に向かう道について考える力だ。そしてその力は、別の「当たり前」を考えることができる、という、思考の柔らかさのうちに宿るのである。
破局の後、私たちは道なき道を進まなければならない。得体の知れないものに躓くかも知れないし、突然、穴に落ちてしまうかも知れない。私たちは壁を乗り越え、高い段差から飛び降り、対岸へと飛び移らなければならない。そのときに、然るべき柔らかさが備わっていなければ、私たちはたちまち怪我を負ってしまうだろう。そこから一歩も動けなくなり、再び、冷たい夜に飲み込まれてしまうだろう。だから私たちは思考を柔らかくしておかなければならないのだ。思考が硬直化するということは、前に進み続けようとする私たちにとって、最大のリスクなのだ。
では、どうすれば思考を柔らかくすることができるのだろうか。おそらく、それには日頃の訓練が必要だ。つまり、思考にもストレッチが必要なのだ。私たちは、まだ日常が機能しているとき、「当たり前」が信頼できているときに、その「当たり前」を問い直す訓練をしておく必要がある。そのようにして、思考の可動域を広げ、やがて訪れるだろう破局に備えなければならない。そして、そうした訓練の機会を提供してくれるものが、哲学的な思考なのである。
だから「哲学が何の役に立つか」と問われれば、答えはこうなる。それは思考のストレッチに役に立つ。それは、破局の後を生き延びるのに必要になる、思考の柔らかさを手に入れることに役立つ。「当たり前」を問い直す哲学的な思考は、「当たり前」を新たに形作る作業に役立つ。別の道を考える練習は、新たな道を切り開くのに役立つ。それが私の考える哲学の価値だ。
哲学とは思考のストレッチである。多分これは、「哲学は何の役に立つのか」という問いへの答えとしては、ずいぶん控えめな、刺激の少ないものだろう。私の考えでは、哲学は、日常のなかでは役に立たないが、その日常が壊れたとき、新たな日常を再建するためには役立つ。正確には、哲学そのものが役立つわけではなく、哲学によって鍛えられた思考の柔軟性が役に立つ。そして、哲学による思考のストレッチは、破局が起きてからするのでは遅い。破局が起きる前に、まだ日常が壊れていないときに、始めていなければならない。まさにそれこそがストレッチなのだ。転んだときに怪我をしないためには、転ぶ前からストレッチしていなければならない。
哲学をストレッチとして理解することには一つのメリットがある。それは、哲学的思考には他者の手助けが必要である、という、普段あまり意識されることのない、しかし無視することのできない側面を見えるようにする、ということである。
もちろん一人でストレッチをしてもいい。ただ、二人でやった方が効率的なのは疑う余地がない。効果的なストレッチには他者のサポートが不可欠である。たとえば空手やダンスの練習では、二人一組になって、一方が床に座って足を広げ、他方がその背中を押して膝の裏の筋を伸ばす、という運動をよくする。それによって一人でやるよりも、効率的に足の可動域を広げることができるのだ。
同じことが哲学的な思考にも当てはまる。私たちが「当たり前」を問い直そうとするとき、その作業に一人で取り組む必要はない。というよりも、一人でやるにはそもそも限界がある。「当たり前」は、それが「当たり前」であるからこそ、自分からは見えにくいからだ。そもそも、自分がそれに拠って立っているということに気づけないこと自体が、「当たり前」の一つの特徴でもある。
だからこそ、それを問い直すためには、「私」とは別の「当たり前」に立つ者、すなわち他者の視点が必要になる。「私」は他者と言葉を交わすことによって、はじめて、自分がよって立っていた「当たり前」が何であったのかに気づくことができる。そして、それが唯一の答えではないこと、その外側に別の「当たり前」が成り立ちうることに、気づけるのである。このような営みが、それ自体として、「当たり前」を問い直す実践に他ならない。
このように考えるなら、哲学は必然的に他者との対話を必要とする、といってもよいかも知れない。対話は私たちの思考の可動域を広げてくれる。それによって、私たちの思考が硬直化することを予防してくれるのだ。
もっとも、それは他者との対話が「私」にとって心地よいものである、ということを意味するわけではない。それもまた、ストレッチと通底している。ストレッチはしばしば苦痛を伴う。しかしそうした苦痛を経験することでしか柔軟性は獲得されない。同様に、自分とは異なる常識をもった他者と対話することは、しばしば苦痛を、あるいは居心地の悪さを感じさせる。もちろん、相手に自分のことを話してスッキリすることもあるかも知れない。しかし、それは思考の可動域を広げていることにはならないだろう。対話はマッサージではないのだ。
私は、対話に特有の、ある種の居心地の悪さを、緊張感を擁護したい。そうしたものから守られた、完全に安心できてリラックスできるコミュニケーションを対話として定義するとき、私たちは対話の範囲を大幅に限定してしまうことになる。もちろんそうした対話も素敵だ。しかしそれだけが対話ではない。そして哲学的な対話には、こうしたある種のストレスがどうしても伴うものではないだろうか。
しかしこのことは、だから私たちは相手に対して好きなだけ苦痛を与えていいとか、相手から苦痛を与えられても黙っていなければならない、ということを意味するわけではない。対話が苦痛を喚起するからこそ、そこには特有の倫理がある。それもまた、ストレッチと同じだ。ストレッチには倫理がある。他者の背中を押すとき、押し過ぎたら怪我させてしまう。しかし楽をさせていたらストレッチにならない。そうした絶妙な力加減を発揮することを求められるし、また押される側は、そうした相手の手腕を信じなければならない。
対話するとき、私たちは著しく脆弱になる。自分が「当たり前」だと思っていることを覆され、相手から批判を受ければ、誰だって立ち直れなくなるくらい傷ついてしまう。そうなれば、思考の可動域が広がることなどなく、怪我を負い、そこから動けなくなってしまうだろう。それはもはや哲学的な思考とは言えない。他者と対話するとき、私たちはそうした形で思考を台無しにすることがないよう、相手を配慮する責任を負うのだ。
私たちは不完全だ。私たちは弱く、傷つきやすい。それなのに、人生には、私たちを打ちのめす出来事が、何度も何度もやってくる。その過酷な世界のなかで、道なき道を進んでいくために、私たちは自分の思考を柔らかなものにしなければならない。そのために、私たちは他者と対話するのであり、背中を押してもらうのだ──こうした哲学的な思考と対話の関係について、この連載のなかで考察していきたい。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。