海を臨む高台に、ポツンと家が建っている。
それは、津波から逃れた、村ではたったひとつの家で、
赤髪の小さなおばあさんが暮らしている。
いまこの家に、遠くから来た旅人と、津波で死んだ人が訪ねてくる。
おばあさんと旅人と死んだ人は、初めて出会うようである。
庭先で旅人が声をかけると、おばあさんが家の中から現れて、
あらあ、あんたたちよく来たこと、と言った。
そして、海に向かってひらけた扇型の地面の方を向いて、ふたりに語りはじめる。
あっちから来た波と、こっちから来た波が、ドオンとぶつかって。
おばあさんは思いがけず軽やかにそう言って、両手をパチンと打った。
そしてね、あっちとこっちに波が広がって、すべてが持っていかれたの。
おばあさんの両手は、ひらひらと西と東へ離れていく。
旅人は、海際からつぎつぎとなぎ倒されていく電信柱を想像する。
波間をすり抜けてくる自動車は、どんな動きをしていただろう。
誰かの声が聞こえただろうか。ものが壊れる音は鈍かっただろうか。
獣たちはちゃんと逃げただろうか。
そんなことを尋ねようと考えている旅人をよそに、
おばあさんは、でもね、わたしは津波を見なかったの、とつぶやいた。
家族みんなが戻ってきてホッとしたところに、
津波が来た来たって逃げていく人の声を聞いたの。
それで、あっという間に庭まで水が来たんだけど、
家までは入ってこなくて助かったの。
だからわたしが語るのは、ぜんぶ誰かに聞いた話だ。
死んだ人は、うんうんと頷きながらほほえんでいる。
旅人は、ふう、とため息をつく。
わたしずっとここにいたのに、何も見てないんだもんね。
だから、あんたとおんなじだ。
おばあさんはそう言って、旅人の方をじっと見る。
旅人は、そうですか、と相槌を打ちながら、
じゃあ誰に話を聞けばいいのだろう? と思っていた。
何か知れる気がしてここへ来たのに、おばあさんさえも知らないというのだから。
それで旅人は、それなら死んだ人に尋ねてみようか、と思ったのだけれど、
死んだ人は、もっと話を聞かせてください、とおばあさんの方を向き直って言った。
旅人が、あなたが一番知っているはずではないですか? と問うと、
死んだ人は、いやいや、わたしはほとんど知りません、と答える。
あの日わたしが見たのはほんの一部のことですから、
大したことはないのです、とはにかむ。
おばあさんは、うーんと首をひねりながら話を続けた。
わたしは怖くて行かないんだけどね。
あっちのまちの方もぜんぶ流されて、なんにもないんだって。
避難所もやられたから、そこで亡くなった人も多いんだってね。
体育館はぐるぐるぐるって洗濯機みたいになったから、
たくさんの身体が絡まってたって言うんだよ。
だから、わたし考えるんだ。
死んだ人はひと思いに逝ったのかなあって。
知っている人が死んだのを見つけた人の気持ち、どれだけ悲しかっただろう。
家族探して安置所回った人の気持ち、どれだけ悔しかっただろうって。
旅人は絶句したまま、ここへ来る途中に見たひしゃげた建物たちのことを考えている。
まちでは瓦礫が避けられ、ぽつぽつと花が手向けられていた。
旅人には、手作りの祭壇の前でしゃがみ込む人にかける言葉が何もなかった。
おばあさんの話に打つ相槌も、ひとつも持っていなかった。
死んだ人は、うんうんと頷きながら、
大変な人もいたんでしょうね、と言って、目を閉じて手を合わせた。
そして、他には、他には? とおばあさんに話をせがむ。
おばあさんは首を傾げながらもまた話しはじめる。
このまえ小学校に物資をもらいに行ったらね、隣にいた人に声をかけられたの。
その人、せっかく生き残ったけど、家も仕事も失って、
これからどうしようって泣きだした。
つられてわたしも泣いてたら、みんなも集まってきてね、
どうしよう、どうしようねって、肩寄せて泣いたの。
旅人は、輪になって泣く人たちの姿を思い浮かべて、ぽろぽろと涙をこぼす。
おばあさんは、ありがとう、と言って旅人の背中をさすった。
死んだ人は、そうかそうかと頷いて、
みんながやさしくてうれしいね、と顔をほころばせる。
おばあさんは、みんな失ったものが大きいんだもんね、と頷いて、
だけどわたしは何もできないんだ、と言った。
話を聞くくらいはできても、それ以上してあげられることがないでしょう。
旅人は、僕もです、何も代わってあげられない、と鼻をすすり、
死んだ人は、わたしが一番何もできないですよ、と言って頭を掻いた。
おばあさんは、あらまあ、と驚いた顔になる。
そうかそうか、あんたが一番何もできないんだもんね。
それが一番つらかったべ。
おばあさんはそう言って、死んだ人の頭をよしよしと撫でる。
ごめんねえ、あんた一番つらかったべ。
死んだ人は一気に力の抜けたような顔になり、ほうっと長い息を吐いた。
すると、海から強い風が吹く。
死んだ人は、見る間に小さな赤ん坊になって、ぽとりと地面に横たわった。
赤ん坊は、大きな声でわんわん泣いた。
おばあさんと旅人が何を言っても泣き止まなかった。
もうどんな話も通じなかった。
何もない風景に高い声が響くので、あたりがざわざわと騒ぎ出す。
だから旅人は、その赤ん坊を抱いて帰ることにした。
おばあさんは、復興したらまた来てくださいね、と言ってふたりを送り出す。
旅人は、今日聞いた話は大切にします、と答えて頭を下げる。
死んだ人は旅人の腕の中ですやすやと眠っていて、
その寝息は静かな波のようだったという。
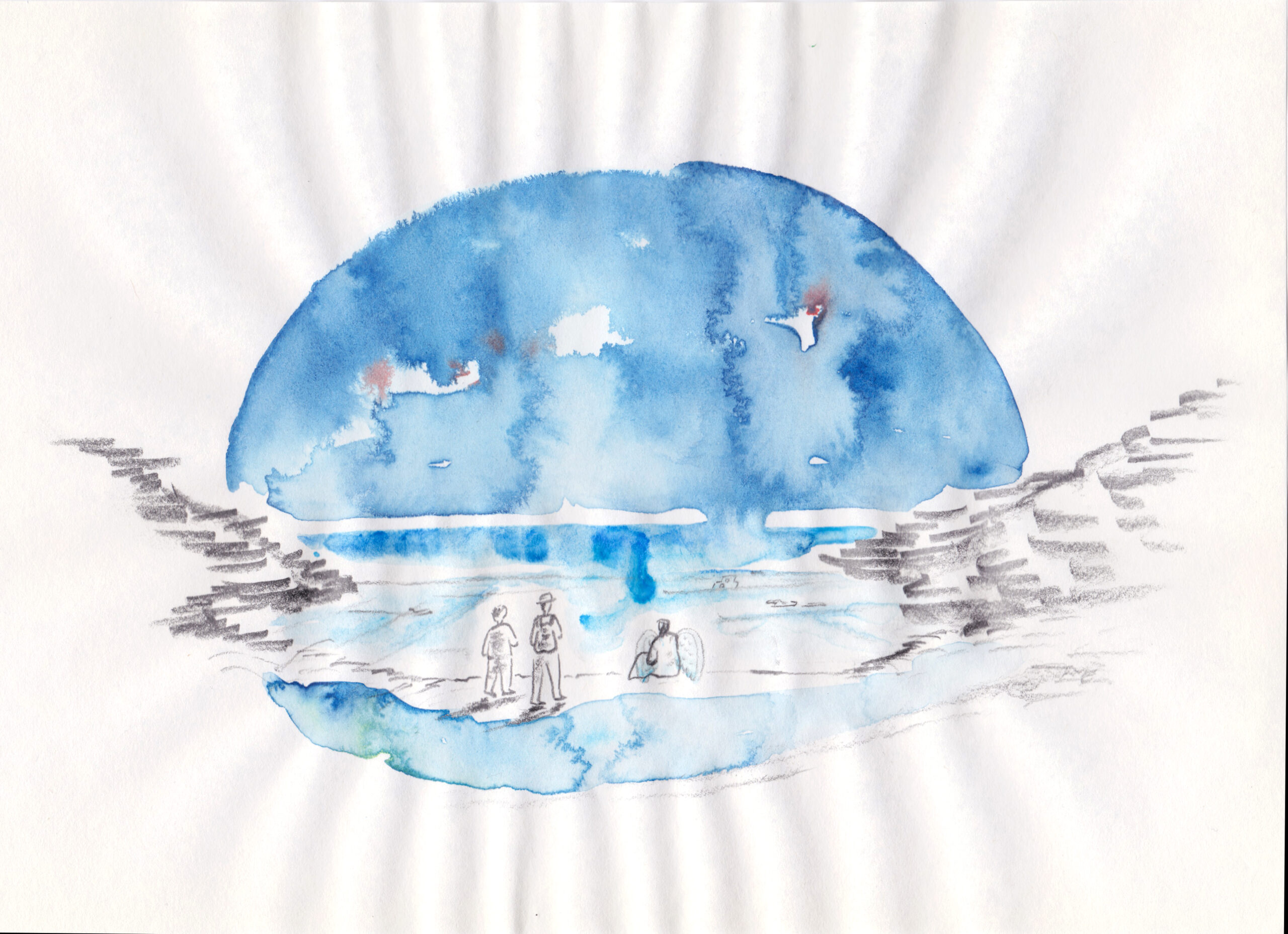
Natsumi Seo
塗りかえられていく風景と、移り変わる人びとのことばを書き留める。できるだけたくさんそのための旅をする。ここ10年ほどの間、それがわたしの行動の指針になっている。
聞かなくてはならない話がきっとどこかにあるのだ。だから訪ねるべき場所を訪ね、会うべき人に会い、話を聞くために出かけなければ、とわたしは思い込んでいる。
こう書いてみるとだいぶ力んでいる感じで恥ずかしいけれど、まだまだ新米旅人なので大目に見ていただけたらありがたい。とりあえずいまのところ、長く旅ができるように生きてみたいと思っているので、早く力が抜けるといいなあと思う。
なぜこんな風になったのかと言えば、きっかけは東日本大震災だった。わたしは、その前と後ではずいぶん変わってしまったと思う。自分自身のことと身の回りのことだけで必死なイチ美大生だったわたしが、知らない人の話を聞くことを生活の中心に据えようとするなんて思ってもみないことだった。
とは言え、わたしは地震の揺れそのものによって変わったのではない。地震の後、被災地域に暮らす人びとに出会い、話を“聞けた”という実感を得ていくひとつひとつの体験が、話を聞くための旅にわたしを引き込んでいった。そしていつもその傍らには、語り得ない、語られない言葉が、そっと存在していたと思う。
「おばあさんと旅人と死んだ人」は、わたしが実際に、“聞けた”、あるいは、“聞いてしまった”と感じた最初の体験をもとにして書いた物語である。わたしの旅の始点がきっとここにあるから、そんな旅から生まれた物語たちを綴っていく連載の第1回目に、彼女に登場してもらいたかった。
2011年4月。わたしは津波に洗われたばかりの陸前高田にいた。3月の終わりから、友人と一緒にボランティアという名目で沿岸各地を巡っており、その道中で、陸前高田の高台に残った一軒家を訪ねたのだ。その家に暮らす赤髪のおばあさんは、わたしのかつてのバイト先の同僚の遠い親戚で、もちろんその時が初対面だった。
そんな彼女に出会うまでの経緯はこうだ。
震災当時、わたしは東京の美大生で、南千住のシェアハウスに住んでいた。地震の後、同居人たちや集まってきた友人らとテレビを見ていると、あの大津波の映像が流れてくる。海の近くに住んだことのないわたしは、津波という自然災害が存在することすら意識したことがなく、目の前のテレビはまさに想像を絶する状況を映していて、ただ驚くよりほかない。
その夜、わたしは自室でスケッチブックを開いた。こんな大変な時に自分は何を描こうとするのだろうと思って鉛筆を握ると、現れたのは手癖みたいな線といつもと変わらないモチーフで、とてもがっかりしたことを覚えている。SNSをのぞけば、被災地域の状況が断片的に、しかし大量に流れ込んでくる。そしてその合間に、こんなことが起きてしまって何をすればいいのか、どんな態度を取るべきかと自問自答する、あるいは互いに問い合うようなつぶやきがすでに見て取れた。そこでわたしは、絵描きに何ができるのか? という問いにつまずいてしまった。
その後しばらくはインターネットやテレビを介して震災の情報を見ていたのだけれど、それもだんだんしんどくなった。原発事故の発生も相まって、ネット上にはまことしやかな、真偽のわからない情報が飛び交っており、それに対して、意見や立場の異なる人たち同士がぶつかりあっている。一方で、被災地域からは悲鳴や嗚咽のようなつぶやきが次々と流れ込んでくる。こうなってくると、特別役に立つような知識も技術も言い分も持たない遠方に暮らす学生のわたしは、いよいよどうしていいかわからなくなり、うまく語れなくなった。
それでわたしは、とりあえず現場に行きたい、行かなくてはと思い込んで、友人を誘い、災害ボランティアとして 、“被災地”を目指すことにした。いま思えば、当時は過剰な情報摂取による被災状態になっていて、何かしらの手触りみたいなものが欲しかったんだと思う。まずはその場に行って何が起きているのかを確かめる。その場でできることがあればなんでもしよう。
絵描きでありたいと思う自分を解体してしまえば、ずっと楽になる。でも、行く先にはきっと何か描くべきものがあるのではという期待も、どこかにはあったと思う。
ということで、震災から三週間後、友人とふたりで物資を詰めたレンタカーを走らせて、ボランティア旅を始めた。被災してひしゃげた風景を目の当たりにするとやはりショックだったけれども、ボランティア先を訪ねれば、そこで暮らしを再建しようとする人たちがいて、そのたびにホッとするような気持ちになった。
そんな旅の何日目かの車中で見ていたSNSで、先述の元バイト先の同僚が親戚のおばあさんの身を案じていて、その人が住んでいるという陸前高田はそう遠くなさそうだから寄ってみようと思い立ち、彼女に住所を教えてもらった。
ナビに案内されると、市街地からは外れた高台の小さな集落に着いた。さっそく目的の家を探してみるのだが、そのあたりに暮らす人たちはほとんどみな同じ苗字で、どれがその家なのかいまいちよくわからない。示された道路の山側にはふつうにまちなみがあるけれど、海側にはもう建物がない。そんな状況では、行きあう人がそれぞれどんな境遇にあるかもわからないから、声をかけるのも慎重になる。ためらいがちに繰り返す何軒目かの訪問で、わたしたちはそのおばあさんの家に行き着いた。もう夕暮れが迫る頃。
玄関先に出てきた赤髪の小さなおばあさんは、見知らぬ大学生たちの登場にしばし驚いていたけれど、わたしが元同僚の名を告げると途端にほっとしたような顔になり、あんたたちわざわざありがとうねえ、と言ってまじまじとこちらを見つめた。そしておばあさんは、こっちにおいでという感じで、その家の目の前の道路までわたしたちを連れていき、遮るものが何もなく、海までひと繋ぎになった扇型の広い地形を見せた。
本当はね、ここから海は見えないんだよ。この辺に50軒以上は家があったんだもんね。それも全部流されたから。でもいまはこんなに海が見えるから、とっても落ち着かないんだ。
おばあさんはひと続きにそう言って、ね、という感じでこちらを見る。
わたしは促されるままに海に向かうゆるやかな斜面をぐるりと眺めた。何もない。というよりも、ここに何があったのかさえわからないから、いまが“ない”状態なのかもわからない。平らな地面には、田んぼらしき区画の境界線がかろうじて見つけられる。あちこちに壊れた何かが落ちている。曇り空で日が沈みかけていて、あたり全体がくすんだ青色になっていく。すこし肌寒いような、怖いような風景がそこにある。
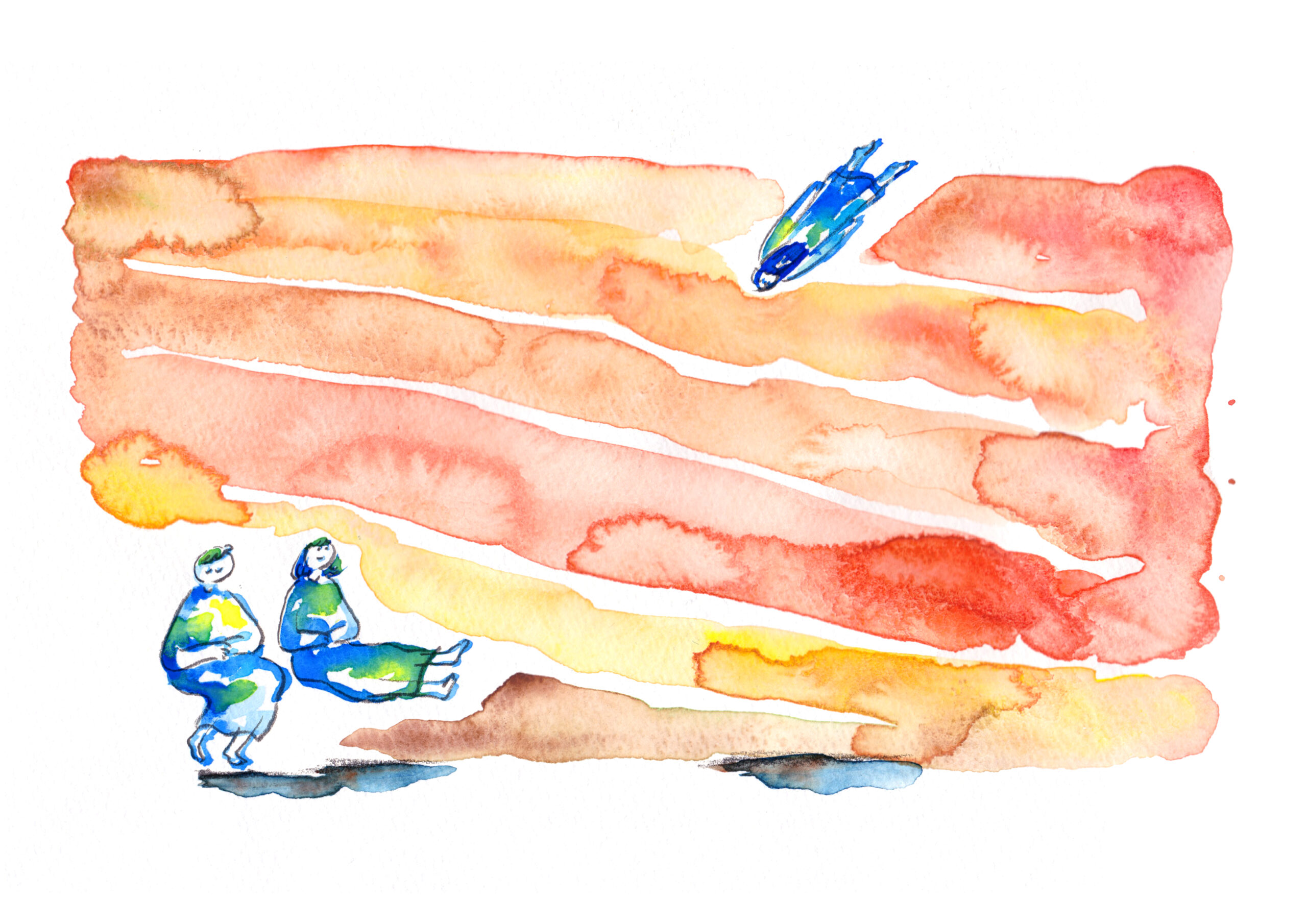
Natsumi Seo
それからおばあさんは堰を切ったように語り始めた。自宅の庭先まで津波が上がってきたけれど、自分は波を見なかったこと。たくさんの友人知人が亡くなったのに、ずっと泣けなかったこと。被災によって明確な境遇の差が出来て、近しい間柄でも迂闊には話せなくなってしまったこと。被災した人たちの気持ちを考えると、何もできない無力感と申し訳なさが湧いてくること。復興するまではきっと途方もない時間がかかり、それを自分は見届けられないかもしれないこと。失われてしまったまちは、とてもうつくしかったのだということ。
わたしはおばあさんの止めどない語りを聞きながら、うん、とか、へええ、とか、まったく気の利かない相槌を打っていた。彼女からすれば、こうして語ることはひとつの気遣いで、せっかく遠方から来た客人に対して手土産を持たせるような感覚もあったかもしれない。けれどわたしは、“被災”という大変な出来事について聞かされている状況自体にたじろいでしまって、彼女がどんな風にこの話を聞いてほしいのか見当もつけられずにいた。
しかしそれでも、彼女が言いたいことは思いのほかよくわかると感じていた。東京からノコノコとやってきたわたしと、“被災地”に暮らす彼女の心情には、もしかしたら似ているところすらあるかもしれないとも思った。
つまり彼女は、被災の“当事者”――家や家族を喪ったりした、彼女より被災の程度が高い人たちに対して、とても気を遣いながら語っていた。自分を当事者性の中心から外れた位置に置き、より中心に近い存在を前提としているからこそ、彼女は、顕著な境遇の差が出来てしまった近しい人たちに対して自分の気持ちを語れなくなり、苦しんでいるように思えた。たとえば東京で暮らしていたわたしからすれば、被災地と呼ばれていた東北沿岸の住人はもれなく当事者のど真ん中にいるように思えていたけれど、その地域のなかにも、いやむしろその中心に近いからこそ、その境遇の差は際立ち、境界線上に立つ壁は高くなる。だから、“当事者性”の中心により近い領域にいる人たちとおばあさんの間より、おばあさんとわたしたちの間にある距離の方が、むしろ近づいてしまうことがあるのかもしれない。それで彼女は、遠方から訪れた見知らぬわたしたちに、被災地の現状を伝えるような形で、その気持ちを吐露したのではないだろうか。
そう思うと、彼女が語ってくれている限り、わたしはここに居てよいのだろうという気分になれた。そして、せっかく聞き手として居させてもらうのだから、この語りを受け取れるだけ受け取ろうとも思えて、できるだけ相槌を打った。
いつの間にかとっぷりと暗闇になる。
彼女はひしゃげた隣家を背景にして、復興したらまた来てくださいね、と手を振ってくれた。わたしはすっかり彼女に親しみを覚えて、復興など待つことができずに、その後毎月のように彼女のもとへ通うようになる。
あのときからもう10年が経とうとしている。わたしは震災の1年後から3年ほど陸前高田で暮らし、いまは仙台を拠点にしながら、相変わらず被災地域に通っている。
これまでに幾度も彼女の語りを振り返ってきたなかで感じたことのひとつは、彼女は、あのまちに暮らすさまざまな境遇に置かれた人たちの存在を含み込みながら語っていたということ。死んでしまった人たちの気持ちを想像し、家や仕事を失った人たちに聞かされた話を伝え、聞き手の様子を探りながら、そして自分自身の心情を整理して語る。当事者性のマッピングのあちこちに置かれた存在たちが意識されることで、語りは多声的なものになりうる。その声は、時にとても豊かな場をつくる。
もうひとつは、他者の存在に配慮しながら、“語れなさ”や居づらさを抱えて迷う者同士は、ふと繋がれる時があるということ。それはたとえ初対面の旅人とでも、ふだんは複雑な関係性にある相手とでも。そして、語りというものはそういう瞬間にこそ、生まれてしまうもののようにも感じている。すこし極端な話だけれど、“当事者”の中心にいるのがすでに死んだ人だとすれば、生きている誰もがそのような迷いを抱えていると捉えることもできる。それならば、生きている者同士は、ある程度の気遣いを持ち合いさえすれば、誰しもが対等に語り合えるのではないか、とも思う。
今回「おばあさんと旅人と死んだ人」を書いたのは、この当事者性の中心にあり、語れぬ存在であるとされる死者とさえ、語れることがあってもいいのではないかと思ったから。すこし怖いようだけど、それだけでもない気がしている。
死者たちを語れないままの存在にしてしまうのではなく、彼らの声を聞きながら、生きている者たちが手を繋ぐことができたら。いったいどんなことが起こるのだろう。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。



