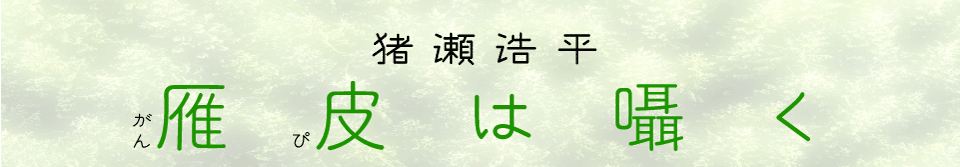雁皮。この灌木のことが気になり始めてから、もう何年も経つ。山や森、植物園を歩く時だけではなく、街を歩きながら街路樹や人の家の庭の中に雁皮を探す。雁皮がそこにあることはほとんどない。それでも私はあの濃い茶色の幹の、小さな葉っぱを付けたあの灌木を探し、そしてかすかに似た特徴をもった木に出会ってドキリとする。こんなところにも雁皮があるのかと。そして、それが雁皮でないことを確かめて、平静な気持ちに戻る。雁皮を気にかけることで、木々や林、森とわたしの関係は確実に以前よりも親密になった。
しかし、わたしは何故に雁皮に惹かれているのか問われても、すぐに明確な答えが出てこない。
雁皮は、楮・三椏とならぶ和紙植物である。栽培が普及した楮、三椏と比べ、栽培は困難とされ、もっぱら人びとが採集したものが和紙の原料として供給されてきた。漉くと独特の黄味がかかる。繊維の細かい雁皮紙は銅版画や万年筆と相性がよく、日本ではひらがなを書くのに適しているとも言われる。
雁皮紙は、17世紀において既に日本発の国際商品として流通してきた。オランダの東インド会社がヨーロッパに紹介した雁皮紙は、その美しさと特質の両面において好評を博した。レンブラントの銅版画の多くも、長崎から運ばれた雁皮紙に印刷されている(貴田2005)。雁皮を原料とする越前鳥の子紙は、奈良時代から漉かれてきた日本の主要な手漉き和紙の一つとして、2017年に重要無形文化財に指定されている。

雁皮
雁皮は和紙になるだけの植物ではない。
雁皮の性質は、人間に対して様々な役割を果たす。たとえば、雁皮を使った紙は手漉き和紙だけでない。機械で漉かれた謄写版原紙は、謄写版(ガリ版)印刷においてなくてはならないものである。紙だけではない。樹木研究の第一人者である有岡利幸は、雁皮をめぐる文章で次のように書いている。
中学一年生の孫娘とその友達をつれてハイキングに行ったとき、谷から尾根へと登る遊歩道のかわたらには、必ずといっていいほど雁皮をみつけた。雁皮は大きなもので根元が鉛筆くらい、樹高は一八〇センチほどであった。大きな尾根筋にのぼると、からからに乾燥した花崗岩の風化土の遊歩道沿いの茂みにもみられた。全体的に高さは五〇センチ以下で、乾燥したやせ山なので、どれも良好な生育はしていなかった。
このとき山歩きというのに孫娘は半ズボンだったので、狭い遊歩道の両側からはみ出したコシダで脛がこすれ、痛いといい出したので、持っていたタオルを足に巻いたが、縛る紐をもっていなかったので、近くのガンピの皮を剥いで、それで縛ってやった。雁皮という木の皮は、靭性があって、少しくらいの力で引っ張っても千切れない。資料や記録は何もないが、昔から山の人たちは雁皮の皮を、薪や材木を束ねるのに用いてきたのではなかろうか。(有岡2018:18-19)
有岡は、朝鮮半島から紙漉きの技術が伝えられた時代に、人びとが雁皮の性質を知っていた、だからこそ、その性質を応用し、雁皮で紙を漉いたのだと推測する。人びとは、紙に漉く以前から雁皮と出会っていた。雁皮は人と交わり、紙だけでなく、紐にもなりえる。そして紙や紐以外にもなりえる。そして、ただ雁皮のままに留まることもできる。
わたしが心惹かれるのは雁皮が人の役に立つその性質だけではない。人にとって有用であるか否かにかかわらず、生きている雁皮に惹かれるのである。人と雁皮は時に深く交わる。しかし多くはすれ違うか、あるいはそもそもすれ違うことすらない。それでも、雁皮はこの世界で息づいている。
雁皮という植物の存在を、わたしはふとしたきっかけで知った。
それまで、わたしの世界に雁皮が存在していなかったわけではない。
雁皮はわたしの世界にあった。
ただ、わたしがその存在に気づいてはいなかっただけだ。
そう書いて、子どもの頃に暮らしていた団地の家の、父の部屋のことを思い出す。
父の書斎――といっても、そこで父が仕事をしているのを見たことはなかった――でもあったその部屋には、木でできた机とチョコレート色の地に白いストライブの入ったマットレスをのせた黒いパイプベッドと洋服ダンス、そして本棚代わりのカラーボックスが重ねられていた。父のいないときに、机の引き出しをこっそりと開けたときに漂ってくる匂いは、今でも鮮明に覚えている。そこにはパイプや万年筆、そして鉄製の先端が鋭く尖ったペンが入っていた。ベッドの下には一メートルくらいの幅のニスの塗られた箱があった。たびたびそこをあけたことはなかったが、好奇心にかられてその扉をあけたときにインクの匂いがした。箱にはHORII MYRIAGRAPH No.4と書かれていた。あとで知ったが、それは堀井謄写堂のガリ版印刷機の箱だった。そして先端が鋭く尖ったペンは、謄写版原紙を切るための鉄筆だった。
ガリ版印刷機があり、鉄筆があった。だとしたら、父の机やガリ版印刷機の箱の中には謄写版原紙があったはずだ。そうであるならば、父の部屋には、わたしの家には、雁皮を原料にする製品があったということになる。謄写版原紙のほとんどは雁皮を原料としているから。
わたしの世界の片隅に、雁皮はひっそりと存在していた。覚えていないだけで、もしかしたらわたしはそれにふれていたのかもしれない。
ある年の大掃除のときに、ガリ版印刷機を捨てることになった。父や母は、障害者運動など様々な運動をしていたが、資料の印刷は母が仲間たちと買ったコピー機や印刷機をつかうようになっていた。ガリ版印刷機はもう何年も使っておらず、そして使うあてもなかった。無用の長物になった、と父と母は判断した。うろ覚えだが、ガリ版印刷機を団地のゴミ捨て場まで運んだのは、父に命じられたわたしだったような気もする。それを捨てるときに、雁皮でつくられた謄写版原紙も一緒だったはずだ。
わたしの記憶のなかには、雁皮の痕跡がある。わたしはその傍らで生きており、そしてもしかしたらそれが何かわからないまま、捨ててしまっていたのかもしれない。
わたしがこれからつづっていく物語は、そうやってこの<わたし>のいる世界にひっそりと存在する雁皮やその痕跡をめぐるものであり、雁皮と人や雁皮以外のものたちとのかすかな交わりである。雁皮と世界がこすれていく中で囁かれる、その声や、音、言葉に耳を傾ける。
雁皮は、人が関心を持とうと、持つまいと、山の中にひっそりと生えている。雁皮は砂礫の多いやせた土地で、太陽の光をあびて育つ。大木にはならない。その匂いや筋張った繊維は多くの生き物にとって、食物としてそれほど魅力的なものではない。春が過ぎる頃に、黄色い、小さな花をつける。
本来、人と植物との関係は素っ気ないものが主だった。人が濃密に付き合う――つまり、採集し、食べ、育て、その属性を自分に都合のいいように改変していく――植物は、この地球に生きる植物のごく一握りでしかなかった。薬草師やシャーマン、あるいは植物学者以外の多くの人間にとって、その暮らしにかかわる植物はわずかだ。
雁皮もまた多くの人にとって、それほど深いかかわりのある植物ではない。
しかし、一部に深くかかわる人がいる。そして人が行った様々な営みが、雁皮の暮らしを大きく変えてしまう。人の営みによって雁皮は時に減り、時に増える。

雁皮が自生する森(高知県四万十町)
国破れて山河在り――。社会に大きな悲惨な出来事があったとしても、山も川もかわらない、と人はどこかで信じている。そのような信念こそが、実は人類がこの地球を劇的に変えてしまっていることに対し、鈍感でいることの一つの理由なのかもしれない。人は、山や川を劇的に変えてしまう。しかし、意のままに変えることはできない。意に反した変化があり、思わぬ帰結がある。人の営みは山や川やそこに生きる植物や生物を翻弄することがあるが、同じように、そして山や川やそこに生きる植物や生物が人を翻弄することもある。調和と征服のあわいで、まだかろうじてともに生きている1。
身近な人や気になっている人、尊敬する人の訃報に接することが多い。超高齢化社会、多死社会ということを強く感じる。
2023年の暮れが押し迫った頃、わたしが会うこともなく、そして直接やり取りをしたこともない、ある知識人の追悼のために文章を寄せることなり、その人の書いたものを読み直し、そしてその人のやっていたことはなんだったのかを人と語った。死の溢れる時代にその人が亡くなったという言葉を受信し、その言葉について考えていた。
しかし、その人の書いてきた生の思想の先に考えるべきは、今は生が溢れる時代でもあるということなのではないか。わたしはそう気付いた。人類の人口は、人類史上、今もっとも多い。人間による生息環境の破壊や乱獲によって減少・絶滅する生物種は後を絶たない一方で、人間の生息域に適応して増加する生物種もある。環境汚染や温暖化によって異常繁殖する植物プランクトンのように人類の営みが間接的、直接的に増殖させてしまう生物種もある。人口が増えただけで、固有名で接する人はどんどん少なくなっているリアリティがある。そして大量に増えていくのは生態系や人類の健康にとって望ましくないという価値判断がある。
ただ、問うべき(≠否定すべき)なのはその発想そのものなのだということを、今、わたしは強く思う。疫病も戦争も、そして様々な矛盾も溢れているこの地球で、この世界にあふれてしまった生を、優劣をつけずにどう肯定するのか、ともに生きのびていくための思想を編み出すのかが問われている2。
わたしがふれたいのは、雁皮が人にとって役にたつのか、たとえば和紙や謄写版原紙の原料になるのかどうかということにとどまらない、時に華やかでありながら、時にぱっとせず、冴えない雁皮自体の生である。この大量死と大量生の時代に生きる思想を、この時代に人の手のなかなか届かないところでしぶとく育ち、増えていく雁皮が与えてくれることをかすかに願いながら、雁皮の囁きを追いかけて彷徨おう。
2022年の11月に四万十川流域から雁皮を持ち帰った。わたし以外の仲間二人が持ち帰ったきょうだい苗はそれぞれその冬や、次の夏に枯れてしまったけれど、わたしが持ち帰った苗は、我が家の決して豊かではない土壌に根付き、日の光を浴びて育ち、2メートルを超えた。2017年1月にはじめて持ち帰った雁皮は、その頃住んでいた家の横に置いた小さなプランターで芽吹き、花をつけたが、わたしがあまりにも水をやりすぎてしまったため、枯れてしまった。ひとまずわたしは庭に根付いた雁皮から、紙を作ろうとはおもっておらず、ただそれが育つに任せていたいと思っている。わたしの家には雁皮があり、その傍らでわたしの家族や隣人たち、小鳥や虫、菌類は日々の花鳥風月に接しながら、あるいは花鳥風月そのものとして生きている。
雁皮と人をめぐる物語、この雁皮のきょうだいたちが育つ森との出会いから始めることにしよう。
参考文献
有岡利幸2018『和紙植物』法政大学出版会
杉田俊介2024「凌駕不能的自然、あるいは、他者にとってもまた私自身にとっても他者であるような自己」『現代思想』52(3):9-98
貴田庄2005『レンブラントと和紙』八坂書房
アナ・チン2019『マツタケ――不確定な時代を生きる術』赤嶺淳訳、みすず書房
写真:森田友希
- 人間以外を含めたさまざまなものとともにある世界を描く、マルチスピーシーズ民族誌の中心人物の一人であるアナ・チンは、種間の相互行為の歴史を取り入れたものとしての攪乱に注目した生態学を模索する。ここにおいて、多くの生物は、調和も征服もせず、ともに生活している。そして疎外とは、このような絡まり合いをなかったことにして、それぞれの存在が独立したものとして扱われることだとする(チン2019:9)。このチンの議論に従うならば、雁皮を和紙植物とだけ見ることは、雁皮を種々や存在間の絡まり合いから切り離して、ただ和紙産業やそれに関連する産業に富をもたらす資源としてだけ位置付けることになる。
- 社会学者で、生存学を立ちあげた立岩真也は2023年の夏に亡くなった。立岩真也の仕事について、杉田俊介は次のように書く。 〈「『花鳥風月』に接することができるようであればよいではないか」。そう書かれていた。唯の生とは、花鳥風月と共にある生であり、それらをただ『受信』するだけの生である。世界を感受し、光を感じられること。ぱっとしない、冴えない生。それで十分であり、それ以上でもそれ以下でもない。それ以上を要求して人生の意味/無意味、できる/できないの区別に固執することは、もちろん個々の自由ではあるのだが、本当はそれ自体がノンセンス(無意味)なのではないか、だとすれば――。/誰もが生きてよい。平等で生きてよい、それは権利以前の権利であり、義務以前の義務である。生きろ、とは言わない。生きてよい、と言う。それは声である。命令でも、契約でも、説明でもない。呼びかけだという。〉(杉田2024:91-92) わたしが描きたいのは、雁皮とそれをめぐる人びとの「唯の生」であり、その困難である。人間と自然の関係を抽象化して描くのではなく、この雁皮とこの人、この地域の「唯の生」を描きながら、この世界の成り立ちを明らかにする。