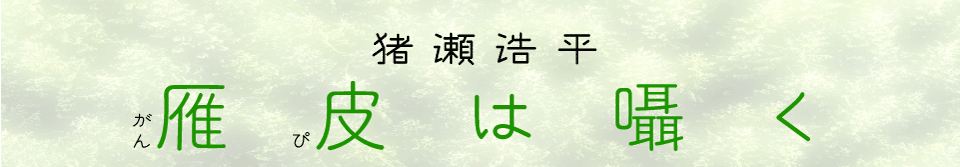不老不死の夢を、現実にするべく研究が進み、そこに莫大な投資がなされていく。コンピューターに意識を移植し、脳をデジタル化するための研究があり1、老化のメカニズムを明らかにし、老化を制御するための研究がある2。様々な困難が待ち受けているのだろうし、議論しなければいけないことがあふれているが、不老不死にむけた研究は着々と進む。それがゴールに達するのが早いのか、人類が滅びるのが早いのかはわからない。
不老不死が未来に実現するかもしれないという話を聞くと、わたしはたじろぐ。わたしは、日々老いていく――この一年でわたしは老眼になり、思わぬところに白髪をみつけるようになった――。わたしは死ぬことを定められている。でも、いつか死なない人が生まれるのかもしれない。その時代に、わたしは間に合うかもしれない。間に合ったとしても、わたしが死なないでいられるのかどうかは別の話である。今、様々な格差が起きているように、不死もまたこの社会のいびつさの中にあるはずだ。不死の人間の到来を、死すべき人間は許せるのだとしたら、それはどんな種類のいびつさによってなのだろうか。
しかし、それはまたわたしの一面の想いに過ぎない。あなたは本当に永遠に生きたいかと問われたら、わたしは即答できない。永遠に生きることが、わたしたちの幸せになるのだろうか。細胞の老いることがなくなったとしても、わたしたちの意識が電子化されて、肉体から切り離されたとしても、それは<永遠>を保障しない。老いない身体も、不慮の事故や、意図的な暴力でその命を断ち切られてしまう。電子化された意識も、それを媒介とするシステムが破綻したらこの世からはなくなってしまう。不老不死が技術的に可能になったとしても、実際に突発的に死んでしまう可能性をなくすことはできない。永遠に生きるためには、偶然の出会いなどいらない。むしろただひたすらに続く平穏な状態があればいい。その永遠に続く、偶然性のない、他者の存在しない世界にあり続けることは、死と何が違うのだろうか。
わたしが願うのは、永遠に生きることではない。一瞬が永遠であることである。わたしには、永遠であることを願う一瞬がある。一瞬が永遠であることを願う技術は、何も不老不死の研究だけではない。
***
永遠に生きられないことを覚悟している時代の人びとが、それでも一瞬の出来事を、束の間の幸せを、そして忘れてはいけない悲惨を未来に託すために、それを書き、描き残す。それは不老不死という夢にむかって研究を行うこととは違うが、しかし一瞬が永遠を願うことである。そしてそのように願うことは、生命科学の先端的な研究をする一握りの人間だけでなく、たぶんすべての存在に開かれている。
御成婚の森で採集された雁皮で紙を漉き、そこに満州開拓の記録を残すべきではないかというわたしの言葉に応じて発せられたオカモトさんの「そうじゃ」という言葉は、その願いと重なるところにあるとわたしは感じる。
***
正倉院の紙も、厳島神社の平家納経も、雁皮の紙を使用していると言われる。紙を使うこと、文字を使うことが特権だった時代、その特権を手にしていた人たちの残した文字や絵が今を生きるわたしたちに伝わる。
今は文字も、紙も、当時では考えられないほど多くの人が使えるようになった。さらにデジタル技術が発達し、紙に依存しなくても、劣化の心配をせずに記録を残すことはできる。それでも、劣化する紙に何事かを連綿と残そうとする。愛媛県のある製紙会社を訪ねた際、店内に次のような文章が書かれた言葉が貼られていた。
家系図用和紙をお求めのお客様へ
千年以上保存したい方は、雁皮紙をお求めください。正倉院に残っている和紙はそのほとんどが雁皮紙だといわれています。従って千年以上保存できる事が証明されている訳です。ただし、ほかの楮紙、三椏紙も100年~200年は十分保存可能だと思いますよ。
雁皮紙を通じて、千年先に残したいと願う人の存在を知り、わたしは永遠の命をめぐる研究とふれたときとは違った意味でたじろぐ。しかしその願いは、雁皮紙に満州移民の記録を残すというわたしの言葉とどこかで重なっているようにも感じる。
姜信子は国家というものが、人びとの記憶や経験を奪っていくその暴力に対峙する方途を、芸能の中に探ってきた人だ。姜は、明治期以降の日本の近代化を、国家による神々の一元化=体系化=近代化とし、次のように語る。
土地の神々と結びついた人びとの生の記憶や物語、声によって開かれた神や物語の宿る「場」が力ずくで消されていったのです。それは、風土に根ざして生きてきた人びとの祈りが奪いとられ、別の種類の祈りに置き換えられていったということでもある。
姜はめざすところを、「たった一つの中心、たった一つの真実に力ずくで縛られる世界ではない」とする。それは、無数の中心が偏在し、その場に根差した真実が中心の数だけ存在して、それが菌糸のように互いにつながり合い、生かしあうような世界である。その世界における真実とは、人間だけでなく、生きとし生けるすべての命に向き合う誠実さの別名であるとする(姜2023:12-13)。
旅ゆく語りの声は道で出会い、互いの声に耳を澄まし合い、物語はひそかに聴きとられ、声と声の間を行き交って、ときには重なり合うように、ときにはそれぞれ異なる語りを孕んで、ときには文字を介して、さまざまな土地で、さまざまな声で、さまざまな形に、豊かに増殖していたのだ。(姜2023:58)
姜の文章を読みながら、シマオカさんの大きな声に導かれて、オカモトさんが囁くような声で語っていく、あの四万十川のほとりの旅行く人びとの風景を思う。
他者の中で生き続ける
生命科学の研究者が個体としての生を永続させる方向で日夜研究に励む。一方、この同時代を生きるイタリア出身の哲学者エマヌエーレ・コッチャは、生はすでに永続するものであると言う。コッチャはこれまでの哲学が、人間を中心にしていたこと、その射程を広げるとしてもせいぜい動物までにとどまっていたことを批判し、植物を対象にした哲学を探求してきた人だ。
コッチャは、「環世界」という概念を提示したユクスキュルが、世界との接点が器官的な性質に限られていることを批判する。植物において、世界との接点は、たとえば葉や気孔といった一部分でのみなされている訳ではない。その身体と存在でもって世界と接しているとする。「かたちも機能も区別することなく、植物は世界に対して開かれ、自身のうちで世界と溶け合う」(コッチャ2019:59)。植物は光をあびながら、風にそよぎ、光合成しながら呼吸し、そして根から水や養分を吸い上げ、生き物に捕食され、そして様々な地衣類やバクテリア、細菌と共棲する。
同じように雁皮も、全身で世界に開かれ、世界と溶け合う。わたしには、雁皮がどのようなものに育つのか、どのような土壌を好むのか、そしてどのように増え、どのように減るのかその理由はわからない。のちにふれることになるが、かつて雁皮が群生していた山口市のある村の森には、もう雁皮はほとんど生えていなかった。子どもの頃にそこで雁皮を採集した人ともに、2024年の2月に森を歩いたのだが、その人が驚くほど雁皮はみつからず、半日歩いて2本しか見つけられなかった。その地域で雁皮をとる人は、もうずっといない。人間が採り尽くしたということは考えにくい。その人も、だからたくさんの雁皮が生えているはずだと考えていた。しかし、雁皮はなかった。その人は、一つの仮説としてその地方で行われた松くい虫防除の空中散布が理由であると語ったが、真実かどうかは定かではない。いずれにしろ、あの山の雁皮も、世界に開かれ、世界と文字通りに溶け込んでいた。
コッチャにとって生とは、わたし自身から生まれたものではなく、他者から受け継がれたものである。わたしたちは植物が生み出した酸素を呼吸し、植物や動物を摂取し、それを腸の中にある菌の力を借りて消化しながら生きている。太陽の光を浴び、風のそよぎに触れ、そして自分の先祖から与えられたDNAによって身体を刻み込む。そしてわたしたちが吐き出す二酸化炭素や、排泄物、老廃物、遺骸は、植物や微生物、バクテリアやウイルスの光合成や分解の作用に託される。わたしたちはともに生きる人間やそのほかの生き物、植物にはたらきかけ、そして未来を託す。だから、わたしたちの生は、自分の生まれるはるか前にはじまり、自分の死のずっとあとに終わる(コッチャ2022 :6-7)。生まれることは、以前わたしたちであったものを忘れること、他者がわたしたちのなかに生き続けることを忘れることを意味する(コッチャ2022:18)。
コッチャは、人間において、その最も私的で譲り渡すことが出来ないと考えられているもの、絶対的に個人的で固有のものと思えるような生ですら、本質的に匿名的かつ普遍的で、どんな種類の身体にも命を譲りわたすものであるとする(コッチャ2022:6;98)。たしかに、わたしが考えたアイデアや、わたしが抱く切ない想い、揺るがないと考えている信念も、それは模範となる人や、愛する人、本の一節や自分が行う日々との授業や会話、メールの一言、その日の気候や、体調との関係の中で生み出されたものであり、わたしの中からおのずから生み出されたものではない。そしてわたしたちが死んだとき、他のすべての存在と同じように、身体は腐り、燃やされ、何かに変容していく。同じようにわたしの言葉や思いも、その多くは忘れられていくのだが、ほんのわずかだけわたしの部分となってわたしの思い通りに引き継がれ、わたしの意図と反して引き継がれていく。
コッチャの議論を敷衍していけば、個体としての雁皮やヒトの生は他者の中で生き続けていくということになる。ハマダさんのように育成を通して植物としての雁皮と直接的にかかわることだけではなく、人間が雁皮を探し、刈り取ること、あるいは雁皮が生えている山を歩いているのに雁皮に気づかずに素通りすることも(マツタケやコウタケを採集し、タヌキの狩猟をすることもあったのだろうし、あるいはハイキングをすることもあっただろうし)、雁皮が目に入らず刈払い機で伐採することも、雁皮の皮をはぎ、小遣い稼ぎのために売ることも、そして黒皮をはいで白皮を叩いてほぐすことも、漉いて紙にすることも、漉かれた紙に書を書くことも、その作品を鑑賞することも、自らの家系図を残すこと――つまり加工された雁皮を通じて触れることも、あるいは漉かれた雁皮の紙に描かれた書を楽しむことも――もつうじて、人びとは雁皮と溶け合う世界に生きてきた。そうやって個体としての雁皮やヒトの生は他者の中で生き続けていく。
皇太子の結婚を祝う目的につくられた、まさに国家による一元化=体系化=近代化の象徴とも言える森の傍らで、シマオカさんの大きな声に促されて、オカモトさんは小さな声で満州移民の経験を語る。そこで語られ、聴き取られた物語を残すために、その山で育った雁皮で紙を漉く。そこに記憶を記録として残し、未来に託す。それは、風土に根ざし、風土から引きはがされ、そしてまた風土に根差そうとした人びとの祈りである。その祈りは、雁皮と溶け合う世界の中にある。
参考文献
姜信子2023『語りと祈り』みすず書房
エマヌエーレ・コッチャ2019『植物の生の哲学――混合の形而上学』(嶋崎正樹・山内志朗訳)勁草書房
――2022『メタモルフォーゼの哲学』(松葉類・宇佐美達朗訳)勁草書房
- 「機械に意識を『移植』 東大発ベンチャーの挑戦」『毎日新聞』2022年12月22日配信記事(https://mainichi.jp/articles/20221221/k00/00m/040/017000c)
- 「『制御できる日は近い』老化 研究の第一人者が語る可能性と懸念」『毎日新聞』2024年4月8日配信記事(https://mainichi.jp/articles/20240403/k00/00m/040/321000c)