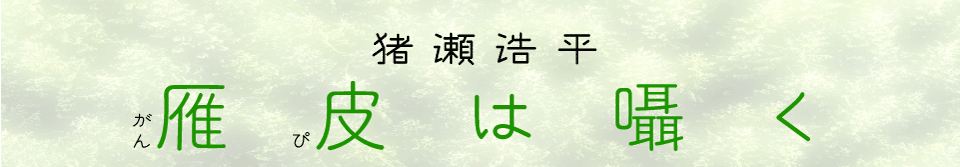「雁皮は囁く」とはどういうことだろうか。
和紙に加工された雁皮は、何かを書き記されるもの、描かれるものである。楮や三椏のように海外から輸入され、栽培によって増殖した植物と違い、雁皮は東北を除く日本列島に自生する植物である。楮や三椏と違い、栽培には適さないとされて、野生のものが採集される。だから希少性は高い。「紙の王」とも呼ばれる雁皮は、肌理が細かく書きやすいだけではなく、保存性にも優れている。だから芸術作品にも、記録文書、公文書や株券、賞状にも使用されてきた。ベルサイユ条約では、鳥の子紙が使われたとされる1。大戦の終結の瞬間は、雁皮で作られた紙に書き記され、そしてそれが後世に伝えられる。このとき、雁皮紙は、国家の力そのものをあらわす。同じように、権力者の居城や邸宅の襖絵を飾る雁皮紙も、その絵の美しさとともに、権力者の威光をあらわす。雁皮は希少資源となり、統制の対象となる。その囁きを聴くのは難しい。
それでも――。
「土佐源氏」と雁皮
「秋じゃったのう
わしはどうしてもその嫁さんとねてみとうなって、そこの家へいくと、嫁さんはせんたくをしておった。わしが声をかけるとニコっと笑うた。わしは「上の大師堂でまってるで」いうて、にげるようにして、その家の横から上へ上る小道をのぼっていった」。(宮本1984:148)
『忘れられた日本人』の最も印象的な章である「土佐源氏」に、雁皮は登場している。ばくろうとしてむらとむらとの境界を生きた男が、年老いて盲目になり、橋の下で乞食となって生きている。その男に付き添う婆がおり、話はその婆が、まだ娘の時分にさかのぼる。彼女の母親は、ばくろうの親方のなじみであった。親方が死んだあと、自分よりも二十近く若い男を世話してきた。親方に比べて頼りないことをしかられながら、男は母親と交わる。それをはたで見ていた娘とも、男はいつしか交わり、そして彼女を連れて逃げた。伊予と土佐の境を越えた。それまでばくろうのみならいをしていた男は、生涯はじめて一人前の人間――隣近所のつきあいもし、世帯を張って子供をもうけて……――になりたいと思った。しかし、生まれてから一度も村の中で役割を持ったことのない男は、一人前のむらびととして受け入れられることはなく、小さな納屋を借り、娘と二人で紙問屋の手先になって楮を買って歩いた。それでも、その3年間が、男のもっとも人間らしい時だった。
土佐のはずれにある官林に雁皮が群生していた。周囲の百姓たちは、お札の原料になると、払い下げをして雁皮を刈り集めた。男はその雁皮を百姓たちから買っていたのだろう。やがて官林に生えていた楮の話をするために、官林を管理する高知城下からやってきた役人に会うようになった。やがて、大きい黒い目をした、鼻筋のとおった、気持ちの柔らかな、その嫁さんと懇意となる。夫の不在時、せんたくのすすぎの水をくんであげると、嫁さんは「あなたはほんとに親切じゃ」といった。男にとって役人は、自分のような悪いことをばかりするものを取り締まる存在だった。山回りをするときは巡査と同じような服を着て、腰にサーベルを下げて歩く、そんな圧倒的な権威を持った存在だった。その嫁さんに一人前に扱われ、お礼を言われたのは生まれて初めてのことだった。感激した男の心に、やがて魔がさす――。男は夫のいないときをみはからい、たびたびその家をたずね、やがて彼女を大師堂に誘う。夕日が差す頃に、絣の着物を着て、前掛けをしながら上がってきた嫁さんを、お堂のなかに招じ入れ、なぜ自分のようなものの誘いに乗ったのかと問うと、嫁さんは「あんたは心のやさしいええ人じゃ、女はそういうものが一番ほしいんじゃ」と答えた。
男は嫁さんと4、5回会ったが、この人に迷惑をかけてはいけないと思い、嫁さんにも、自分の女房となった娘にも何も言わず、雪降る道を伊予へと去った。
入会権をもとに、官林の払い下げの恩恵を受けた村人たちが、お札の原料として売るために雁皮を採集する。男はその取引を媒介しながら、自身は採集には加わらず/加われず、官林を管理する役人の妻と交わる。しかしそれは長続きせず、国を越えて逃げる。そしてその美しく、切ない想い出を、宮本常一に囁く。
雁皮が呼び水となって、人が山に入り、そしてそこで集められた楮や雁皮を媒介する周縁的な存在が、権力を代行する存在の傍らにある人と越えてはいけない一線を越える。雁皮は紙幣となって流通する。男や嫁さんのかりそめの交わりは忘れられていく。忘れられていくその手前で、民俗学者はその囁きを聴き取り、文字にして託す。
権力による監視と動員
明治政府は各藩で発行されていた藩札を廃止し、統一した紙幣を発行した。当初、楮をつかって太政官札がつくられたが、質は低く、偽造が可能だった。やがてドイツ・アメリカから輸入されるようになった。しかし用紙の耐久性の問題や、経費がかさむ問題もあり、1877年に大蔵省紙幣局が初めて国産の紙幣を発行した。このときの一円券は原料の30%が三椏、70%が雁皮、抄造法は流し漉きだった。五円券は20%が三椏、80%が雁皮であり、溜め漉き法によっていた。やがて、栽培が難しい雁皮では需要に応えられないという判断から、次第に雁皮は原料として使われず、三椏が主流となる(大蔵省印刷局1972:57)。
大江健三郎は愛媛県喜多郡大瀬村に生まれた。山と森に囲まれた、谷間の小さな村である。彼の家は、印刷局に三椏を納入することを家業にしていた。紙幣の原料にする三椏の繊維を精製し、重さと大きさを揃え、父が工夫してつくった機械で梱包して、内閣印刷局に納める。戦時中、大江は愛媛県知事が視察に来た時のことを次のように書いている。
作業の様子を、愛媛県の「銃後」の民間産業の、小さな実例として示すことになった。県知事が視察に来ました。知事の部下が私の父に、その機械で梱包をやってみるように命じたんです。その機械は二人が両側から圧力のバランスをおりながら動かすものなのに、戦争で家で働いていた人たちは招集されて、父がただ一人なんです。そこで、「できない」と父がいったんですよ。一緒に来た警察署長が「おまえやって見せろ!」だったか「やってお見せしろ」だったか、そういう言葉で命令した。父がむっとしたのはわかりました。しかし、父が立ち上がって、機械の両側を行き来しながら、なんとか作業を始める……私は、話し言葉にこういう権力を持った人間が押しつける言葉、弱い者には抵抗できない言葉がある、自分の父親は、抵抗ではないほうなんだと、強い印象を受けたのを覚えています。(大江2007:17)
権力を持った人間が視察にやってきたのが、紙幣の原料である三椏の精製・梱包・出荷作業だったというのは象徴的である。紙幣は国家による厳重な管理の中で生産される。偽札がつくられてしまったら、その国の経済に影響を与えるばかりではなく、国家の威信は傷つく。国家権力の代理人として、紙幣の生産状況を監視するために発せられた言葉は、父を不快にさせながら、それでも言ったとおりにはたらかせてしまう力を持っていた。
少年時代の大江は、村の暮らしの中で二つの言葉があると感じていた。一つは人びとが日常に話す言葉で、権力を持っていない人間の言葉としてつくられている。もう一つは権力を持つ人間の言葉であり、それで話しかけられると村の大人たちは卑屈な感じで答えるしかない。「おまえやって見せろ!」は権力を持つ人間の言葉である。
紙幣は和紙を必要とし、国家は三椏をその原料として厳重に管理し、人びとに調達し、加工させる。
三椏や雁皮が国家に利用されるのは、なにも紙幣になるからだけではない。たとえば農商務省が1945(昭和20)年1月に発行した『週報』では、「戦う物資 楮・三椏・雁皮」という記事が掲載されている 2。
戦争が大きくなればなるほど軍費も国費も嵩んでくるので、紙幣もたくさんつくらねばなりません。占領地には軍票も必要です。占領地がだんだん広くなれば軍票も厖大な発行量になるわけです。また国債も公債も発行しなければなりません。
和紙が戦争に使われる面はまだまだあるのです。気球原紙もそうです。南方では軍用天幕にも使われています。爆薬包装紙はもちろん、擬皮原紙からつくられるパッキングは航空機に欠くことができません。作戦を遂行するのに使われる地図とか図引紙、作戦命令を出す場合の複写紙等、和紙も勇猛果敢な皇軍将士の手で使われているのです。
銃後ではどんなものに使われるのでしょう。温床紙、米黍防雨用の天幕、蚕種掃立紙等、農業用に、社債、株券、証券、複写用紙等、数え上げると和紙でなければならないものがいくらでもある筈です。
和紙は戦争にも国民生活にも大変重要になったので、どうしても楮、三椏、雁皮を増産していただくと共に、どしどし供出していただかねばなりません。
強靭な和紙は前線においても、銃後においてもさまざまな用途を持つ。この文章の末尾は、「是が非でも、最も質の良い時期である冬の間に生育している楮、三椏、雁皮は全部刈り取るのだという意気込みで、供出していただきたいのです」で結ばれる。権力を持つ人間の言葉で、雁皮は他の「和紙植物」と一緒くたにされて、動員を迫られる。
幼い日の大江は弱い側の言葉の中に、ふだんのあいまいな話し言葉とは違う、別の話しぶりの言葉があることに気付く。祖母や母親が、村の伝承を語る時、小さな歴史を語るとき、その話しぶりは現われる。それは聞き手を面白がらせる繊細な配慮があり、単に事実や情報を伝えるだけでなく、さまざまな仕組みがある。大江はそんな物語を聴き、書き残すべきものとしてそのまま記憶しながら、やがて明治維新前後に大江の暮らす地方で起こった一揆という大きな軸を理解していく。
両義性と可逆性
雁皮は植物である。しかし、文字や絵が書かれる/描かれる媒体=紙の素材となる。 雁皮は栽培できず、採集に頼らざるを得ない。そしてその採集すら計画的に行うことはままならない(雁皮自体の生育状況の不確定性とともに、採集する人間の人手不足)。これは、人間による野放図な資源化をかいくぐっていることのあかしである。雁皮が希少であることは、人間がつかう素材としての雁皮の価値を高めてしまう。雁皮をつかった紙の権威は高まり、雁皮をもちいるそしてそれを使う人間や、それによって描かれる人物や記録される事物の権威を高める。その一方、雁皮があまりに稀少になっていくと、より質の劣るとされる、より計画的に栽培・収集できるものに代替されたたり、その価値を忘れられたりしてしまう。雁皮の存在は、この世界の雁皮と直接かかわるものによっても、直接かかわっていないものによっても、意味付けを変えていく。そして雁皮に与えられた意味付けが、また世界を形作っていく。
描くべきなのは、この両義性と可逆性である。
その両義性と可逆性は、雁皮だけでなく、わたしという存在のもつ両義性と可逆性に通じる。コッチャは「わたしたちがみな絶対的に個人的で固有のものと考えるような生は、じつのところ、本質的に匿名的かつ普遍的で、どんな種類の生ける身体にも命を与えることができる(コッチャ2022:98)」と書く。これを受けて藤原辰史は、コッチャのこの言葉を「自分自身が自分の生を生きていると思っていても、それはこの惑星の生の漂流のひとつを体現しているにすぎない」と言い換える3。 コッチャ=藤原の言葉を敷衍すれば、匿名的かつ普遍的な生を生きているわたしたちは、そのことに耐えられず、絶対的に個人的で固有なものであろうとする。それが、雁皮という存在の両義性と可逆性を生み出す。
宮本常一が聴き取った土佐源氏の囁きも、大江が聴き取った祖母や母の囁きも、絶対的に個人的で固有なものであることにこだわらない。この世のありふれた、とるに足らない一人の人間が、普遍的に経験する苦悩と、世の中の出来事や歴史の解釈との境界線を、そして人と人以外のものがともにある世界の線を、素っ気ない素振りで体現してしまう。
そこで、雁皮は囁く。
*『忘れられた日本人』の読解については、門田岳久さん、中村寛さんにご教示いただいたことが手掛かりになった。どうもありがとうございました。
参考文献
安部栄四郎・柳橋真1980『紙漉き七十年――安部栄四郎の世界』アロー・アート・ワークス
今立町誌編さん委員会1981『今立町誌』今立町役場
大江健三郎・尾崎真理子2013『大江健三郎 作家自身を語る』新潮文庫
大蔵省印刷局1972『大蔵省印刷局百年史 第2巻』大蔵省印刷局
エマヌエーレ・コッチャ2022『メタモルフォーゼの哲学』(松葉類・宇佐美達朗訳)勁草書房
宮本常一1984『忘れられた日本人』岩波文庫
- 出雲で雁皮紙を漉き、人間国宝としての指定をうけた安部栄四郎が1980年に出した著書でこの点に言及している(安部・柳橋1980)。一方、1981(昭和56)年に福井県今立町が編纂した「今立町誌」は、三椏を主とした鳥の子風の紙である滝ぺーパー(輸出程村)が、世界一の紙とされ講和条約の紙として伝えられたとしている(今立町誌編さん委員会1981:744)。一方、1940(昭和15)年に刊行された八木吉輔編『日本紙業史・京都篇』では、「ベルサイユの講和條約締結の時、その條約書には世界中で最も良い紙とインクとを使いたいとの事で選擇の結果、インクは英國製を利用し、紙は實に日本紙になったのである」(八木1940:47)と書かれており、それがどこの産地のどんな紙だったのかの記述はない。
- 表紙には、「隣組・職場で必ず回覧を」と書かれている。
- 藤原辰史「書評 メタモルフォーゼの哲学」『朝日新聞』2023年1月14日。