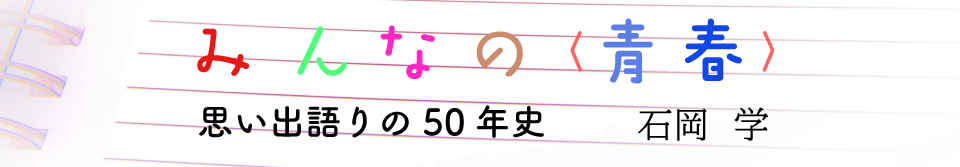長丁場だと思っていたこの連載も、残すところあと2回というところまで来てしまった(ずっと読んでくださっている方々、ありがとうございます)。いよいよ終わりが見えてきたということで、今回は「青春の終わり」に焦点を合わせてみたいと思う。
前回(第10回)では生涯青春、つまり終わらない青春について考えてみたのだが、最終的にそれは「ずっと青春の気分を持ち続けなければならない」という規範なのではないか、というところに着地した。そうだとすれば、「青春の終わり」を明言することは、なかなかに勇気のいることである。あるいは、そう言い切ってしまうだけの何か重大なきっかけがあるのではないか、とも思われる。そんなことについて、今回もいろいろな「語り」に触れながら思いを巡らしてみることにしたい。
生き方が決まったとき青春は終わる?
この連載では何度も書いていることなので恐縮だが、近代的な青春は子どもから大人への過渡期が長期化したことによって成立した概念である。そうであるならば、何らかの契機で「大人になった」ということが自覚されたとき、つまり過渡期が終わったと認識されたときに、青春はその終わりを告げるのではないかと想定できる。
このような自覚について、かなりの主体性をもって語っているのが、俳優の藤原竜也(1982年生まれ)である。藤原は雑誌のインタビューの中で、役者として「デビューするまでの中学校の2年間が青春でした」としたうえで、次のように語っている(「インタビュー 藤原竜也 役者として生きていく。そう決めたとき、僕の青春は終わった」『パピルス』2009年8月号)。
10代だったし、まだまだ遊ぶことが楽しいし、地元に帰って友達と一緒にいたほうが楽しいんじゃないかって。そういう想いはずっとありました。それが変わったのが17歳のとき。唐十郎さんが書いた『滝の白糸』という作品を蜷川さんの演出で演じたときに、この仕事で生きていこうと決めた。「これが俺の仕事だ」って思えた。そう決意したときに、僕にとっての青春は終わったと思う。それからはストイックに真面目に芝居に向き合ってきたから、もう青春なんかじゃないと思う。
藤原は、俳優として生きていくことを主体的に引き受けた瞬間に、青春は終わったという。逆にいえば、青春とは「どのように生きるべきか」といった悩みの渦中にいる時期だということになるが、このとらえ方は「かつての青春」のイメージに近い。上のインタビューでは「17歳のとき」と言っているが、別のところで彼は、やはり蜷川と唐の「高貴な」会話に衝撃をうけ、「僕が学ぶべき場所は高校じゃなくて稽古場なんだと思」い、高校を4日で中退したと明かしている1。現代の日本において、高校に行かないという選択をとることは、かなり思い切ったことだ。実際はこのときに、藤原は早くも青春と決別していたと言えるかもしれない。
俳優の赤楚衛二(1994年生まれ)も、似たような「青春の終わり」を経験している(吉田可奈「『青春は過去のもの』と言う赤楚衛二が演じた青い季節」『キネマ旬報』2020年7月23日号)。赤楚は、「青春って、言葉を選ばずに言えば、無責任でいられる時間だと思うんです」と言い、「20歳を目前にして、親にそれまで言えなかった“俳優をやりたい”という気持ちを告げ、上京をしてからは、責任と覚悟を持って、仕事のこと、将来のことを考えるようになりました」と語る。まだ何者にもなっていない青春時代とは、それゆえの不安もある一方で、いろいろな責任を負わなくても済む時期なのだというのが、藤原や赤楚に共通した認識であるといっていいだろう。
その2人に比べ、より不可抗力的に生き方が決まったように感じ、それによって青春の終わりを自覚したと語るのは、漫画家の東村アキコ(1975年生まれ)である(「30代がくれたもの 20回 東村アキコさん」『CLASSY』2017年9月号)。
東京に出てきてからは仕事も激烈に忙しくなって、週に1度、締切りが来る生活でした。それに加え出産後は子育てにも追われていたので、29歳にして青春はもう終わりだなと思いました。仕事もやっとうまくいき始めて、お金も使えるようになったのに…。私は一生、母&労働者として生きていくんだなと鏡を前に思った記憶があります。陣痛が始まって分娩室に行くときに、母となる前の最後の顔を見ようと鏡を手にしたら、そのとき脳内に流れてきた音楽は『大阪で生まれた女』(笑)。別に好きな曲でも、よく聴いていたわけでもないのに、“♫これで青春も終わりかなとつぶやいて~”って歌が流れてきて(笑)。青春のピリオドを打った感がありましたね。
先にみた藤原のケースと比べて、「母&労働者」という生き方が決まったことで、青春に未練が残っていたことがうかがえる。だが、いやだからこそという言うべきか、実は東村にとっての青春は終わっていなかった。彼女は同じインタビューの続きで、「まさかの30代に人生最大の青春が待っていました。最初2、3年は育児が大変だったけど、蓋を開けてみれば30代はめっちゃ楽しくて、すべてがピタッとハマった時代でした」と語っている。ここでいう「青春」は「充実した時期」と言い換えられるが、藤原が語っていた「青春」とはその意味合いが違っている。このあたりに青春の多義性がよくあらわれていて、面白いと同時に難しいなといつも思う。ただ、いずれにせよ、生き方が決まり「大人になった」という自覚が、青春の終わりという認識に結びつきやすいのは確かなようだ。
気づけば「大人」になっていた
とはいえ、そのようにはっきりと自覚できるケースが必ずしも多いわけでもないだろう。以前にも取りあげた作家の辻村深月(1980年生まれ)と新城カズマ(1951年生まれ)の対談では、「自分が大人になったなと思う瞬間って感じたことあります? 実は私は、一度も感じたことがないんですよ。年は取っちゃったけれども、大人になった実感は一度もないままで」(新城)、「私も同じことを感じてます。大人っていないですよね(笑)」(辻村)というように、2人とも大人になったという自覚や実感はないと語り合っている(辻村深月×新城カズマ「青春を“生き延びる”ということ」『小説すばる』2010年5月号)。このような感覚に共感する人も、少なくないと思う(私もそうだからだ)。
ただそれでも、いつの間にか若い頃とは違う感じ方や考え方、行動をとっていた、ということを認識することはあるだろう。あまり自覚はなかったけれども、気づいたときにはもう大人になっていた、という感覚である。
たとえば、劇作家の岡部耕大(1945年生まれ)は、次のように語る(岡部耕大「あれが青春だったのか(特集・青春 その甘き香りと影)」『テアトロ』1995年2月号)。
いまのいままで青春を振り返ってみることもなかったが、あれが青春だったのかとしみじみ思ってみた。「青春とは何だ」と聞かれたら、驕り高ぶりが許される時代とでも定義するのだろうか。演劇と酒に明け暮れたような青春だったが、飲む金に困ったという記憶がない。毎晩、大酒を飲んでいた。勘定はだれが払っていたのだろうか。ある日を境にして「今夜は俺が払うよ」といっている自分に気付く。その日が青春と訣別した日ではなかろうか。
気付いたときには、奢ってもらう側から奢る側に立ち位置が変わっていた。あれが青春の終わりを意味していたのではないか、という回顧である。責任を引き受けることを青春の終わりと見なしている点で、先に見たケースと似ている点もあるが、「いまのいままで青春を振り返ってみることもなかったが」とあるように、岡部の場合はそれがはっきりと意識化されていたわけではない。
きっかけになった出来事が、もっと曖昧なこともあるだろう。このあたりのことについて、みうらじゅん(1958年生まれ)にまたもご登場いただきたい。みうらは、そのものずばり「青春の終わり」をテーマにして、脚本家の宮藤官九郎(1970年生まれ)と対談をしている(「みうらじゅんと宮藤官九郎の大人になってもわからない vol.131 “青春の終わり”って、いつ訪れるんだろう?」『週刊プレイボーイ』2014年12月1日号)。まずここで彼らは、「童貞を捨てたからって、大人になったわけじゃないしね」「学校と青春の卒業は関係ないもんねぇ」(みうら)、「たぶん、結婚したときでもないですよね?」(宮藤)と、出来事ベースで青春の終わりは確定できないことをおさえたうえで、次のように話を展開させていく。
宮藤 僕はある時期に禁煙しちゃいましたけど……。
みうら それって体に悪いからだよね? 青春って逆に、体に悪いことを進んでやるもんでしょ(笑)。
宮藤 まあ確かに、体のことを気にしてジム行ったりランニングしたりっていう発想は生まれないですからね、若い頃って。
みうら 体に悪いことイコール、カッコいいことだって思ってたもんね。
宮藤 どうせ酒飲むならゲロ吐くまで飲むみたいな(笑)。悪酔いして飲み屋で大ゲンカしたりとか、そういうのも青春ですもんね。
みうら 青春はできる限り人に迷惑かけなきゃダメでしょ(笑)。
宮藤 傲慢ですけど、そういうもんですよね。
みうら でもあるとき、あんまり他人に迷惑かけないで生きていく方が楽なんじゃないかって気づくわけじゃないですか?
宮藤 そうですね。なるべく波風立てないようにっていう。
みうら そう思い至った瞬間が青春の終わりなのかねぇ。
なるほどなあ、と思う。確かに、他人に迷惑をかけず自分のことは自分で処理するようになると、「大人になった」と肯定的に評価されることも多そうだ。しかし、みうらに言わせれば、それは「他人に迷惑をかけんのがめんどくさい」からなのであり、大人の自覚というよりは「老化」に近い感覚かもしれない。対談のラスト近くでみうらは、「要するにさ、グレる可能性が完全に絶たれたところで、青春っていうのは終わりなんじゃないの?」と端的に語り、それに対して宮藤は「だとしたらもうとっくに青春終わってるっていうのを認めざるを得ないですよね、われわれも(笑)」と発言している。「グレる」というところに焦点が当たっていることからもわかるように、ここで考えられている青春も、社会への反抗や反発を含んだ「かつての青春」に近い。だからここで言われていることは、学者的な表現に言い換えるならば、既存の社会秩序への適応(=社会化)が完了したときに青春は終わる、ということになるだろう。
もっと笑い話のレベルで、青春の終わりを語るものもある。たとえば長野県の27歳の女性は、出産と育児という経験を通じた自身の変化について、次のようなエピソードを披露する(「花のレポーター・スクープ 第41弾 私の青春が終わったとき」『週刊女性』1991年7月30日号)。
丼ものは全部を食べきれず、おまけに食べるのが人一倍遅かったのは独身時代の話。子供から目を離さずに家族の残りものを平らげる今の私は、昔の3倍の量を2倍の早さで食べてます。そこで先日、夫の勧めで商店街のソバ早食い競争に出ることに。恥ずかしかったけど、賞品の海外旅行は魅力。1人脱落、3人脱落、6人脱落……。このころから“参加賞だけでも”といっていた夫の口がアングリ。そしてなんと、私は見事優勝してしまったのです! その瞬間、子供の手を引いて隠れるように逃げ出す夫の姿を見たとき、私の青春は終わったのでした。
同記事の冒頭には、「女性週刊誌を見るのも恥ずかしかった私が、いつのまにか週刊女性を毎週買うようになり、気がつくと『花レポ』に投稿するようになっていました。今のところボツ続きですが、採用されたときが私の青春のゴールですね」という28歳女性の声も掲載されている(つまりこれで青春が終わったというわけだ)。
いずれも、「恥を感じなくなったこと」を青春の終わりととらえていて、「大人になった」というよりは「中年になった」と受け止めているように感じるので、現代の目から見ると若干の違和感がある。ただ、この記事が出た1990年前後のデータをみると、平均初婚年齢は25.8歳(1992年)で2、20代後半女性の未婚率は40.4%(1990年)だった3。現代ではそれぞれ29.1歳(2021年)、62.4%(2020年)となっていることと比較すると、20代半ばに結婚・出産を経ることが一般的であった時代においては、このあたりが中年の入り口と捉えられていたのではないかと思われる(ただ、いずれも女性の話なので、男性に同様の「恥がなくなった=青春が終わった」という感覚があるのかどうか?)。
「象徴」との惜別
一方で、ここまで見てきたような語りとはやや趣の異なる「青春の終わり」についての語りがある。それは特に新聞の投書にたびたび登場するのだが、自身の青春を象徴するような人・ものがなくなることによって、青春そのものが終わってしまう、という感慨である。
まず、青春時代に憧れていた俳優・芸能人の死にまつわる語りが、よくみられる。たとえば、当時75歳だった女性による投書をみてみよう。
世紀の名女優ディートリヒさんが亡くなった。「嘆きの天使」を初めて見た時はまだ女学生、夏休みに兄に連れられて見たその艶姿が忘れられなくて、早速レコードまで買いに行った。白いシルクハットに白のエンビ服姿の素晴らしさは脚線美よりも私を魅了したのである。(・・・)当時の若い娘は、若貴兄弟の肌にさわってキャアキャア言う様なファンではなかった。たとえ日本のスターに対してもファンのマナーは知っていた。「間諜X27号」も何度場末の映画館まで出かけたことか。書き並べたらきりがない。ここまで来てついにディートリヒさんを見送って、私の長い長い青春が終わったのである。合掌。(「私の青春飾った名女優の死を悼む」『読売新聞』1992年5月13日)
ディートリヒとは、いうまでもなく、ドイツの映画俳優マレーネ・ディートリヒ(1901-1992)のことである。その死によって「私の長い長い青春が終わった」と語る投稿主であるが、逆にいえばそれは、75歳まで青春は続いていたという感覚だったことを意味している。
「私の青春時代の歌番組の司会と言えば、『1週間のごぶさたでした』の玉置宏さんでした。歯切れが良くて、出演者に優しい司会ぶりは天下一品でした。訃報に接して『生涯青春』をモットーにしていた私は、青春がどこかへ飛んで行って消えたようで、とても寂しいです」(「玉置宏さん天国へ 青春失った寂しさ」『読売新聞』2010年2月20日。56歳女性からの投書)、「ニュースを見て、京唄子さんの訃報を知った。またひとつ青春の灯が消えた思いだ」(「美容室から旦那さん応援」『読売新聞』2017年4月19日大阪版。78歳女性からの投書)など、同じような趣の投稿は、時期を問わず実にたくさん見つけることができる。
人ではなく、ものについても事情は同じだ。たとえば、大阪-長野間を運行していた急行「ちくま」の定期運行廃止をめぐって、63歳女性による次のような投書がある(「青春彩った、夜行「ちくま」 思い重ねて」『朝日新聞』2003年9月23日大阪版)。
大阪-長野間を走る夜行列車「ちくま」が今月限りで定期運行をやめると聞いて、平素遠のいていた青春時代がよみがえった。(・・・)眠れないのに、なぜか夜行列車が好きだった。夜が白々と明ける頃、車窓から見る信州の緑はことのほか素晴らしい清涼剤だった。やぼったいリュックを背負って黙々と歩いたあの頃、来るべき未来をどのように描いていたのだろう。「ちくま」が消えることは、私の青春時代が消されそうで寂しい。いや、永遠に「ちくま」は私の心の中で生き続けている。青春時代を心豊かにしてくれた「ちくま」よ、さようなら。そしてありがとう。
こうしてみると、青春時代そのものは過去になっても、青春の思い出と結びついた人やものが生きのびている限り、「青春は終わっていない」という感覚が持続することがわかる。これは、前回のテーマ「生涯青春」と似ているようにも思える。しかし、現在進行形で何かに熱中しているということが「生涯青春」の意味するところだったので、過去の思い出と結びつけられた今回のような語りは、やはり別種のものだと思う。
また、「青春の象徴」は必ずしも一つには限らない。そのため、青春の喪失感が何度もおとずれるような経験をするケースもありうる。たとえば、シンガー・ソングライター河島英五(1952-2001)の急逝をめぐる語りをみよう(「主人の『青春』また一つ消え」『朝日新聞』2001年4月25日。投稿者は33歳女性)。
河島英五さんの突然の訃報に悲しい思いをされている40、50代の方も多いと思います。主人もその1人で、河島さんがデビュー当時からのファンです。告別式の夜、しょうちゅう片手に遅くまで河島さんの歌を聞きながら「また一つ、僕の青春が消えてしまった」と言っていました。結婚して10年、私がこの言葉を聞くのは3回目です。1回目は、新婚時代から年2回は訪ねていた旅館がダム建設のため取り壊された時。2回目は、結婚前、デートの後に必ず2人で飲みに行っていた居酒屋が店じまいした時でした。
ただ、この投書には、「旅館も居酒屋も無くなりましたが、お世話になった方々は、今でも私たちを温かく迎えて下さいます。人生の先輩が新しい土地、環境の中で頑張っておられる姿を拝見して、『私たちもまだまだ青春できる』という気持ちになります」という、続きがある。この語りには希望を感じることもできる一方で、やはり人の死の不可逆性も感じさせられる。筆者は、今回のテーマを書くにあたって多くの記事に目を通し、ものの終わりよりも人の死をめぐって「青春の終わり」がより多く語られるように感じたが、それはこのあたりの事情に由来するのかもしれない。
しかし、誤解を恐れずにいうと、はっきりと終わってしまった方が気持ちの整理がつく分だけ、いいのではないかという思いもある。実は、私にとっても、高校時代・大学時代にそれぞれ傾倒していたミュージシャン(バンド)がいた。2022年現在、このバンドは2組とも現役なので、「私の青春は継続している!」と言えそうなものなのだが、結論からいうと全くそうは思っていない4。高校時代に好きだったバンドは、その後、思想的に相容れない方向に走っていったので、途中から私は全く興味を持てなくなった。世間的にずっと人気はあるので、むしろそのことがかえって私をアンチにしてしまっている5。大学時代にドはまりしたバンドは、私が大学卒業後の進路が定まらないまま留年決定した時期に活動休止し、その数年後に解散した。そのため、私の中ではかなり明確に「青春の終わり」を感じたものだったのだが、実はその10数年後に再結成し、現在にいたっている。だが、私は再結成後のそのバンドにはほとんど興味を持てない。それは、嫌いというのではなくて、私にとっては終わった(終わらせた)ものだからである6。単純に再結成を喜んでライブに誘ってくる同級生などもいたが、断るのになかなか苦労した。いま書いたような面倒くさいことを言っても、あまり共感してもらえないような気がしたからである。
と、最後に個人的な思いをぶちまけてしまったが、このあたりも、私が青春にこだわり続けていることの遠因かもしれない。別に青春の思い出を否定するわけではないが、思い出はあくまで思い出なのであり、いつまでもそれが継続してほしいという欲望は、私にはあまりよくわからないのだ(とはいえ、思い出にとらわれて「あの頃はよかった」と現状否定し続ける、いわゆる「懐古厨」も苦手)。青春とうまくつきあうのは本当に難しいものだなと、つくづく思う。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。
- 「藤原竜也『3日で高校中退』の噂を訂正『4日です』」(https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/01/07/kiji/20200107s00041000135000c.html)(2022年10月5日閲覧)。
- 国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査 結果の概要』(2022年9月9日公表)より。(https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/doukou16_gaiyo.asp)
- 内閣府『令和4年版 少子化社会対策白書』第1部第1章3より。(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2022/r04webhonpen/html/b1_s1-1-3.html)
- 2組とも非常に知名度が高く、具体名を出すと叩かれるかもしれないから、名前は伏せる。
- ただ、歌詞の内容が嫌いなだけで曲は素晴らしいものもあり、妙に悔しい気持ちになる。
- 一応、新しい曲が出れば聴いてはみる。だが、かつてのギラついた雰囲気が好きだった私としては、「枯れた大人のロック」のようになってしまった今の路線は、正直言って心に響かない。