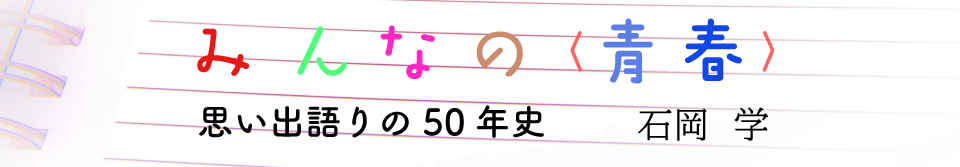過去50年間の青春をめぐるさまざまな「語り」をひもときながら、青春についてあれこれ考えてきたこの連載も、とうとう最終回を迎えることになった。ラストなので、この連載を通して少しずつ見えてきた現代の青春の姿について、改めてこれまでの内容を振り返ってみることにしようと思う。
もともと、青春について考えてみたいと思った動機は、私自身が青春というものに対して抱いてきたある種の違和感に端を発している。連載初回に打ち出した、私にとっての「青春をめぐる謎」を、ここでもう一度書き出してみよう。
・青春のイメージはコンテンツとして消費され、様々なメディアを通じて価値づけられ意味づけられている。
・それを参照点にして、それぞれが自身の青春を評価している。そしてその評価が、現実の人生に少なからず影響を与えている。
私が考えてみたかったのは、このような、青春をめぐるイメージと現実の往還のありようについてであった。自分自身も含め、多くの人々が、そうした往還の渦中にあって、さまざまに葛藤を抱えながら生きてきたのは間違いない。だから、この謎について考えることには社会的な意味があるのだ、ということも初回で書いた。いま振り返ってみて、この当初の問題設定はやはり的を外していなかったと思う。イメージと現実とが相互にフィードバックし合う中で、青春はある面ではかなり変容してきたが、一方では変わらない面もある。この二つの側面に照準を絞り込んで、このことについてもう少し具体的に振り返っていくことにしたい。
変わる青春
まずは、青春の変容の方に目を向けてみよう。
高度経済成長期の末期、すなわち1970年前後を境として青春が「終焉」したと論じたのは、三浦雅士(2001)であった。同様に、古屋(2001)は、その時期以降、青春は「亡霊」になったと述べている。
二人の指摘は、たしかに部分的には正しい。部分的に、というのは、かれらがいう「青春」は狭義のものであって、長い学生時代を享受することができる男性エリートにのみ許されていた「青春」を意味しているからである。それは、特権的・概念的・思弁的であると同時に、明確に近代イデオロギーの色彩を帯び男性性と結びつけられたものであった。挫折や苦悩を乗り越え努力することへの(過剰な)意味付与は成長第一主義をベースとしたものであるし、それは男にのみ許され求められたことだったのである。だから、高校・大学が大衆化した高度経済成長期以降にあって、このような青春イメージ(この連載で使ってきた言葉では「かつての青春」)が主役の座から降ろされたことは、ある意味必然ではある。ただ、「かつての青春」はその後も青春イメージの底流にしぶとく残存し続けているから、「終焉」ではなく「亡霊」の方が的確だと思う。
いずれにせよ、その結果として1970年代以降、青春は若者を取り巻く社会状況の変化を如実に反映するようになった。具体的には、進学率の上昇、景気の変動、メディア環境の変化、ジェンダー規範のゆらぎ、等々である。
60年代半ばから始まるTVの青春ドラマには、すでにその萌芽があった。学校の部活動(ただし文化系ではダメ)を舞台として繰り広げられる汗と涙、そして挫折と希望と情熱の物語は、「かつての青春」の要素をいくぶんかは継承しつつも、そこから暗さや悲劇性・逸脱性を脱色してできあがったものである。時期的には学生運動の最盛期と重なっているが、それ自体が大衆化していく大学への反発という側面をもっていたように1、この時期の高校・大学進学率の急上昇は、あっという間に学生をエリートから普通の若者へと「格下げ」した2。それにともなって、青春もより日常的・具体的な要素と結びついていくようになる。
高度経済成長は終わったとはいえ、70年代半ばからバブル期にかけても、日本社会は比較的安定的な経済成長を続けていく。若者は、それ以前に比べればはるかに経済的な豊かさ(とヒマな時間)を獲得できるようになった。そこで浮上してきたのは、消費社会における有力な「お客さん」としての若者である。特にポピュラー音楽市場は、同世代のファンをターゲットとしたシンガーソングライターやアイドルというジャンルの確立、さらにはポータブルオーディオやミニコンポの普及などによって、若者を主要な顧客として設定するようになった。そこで描かれたのは若者の率直な思いや感じ方、そして恋愛模様であり、それが青春をめぐる表象のメインストリームになっていく。もちろん、映画やTVドラマといったコンテンツにおいても、事情は似たようなものである。
こうした傾向は、80年代における「かつての青春」批判(というよりも茶化し)を経て、90年代以降になるとはっきりと青春のありようを変化させることになった。メディア表象においては、日常的なリアリティのある「ありのままの青春」を描くことが定番化していく。それはフィクションであるにもかかわらず、そのリアリティゆえに、誰しもがそのような青春を送れるという錯覚、送りたいという願望、そして送らなければならないという強制力をももたらす。「かつての青春」とは違う意味で、青春は新たな規範性をもつようになったのである。
さらに2000年代になると、青春は「純粋な心で何かに熱中している状態」という意味合いを強くもつようになっていった。「NEO青春もの」と呼ばれた一連の映画・ドラマ作品(『ウォーターボーイズ』、『スウィングガールズ』など)をはじめ、青春はそれ自体で至上の価値をもつ自己充足的なものとして描かれるようになり(宇野2008)、大人への成熟に向けた過渡期としての側面は後景化した。むしろ、大人になることで失われてしまう「大切な何か」を象徴するものとして青春は意味づけられ、その観念の性質としては子どもらしさの方に接近している。この連載で十分に論証できたとは言えないが、このような青春イメージの変化は、若者のコンサマトリー化と呼ばれた現象と決して無関係ではないと思う。近代化の一定の完了と経済的停滞によって、「将来のために現在を犠牲にする」という感覚を持ちにくくなったからこそ、この時期に青春はそれ自体が自己目的化していったのではないかと考えられるのである。第4回で詳しく述べたように、2000年代以降、現役の中学生や高校生が、文化祭や体育祭などでの自身の体験を「青春してる」と自己言及する言説がみられるようになったことも、明らかにこのような事態と連動している。
この傾向は、2010年代以降も基本的には継続している。この時期の若者を取り巻く変化といえば、何といってもスマホの普及だろう。画像や動画で記録を残し他者に発信することが、これほど容易になった時代はない。自己目的化した青春と、このようなメディア環境が相まったところに現れたのは、「いかにして青春のミッションをクリアしていくか」という課題であった。「青春のミッション」といっても、挫折や苦悩を乗り越えて成長するといった内面的な問題ではなくて、「青春っぽい」こと(つまり青春イメージ)をどれだけ経験するかということである。もっと正確にいえば、そういうシーンを記録し、発信し、共有し、「充実した青春を過ごした」と他者に認定してもらうことが、現実の青春達成度を左右するのだ。そして、そのように達成されていく現実の青春が、SNSなどを通じて再び青春の表象として流通していく。そういう意味では、現代ほど青春イメージが氾濫している時代はなかったのであり、青春をめぐるイメージと現実の往還も、かつてないほどに激しくなっているのかもしれない。
ただ、恋愛と青春をめぐる関係については、やや錯綜した状況もみられる。この時期、「キラキラ青春映画」と称されるような極めて個人化・局所化された恋愛関係を描く作品群が量産される一方で、青春小説の中には、恋愛という要素をあえて排除するような作品も少なからず発表されるようになったからである。映画と小説という媒体の違いもあるだろうが、男女関係の中に必然的に持ち込まれてしまうジェンダーの非対称性が青春を描く際に足かせになってしまうことを、一部の作家たちは敏感に察知しているのだと思う(もともと「男らしさ」と結びついていた青春のジェンダー性!)。少子化対策だ、婚活促進だ、などと騒ぎたてる勢力がある一方で、そういうものと結びつけられる恋愛に興味を持たなくなっている若者が無視できないボリュームで存在しているのが日本社会の現状である。上記の錯綜した状況は、そのような事態を反映しているように思えてならない。
このように、青春は若者を取り巻く社会状況の変容にともなって、少しずつその相貌と意味づけを変えてきたのである。
変わらない青春
その一方で、青春にはずっと変わらない側面がある。それは、一言でいってしまえば、青春が魔力と言っていいほどの魅力を持っているということだ。「青春なんか全く気にしたこともない、どうでもいい」と超然としていられる人は、たぶんほとんどいない。好きか嫌いかにかかわらず、青春というものに対して、みな何かしらひとかどの思いを持っているものだと思う。それだけ、青春には人を惹きつける不思議な力がある。だからこそ、青春は「売れるコンテンツ」として大量生産大量消費され続けているのだ。
この青春の魅力(魔力)とは、前節でみたような具体的なイメージよりも、もっとメタ的な何かである。しかし、単なるノスタルジアでもない。とにかく「充実した青春を送った」という実感を持てるかどうかが必要なのであり、それが得られないことは大いなる喪失感をもたらす。
だから、青春へのとらわれは、そのような実感を得られなかった者において、より顕著にあらわれてくる(私もそうだ)。第5回から第7回にかけて「青春ダークサイド特集」と称して取り上げたのは、このような問題であった。青春の魅力(魔力)は、ダークサイドから逆照射することで、よりクリアにその本質が浮かび上がってくると思ったからである。実際、私自身はこのテーマについて考え書いているときが、やはり一番面白かった(一番難しくて苦しんだところでもあるけれど)。
「かつての青春」においては、青春が持つ力の源泉は、やはりその特権性にあったと考えられる。選ばれし者だけに享受が許されたということは、すでにそれ自体が魅力的である。また、「かつての青春」は希望と不安、楽観と悲観、成功と挫折といったように、正負両面の要素をその規範として含み持っていた。そうした青春時代を乗り越え、成熟した大人になることが最終目標だった時代においては、どのような経験であれ「充実した青春時代」として評価することも可能であったのだ。あるいは、そうした青春を享受できない者たちにとっては、その原因を社会に求めやすかったために(貧困、地域格差、ジェンダー規範など)、自身の人間性の問題としてはあまり悩みを抱かずに済んだ3。
青春が大衆化したということは、青春の機会均等が実現したことを意味する。それによって、充実した青春を送れるかどうかは、個人要因に帰せられるようになった。70年代以降においては、そういった意味で理想通りの青春を送ることの難しさが立ち上がってきたのである。それは、青春イメージがリアリティを重視し自己充足的になっていく90年代以降、特に顕著になっていったと思われる。
「メディアに描かれる青春なんて、しょせんは虚構だ」と突き放せるのであれば、別にそれほど大きな問題はない。だが、そうでないから青春はやっかいなのだ。中高生、あるいは大学生になる前から、現代人は大量の青春イメージを浴びせられながら生まれ育ってきている。青春への夢や希望をあらかじめ掻き立てられているからこそ、いざその時期を迎えたときに現実と引き比べて「こんなハズジャナカッター!」となることが往々にしてあるのだ。
そして面白いのは、そうした青春の喪失感・挫折感が、さらなる青春コンテンツを生み出す原動力になっていくという点である(第5・7回参照)。しかもそれは、輝ける青春イメージの虚構性を批判し「地味で輝いていない青春」を表現したい欲求にも、欠損を埋めるために輝ける青春イメージをさらに旺盛に生産・消費する方向にもつながっていく。こうして、青春イメージは現実の青春とフィードバックし合いながら、その誘引力を維持(あるいは強化)し続けているのである。第10回でみた「第二、第三の青春」「生涯青春」といった類の語りも、このことと無関係ではない。青春を取り戻したい、やり直したいという思いは、青春に対する喪失感・挫折感があればこそ出てくる欲求だからである。
結局、若々しくあること、何かに夢中になれること、努力し成長し続けることに価値が置かれ続けている点が、青春の不変の特徴だと言えそうだ。そういう意味では、青春は単なるイメージではなく、常に規範性を伴っている。イメージの具体的な内実は変容しても、青春が相変わらず人々を惹きつけ続けているのは、実はこの規範の強制力ゆえではないか、とも思われるのである。
おわりに
青春について考え尽くしたとはとても言えないが、このあたりでひとまず区切りをつけることにしよう。もともと最初から語り尽くせるわけはないと思っていたし、そんなに簡単なテーマなら別に研究しなくたっていいのだ。いま改めて初回を読み返してみると、「膨大過ぎてほとんど手がつけられていないテーマに、まずはとっかかりを得ようとしてみることに意義があると私は考えている」と書いていた。この時、どのくらい達成できれば「とっかかり」になると考えていたのかはもうはっきり思い出せないが、正直な感想としては、想像以上に見通しの立つ素描はできたような気がしている。少なくとも、自分にとってはそうである。
それにしても、連載初期の文章を読み返してみると、思った以上に肩ひじ張ってるなという印象で、ちょっとびっくりもしている。1年間連載を続けてみて、私にも変化や成長の余地があるのだなという感慨すら抱いてしまった。まだ私も青春の中にいるのかもしれない(笑)4 。
しかし、そのしゃちこばった感じは、やはり長期にわたる連載という初の体験に対する不安感のあらわれだったのだろうと思う。普段、論文や本を書くときは、割と事前に構想を固めてはっきりとした見通しを立ててから始めるスタイルなので、12回の連載を完走できる確信がないままにスタートするのはなかなか勇気のいることだった。しかし、こういう機会でもないと青春というテーマに挑んでみようという勇気もまた持てなかったと思うので、とてもありがたいチャンスをいただけてよかったなというのが、率直な今の気持ちである。せっかくだから、青春の探究をこれからもしばらく続けてみようと思っている。
それでは、ここでとりあえず筆を擱くことにいたします。これまでお読みいただいたみなさん、どうもありがとうございました。
*本連載を加筆訂正の上、書下ろしを加え書籍化する予定です。
【参考文献】
宇野常寛、2008、『ゼロ年代の想像力』、早川書房
小林哲夫、2012、『高校紛争1969-1970 』、中央公論新社
古屋健三、2001、『青春という亡霊』、日本放送出版協会
三浦雅士、2001、『青春の終焉』、講談社
- 大学紛争に比べて相対的に知られていないが、同時期に高校でも少なからず「闘争」が勃発していた。高校生という立場にも、まだエリート性が残存していたことがうかがえる。詳細は小林(2012)を参照。
- 専門的には「学歴インフレ」と呼ばれる現象で、近代化した社会では学歴社会化の進行とともに普遍的に起きる。ただ、日本のような後発近代国家ではそれが急速に起きることが特徴である。
- もちろん、その方が楽で良かったというのではなく、悩みの質が違っていたことを指摘したいのである。
- 青春語りのルールとして、ここは「(笑)」が絶対に必要である。詳しくは第10回連載参照。