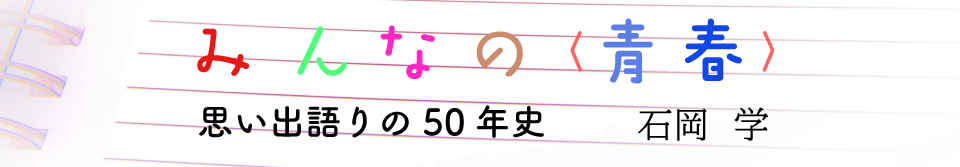イントロダクション
この連載では、高度経済成長期以降の日本社会において、「青春」がどのように語られ、どのようなイメージをまとってきたかを、歴史社会学的に読み解いていこうと思う。
こんなテーマを掲げると、「そんなに青春が好きなんですか?」と聞かれそうだが、実際は逆で、当事者だったと言ってもいい学生の頃から、あまり「青春」というものがピンと来なかった。そのときの自分を「青春まっただ中」と思うのも妙な気がしたし、あとから振り返って「あの頃はよかった」と思うこともかなり少ない。むしろ、忘れたいのにフラッシュバックしてくる苦々しい思い出の方が確実に多い(ここで具体的なエピソードを書いてくださいと言われたのだが、黒歴史なので書けない)。にもかかわらず、いやだからこそ、完全に中年の域に達してしまった現在にいたるまで、ずっと「青春」には何か引っかかりを感じながら生きてきた。なぜ「青春」はかくも美化して語られ、過剰に意味づけられるのだろうか。自分にとっては何が「青春」だったのか、それはいつ終わったのか(あるいは終わっていないのか)。そもそも「青春」とは何のことなのか……。
しかし、何分にも「青春」はテーマとして大き過ぎて、真正面から立ち向かっていくとなると、なかなか歯が立ちそうもない(試みに国会図書館(NDL online)で「青春」を検索してみると、39,856件もの資料が出てくる)。そういうわけで、青春への関心は持ちつつ、それと関連しながらもう少し手をつけやすいテーマを選んで研究してきた。具体的には、子どもや若者に対して社会が投影してきたイメージの歴史的変遷である(石岡2004、石岡2017など)。教育学の周辺領域で過ごしてきたので、こうしたテーマは学術研究の中に比較的位置づけやすい。ただ、いずれは何らかの形で「青春」そのものを中心テーマにすえた研究をやってみたいという、半分は知的な、半分は興味本位な欲求はくすぶり続け、「いつかは必ず……」と思いながら年月が経過していた。
そこへ、まさに渡りに船とばかり今回の連載をご依頼いただいた。担当の篠田里香さんは、アイドルホース(競走馬)をめぐる語りとその意味について論じた拙著『「地方」と「努力」の現代史』(青土社、2020年)を大変に高評価してくだり、過去をめぐる語りを読み解く面白さという点にとても興味を持たれた。その話の流れで、「たとえば青春などテーマにしてみたらどうでしょう」とのご提案が出されたのである。まだ直接会ってお話したこともない段階で、何かこちらの問題関心を的確に掴まれた気がしてしまい、この船に乗らないわけにはいかないだろうと、割と早く依頼を引き受ける決心がついたのだった。
とはいえ、やはり青春が非常に大きなテーマであることには変わりない。どうやってこれを読み解いていけばいいだろうか。うまく視点を定めないと、「いろいろな青春がありますね」で終わってしまう(質的研究の陥りがちな罠)。そこで、連載初回では、これから何をターゲットとして、どういう視点から青春を読み解いていくか、これを確定させていくこととしたい。具体的には、私が青春についてずっと気になっている点を整理し注目ポイントを絞り込んだ後、青春がこれまでどのように研究されてきたかを検討し、それらを通じて今後のねらいを定めていこうと思う。そんな面倒なことはせずに「とにかくこれに興味があるから!」と言って進めてもいいのだが、どうしても本業が学術研究者なので、こういう手続きを踏んでいかないと気が済まない(いや本音を言えば、同業者からのツッコミ防止対策である)。とはいえ、どんな研究でもそうだが、出発点はやはり「私」なのである。まずは、私にとっての青春をめぐる「謎」を整理するところから始めていきたい。
青春の独特さ・奇妙さ
さきほど、青春は非常に大きなテーマだと書いた。だが、大きいというよりもむしろ、あまりに多面的で掴みどころがないという方が正確かもしれない。
試みに、読者のみなさん自身にとって「青春とは何だったか」を問うてみてほしい。まず、「楽しかった/辛かった」「戻りたい/戻りたくない」といった感じに、大きく分かれるだろう。「それは具体的に何歳ころのことか」と尋ねれば、中学生ころだと答える人もあれば、30〜40代ころと答える高齢者もいるだろう。住んでいた地域や時代、あるいは性別によっても、青春の経験とその意味は千差万別である。
だが一方で、青春時代は特別な時代であり、青春には何か大きな意味がある(と考えられている)ということについては、否定する人はほぼ皆無ではないだろうか。楽しかったと懐古できる人にとってはもちろん、青春に何らかの挫折を経験した人がしばしばそれを引きずりがちになるのも(「青春を取り戻す」!)、それが特別な意味を持つ何かであればこそだと思われる。
これが、私が青春というテーマに惹かれる、というよりむしろ引っかかりを覚える理由の第一である。つまり、青春には必要以上に過剰な意味・価値が付与されているのではないか、ということだ。何か「理想の青春」のようなものがあって、自分自身の青春時代をそれとの比較でとらえようとする向きは、非常に強い。それは、中高生くらいであれば自らを「理想の青春」に近づけようとする努力として現出する(例えば、恋愛だったり部活に打ち込むことだったり)。もっと年長の世代であれば、「理想の青春」ではなかった自身の青春時代への悔恨としてもあらわれうるし、何か新しいことにチャレンジしてそれを「第二の青春」「生涯青春」などと言ってみたりもする。青春は、単なる年齢の若さを意味しているのではなく、いわば人生のピークとして位置づけられているのである。いったいなぜ、かくも多くの人が青春にとらわれ続けてしまうのだろうか。言い換えれば、多くの人の心の中でなぜ青春は無視できないほどの存在感を持って生きのびてしまうのか。これが、私にとっての青春をめぐる第一の謎である。
その理由の一端は、青春がコンテンツとして消費される格好のネタとして存在していることに関わっていると思うが、それこそが私が青春に興味を抱く第二の理由である。青春映画、青春ドラマ、青春小説、青春ソング、といったように、青春はフィクションの題材として確固たるジャンルを形成している。つまり、青春はそれだけ「売れる」コンテンツだということである(中年ソングなど、多分ネタにしかならない)。青春を売り物にしたコンテンツとしては、ほかに、アイドルや学生スポーツを挙げることができる。青春映画・ドラマにはしばしばアイドル(あるいはアイドル的な若い俳優)がキャスティングされるし、アイドルソングには青春をテーマにしたものも多い。アイドルの「適齢期」がおおむね10~20代前半とされていることも、アイドルと青春の親和性を裏づける。また、学生スポーツも青春を消費するコンテンツと見ることができる。高校野球や箱根駅伝などが長年にわたって人気を博していることは、それらがメディアイベントとして「売れる」ものであることを端的に示しているし、それらの人気が単にアスリートとしての技量の高さによるものだけではないこと、すなわち青春と結びつけて捉えられているからこそであるのは、明らかであろう。
このように、フィクションのみならず、現実における青春の生きざまを通じても、「理想の青春」イメージは表象され、コンテンツとして消費されている。この「理想の青春」イメージは、翻って現実の青春を規定する力を発揮し、「もっと青春したい!」「これって青春ぽくない?」といったように、しばしば自己言及的な語りを産出することとなる。これが、私にとっての青春をめぐる第三の謎である。
私自身、学生の時分に同世代がこのような発言をするのを耳にするたびに、何とも言えない気分になったのを記憶している。何か、与えられたイメージをそのまま躊躇なく演じることは非常に主体性のないことのように思われ、そこはかとない違和感があったのだ。それに、通っていた中学・高校は色々とルールや縛りがきつくて私は精神的に委縮していたし、男子校で球技が苦手というのは致命的に人間を歪める。そういうわけで、学生時代はあまり楽しくなく、世の中に蔓延する「青春時代は素晴らしい」というイメージに全く共感できなかった。むしろ、森田公一とトップギャラン『青春時代』の「青春時代の真ん中は道に迷っているばかり」「胸にとげさすことばかり」という歌詞にシンパシーを感じながら、「青春時代はしんどいと思っている自分の方が正しい!」などと憤っていた。今はそこまでの反発感はないが、自己言及される青春への違和感そのものは、未だに解消されないまま残っている。青春への自己言及にはどういう意味があるのか、そのような現象はいつから見られるのか、これは是非とも探ってみたい疑問の一つである。
というわけで、ここまで整理してきた私自身の青春に対する引っかかりを改めてまとめると、次のようになる。
・青春のイメージはコンテンツとして消費され、様々なメディアを通じて価値づけられ意味づけられている。
・それを参照点にして、それぞれが自身の青春を評価している。そしてその評価が、現実の人生に少なからず影響を与えている。
青春をめぐるイメージと現実の往還。一言でいえば、私が明らかにしてみたい「青春をめぐる謎」はこれである。いま述べてきたように、私自身がその枠組みから自由でなかったわけだが、これは何も私個人に特異なことではないはずだ。そうでなければ、これほど多くの青春にまつわるコンテンツが生み出され、消費されるわけがない。だから、この謎は社会的な現象として解明に挑んでみる価値が十分にあるものだと思う。
近代のイデオロギーとしての青春?
では、このような「青春をめぐる謎」に迫るためにはどの時期の、どんなデータにアプローチすればいいだろうか。照準をもう少し絞り込んでいくために、ここでは関連する先行研究について概観していきたい。
青春を主題とした研究がこれまで最も盛んに行われてきたのは、おそらく文学研究の領域である。特に高度成長期ころまでは、文学作品そのものが青春を好んでテーマとして取り上げることも多かったし、それらをめぐる青春論も盛んであった。詳細は次回に譲りたいが、それらは多分に西洋由来のビルドゥングス・ロマン(教養小説)の影響を受けており、実際に生きられた青春がどうであったかという以上に、「あるべき青春のあり方」をめぐる模索の軌跡であったといえる。だが、そうした意味での青春は、日本では高度成長期の終焉と前後して急速に衰退したとされる1。三浦雅士(2001)と古屋健三(2001)の研究は、いずれもそうした認識に基づき、近代という時代を背負った青春、あるいは青年のイメージはそれ以後規範的な影響力を持たなくなったと指摘している。1990年代以降の歴史研究において、「青春」や「青年」を近代社会に特有の概念だとして相対化するものがあらわれてくるが、これらもこうした文学研究の知見に接続するものだといえよう(北村1998、木村1998、平石2012、田嶋2016、和崎2017など)。さらに近年では、メディア史研究者によっても、戦後日本における青年イメージの変遷と衰退のありようが明らかにされてきている(佐藤2017、福間2017、福間2020、など)。
しかし、2021年の現在でも、青春という言葉を聞いたことがないという人はまずいないだろう。ということは、青春は消滅したわけではなく、その意味を変容させつつ現代まで生きのびているということである。では、高度成長期以後、同時代の青春はどう研究されてきたのかといえば、実はあまり真正面から主題として扱われてきたとはいえない。もちろん、社会学の文脈において青年・若者には少なからず関心が向けられてきたが、それらは主に①逸脱行動・現象に関する研究、②青年・若者(文化)研究、③青年・若者論研究、といった形で主題化されてきた。①は高度成長期以前から存在するが、いわゆる「青少年問題」という形で青年・若者の間に見られる問題行動(非行・犯罪など)を取り上げ、その解決を志向するタイプの研究である。②は、1980年代以降に増えてきたもので、若者の意識・価値観の変容やその原因となる社会的要因について、分析・解釈するものだ。特に、成人世代のものとは相対的に自立するようになった若者世代のカルチャー、すなわち若者文化に焦点を当てたものも多い(宮台・石原・大塚1993、浅野編2006、難波2007、古市2011、片瀬2015など)2。③は、②から派生して特に2000年代以降に浮上してきたテーマで、若者の「語られ方」に着目することで若者論・世代論自体の相対化を志向するものである(羽渕編2008、浅野2013→2015、後藤2013、川崎・浅野編著2016、木村・轡田・牧野編著2021など)。いわば、若者について語りたがる社会の側に注目し考察したものがこれにあたる。これらのうち、特に②③の研究は私の問題関心と関連するが、前節で述べた私にとっての「謎」に直接的に答えてくれるような研究は、管見の限り見当たらない。
紙幅の都合で今回はこれ以上の詳細な検討を避けるが、これまでの青春をめぐる研究状況は、ひとまず次のように整理することができる。すなわち、「青年」や「青春」は普遍的概念ではなく、近代的イデオロギーを帯びた歴史的構築物であることがわかってきた。日本社会においては、高度成長期の終わり=近代化の一定の完了とともに、青春という概念が持っていたそのような圧倒的な影響力は消滅したとされる。一方で、青春はその意味を変質させながら、現代にいたるまで規範として強い影響力を持ち続けている。だが、高度成長期以後の日本社会における青春のありようは、意外なほどよくわかっていない。青年・若者に関する社会学的研究の知見は重要な参考にはなるものの、これらの領域で青春そのものが真正面からは取り扱われることはほとんどなかった。
こうしてみると灯台下暗しで、ここ50年間ほどの青春についての研究が抜け落ちてしまっていることがわかる。どうやら照準すべき時代が定まってきたようだ。
生きのびる青春
現代において「青春」と聞けば、まず学生時代を連想する人が多いだろう。しかし、10〜20代の時期を多くの人が学生として過ごすようになったのは、実は割と最近のことだ。1950年代、義務教育後に高校へ進学した者はまだ同世代の半分程度であったし、大学進学者にいたっては1割程度であった(戦前はもちろんもっと少ないし、そもそも小学校より上の学校で「男女共学」は存在しなかった)。それが、高度成長期の十数年間で進学率が急上昇し、1970年代前半には高校進学率は9割を超え、大学進学率も3割を超えるほどにまでなった。文学研究においてはこのあたりが「青春の終焉」を迎えた時期ということになるが、私にとってはまさにこの時期以降こそが重要である。というのも、多くの人が青春時代を学生として過ごすようになったからこそ、先に挙げた青春をめぐる謎も生じてくるからである。さまざまなコンテンツに描かれた青春に自分を照らし合わせようとする欲望が生じるためは、その青春があまりに自分と縁遠いものであってはならない。自分もそのような青春を送ることができるという可能性がなければ、そもそも引き比べることはできないのだ。いわばモラトリアムとしての青春時代を多くの人が享受できるようになった時代だからこそ、先の青春をめぐる謎も生じてくる。そう考えるならば、照準すべき時期は概ね1970年代後半以降ということになる。
これは、ちょうど前節で述べた研究の空白を埋めるという意味でも、妥当な時代設定だろう。加えて、1970年代以降は、それ以前にまして青春がコンテンツとして盛んに消費されるようになった時代である。従来の映画や小説といったメディアに加え、テレビドラマ、コミック、流行歌など、よりさまざまな種類のメディアが社会に普及し、特に若い世代をターゲットにしたコンテンツにおいて盛んに青春が題材として取り上げられるようになったからである。さらに21世紀以降は、それにインターネットメディアが加わってくることは言うまでもない。
となると、1970年代以降のメディアコンテンツに描かれた青春のありようを今回のターゲットにするのが自然なように思われる。しかし、これらを直接の研究対象とするアプローチは、やや私の問題関心からずれる。もちろん、そういった研究は興味をそそられるし、十分に意義もあると思う。ただ、私自身、文学や映画のような文化そのものを研究の専門領域としてきたわけではないので、下手をすると素人めいた評論になってしまうおそれがある。それに、単にフィクションにおける青春の描かれ方を検討しただけでは、青春をめぐるもう一つの謎――青春を参照点とした自己評価とその影響――が解明されないままに終わってしまう。メディアに表象される青春を受容するにせよ反発するにせよ、人々がそれをどう感じ取り解釈したのか、それはその人の人生にどう影響したのかしなかったのか。それを是非とも明らかにしたいのである。そのためには、人々の青春をめぐる「語り」に着目する必要がある。
そこで、この連載では、概ね1970年代後半以降の時期における青春をめぐる「語り」を考察の対象としたい。その中でも、雑誌(主に週刊誌・総合誌・女性誌)記事と新聞記事を中心的資料として取り上げていこうと思う。著書、特に自伝などで青春が語られる場合も少なくないだろうが、これらは「読みたい」と思う人がわざわざ手に取らないと読まれないものである。それに、少数の人の考えを掘り下げていく方法は、あまり今回のテーマにはふさわしくない。むしろ、より多くの人が何気なく目にするより日常的な記事を大量に集めてみていく方が、かえって青春をめぐる「語り」の定型とその意味が浮かび上がってくるのではないか、と思うのである。
最後に、ここは完全な手続き的記述となってしまうが、具体的な資料の選定方法について説明をしておきたい。
まず、雑誌記事の検索にあたっては、「大宅壮一文庫雑誌記事索引検索web版」を用いた。記事分類を「インタビュー」「対談」「座談」にそれぞれ限定し「青春」で検索した結果(2021年7月9日時点でそれぞれ3121件、515件、214件)に加え、「青春」とそれに関連すると思われる単語3とを「and検索」し一定以上の件数(目安として100件以上)の結果が出た記事を抽出する。これらのうち、筆者が記事タイトルなどに基づきピックアップしたものを具体的な検討対象としたい4。新聞記事については、朝日新聞のデータベース『聞蔵Ⅱビジュアル』、読売新聞のデータベース『ヨミダス』を用い、青春をテーマとした投書記事を中心に取り出して検討したい5。これらの資料を併用することで、雑誌記事における「有名人」の語りと新聞記事における「一般人」の語りをともにカバーすることができる。
ただし注意しておきたいのは、これらのデータベースで検索できる範囲が、1980年代後半以降に限定される点である6。いずれも1980年代前半以前の時期について検索は可能であるが、検索のシステムが異なるため、かえってややこしい事態を招いてしまうおそれがある。ただ、青春については何年、何十年たってから振り返って語られることも少なくないため、1980年代前半以前の青春についても、今回検討対象とする資料によってある程度は把握できるものと考えている。
以上のように、今回の資料の選定は、厳密に客観的な基準によったものとは言い難い。しかし、別にこの研究だけで青春をめぐる語りのすべてを明らかにしようなどとは毛頭思っていないし、膨大過ぎてほとんど手がつけられていないテーマに、まずはとっかかりを得ようとしてみることに意義があると私は考えている。今回の連載では、学術的な精緻さにこだわるよりも、ここ50年間の日本社会において青春はどう語られ経験されてきたのか、その大枠の把握を目指したい。いわば、「高度成長期以後の日本社会における青春とは何だったのか」という大樹海のような問いに対して、まずは俯瞰図を描いてみたいと思うわけである。
では、手続き的な話はこのくらいにして本題に移っていこう! と思うのだが、残念ながらもう既定の字数をオーバーしてしまった。次回は改めて、「青春は普遍的な概念ではない」という問題について考えていくことから始めていきたいと思う。
【参考文献】
浅野智彦、2013、『「若者」とは誰か』、河出書房新社 →2015、増補新版
浅野智彦編、2006、『検証・若者の変貌』、勁草書房
福間良明、2017、『「働く青年」と教養の戦後史』、筑摩書房
――――、2020、『「勤労青年」の教養文化史』、岩波書店
古市憲寿、2011、『絶望の国の幸福な若者たち』、講談社
後藤和智、2013、『「あいつらは自分たちとは違う」という病』、日本図書センター
羽渕一代編、2008、『どこか「問題化」される若者たち』、恒星社厚生閣
平石典子、2012、『煩悶青年と女学生の文学誌』、新曜社
古屋健三、2001、『青春という亡霊』、日本放送出版協会
石岡学、2004、「「理想の子ども」としての健康優良児」『教育社会学研究』75、pp65-84
―――、2017、「高度成長期のテレビドキュメンタリーにおける「青少年問題」の表象」『教育社会学研究』101、pp.69-89
岩見和彦、1993、『青春の変貌』、関西大学出版部
岩見和彦編著、2015、『続・青春の変貌』、関西大学出版部
片瀬一男、2015、『若者の戦後史』、ミネルヴァ書房
川崎賢一・浅野智彦編著、2016、『〈若者〉の溶解』、勁草書房
木村絵里子、2021、「「若者論」の系譜」木村絵里子・轡田竜蔵・牧野智和編著『場所から問う若者文化』、晃洋書房、pp.1-23
木村直恵、1998、『〈青年〉の誕生』、新曜社
北村三子、1998、『青年と近代』、世織書房
小谷敏編、1993、『若者論を読む』、世界思想社
三浦雅士、2001、『青春の終焉』、講談社
宮台真司・石原英樹・大塚明子、1993、『サブカルチャー神話解体』、PARCO出版 →2007、増補版、筑摩書房
難波功士、2007、『族の系譜学』、青弓社
佐藤卓己、2017、『青年の主張』、河出書房新社
田嶋一、2016、『〈少年〉と〈青年〉の近代日本』、東京大学出版会
和崎光太郎、2017、『明治の〈青年〉』、ミネルヴァ書房
- 文学研究の文脈以外でも、こうした見方がある。例えば、教育社会学者の竹内洋は「戦後の新制中学と新制高校こそ青春を大衆化し、ティーン・エイジャーを創出した装置だった。(中略)この年(=「高校三年生」が大ヒットした1963年:引用者注)の高校進学率は六七%である。しかし、ここあたりを峠として青春と友情のそして文明化の装置としての学校の意味と輝きが喪失しはじめる」(竹内洋『学校と社会の現代史』左右社、2011年、p.4)と述べている。
- タイトルに「青春」を冠した社会学の研究書として岩見(1993)および岩見編著(2015)があるが、内容としてはこの②の系統に含まれる。
- 具体的な単語は、以下の通り(順不同)。懐(240件)、青春だった(178件)、あの頃orあのころ(133件+34件)、思い出or想い出(498件+22件)、悔(83件)、苦(234件)、挫折(63件)、悩(212件)、痛(112件)、恥(107件)、甘(134件)、夢(525件)、恋愛(474件)、輝(316件)、青春時代(863件)。カッコ内は2021年7月9日時点での検索結果件数。
- 基本的な方針として、「青春に対する何らかの認識が語られているもの」をピックアップしている。単にかつての文化・流行を振り返って紹介する趣の記事や、タイトルに「青春」が含まれていてもそれが中心的話題ではないと思われる記事などは、検討の対象外としている。
- 朝日新聞については、検索面を「オピニオン・声」+「生活」+「be」に限定し、「青春」で見出しのみ検索した(2021年9月17日時点で426件)。読売新聞については見出しのみ検索ができないため、「青春 気流」で検索した(2021年9月17日時点で1542件)。読売新聞の件数がかなり多いが、2000年4月から2007年12月まで若年層に投稿者を限定した「青春気流」というコーナーがあったため、このような結果になったと考えられる(「青春気流」での検索結果は985件)。
- 大宅壮一文庫web版は1988年以降、『聞蔵Ⅱ』は1985年以降、『ヨミダス』は1986年以降が対象範囲