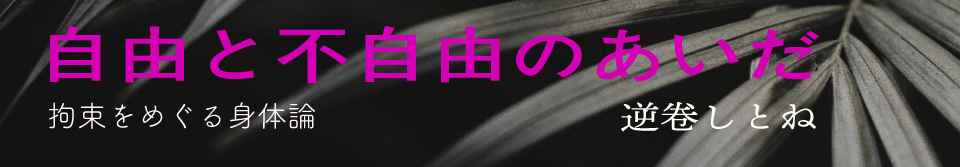第7回は公開終了いたしました。
逆卷しとね(さかまき・しとね)
1978年生。学術運動家/野良研究者。専門はダナ・ハラウェイと共生・コレクティヴ論。連載にWebあかし「ウゾウムゾウのためのインフラ論」、HAGAZINE「ガイアの子どもたち」。論稿に「喰らって喰らわれて消化不良のままの『わたしたち』――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい vol.1』 亜紀書房 2019年)など。共著に『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』(荒木優太編 明石書店)、『コロナ禍をどう読むか 16の知性による8つの対話』(奥野克巳+近藤祉秋+辻陽介編 亜紀書房 2021年)がある。
・逆卷しとねツイッター
・逆卷しとねツイッター
- 第1回囚われを生きる(1)
- 第2回囚われを生きる(2)※公開終了
- 第3回個人認証と不審な《この生》※公開終了
- 第4回《この生》はすでに人外※公開終了
- 第5回わたしたちを食べる(1)※公開終了
- 第6回わたしたちを食べる(2)※公開終了
- 第7回わたしたちを食べる(3)※公開終了
- 第8回わたしたちは遊ぶ
- 第9回わたしたちは散歩する