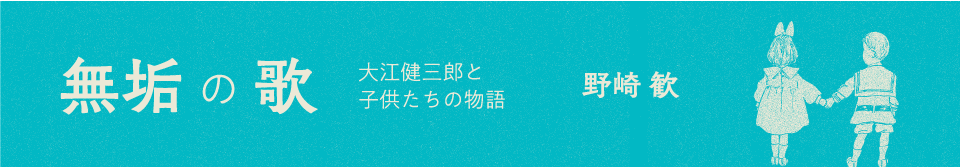人物再登場
一九八〇年代以降、大江作品にはかつての自作に対する言及が目立って増えていく。旧作を自ら批判したり書き換えようとしたりするような姿勢が顕著になる。それを批評家たちは「ポストモダン的」とか小説の「脱構築」とか呼んだ。しかしその実態はいささかわかりにくいし、流行りの言葉を当てはめたという印象も否めない。
長い小説の歴史においてとらえるなら、これはむしろバルザック的な小説の伝統から新たな可能性を引き出した例と考えることができる。バルザックは一つの作品に登場させた人物を別の作品にも登場させることで、一冊きりでは完結しない巨大な「人間喜劇」を構想した。大江においても、小説はもはや一冊単位で完結せず、作家の人生の歩みとともにさらなる展開を見せる。そして過去の自作への言及は、作中人物の再登場と緊密につながっている。旧作で強い印象を放った人物のその後が語られるという点で、大江はバルザック的手法を現代によみがえらせたと言える。
それは読者にとって、思いがけない再会の機会となる。『新しい人よ眼ざめよ』巻末に収められた表題作での「キーコ」の登場などは、その最たる例である。
「テレビ・チーム」ともどもヨーロッパを訪れた「僕」が、ベルリンに滞在していたときのこと。深夜二時、「枕もとの電話が鳴った」。それは学生時代の友人で、イーヨーが生まれた直後に性的な関係をもった相手でもある「キーコ」からの電話だった。ハワイで「国際作家」に奇襲をかけてきたかつての同級生「高安カッチャン」と似たような不意打ちである。そして読者は「僕」の口から、そのキーコとの関係こそは「『個人的な体験』の、ブレイクを卒論にした同級生との性的なシーンに反映している」と明かされる。
あの忘れがたい「火見子」にはモデルがいたのか、あそこに書かれていたことは本当だったのか。驚きのうちに読者はそう考える。キーコもまた、『新しい人よ眼ざめよ』という小説の登場人物にほかならず、そこに事実そのものが綴られている保障などないことを忘れてしまうのだ。とはいえ、そんな読み方は作者自身によって誘導され、許諾されているとも言える。何しろ細部にわたって詳しく情報が与えられているからだ。「僕」が「二十歳」のころ、「H君」に紹介されて「二歳年下」の彼女の家庭教師に雇われたのがキーコと知り合ったきっかけだった。そのころキーコは「現在バルザック学者であるI君」が下宿していたのと同じ「本郷の大学近辺の戦前からの下宿屋」の一室に暮らしていた、等々。「H君」が病死した塙嘉彦、そして「I君」がバルザック作品の研究・翻訳で知られた石井晴一を示すことは明らかだ。それら仏文の同級生たちの名前まで仄めかされているのだから、読者がそこに告白を読みとりたくなるのも無理はない。
障害のある息子の誕生で「混乱した低迷状態のうちにあったさなか」に「いかにキーコの無私の献身に援護されたか」を「僕」は思い返す。それは「エゴサントリック」な、つまり「僕」にとって虫のいい話ではある。「自分の若かった時分の、甘ったれた酷たらしさになおよく直面しえてはいない」と「僕」は反省する。
しかしいま問題とすべきは「僕」の反省モードではなく、久方ぶりに再会したキーコが放った「僕」の息子に関する一言である。
「あなたの息子さん(……)、もうそろそろ成人だわね? “must”の場合、困るでしょう、対策は考えているの?」そう言われて「僕」は「血相を変え」るほどかっとし、「“must”というのか、きみは? 僕の息子が象か駱駝のように発情するが、撃つわけにもゆかないだろう、というのか?」と抗議する。
これだけではなぜ象や駱駝が出てくるのかわからないし、mustの意味も不明だ。続く部分に「『象を撃つ』からの引用だとはわかっているよ」とあるので、ともかくイギリスの作家ジョージ・オーウェルが、ビルマでの体験を描いたそのエッセイを参照してみよう。
ビルマで帝国警察の警察官となったオーウェルは、ある日、象が暴れて市場をめちゃくちゃにしているという連絡を受ける。ポニーに乗って出かけてみると、「人に飼われている象が『さかり』を迎えて狂暴になっているのだった」(「象を撃つ」『あなたと原爆 オーウェル評論集』所収、秋元孝文訳)。mustはここでは発情した象の狂暴な状態を示す名詞なのである。オーウェルは市場の群集の前で、白人警官としての体面を保つため、象を撃ち殺したのだった。
火見子改めキーコと「僕」は、お互いがオーウェルの原文を知悉していることを前提として高尚なやりとりを交わしている。だが、そこで問われていることはきわめて露骨だ。息子の性欲処理はどうするのかとキーコはずばり訊いてきたのである。
非=性的人間?
だがキーコに対して「僕」が憤慨するのは、いささかお門違いとも感じられる。なにしろ長旅から戻ったときのやりとりが示すとおり、「僕」自身、イーヨーにおける性の目覚めをひどく恐れているのだ。やはり家族を登場させた『静かな生活』(1990年)は、イーヨーの妹「マーちゃん」を語り手とする短篇連作だが、そこでも同じ問題が扱われている。「父」は「イーヨーの『暴発』を心配」して、スポーツをさせなければなどと言い出す。新聞報道で「精神障害者の性的な『暴発』」がしきりに取り沙汰されていることが背景にあった。父の反応はあまりに「素直」で「通俗的」だと「マーちゃん」は眉をひそめる。
しかし『新しい人よ眼ざめよ』に戻れば、「僕」の心配は昨今の報道よりはるかに古い記憶に根ざすものだった。「僕」には「少年時に深い動揺をあたえられた」新聞記事の思い出があった。「瀬戸内海の小さな島で、脳に障害のある少年が、少女を殺害した」という事件である。その衝撃的な内容が彼の脳裏に刻まれていて、イーヨーの行動にまで危惧を抱かせたのだった。
とはいえ、それはイーヨーにとっては迷惑な邪推ではないだろうか。そもそも、くだんの記事に記されていたという、悲惨にしてグロテスクな性犯罪に、激しく慄きながらも同時に呪縛され、自作で繰り返し同様の事件を取り上げてきたのは大江自身である。二十代のころ、すでに彼は宣言していた。「性的なるもの」は「できるだけ奇怪で異常で危険きわまりないものでなければならない」。それこそが「内部の深淵」を開くとともに「深く現実の核心にかかわ」る手掛かりとなるのだと(『厳粛な綱渡り』1965年)。『新しい人よ眼ざめよ』や『静かな生活』に至ってもなお、イーヨーやマーちゃんのすぐ身近なところで、痴漢、さらには強姦殺人といったとんでもない犯罪が勃発する。
そうした事件を大江は、刺激的なエロティシズムを喚起するふうにではなく、犯人自身にとってすら恐怖と苦痛のほか何ももたらさないような恥辱の体験として描いてきた。その一貫した態度には、いくつになっても純粋な青臭ささえうかがえる。いずれにせよそこにわだかまっているのは「性的人間」であることの厄介さである。それと妥協のない形で向かい合わなければならないという、作家としての律義な義務感も感じられる。
自らの内なるそうした厄介さを、「僕」はついイーヨーに投影してしまう。それは彼自身認めざるを得ないところだ。「獣じみた不発の衝動も、僕がヨーロッパの旅で自分のうちにこそやどしていたものではなかったか?」。「僕」だけではない。イーヨーのふとした行動に性的な要素を嗅ぎつけようとする者はほかにもいる。中学校のころ、遠足か何か、特別な行事のあとで普段より下校時間が遅くなったある夕方の一情景。
「(……)薄暗がりのしのびよる校庭で、子供らが別れを惜しみあっている。イーヨーは自分の身長の三分の二ほどの、体重は半分にもみたぬ、小児麻痺の後遺症のある女の子に向けて深ぶかと覗きこみ、ゆっくりした挨拶を繰りかえしている。
――さようなら、さようなら、それではお別れいたしましょう! どうか、お元気で、明日まで、ご機嫌よう!」
その様子を「僕」がほほえましく見守っていると、傍らから「厭だわ、厭だわ、もう沢山!」と「痙攣するような声音」が聞こえてきた。イーヨーのあまりに丁寧な挨拶ぶりに苛立った若い女教師の声だった。互いに好意を抱いているらしいイーヨーとその女の子とのあいだのやり取りに対して、女教師の反応は不当でヒステリックだと思える。挨拶くらい好きなだけ繰りかえさせてあげればいいではないか。女教師はじつは「彼女の内部の性的な暗闇に根ざしての反応」を示していたにすぎないと「僕」は推測する。おそらくそれは正しいのだろう。要するに、イーヨーをめぐってはとかくそうした状況が出現するのである。彼の存在は周囲の人間の性的なコンプレックスや思い込みを映し出さずにはいない。
逆に言えば、イーヨーとは澄み切った鏡である。「僕」は折にふれ息子と自分との一体感を強調してきた。しかしどうやらここに二人を分かつ大きな違いがある。二十歳のころを振り返って、「僕」は自分と火見子/キーコは「毎日ただ性交するためだけに会うという関係」だったと何とも即物的に記している。二十歳のイーヨーにそんな相手はいない。そして周囲がどう思おうとも、彼にとってはそれで別段不足はなく、「暴発」などしないのだ。父親が追求してきた「性的人間」のカテゴリーとは無関係の非=性的人間がいるとしたら、それはイーヨーなのかもしれない。
「イーヨーは性的な冗談をいったり悪ふざけをしたりすることはなく、裸のグラヴィアであふれた大判の月刊誌がおくられてくると、郵便物の整理を手伝う一方、紙袋のまま屑籠に棄てる、謹直なところを持っていて(……)」
そんな慎みぶかく純潔なイーヨーに知られたら、棄てられかねないどぎつい事柄を含む小説を父はたくさん書いてきたのだ。しかしそれだけに父の小説にとってイーヨーの存在がいかに貴重であるかもよくわかる。イーヨーは別に禁欲的なわけではないし、ものを感じる心を持たないわけでもない。何しろイーヨーとは、官能の喜びに満ちたモーツァルトの音楽をはしからはしまで知り尽くしている人物なのだ。たんに、彼は性を重荷として背負ってはいないし、性行為の必要に駆られてもいない。あくまで自然体のまま、セクシュアリティにとらわれずとも悠然と生きていけることを示している。やはりジョージ・オーウェルから大江が援用する形容詞を用いるならば、それはじつに“decent”(上品)な姿なのである。
非=生産的人間?
だが、イーヨーのそうした個性を上品だと尊重する人間ばかりではない。それどころか、イーヨーの存在を否定してかかる者たちがいくらでもいる。彼らによればイーヨーは、非=性的という以上に、端的に非=生産的な存在なのである。
たとえば「僕」のもとに「一読者」から送られてきた手紙にはこう記されていた。「これ以上世に害毒を流さぬよう、貴君の障害児とともに、自殺とはいわぬまでも沈黙なさってはいかがでしょう?」核武装して「ソヴィエト独裁ファシズム」と闘う「自由陣営の働き手」を、貴殿はなぜ批判するのか。「平常時においては娯楽も必要」だが「非常時には、作家は社会に寄生する無用物であり、障害児はさらにそう」ではないかというのが、手紙の書き手の主張なのだった。
あるいは、イーヨーが下校時に誘拐されたあの陰湿な事件。それは「僕」のもとを訪れて自分たちのセクトへの協力を頼みこんできた学生二人組のしわざだった。運動への寄付として身代金を払わせようとする彼らの犯行は不首尾に終わったが、その十年後、二人組の片割れが再登場する。両者の名は「宇波三吉および稲田彰」とされている(それぞれの苗字と名の組み合わせを変えると世に知られた学者二人の名前になるのが気にかかる)。宇波が「僕」の不在時に一人で家にやってきた。「僕」の妻が、かつて彼らがイーヨーの命を危険にさらしたことを「遅ればせながら糾弾」すると、宇波はいけしゃあしゃあと「その方が良かったのじゃないですか」と切り返す。
「シビアに考えれば、いうまでもないことやけど、頭に障害のある子に生産性はないですよ。社会の物質代謝のやね、一環たり得ないですよ。ところがそんな子供を免罪符にしてやね、御主人は社会の波風に直接に立ち向かってはゆかないのや。(…)このまま哲学的な成熟なしに年とって、いったいどうするのかと、批評家にいわれておったじゃないですか」
許しがたい意見というほかないが、2016年に神奈川県相模原市の障害者施設で起こった、被害者45名におよぶ殺傷事件が示したとおり、「生産性」のない人間の抹殺を企て実行に移す者さえ現実にいるのだ。大江作品におけるイーヨーの受難は、われわれの社会の根底に見え隠れする差別と排除のありかを浮き彫りにしていた。
「シビア」な考え方に露呈しているのは、障害者を見下す健常者の傲りと偏狭さである。スナウラ・テイラーは「障害をめぐる苦しみのほとんどが健常者中心主義に由来する」と指摘している(『荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放』今津有梨訳)。しかも健常者中心主義を支えている健康や正常性、自立といった概念は「進化学的適正」を論拠として正当化される。健常者以外は進化の過程において振り捨てられてもしかたのない存在とされるのだ。
そういう具合に論理の筋が通っていると確信しているがゆえに、くだんの二人組のような者たちは、イーヨーの人生など生きるに値しないと簡単に断定することができるわけである。それに対し、別の理屈をぶつけて論破し、相手の考えを変えさせられるならば手っ取り早いが、なかなかむずかしい。それどころか、「障害をめぐる苦しみ」を敷衍していくと、どんな人間であれ、生まれてこなかったなら余計な苦しみや不幸を味わずにすんだのだから、そのほうがよかったのではないかという「反出生主義」の哲学的問題にまで広がっていく可能性がある。簡単に解決のつく話ではない。
大江が追求したのはもちろん、哲学者ではなく小説家としての思考であり、表現だった。イーヨーという人物の日常生活をとおして、彼がいったい家族や周囲の人間たちに何をもたらしているのかを丹念に掘り下げて描く。イーヨーの人間像を魅力あふれるものとして造形することで、小説はおのずから障害のある人間を擁護し、肯定する。そのことが大江作品のこのうえなく貴重な輝きとなる。
「生産」という事柄を、数値化できる利益や効率性、はたまた子孫を産み増やす能力などに限定するのは偏狭で誤った考え方だと思わせてくれるだけの闊達さが、イーヨーにはある。日々のびのびと暮らし、好きなものに打ち込み、食事をおいしく味わう。たとえ「健常者」に比べて能力的に劣るところがあるとしても、イーヨーの毎日は充実している。ピアノを習い始めたのち、先生独自の指導よろしきを得て自分で曲を作るようになってからは、それがイーヨーのとりわけ熱心に取り組む事柄となった。『新しい人よ眼ざめよ』第5篇の記述によれば――
「(…)イーヨーはいったん湧き起ったメロディーと調音を忘れることはないのである。ピアノの授業の後で、モヤシのように長い音符を、居間の床に腹這いになったイーヨーが五線紙に書いてゆく。妹や弟が脇でテレヴィの音楽番組を聴いていてもいっさいかまわぬのであった」(「魂が星のように降って、跗骨のところへ」)
ひたむきなお茶の間作曲家ぶりが微笑ましいが、イーヨーはたゆまぬ努力を実らせて堂々たる『ヒカリ・パルティータ 第二番』や、自分の通う青鳥養護学校の体育祭のための行進曲『ブルーバード・マーチ』、障害児施設のクリスマス行事のための音楽劇『ガリヴァーの足と小さな人たちの国』などを次々に完成させていく。さらに『静かな生活』では、彼が福祉作業所に通って「せっせと働く」かたわら、いよいよ作曲に力を注ぎ、「すてご」や「ろっこつ」といった題名からしてユニークな楽曲を生み出したことが紹介されている。そして現実に、光は1992年、29歳で最初のCDをリリースして20万枚を売り上げ、ゴールドディスク大賞を受賞。94年には2枚目のCDによって日本レコード大賞企画賞を受賞する。驚くべき「生産力」ではないか(もちろん、彼の音楽をどう評価するかは別問題だし、さらには音楽など「娯楽」にすぎず「無用物」だという人もいるだろうが)。
人間の真っ当さ
とはいえ、CDのリリースや受賞といった事柄が、大江作品の読者にとって真に重要なわけではない。そうした輝かしい成功とは別に、大江の小説の言葉にイーヨーがもたらした要素こそが何と言っても大切なのだ。つまりユーモアと上品さである。
イーヨーの発言が往々にして周囲を(そして読者を)和ませ、楽しませてくれるものであることは、ここまでの引用からもおわかりいただけたと思う。しかもイーヨーは、毎週「『大喜利』番組」を欠かさず見るお笑い好きでもある。ともすればあまりに生真面目で文学的になりすぎる父親の作品に、ほどよい俗っぽさを加えてくれる点も貴重だ。イーヨー自身、そうした役割を演じようとする意欲も備えている。
父親がヨーロッパにいっていないあいだ「荒れに荒れた」イーヨーだったが、父の帰国とともに落ち着いた。その事態の診断を仰ぐためもあって、イーヨーは長年診てもらっている大学病院で検査を受ける。そこで担当医は、19年前の手術のことを改めて説明し、イーヨーには「頭蓋の欠損をはさんで二つの脳があった」ことを付き添った母親に告げる。
診察を終えて出てきたイーヨーは外で待っていた父に「大変苦しかったが、がんばりました!」と元気よく報告する。そしてタクシーに乗り込むとこう述懐する。
「――(…)僕には脳がふたつもありました! しかし、いまはひとつです。ママ、僕のもうひとつの脳、どこへ行ったんでしょうね?」
当時テレビでさんざん流れていた角川映画『人間の証明』の予告CM(「母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね?」)のもじりである。残念ながら期間限定のギャグではあるが、それを承知の上で引用したのは、以後、タクシーの運転手がいわば相方を務めてイーヨーとのあいだに漫才ふうのやりとりが展開される様子をぜひ見ておきたいからだ。
「病院を根拠地にするタクシー運転手」らしく、「患者やその家族に親身な態度」を示そうとしながら「聞き耳をたてていた」この運転手は、イーヨーのせりふに思わず「プッと吹き出し」てしまう。「僕」はイーヨーに「きみはいまの脳を大切にしてがんばって、長生きしなければならないね」と言って励ます。
「――そうです! がんばって長生きいたしましょう! シベリウスは九十二歳、スカルラッティは九十九歳、エドゥアルド・ディ・カプァは、百十二歳まで生きたのでしたよ! ああ! すごいものだなあ!
――坊ちゃんは、音楽がお好きですか? と失地回復をはかる心づもりの運転手が、前を向いたまま声をかけてきた。エドゥアルドという人は、どんな音楽家?
――「オー・ソレ・ミオ」を作曲いたしました!
――坊ちゃんは、たいしたもんだなあ。……がんばってくださいね。
――ありがとうございました、がんばらせていただきます!」
どぎつさや攻撃性のみじんもないこうしたやりとりに、イーヨーがいるからこその楽しさが満ちている。イーヨーの音楽に対する並外れた愛情と知識にすかさず反応した運転手も立派だ。「がんばる」という言い回しはしばしば会話における安易な表現の代表としてやり玉にあげられる。だがここではその凡庸な言葉のやりとりが微笑を誘い、温かな空気をもたらす。生きる喜びがそこに脈打つとさえ感じられる。
死に対するイーヨーなりの深刻な恐怖が描かれていただけに、ここでの長寿音楽家礼賛には真率さがこもっている。いかにも感に堪えないというふうなイーヨーの「ああ!」は、いにしえの『芽むしり仔撃ち』(1958年)の幼い「弟」を思い起こさせる。彼はなにごとも「驚嘆の眼」で見つめ、年上の者たちの自慢話に「ああ」と「夢みるように、うっとりと」嘆息していた。あの弟とイーヨーは、大江文学にとっての無垢の双極をなしている。
ただし、イーヨーは単に幼稚なのではない。彼はいわば自らのスタイルをしっかりと確立し、無垢でありながら大人という不思議な安定感を備えてもいる。それを支えているのは彼の言葉づかいだ。
イーヨーは家の中でも外でも、つねに丁寧な調子を崩さない。彼が用いる「もっとも拒否的」な「定まり文句」とは「――もういいよ、やめましょう」であり、断固とした口調でこれを言われると彼の母親はすっかりめげてしまう。一般に、かっとなったときに子供が親に対して投げつけるものとされている「定まり文句」を想起してみるならば(ウッセー、死ネ、クソババア等々)、何という上品さだろうか。
イーヨーは幼いころから、テレビニュースやFMラジオの音楽番組が大好きで、それらのアナウンサーの口調をとおして言葉を身につけたのだった。彼の丁寧な言葉づかいにはその影響が表れている。障害児心理の専門家によると、ASD(自閉スペクトラム症)の子供たちの多くは方言を話さない。それは「対人的・社会的コミュニケーションの障害」の表れであり、「自然言語を学ぶことが難し」い児童は、「テレビやビデオ」を頼りとして「意図理解なしの模倣や連合学習によって」言葉を学ぶことになる。方言主流の地域に暮らしていても、テレビやラジオでは共通語が優勢であるため、結果として彼らは方言が話せなくなるのだという(松本敏治『自閉症は津軽弁を話さない 自閉ペクトラム症のことばの謎を読み解く』)。
そうした分析が科学的に本当に根拠をもつのかどうか、素人には判断できないし、そもそもイーヨーはASDではないだろう。イーヨーの場合がわれわれに伝えるのは、アナウンサーや司会者を思わせる彼の語り口が、人柄の温厚さや優しさの表れとなっており、あくまでも丁寧な物言いがユーモアの貴重な源でもあるということだ。おそらく彼の場合も、「自然言語を学ぶこと」には困難があったのかもしれない。だが彼はテレビ・ラジオを通して身につけた語り口をディーセントに活かし、大切に磨き上げている。そこには言葉に対する敬意と謙遜がにじんでいる。日本語という乗り物を彼が我が物顔で乱暴に乗り回すことはない。大切に、穏やかに、そして愉快そうに操縦するのである。
ジョージ・オーウェルが「ディーセンシィ」というキーワードを用いた例として、ディケンズ論の中のこんな一文がある。「ディケンズが昔も今も人気があるのは、人々の記憶に残るような仕方で庶民の『ネイティブ・ディーセンシィ』(生まれつき持っている人間の真っ当さ)を表すことができたからである」(佐藤義夫『オーウェル研究 ディーセンシィを求めて』中の引用による)。イーヨーが読者に示しているのは――あるいは大江がイーヨー像をとおして訴えたのは――まさしく「ネイティブ・ディーセンシィ」とは何かということである。それはおそらく、たやすくは「生産」などできない、しかもだれもがそれに照らしてわが身を顧みることが可能になるような、きわめて大切な何かだろう。人間の真っ当さを教えてくれるイーヨーが社会にとって不要な存在だと考えることはできない。
イーヨーの作った曲に「すてご」と題されたものがあることは先に触れた。イーヨーが自分を「すてご」だと思っていたのかと、一瞬ぎょっとさせるが、そうではなかった。福祉作業所の仲間があるとき、公園清掃の際に、公園に棄てられた赤ちゃんがいるのを見つけて保護したことがあった。幾年も前のその出来事を胸に刻んだイーヨーは、「自分の当番の折に棄て子がいたら救けよう」という気持ちを込めてその曲を作ったのだった(『静かな生活』)。
ライ麦畑から落ちてくる子供をキャッチしてやりたいと願う、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の主人公ばりの使命感ではないか。おそらくイーヨーの胸には、そうしたさまざまな人助けの企図が抱懐されているにちがいない。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。