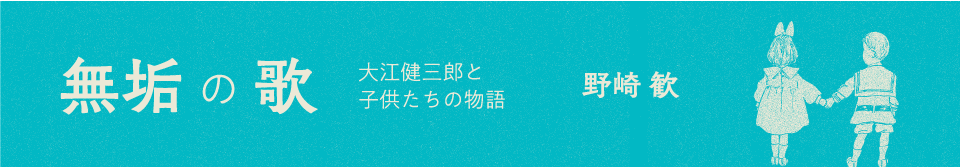「文学国語」と「論理国語」
あなたが、もうすぐ高校に入学する年ごろだと想像してみよう。高校ではどんな授業が待っているのだろうか。先生が何を教えるべきかは、「高等学校学習指導要領」によって定められている。文部科学省が2018年に告示したその最新改訂版――2022年から施行される予定――には、「論理国語」と「文学国語」なる聞きなれない表現があるらしい。
そのことを知人に教わったとき、何とも不可解な、そしていささか不愉快な思いにとらわれた。「国語」を「論理」と「文学」に分けられるものなのか。そんなふうに分けるべきなのか?
やがて明らかになってきたのは、高校2年になったら従来の「現代文B」ではなく、この2つから選択しなければならないということ。そして大学受験等との関係で、「論理国語」を選択する(せざるをえない)生徒が多くなるのではないかということだった。問題はその「論理国語」とは何かということだが、文科省のHPに上がっているくだんの指導要領の文章は、なかなかむずかしくて頭に入りにくい。とにかく徹底して「論理的」、かつ「実用的」な国語を教えることとされている。教材とすべき「論理的な文章」としては、「説明文、論説文や解説文、評論文、意見文や批評文、学術論文など」が想定されている。また「実用的な文章」というのは「実社会において、具体的な何かの目的やねらいを達するために書かれた文章のこと」で、「報道や広報の文章、案内、紹介、連絡、依頼などの文章や手紙のほか、会議や裁判などの記録、報告書、説明書、企画書、提案書などの実務的な文章、法令文、キャッチフレーズ、宣伝の文章などがある」のだという。「また、インターネット上の様々な文章や電子メールの多くも、実務的な文章の一種と考えることができる」とも付記されている。
でもインターネット上には「文学国語」的な文章だってたくさん存在するのではないかと揚げ足を取りたくなる。だが、すぐあとに、こんなきつい一言が続いていた。
「論理的な文章も実用的な文章も、小説、物語、詩、短歌、俳句などの文学的な文章を除いた文章である。」(https://www.mext.go.jp/content/1407073_02_1_2.pdf/)
これはつらい。もしあなたが高校2年生になって、「論理国語」を選択することになったとしよう。むかしゲンコク(現国)の時間と呼んでいたものは、ロンコクの時間となるのだろうか。そこでは毎時間、説明文や報告書やキャッチフレーズ(?)ばかり読まされる。決めつけては悪いかもしれないが、実に面白くなさそうだ。かつてのゲンコクはそれなりに潤いのある教科だったから、思い出をもつ人も多いはずだ。ぼくの通っていた地方都市の高校では、教科書に出てきた井上靖『夏草冬濤』の抜粋が面白かったので、分厚い小説の全編を読む生徒が続出した。ある登場人物が「蘭子」という女の子の名を叫ぶのを真似をして、「ラン、チャーン」と意味なく叫ぶのが一部で流行ったほどだ。さらに忘れがたい思い出を残してくれたのが梶井基次郎の短篇「闇の絵巻」である。そこに描かれた漆黒の闇の感触を少しでも実感したくて、友人と真夜中に浜辺の松林を駆け抜ける「闇の絵巻ごっこ」に興じたくらいだ。
そんな文学作品との出会いの機会が奪われるだけではない。論理・実用一点張りの文章ばかり読まされたら、嫌気がさしてきて、文章の読解力や表現力はむしろ低下するのではないかと危惧される。さらに本質論として、「論理」と「文学」を切り離す発想があまりにわびしいと思う。どんな論理的・実用的な文章でも、少しでも表現として魅力を湛えているとき、それはすでに文学でありうるのではないか?
「文学的な文章を除いた文章」――この文言におののかされる。文学はいつでも、いくらでも切り捨てることができる。小説や詩が一切存在しなくたって「国語」は成り立つという発想が見て取れる。
大江健三郎を教科書に?
そんな思いを抱きながら、何の手立てもなく過ごすのみだったところに、一冊の新書が届いて心を励まされた。『ことばの危機』と題されたその一冊の巻頭で、国文学者・安藤宏はこう書いている。
「たとえば小説や詩歌が『文学的な文章』である、という点では異論はないでしょう。しかし仮に大江健三郎が核兵器の廃絶を『想像力』の重要性と共に訴えている評論を書いていて、教材として採用したい場合、明快な論旨を持っているから『論理的な文章』なのでしょうか、それとも小説家が想像力の重要性を説いているのだから『文学的な文章』なのでしょうか。」(『ことばの危機――大学入試改革・教育政策を問う』東京大学文学部広報委員会編、阿部公彦、沼野充義、納富信留、大西克也、安藤宏、集英社新書、2020年、12ページ)
大江の評論は「論理国語」と「文学国語」のどちらのカテゴリーに属するのか。教科書作りにあたって、そんな問題に頭を悩ませる担当者は気の毒である。安藤は「若い人たちに読ませたい、魅力的な評論文ほどジャンル横断的なのです」と書いているが、わが意を得たりだ。安藤が実例として大江のケースを持ち出してることもまた、じつに共感できる。大江健三郎こそはじつに豊かな「横断」の実践者だ。評論や論説がそのまま文学になり、文学が同時に評論や論説になる。そんな事態がいくらでもありうることを、大江の作品は納得させてくれる。
指導要領で「論理国語」で教えるべき実例の筆頭に上がっているのは「説明文」である。何か読者が知らない、聞いたこともない対象について、文章でわかりやすく説明する。それはいつだってむずかしいことだ。そしてそれがうまくいったとき、読者は単に的確な情報を得たというだけではない、情報には還元できない種類の喜びを味わうことができる。その例として、ぼくの頭に思い浮かんだのは大江の次のような文章だった。短篇連作からなる『「雨の木」を聴く女たち』(1982年)の一節だ。
ハワイには「「雨の木」と呼ばれる巨大な樹木が生えているというのだが、いったいどんな木なのか。大江は、登場人物であるハワイ在住の女性の口をとおして、次のように説明してみせる。
「『雨の木』というのは、夜なかに「驟雨」があると、翌日は昼すぎまでその茂りの全体から滴をしたたらせて、雨を降らせるようだから。他の木はすぐ乾いてしまうのに、指の腹くらいの小さな葉をびっしりとつけているので、その葉に水滴をためこんでいられるのよ。頭がいい木でしょう。」
レイン・ツリーという名前の由来が語られているわけだが、大きな樹木が雨水を蓄え、やがて枝から雨滴を降らせるさまが目に浮かぶ。「指の腹くらいの小さな葉をびっしりとつけている」という描写がひときわ印象的だ。雨を受け止める葉の一枚一枚までが、きらきらと光を放つかのようだ。
こうした比喩表現に生命感を宿らせる腕前において、大江は比類のない書き手である。「説明文」とは、対象をよくとらえてその本質に触れるとき、ほとんど詩に近いような言葉の味わいを獲得するものだということを、大江の作品は随所で示している。未知の樹木だったレイン・ツリーは、この数行の説明のおかげで、鮮烈なイメージとなって読み手の脳裏に枝葉を広げることだろう。
それにしても、いま引用した箇所の「頭がいい木」とは、ややわかりにくい形容ではある。これは「論理国語」としては認めがたい逸脱、いかにも非論理的な余計な感想ではないか? いや、そうではない。ただしこの表現が的確であることは、『「雨の木」を聴く女たち』を読み進めなければわかってこない。説明は一気には得られないのだ。しかしこの表現を謎かけのように受け止めて、じっくりと読んでいくなら、小説全体の根底には世界が「核の大火に焼かれる」という恐ろしいヴィジョンがひそんでいることがわかってくる。その恐怖は、樹木が「炎に焼かれ」て滅ぼされるという無残な事態によって表現される(第四篇「さかさまに立つ『雨の木』)。とすれば、第一篇で描き出された「雨の木」とは「生命の樹」そのものの姿を示していたのである。水を豊かに含んでしずくを滴らせる様子は、「核爆弾をつくり出す文明」にあらがう自然界の生命の端的な表現だった。「頭のいい木」とは、世界を炎に焼くような知的文明の愚かしさと対比されたときに俄然、光を放つ形容だったのである。
「説明文」は文学的なものでありうる。そして文学作品をかたちづくるのはそれ自体、明確な「論理」に支えられた「説明文」なのではないか?
子供っぽさの魅力
「雨の木」をめぐる数行にもう少しだけこだわってみよう。対象を把握し、説明するというだけではない。そこには説明する側の感情や思いがこもっている。ほかの木が乾いてしまってもひとり潤いを失わないレイン・ツリーへの感嘆の思いや愛着の念が、明らかに感じ取れるのだ。
「説明文」というのはつい、書き手の主観を排した、ひたすら客観的な文章であるというふうに思いがちなのではないか。文部科学省が「論理国語」で教えるべきと考えているのもそういう文章だろう。だがそれとは別の種類の「説明文」があることを大江の一節は示している。その違いとは、何によるものなのか。
レイン・ツリーを前にして大したものだと感嘆し、「頭のいい」木だと褒める。そんな心の動きには端的にいって、子供っぽいところがある。自然の力に目を見張り、感応する一種の純真さが、レイン・ツリーをめぐる文章を支えている。それは何といっても、大江作品の子供たちがよく体現する資質なのである。
初期の傑作『芽むしり仔撃ち』(1958年)に登場する、じつに可憐な「僕の弟」がその典型だ。少年院の十五人の少年たちが、無理やり山の中の村に集団疎開させられる。だが村には伝染病が蔓延していた。村人たちは彼らを見捨てて村から逃げ出し、交通を遮断してしまう。疎開にくっついてきてしまった「僕の弟」は、そんななかでもつねに好奇心満々で、遠足気分を失わない。何を見ても感心し、「時どき僕のところへ駆けてきては、感動に声をうわずらせ熱い息を僕の耳たぶにからませて」あれこれの発見を報告する。周囲を「驚嘆の眼」で見つめ、年長の少年たちが危ない目にあった話を誇張気味に聞かせると「ああ」と声を上げて「夢みるように、うっとりと」嘆息する。
子供のなかの子供とでもいうべきこの「弟」像を描き出したことは、大江文学にとって大きな意義をもった。いかにも幼稚で、非力で、無知な「弟」だけれど、彼が世界とのあいだに結ぶ関係には貴重で尊いものがある。世界を受け容れ、肯定するためにどうしても必要な足掛かりが、そこに見出される。後年の作品の言葉を引用するならば、「それは、子供には想像力がある、ということじゃないですか?」(『二百年の子供』2003年)
子供たちに重要な役割を演じさせる大江作品は、子供時代と強いきずなで結ばれ、子供とつながる想像力に支えられている。作家自らが述べるとおり、「いつでも呼び出すことのできる自分のなかの少年」(『「伝える言葉」プラス』2006年、50ページ)が存在し続けているのだ。その少年との対話を絶やさないことで、作品には新鮮なヴィジョンと表現がもたらされる。
文部科学省のいう「論理国語」とは、子供ならではの要素を切り捨てて、大人による大人のための言葉の論理に習熟させることをめざす教科なのだろう。その訓練はもちろん大切だ。ただし、子供の言葉の論理にこそ大人にとって救いになるような何かが含まれているのかもしれないということも、忘れたくないのだが。
チャイルドライクな文学
自分は作家としてデビューした当時から、「子供っぽい人間、子供っぽい作品」と批評されてばかりいた。『懐かしい年への手紙』(1987年)で、小説家の「僕」はそう回想している。「老人になったならば、子供っぽい老人という評判につつまれて生きることになるのじゃないか」と予測されるほどなのだ。
子供っぽさを「チャイルディッシュ」ととれば幼稚な、未成熟で大人げない、という非難になる。しかし「チャイルドライク」ととれば、無邪気で純朴、素直で可憐という肯定的評価になるはずだ。若くしてのデビューから、まさしく老齢に至るまで、一貫して「チャイルドライク」であり続け、子供の無垢への追憶と志向を保ち続けたところに、大江文学の素晴らしさを見出したいのである。
ふたたび『芽むしり仔撃ち』を開いてみよう。題名からして何と不思議な響きだろうか。「芽」をむしり「仔」を撃つのは無責任で残酷な大人たちだ。それに対し自立を強いられた少年たちは協力しあい、ひとつの共同体を作ろうとする。くんずほぐれつの喧嘩もするし、みんなで焚火を囲んでの盛大な祝宴を催したりもする。そんななかで「僕」は、村にひとりぼっちで取り残されていた少女と結ばれることになる。「僕」は自分たちを見殺しにした村人たちへの憤怒に燃えつつも、その炎は彼女への想いに転化されていき、ふたりのあいだには「むくむくする情念」がふくらんだ。さて、二人が「土蔵のなか」で結ばれる様子はどんなふうに描かれるのか。いみじくも「愛」と題された第六章のクライマックス。
「僕らはすっかり暗い床の上に土足であがりこみ、黙りこんだまま大急ぎでズボンを脱ぎスカートをめくりあげた。僕は少女の躰の上へたおれた。勃起してアスパラガスの茎のような自分のセクスが下穿にひっかかって殆ど折れそうになったので僕は呻いた。それからあわてふためいている少女のセクスの冷たく紙のように乾燥している表面との接触と小さな身震いをしながらの後退。ぼくはふかぶかした溜息をついた。」
これぞ「文学国語」といいたいのだが、教室でみんなで読むのはまあ無理だろう。高校生よ、放課後に文学と出会えというほかはない。ともあれ、いまなお高校生の心に届くくだりにちがいない。『大江健三郎全小説』全十五巻の解説を担当した尾崎真理子は、この箇所を引用してこう書く。
「衝動的で純粋な行為の描写が美しい。『セクス』という語の、今もなんと純な響き。周囲から完璧に閉鎖された、いつ壊れるかわからぬ世界に咲いた透明な雪の花のような『愛』。」
そうなのだ。透明にして純。刊行から六十年以上たってなお、古びておらず、手垢がついていない。少年少女の初めての体験を描くうえで、通俗な紋切り型からはるかに遠く、またその行為を安易に美化するような姿勢も感じられない。少年の視点から描かれているが、とかくありがちなマッチョな妄想の押しつけは皆無だ。「僕は少女の躰の上にたおれた」という一行、そして「アスパラガスの茎」が「殆ど折れそうになった」という、未成熟な身体に即した表現の清冽なことに驚かされる。
それにしても、尾崎も注目している「セクス」の一語はどこから来たのか。この表記は「死者の奢り」(1957年)や「飼育」(1958年)にも見られ、『芽むしり仔撃ち』では冒頭から登場していた。いわば若き大江の愛用語であり、また大江以外のだれもこんな表記をした作家はいない。思うにこれは、フランス語のsexeをカタカナ表記したものではないだろうか。
高校時代に渡辺一夫の『フランス ルネサンス断章』を読んで感銘を受け、渡辺の教える仏文科をめざして東大に入学した大江は、熱心にフランス語を学び、講義に出席し、原書を読んだ。真剣な勉強によって得られたフランス語の知識はのちのちまで、作品の随所に示されることになる。「セクス」に関しては、フランス語には基本的に、小さな「ッ」で表されるような「促音便」がないという基本事項が反映されているように思う。たとえばxがフランス語では「エックス」ではなく「イクス」になることを、大江はフランス語の最初の授業で学んだだろう。英語のsexはフランス語ではsexeと綴られ、「セックス」ではなく「セクス」と発音される。ごくささいな違いだが、「ッ」を取り去っただけで、世にあふれる「セックス」描写を脱して、すべてを新しい文脈のもとに置き直すことができる。それが学生作家の大いなる発見だった。そして自作の主人公の少年にその一語をプレゼントしたのだ。
言葉を自分なりの感覚で、自分にとって好ましく面白い形に変形させたり、作り替えたりして用いる。そんなところに脈打つチャイルドライクな創造性は、大江文学の変わらない特色をなす。ところが、そこではしばしば「子供」が危機的な状況にさらされてもいる。そのことが徐々に、大江文学にとって重要なテーマとなっていく。『芽むしり仔撃ち』のラストは次のように結ばれる。
「僕は自分に再び駈けはじめる力が残っているかどうかさえわからなかった。僕は疲れきり怒り狂って涙を流している、そして寒さと餓えにふるえている子供にすぎなかった。ふいに風がおこり、それはごく近くまで迫っている村人たちの足音を運んで来た。僕は歯をかみしめて立ちあがり、より暗い樹枝のあいだ、より暗い草の茂みへむかって駈けこんだ。」
この見事なオープンエンディングとともに、大江の小説の原点が刻まれた。「子供」は危機に瀕し、おびやかされ、逃げ場を失ってふるえている。それが大江の小説の立脚する基盤となる。『芽むしり仔撃ち』の数年後には、「子供」の主題はいっそう切迫し、深刻さを帯びて回帰してくるだろう。わが子もろとも、若き作家は危機に直面するのである。その危機を――大江の愛用語でいうならばその「ピンチ」を――どう生き抜くべきなのか。どうすればしのぎ、乗り越えることができるのか。人生に直結した問いに挑み続けることが、大江健三郎という作家をたくましく作り上げていった。その結果、だれよりも果敢な「文学国語」の冒険者でありながら、大江は作品をだれにでも開かれた、人生を考えるための場とすることができた。
だからこそ、自分が、そして社会もまた、いまや「ピンチ」におびやかされているのではないかと感じるとき、大江作品と向かいあうことは大きな意味をもつのである。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。