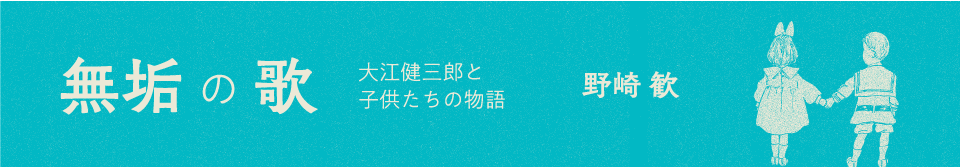イーヨーとお祖母ちゃん
イーヨーが「頭に瘤をつけて生まれて来てくださった」(『М/Tと森のフシギの物語』(1986年)そのときから、父方の祖母は孫に深い愛情を示し、彼の存在を全面的に肯定していた。出産直後、四国の森の奥からはるばる会いにやってきた祖母は、作家である自分の息子について、あんな息子が父親では頼りにできないと嘆く。そして「あなたのチカラ(で)、イーヨーさんに助かってもらわねばなりません」(『新しい人よ眼ざめよ』)と嫁に頼み込んで帰って行った。
ところがそれ以来、『М/T』によればイーヨーが「二十歳の誕生日を迎えるまで」、祖母と孫は再会することがなかった。電話や手紙では密なやりとりがあったことがうかがえるのだが、それほど四国の森は遠かったのか。二十年後、ようやく「僕」は家族ぐるみで村を訪れ、イーヨーは祖母と対面する。それは単に家族にとって大きな出来事というに留まらない。東京の田園調布の家を中心として展開されてきたイーヨーの物語と、作家が幼少時を過ごした四国の森を舞台とする作品群がこのとき、ついにつながった。
成人した光はイーヨーというあだ名を拒むようになっており、『М/T』では「光さん」と本名で呼ばれている(のちに光は、これまでどおりイーヨーと呼んでくれてもいいと態度を軟化させるのだが)。「僕」の「妻」はそのことを電話で祖母に知らせる。すると祖母は、「イーヨーという名前を、私らは良い名前と思っておりましたが」、本人が「軽んじられておるように聞いて」いたとしたら、二十年間も、申し訳ないことだったと述べて「妻」を「恐縮」させた(『М/T』)。
さて、事実上の初対面をはたしたイーヨーと「お祖母ちゃん」のあいだに、会話はうまく成り立つのだろうか。祖母は大きく育った孫に「気おくれした小さい声で」呼びかける。『М/T』の一場面である。
「――光さん、よく会いに来てくださいましたなあ…… 私は八十歳になりましたが!
息子の挨拶は、再び妻を恐縮させたのです。
――八十歳になりましたか! ああ、大変なものだなあ! 八十歳になったのでは、もう死ぬのではないでしょうか? 大変なことだなあ!
――そうです、大変なことですが! 心配してくださって、ありがとうございます!」
おそらくお祖母ちゃんはイーヨーにとって、親しく接した相手としては最高齢だったのではないか。例によって彼の感嘆ぶりにはくもりのない純真さが表れている。そして、子供が老人と触れあうことの大切さが感じられる。自分よりはるかに「死」に近づいている人が、なお元気で生きている。その事実を驚きとともに受け止めるとき、子供の心に生とは「大変なもの」であり、だからこそ尊いということが刻みつけられる。
田舎の家を去るとき、イーヨーは「元気を出して、しっかり死んでください」とお祖母ちゃんを励ます。これは「しっかり生きてください」の言い間違いだった。あとからイーヨーは「私は、失言いたしました!」と反省するが、祖母は彼の真意をあやまつことなく受け止めていた。
やがてイーヨーは自分ひとりで祖母に会いに行くと言いだし、飛行機で四国まで旅する。そして祖母と昵懇な時を過ごす。ふたりはすっかり意気投合した様子なのである。
個人神話を造り直す
イーヨーと祖母のやりとりが意義深く思えるのは、大江作品の中で、この二人の発する言葉にはつねに、特段の重みが担わされてきたからである。そのことは視覚的にも一目瞭然だった。イーヨーに関しては、短篇連作において彼の言葉は黒々とゴシック体で印刷され、他の文字からはっきりと際立たされていた。
他方、祖母、つまり「僕」の母の言葉では「!」が特徴的である。「私は八十歳になりましたが!」とあるが、ここだけ感嘆をこめて「!」が用いられているわけではない。大江作品に登場するとき、母はつねにこういう話し方をするのである。「みずから我が涙をぬぐいたまう日」(1972年)では、「谷間の方言の、語尾に『が!』という強調をおきながらそれでいて意味全体には、ある冷ややかな客観化の印象をそえる独自のアクセント」と説明されていた。読者にとっては、この「が!」はとにかく語気の激しさ、口調のきつさとして受け止められる。
かつて「みずから我が涙をぬぐいたまう日」では、母親は作家とおぼしき「かれ」に向かって、おまえは「三歳の時に発狂してずっとそのまま」だ、「幼児のぶんざいでとっくに発狂してしまっていた」などと凄いことを言っていた。息子を「冷ややか」に突き放す態度は、その後の母親像にも一貫している。同時に、母の言葉はつねに力強く、正しいとも感じられる。異様に切迫した文体で書かれた「みずから我が涙をぬぐいたまう日」の場合など、お母さんの言うとおり、これは「幼児のぶんざいで」狂ったきりの男が、その狂える魂をみごとに発揮した作品に違いないと思えてくる。
『М/T』において、イーヨーの誕生直後に「あんな息子では頼りにできない」と母が断じたのは、「僕」が「W先生」に言われた言葉を母および妻の前でつぶやいてみせたからだった。「W先生」は、赤んぼうが生死の「さかいめ」にいるとしたら、赤んぼうの自由にまかせたらいいではないかと「僕」に説き聞かせたのである。
「生まれてこなかったより生まれてきたことが、必ずしも良かったとばかりはいえない時代なんだから……」
『個人的な体験』でもすでに、「ロッキング・チェア」に坐った教授の口から同じ感想が洩らされていた。それを賢者の言葉であるかのように援用する息子に、母親はあきれたのだ。つまり母親は、息子の崇拝する「W先生」(=渡辺一夫)の発言を一蹴するほどの力を持つ、強靭な批判者なのである。「反出生主義」ふうの生命を軽んじる考え方を、母はにべもなくはねつける。そこに理屈はなく、議論もない。母にはただ、「生まれてこなかったほうがいいのではないか」という発想への反発と、子供を生かすための行動があるのみだ。
かつてウグイの巣にはまって溺れかけた「僕」を「巨大な力」で引っ張り上げて救出したのは母だった。息子の自殺的行為を予測したかのように後をつけてきていたのである。障害のある孫の誕生直後、母は子を守る女の気概を嫁に伝え、以後二人は(電話ごしにではあれ)堅固な同盟関係を築いた。
成長したイーヨーもまた、一途な生命肯定と語末の「!」によって、祖母と共通する精神の佇まいを見せている。彼の言葉はもはやゴシック体で強調される必要もなしに、祖母の言葉とこだましあい、通いあう。
ただし「僕」が彼らの交流から弾き出されているわけではない。それどころか、祖母と孫のコンビは、作家である「僕」の創造に加担してくれてさえいる。『同時代ゲーム』に記された「壊す人」をめぐる伝承は、『М/T』では子供のころ「祖母」が「僕」に聞かせたものとして提示されている。神主の父がスパルタ教育式に伝説を教え込んだという『同時代ゲーム』での設定からの変更だ。そしていま、「僕」の母は孫である光に村の「神話と歴史」を語って聞かせ、光は素直に耳を傾ける。かつての「僕」の祖母と「僕」の結びつきを、「僕」の母と光が反復している。光は祖母から聞いた物語をもとにピアノ曲 Kowasuhitoを作曲し、カセットテープを送られてそれを聴いた祖母は「『森のフシギ』がリンリンと鳴る音楽だ」と喜ぶ。
『М/T』には「Kowasuhito by Hikari」の楽譜がそっくり転写されている。そのうえ、単行本として刊行されたときには、クロース装の表紙に「オリジナル楽譜より」として「大江光作曲『森のバラード』変イ長調」の楽譜が印刷されてもいた。

『M/T』表紙に印刷されている楽譜
こうしたなりゆきの意味するところは大きい。『同時代ゲーム』での、周囲から隔絶した「村=共同体=小宇宙」をめぐる「神話と歴史」が、それ自体、徹底して孤独な言葉から成り立っていたことはすでに指摘した。作家の想像力の横溢には読者を瞠目させるものがあった。しかし物語の構成要素がどこまで実際の村の伝承に根拠をもつのかは、保証の限りではなかった。「この種の言い伝えは土地に実在しない」とか、「この土地が未開の場所のように誤解される」といった故郷の人たちからの抗議があったことが、のちに『晩年様式集』(2013年)で明かされている。だからこそ、イーヨーとその祖母の参画は作家にとって重要だった。作家個人の空想にもとづく労作であるかと思われた「神話と歴史」のエッセンスは、家族によって共有され、次世代に受け継がれるものとなった。それが深い森に由来する生命を保っていることは、イーヨー=光の曲がその素朴で澄んだ響きによって示している。「壊す人」の物語は音楽に転生したのだ。
「村=共同体=小宇宙」の神話は、もはや作家一人の個人神話というにはとどまらない。その言葉を受け容れる者たちによって造り直され、更新されていく可能性がある。そこには新たな「村=共同体=小宇宙」の夢さえ宿りうる。作家にとっては勇気が「りんりん」と湧いてくるような展開が、『М/T』とともに実現された。
時間差と悲しみ
四国の森の谷間は、つねに変わらぬ希望を託すべき場所であり続ける。新たな共同体のあり方を模索する長篇を大江は書き継いでいく。しかしながら、絶望に接する暗澹とした想念も、大江作品の中核をつねに脅かしている。未来のヴィジョンを追求すればするほど、ダークネスが広がり出す。『治療塔』(1990年)『治療塔惑星』(1991年)というSF二部作がそのことをまざまざと示している。
大江は若いころから筋金入りのSF愛好者だった。アメリカの作家カート・ヴォネガットとの対談「テクノロジー文明と『無垢』の精神」(『新潮』1984年7月号)が興味深い。大江はヴォネガットをかねてから英語で愛読しており、彼が東京で開かれた国際ペン大会のために来日した際に対談の機会を得た。その際、大江はヴォネガットのエッセイの次のような一節を引用している。
「SFの作家は偉い。普通の作家がやらないことをやっている。一つは、本当に恐ろしい変化というものが進行している。それについて語っている。それから未来について心配する気力を持っていることだ。」
その二つは、大江の実作においてもつねに感じられることだった。それをひときわ明確化させたのが『治療塔』二部作なのである。
二部作の背景となる「恐ろしい変化」とは、「核戦争のもたらしたものはいうにおよばず、世紀末に続発した原発事故の影響や、大出発とその後の混乱期に加速度的に悪くなった環境破壊の結果が大気をみたしている」ことである。21世紀、「汚染されつくした」地球から、「人類が生き延びる手だて」を求めて「百万人もの宇宙船団」が「新しい地球」をめざし旅立った。それが「大出発」である。
もちろん、地球の全人口に照らせば「百万人」といえどもごく限られた人数にすぎない。それは「知的にも肉体的にも選び抜かれた人びと」である。逆に、残留を余儀なくされた者たちはすべて「落ちこぼれ」なのだ。ところが十年たって、宇宙船団が地球に戻ってきた。それが長篇の始まりである。語り手は「落ちこぼれ」の一人と自認する「リッチャン」。彼女は「大出発」後の混乱期につらい体験をしていた。その彼女と、帰還した宇宙パイロットである従兄の「朔ちゃん」との関係がストーリーの主軸をなす。
宇宙旅行プロジェクトの大元締めである「スターシップ公社」は、帰還者を特権階級とする体制を樹立して地球の再建を図る。その際、帰還者は残留者と結婚してはならないという法律が制定された。朔ちゃんの子を宿したリッチャンは、結婚を諦め、未婚の母として赤んぼうを生み育てる決心をする。ところが、無事生まれた男児タイちゃんがほとんど感情を示さない、しかし高度な知性をもった特別な子であることが判明する。「特別学級」で学び始めたタイちゃんは、やがて「宇宙少年十字軍」の企図に組み入れられることになる。
クラークやハインライン、レムやストルガツキー兄弟につらなるSF的センス・オブ・ワンダーが横溢する作品だ。しかしあくまで地球に留まっている「リッチャン」を語り手とすることで、この小説は未来の地球からの報告として、じつにリアルな問題提起力を持つ。何しろこの二部作ののち、われわれは原子力発電所のメルトダウンを現実に経験し、気候変動の影響による災害とパンデミックのただなかで生きている。地球は「大出発」前夜の状態ではないのか? 小説は今こそそう問いかけてくる。
偉大な作家とはつねに、彼独自の世界とともに予言をもたらすものである。カミュはサルトルの短篇集『壁』の書評にそう記した。それは大江健三郎の場合にもあてはまる。そして大江作品の独自性は、未来のヴィジョンを子供が具現するところにある。子供は大人にとって、未来からやってきた何者かなのだ。その顔にはまだ見ぬ時代の光が差している。大人は子供の表情に目を凝らし、今後の世界のゆくえを読み解くべく努めなければならない。だが、子供と大人のあいだには根本的な“時間差”が横わたっている。それが親にとっては懊悩の源ともなる。親は子供を自分がもはやいなくなったあとの世界に向けて送り出すほかはないのである。
『治療塔』二部作では、その“時間差”の問題が幾重にも変奏されている。朔ちゃんを始め帰還者たちの多くは、驚くほど若返って地球に戻ってきた。宇宙旅行の生む時間のパラドクスによるものかとリッチャンは考えるが、そこには「新しい地球」で彼らが遭遇した「治療塔」の力が関わっていた。謎の塔に入った者には若さと健康が与えられ、「死人までよみがえらせられた」という。朔ちゃんとのあいだの子を宿したときから、リッチャンは、これから生まれるのは「若わかしくなりまさる人」、「もっとも新しい人よりさらに新しい人」なのだと感じる。それはまた、自分が古い人であり、これからもっぱら老いていくほかないという意識につながっている。
特別な能力を備えているらしいタイちゃんに対し、母親のリッチャンはあくまでも普通の人間である。朔ちゃんやタイちゃんが「治療塔」のほうへ、未来の宇宙へと向かう一方、彼女は取り残される定めだ。分断の力学がいかんともしがたく働いている(コロナ禍で浮上した問題と絡めて言えばまさに「トリアージ」である)。そこにこの作品がメランコリーに浸されている理由もある。「ほとんどあらゆるところに充ちている、『悲しみ』の感情に驚きました」と、大江は文庫版(2008年)へのあとがきで自作再読の感想を綴っている。
オープンエンディング
『治療塔』連作を浸す「悲しみ」は、子供との関係につきまとう本質的な感情の表れとして理解できるのではないだろうか。1990年、大江は『治療塔』を出す直前に『人生の親戚』を刊行していた。子供たちの死、それも障害を持つ子供たちの自殺という、痛ましく耐えがたい出来事に耐えて生きる女性の姿を描いた力作だった。
「人生の親戚」とは「悲しみ」のことを呼びなしているのだと、同作品の最後で説明されていた。そこには親子のそれぞれが生きていく時間のずれが関係している。子どもの人生を最後まで見届けることはできないという認識は、親の心をときおり鋭く刺し、悲哀をもたらすだろう。『人生の親戚』の物語は、母親が子供たちに先立たれるという設定によってそのずれを逆転させ、悲劇的に際立たせた。『治療塔』連作では、リッチャンは息子の未来を共有できない自らの限界をかみしめている。同様の悲哀を、どんな親でも子供に対して抱かざるをえないだろう。
リッチャンがタイちゃんの姿をじっと見つめる印象的な場面がある。「宇宙少年十字軍」の一員として惑星からの通信を受け取るため、タイちゃんはカプセルに入れられ、他のメンバーとともにスターシップ公社の「処置プール」に浮かべられた。
「選ばれた子供たちが繭カプセルに入って浮かび、おそらく微細な動きをつづけているために、ソラマメのようなかたちのものがヌメヌメと生きものの肌ざわりをあらわしている。その全体を眺めていながら、やはり私の眼は最前列中央のカプセル[=タイちゃんの入れられたカプセル]にひきつけられるのですが、そこは幾分矩形の囲いが広いため、黒ずんだ溶液の流れもよくわかります。こまかな泡に見えるものが浮かび上がりながら、水面で弾けずまた深みに巻き込まれて行くのは、それが糸くずほどの帯電性のセラミック片であるからだとは、さきに教えられていました。(……)すべてがじつにゆっくりと動き、しかもあらゆる動きが同時的に起って、流れるような律動に渋滞感がない……」(『治療塔惑星』)
リッチャンは溶液に浮かぶカプセルを凝視しながら、ブレイクの描いた「最後の審判のヴィジョン」を思い起こす。それは復活したキリストのまわりを「人の群れの流れが渦巻いている」絵だった。終末の果てに訪れる宗教的、神秘的な光景である。
さらに彼女は、朔ちゃんから教わったイェーツの詩「再来」を想起する。「ザ・セカンド・カミング」とは、ブレイクが絵に描いたように、最後の審判の日にキリストが再臨することを意味する。だがイェーツにおいてはそれが本来の語義を離れ、「幼児キリストではなくスフィンクスに似た野獣が生れ、新しい野蛮な文明がはじま」る、そしてまたその過程が繰り返されるという「循環歴史説」を表すという(『対訳イェイツ詩集』編者・高松雄一の注)。それら詩人たちの残したイメージを手掛かりに、リッチャンはカプセルで眠るタイちゃんが目覚めたのちに待つものを、懸命に思い描こうとする。
このシーンには、『個人的な体験』に描かれていた光の誕生直後の記憶が投影されているのではないか。「特児室」のガラス越しに保育器に入った赤ん坊たちを眺め、そのなかに自分の赤ん坊の姿を認めて、若い父親は暗鬱な思いにとらわれたのだった。『個人的な体験』に比べると、この未来小説が宗教的な色合いを濃く帯びていることがわかる。
リッチャンには結局のところ、タイちゃんの今後の運命はわからない。ただ、タイちゃん、そして朔ちゃんのために破滅を越えて「宇宙的な恩寵」が与えられることを願うばかりだ。彼女は「宇宙精神そのものとしてのあなた」に向けて祈念する。「心の力をすべて出しつくすようにして」祈る。作品はその先を示すことなく終わりを迎える。
「宇宙精神そのもの」とは何かは明らかではない。しかしこれは、親の力の及ぶ限界に触れながら、そこに湧き上がる強い感情を伝えて、心にしみるオープンエンディングとなっている。親にとって、子供への執着を捨て、自らの無力と和解するためにできるのは祈ることだけだ。危険な予兆に充ちているだけになおさら、親は子供が生きていく未来に向けて祈らずにはいられない。
「現在、宗教のある人間もない者も含めて世界中でいちばん大きい祈りは何かというと、私たちの後にも世界が続くようにということじゃないかと思うんです。この時代が続いて、そして自分の子供や、皆さん方がこれからお産みになる赤ちゃんや、そのまた赤ちゃんの子供たちが生きていける環境を自然に残しておきたいというのが、いちばんの祈りじゃないかと私は思っています、世界中の人間の。」(「信仰を持たない者の祈り」、『人生の習慣』1992年所収)
東京女子大学での講演の一節である。こうした想いを込めて「私たちの後」の世界を考えるとき、「自分の」子供という限定がもはや無用であることは言うまでもない。我が子であろうがなかろうが、あらゆる子供のために大人は祈らなければならない。その祈りを未来に届かせるために、現在を生きなければならないのだ。
文学は再来する
それにしても、SF小説においてもなおブレイク、そしてイェーツといった、自らの愛読する詩人たちの作品を持ち出さずにはいられないところが、何とも大江らしい。いわば宇宙の秘密にまで達する射程を秘めたものとして、過去の偉大な文学が頼りにされている。リッチャンは大江の文学への愛をわかちもつ人物であり、こんなふうに語っている。
「しかも詩のメッセージのいいところは、将来さらに深く読みとることができるようになる時、同じ詩がまさにその際の私に必要なメッセージであるはず、と信じられることじゃないでしょうか」
詩の読者が少なくなり、そればかりか本を手に取る若者がめっきり少なくなったいま、リッチャンの言葉にはほとんど現実離れした響きがあるかもしれない。だが、単に「情報」として記されているのではなく、将来さらに新たな意味を目覚めさせる萌芽を秘めた言葉が埋め込まれているのが文学である。その言葉は大江のように真剣に、一心不乱に読み続ける読者にとっては、ただひととき表面の意味を読み取れば終わるというものではない。文学の言葉はいつかまた「再来」のときを迎え、眠っていたメッセージを浮かび上がらせる。
実際、大江の作品においては、そんな「再来」のドラマが随所で生じている。先に引用した「処置プール」をめぐる一節がやはり気になる。ブレイクやイェーツと共鳴しながら、『個人的な経験』に描かれた「特児室」の記憶と結びつく情景である。しかしこの一節は、それらよりもさらに以前、まだ学生だった大江の名を一躍世に知らしめた、「死者の奢り」(1958年)の冒頭ですでに予告されていたのではなかったか?
「死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび、また半ば沈みかかっている。(……)死者たちの一人が、ゆっくり体を回転させ、肩から液の深みへ沈みこんで行く。硬直した腕だけが暫く液の表面から差し出されており、それから再び彼は静かに浮かびあがって来る。」
「死者の奢り」のそんな異様な情景は、スターシップ公社でリッチャンが目の当たりにする光景となって回帰している。「死者たち」を浮かべていた医学部死体処理室の水槽の「濃褐色の液」は、『治療塔』では「墨色に翳る溶液」となって、「繭 カプセル」に収まった子供たちを浮かべている。「死者の奢り」に書きつけられていたイメージは、何十年もかけて「再来」した。そしていかなるものとも知れない未来の予兆にふるえるような文章を紡ぎ出したのだ。
文学作品とは繭カプセルなのではないかという思いを誘われる。読者も、作者も、コクーンから目覚める新たな子供の誕生を信じて読み、書き続けるならば、やがて「再臨」は実現するのかもしれない。
突飛な空想だ、文学への思い入れが過多だと言われるだろうか? しかし、そういうひたすらな信念を忍耐強く守りとおすことで、自らを大きく育てていく生き方があり、読み方・書き方がある。大江健三郎は、われわれに身をもってそう教えてくれている。
エピローグ――年老いたヒカリとともに
その後のイーヨー=光に話を戻して終わりにしたい。『M/Tと森のフシギの物語』以降のいくつもの作品をとおして、彼が着実に年を重ね、物静かな中年男となっていく様子をうかがい知ることができる。それは大江の小説を読み続ける者にとっての大きな喜びだ。そして、現実を超えた遠い将来における彼の姿をわれわれに垣間見せているのが『治療塔』なのである。
宇宙からの帰還者たちが特権的エリートとして君臨する一方、いわば二流市民である残留者たちは彼らの支配下に置かれている。二流市民ながら一流市民の朔ちゃんとのあいだの子供を身ごもったリッチャンは、古くからの「コンミューン」が北軽井沢にあると聞いて、そこに身を隠しに赴く。迎えてくれたのは、「前世紀末」に若者たちが建設した、農場を営んで自給自足する集団だった。そこでリッチャンは「絶対音感」をもつ「ヒカリさん」という「老人」と出会う。
「ヒカリさんは生まれた際の頭部の畸形から、知能に障害がある、しかし音楽にはかえって特別な才能のある人ということだった。こうした人物が混乱期をどうやって生き延びられたものか…… 想像するのも酷たらしいほどだが、ヒカリさんは老年を健康に迎えられて、別荘村の一角の古い家に、大量のレコードを所持してひとり住んでいられる。隔週ごとの日曜には、いまも教師をしていられる妹さんが東京から訪ねてこられるということだった。」
ヒカリの父も母ももはやこの世の人ではないのだろう。「大出発」で地球に残された「落ちこぼれ」のうちでもとりわけ弱い立場にいたヒカリが、それでも穏やかな老年を迎えられたことはわれわれをほっとさせる。未来のヒカリ=イーヨーはどんな様子なのか?
彼は音楽を聴いたり昔の自作曲を見直したりして「山荘」で暮らしながら、農場にやって来ては料理の下ごしらえを手伝っている。とりわけ玉ねぎのミジン切りが得意だ。毎日服まねばならない「テンカン制禦剤」は、三週間ごとに「農場の若い人」が病院に取りに行ってくれる。そして「古いものだけれど布地も仕立ても良い背広」を着て、農場の子供たちの合唱を指揮するのだ。
その薬は、かつては服み忘れないよう父母が気を配って服ませていたものだ。仕立ての良い背広も父母が生前にあつらえてくれたものだろうか。十代のころのイーヨーは「通学用の黒いダブダブのズボンに、こちらは窮屈そうな僕[=父親]の古ワイシャツを着」こんだ姿で、その無造作ないでたちがしっくりと似合っていたものだった(『新しい人よ眼ざめよ』)。当時の雰囲気のまま、音楽に支えられ、子供たちに囲まれてイーヨーは生きている。
大江の作中には、自らの亡きあとのイーヨーを心配する言葉がときおり書きつけられていた。とするとこの未来小説にヒカリを“特別出演”させたのは、親が世を去ったのちの彼の様子を見たい、その健在を見届けたいという願望を満たすためだったのか。
それだけではないだろう。ヒカリが自らの場所を保ち続けることは、社会のあり方にとって大切な意味をもつ。分断と排除の力を押し返すような「コンミューン」が存在しうるとしたら、それこそはこれから求められる共同体であるはずだ。「コンミューン」communeが、仏文の学生時代に大江を感激させた「宏大な共生感」の「共生感」communautéと同語源の語であることも興味深く思われる。「宏大な共生感」をもたらすような集団のあり方を、大江は『M/T』以後の作品で懸命に探ろうとする。それは長篇作家としての壮大かつ困難な挑戦だった。だが、子供の老後を垣間見せるだけの『治療塔』のささやかなエピソードには、来るべき「共生」の場をわれわれに思い描かせる喚起力が確かに備わっている。
年老いたヒカリとはいえ、かつてイーヨーだったころの特徴を失ってはいない。リッチャンが耳にする彼の声は「声がわり前の子供のように澄んだ声」だ。そしてときおり彼の顔に浮かぶのは「満悦した赤ん坊の微笑」である。子供は子供であることをやめて大人になるとはかぎらない。老人になってもなお子供であり、赤ん坊であり続けるような人たちがいてもいい。彼らとともに暮らしていける社会が望ましい。そういう人たちがかたわらにいることは、われわれにとっての幸福であるにちがいない。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。
*ご愛読ありがとうございました。本連載を加筆訂正し書下ろしを加え書籍化する予定です。ぜひお楽しみに。