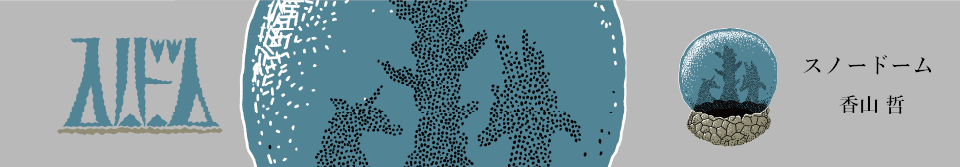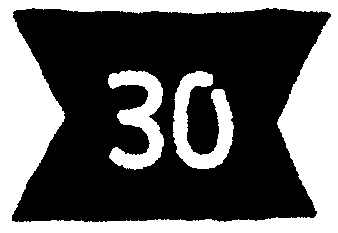
これまで何度も学生2人は印刷のために雑貨店に来ていて、大寒波についての話も自分たちは耳にして知っていた。しかし今日の2人の会話は特に聞きごたえがあった。なぜかといえば、次回の冊子の特集が「大寒波はいつ来るのか」ということだったからだ。自分たちが今抱えている滅亡についての関心もまさに、「いつ来るのか」という問題が存在感を帯びていた。


「いつ来るのか」について考えることは、どれだけ優れた考えを展開できたとしても「いつ来るのか」自体には影響を及ぼさない。大寒波や滅亡が1年後に来ることが分かったとしても、それを2年後に延ばすことはできない。しかしそれでも、もしたとえば1年後だと分かれば、それまでに何をして生きていくか考えるための材料になる。1年後に滅亡するなら、5年かかるようなことはしないだろうし、あえてするとしても覚悟の上でできる。サバイバルクラブの2人が大寒波の来る時期について会話しているのは、そういう観点から興味深かった。

ところが、2人の会話は平和ではなかった。何か冊子の内容でお互い気に入らない部分があるようで、非難し合うような雰囲気だった。帽子をいつもかぶっている学生と、傘をいつも持っている学生のうち、帽子のほうは、どんな缶詰がどういいかとか、野草の食べ方とか、方角の知り方などが好きだった。いっぽう、傘のほうは自然災害が起こるメカニズムだとか、火災現場で助かる方法などが好きだった。どちらもサバイバルという話題には変わりないし、重なる好みも多かったが、2人でいると2人の違いが際立つ。2人で冊子作りを続けるうちに、自然と2人は同じことを追求するよりも分担するようになり、分担によって関心や知識の蓄積が分化してきたとも言える。
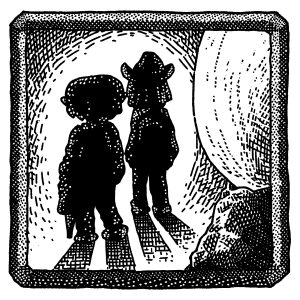
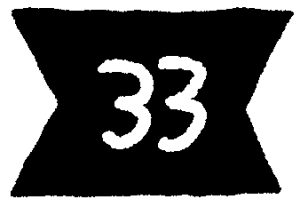
2人の言い合いはほとんど攻撃的ではなかったが、明らかに楽しそうな雰囲気でもなかったので、店主も若干そわそわしている様子だった。だけどその日は間もなく印刷が完了し、学生は店主に使用完了を伝え、店主はコピー機の印刷数表示を確認し、会計のほうにある帳簿に記録して代金を告げた。学生2人はちょうどの金額で支払い、店を出た。
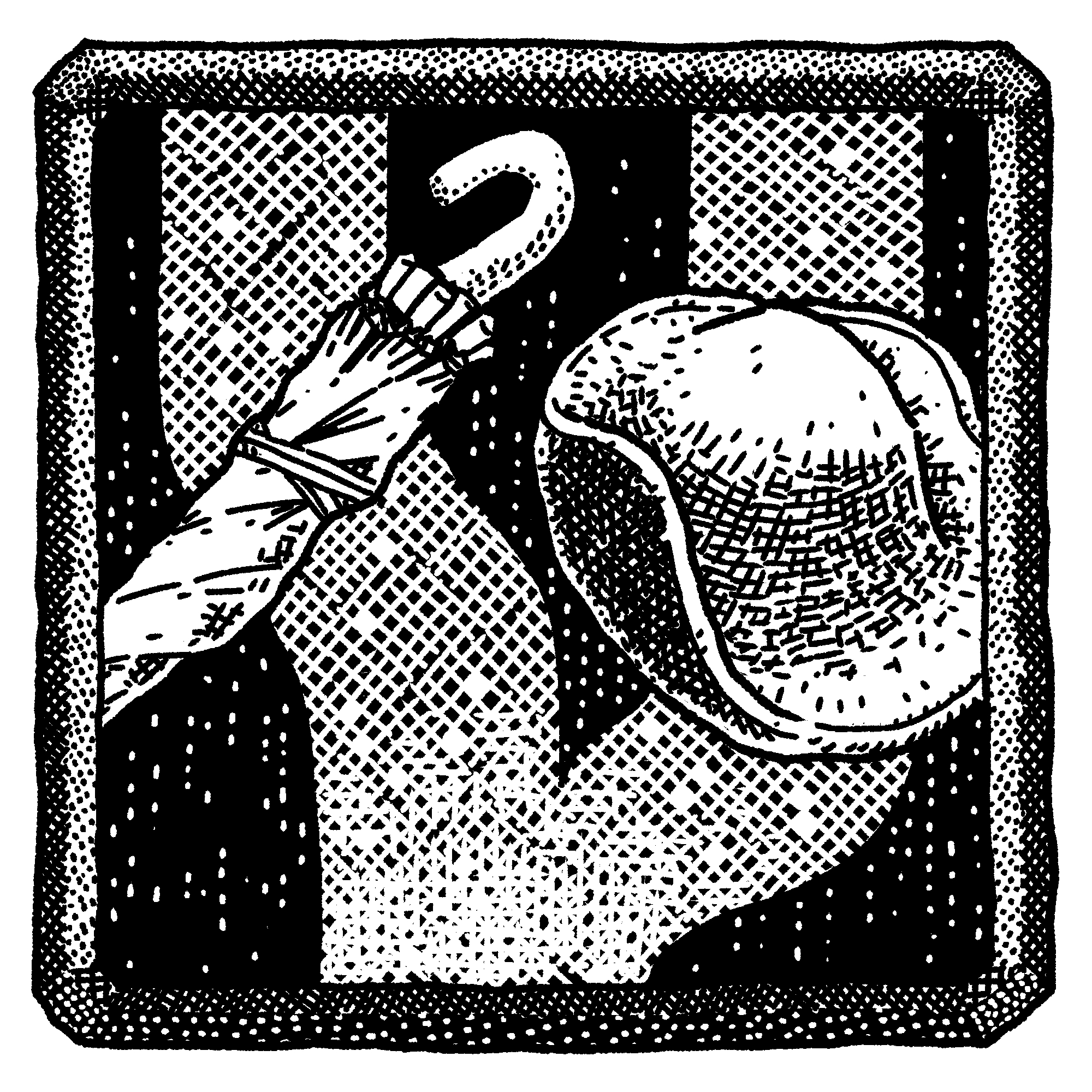

滅亡について会話を繰り返す自分たちと、大寒波について話すサバイバルクラブの学生たち。自分はあの人たちに親近感を覚え、学生たちが去った後もしばらく、自分たちと比べていた。あの人たちは自由に動き回って、一緒に行動したり、それぞれ違う家に帰ったりする。自分たちにはそういうことはない。たくさん動き回る学生たちと、一歩も動かない自分たちが、同じテーマで何かを考えている。そのことが不思議に思える。