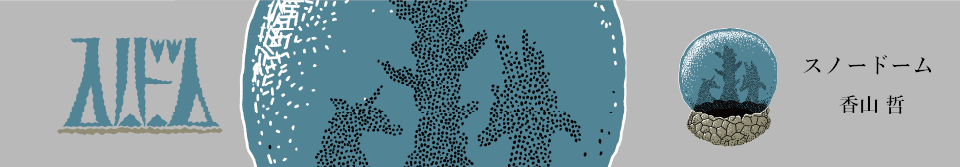スノードームというものは、人間と違って神経や筋肉を持たない。土台と天蓋と液体と、人形や飾り付けで構成されることが一般的で、樹脂やガラスでできている。素材や造作が上等なものもあれば、粗雑なものもある。たとえば土台とガラスの間の接着がいい加減だと、見栄えに影響したり、長い時間をかけて液体が放散してしまうこともある。スノードーム製造に使用される素材は、地域や年代によって異なるが、自分たちの出身工場では、圧倒的に「樹脂の土台とガラスの天蓋」という組み合わせが多かった。中に充填される液体は、工場の水道水を精製したものがメインで、添加物を加えて仕上げていた。添加物は防腐や防カビのため、凍結防止のため、粘度や安定度を上げるため、ほんのすこし色味をつけるため、などのような意味があると思われる。


スノードームは、小さな人間のこどもが投げたり落としたりもする。人間と同居する犬や猫などが突き飛ばすこともあるかもしれない。簡単なことでは壊れないように、あるいは劣化しないようにスノードームは頑丈に生まれてくる。だけど、その寿命を使い切れるスノードームはそれほど多くないのが現実だろう。壊れる前に処分されるものが多いのだ。そのことで自分が悲しいと思うこともあったが、色んな考え方を経由して、今ではそんなに単純な気持ちではなくなっていた。
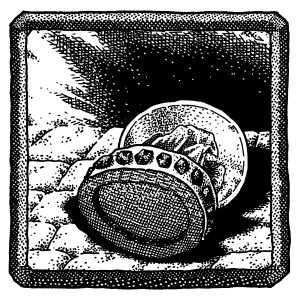
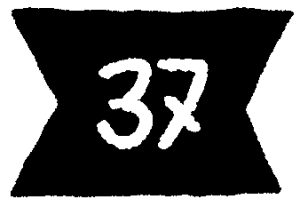
スノードームと人間は、大きく違った存在だ。しかし多くの共通点もある。たとえば、スノードームたちも人間たちも、「生まれてこよう」という意思を持たずにこの世に生まれてくる。こういうことは、大きな共通点に思える。自分たちも、どの人間も、「よく分からないけど各自、自分として生まれてきた」という状態で生を始めている。そういう枠の中にいるという意味では、自分たちスノードームと人間は同じ仲間なのだ。

そして、もう1つ重要な共通点がある。生に終わりがある、ということだ。
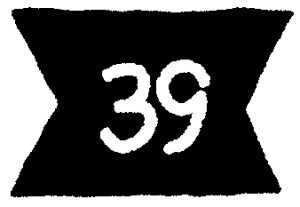
スノードームたち、人間たち。よく分からないけど自分として生まれてきた。「始めるぞ」という意思もなく始まった生が、なんだか続いて、いつか終わる。そういうものたちが今、滅亡とか大寒波のことで頭がいっぱいになっているんだなと思うと、不思議な感じがする。この感覚は、浮き上がってきた最初にはとらえどころがなくて単に不思議に感じただけだったけど、手放さずに眺めていると、色々分かってきた。

まず、「いつか死ぬことが確定しているのに、滅亡や大寒波を恐れること」は、不思議な感じはするけど、滑稽なことや誤ったことではないと思った。

滅亡や大寒波は、生に必ず終わりがあることとはあまり関係がない。滅亡や大寒波は関係なくやってきて、たまたまそこに生きる者たちの生を終わらせるだけの大きい力を持っているに過ぎない。だけど、滅亡や大寒波によって死んでしまうと、寿命で生を終えることができなくなる。2回死ぬことは、多分できないから。

そうなんだ。おそらく滅亡は、それと大寒波も多分、大きな破壊力を持っているだけだ。たとえば滅亡が来て、自分たちが生まれてきた事実ごと消したりすることもないし、死を2回発生させたりすることもない。そういう、生死の土台のルールを変更するような力は持ってないんだ。


むしろ滅亡や大寒波の恐ろしいところは、「助かるかもしれない」ということだ。その発生を避けられるかもしれないし、それから逃げられるかもしれないし、それを弱められるかもしれない。絶対に回避や防御ができない寿命とは、そこが決定的に違う。滅亡について一生懸命考えたり、不安で頭が一杯になるのは、「助かるかもしれない」からだと思う。

つまるところ滅亡や大寒波は、「助かるかもしれないもののうち、最も助かりにくい部類のもの」なのかもしれない。スノードームが犬や猫に突き飛ばされる時には、どんなスノードームだって、落ちながら1%ぐらいは死を覚悟する。だけどたいがい杞憂に終わる。それでも落下先が木の床なら2〜3%、石床なら一気に15%ぐらいまで、助からない見積もりを引き上げるし、気持ちがぞっとする度合いも強まる。その延長線上に滅亡や大寒波はあって、そして、助からない見積もりを絞り込みづらいのが特徴だ。


そういった印象や考えを、自分はみんなに話した。色んな反応や対話が起こったけど、面白かったのはマーズの感想だった。マーズが言うには、「もし直感的に見積もろうとすると、助からない確率が1000%とか50000%になってしまうようなものが、滅亡というものなんじゃないか」とのことだった。確率が50000%というのはおかしいけど、言いたいことは分かった。つまり、善処してもあがいても、全然助かりそうにないということだと思う。