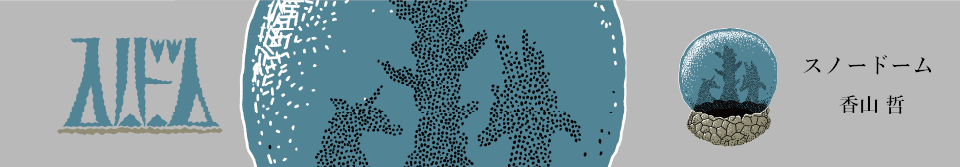帽子の学生はコピー機での作業を終えて、紙をバインダーのようなものにしまったりしながら、店主に精算をお願いした。店主は短い返事をして、立ち上がる面倒臭さを気持ちの中で消化したのだろうか、3秒ほどしてから立ち上がり、コピー機のカウンターが示す数字を確認した。

現在の数字を帳簿の最終行に記録する。今記録した数字から、前回記録した数字を引き算すれば、帽子の学生が今コピー機を作動させた回数が分かる。
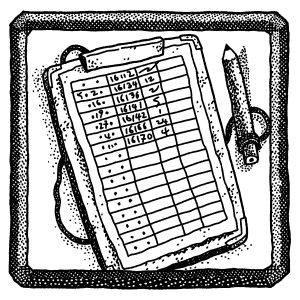

「今日は1人なの? 中学校、忙しい?」店主は2問繰り出した。毎回ではないし頻繁なわけでもないけど、店主にはそういう癖があった。

「忙しくないです。」学生は答えやすいほうにだけ答えた。

「……。」店主にはこういう経験が多かった。聞きにくいけど興味がある質問をして、その次に、聞きにくさを薄めるためにどうでもいいダミーの質問を追加で放つ。その結果、あとから投げたどうでもいい質問への答えが返ってくる。どうでもいいので、その返答に対して、大した反応ができなかった。

「友達もまた別の日に来ると思います。今、別々に作業してるんで。」帽子の学生は、質問された1問目にも答えた。

「そうなんだ。」店主は返事した。こっちの質問に対しても、特に展開は用意していなかったし、即席で思いつくこともなかった。偶然今日は学生が1人だったから声をかけやすかった、単にそれだけだった。店主は、自分が中学生の気持ちや生活にあまり関心がないということを改めて知った。学生は、金額ぴったりの硬貨を渡して、店を去った。
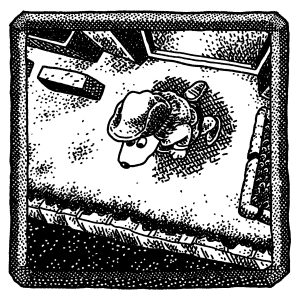

正直言って、コピー機は店にとって、ほとんど売り上げに貢献していなかった。しかしデメリットも少なかった。公衆電話のようにうるさい会話が聞こえてくることもないし、ガムボールマシンのように小さい子が叩いたり蹴ったりすることもない。
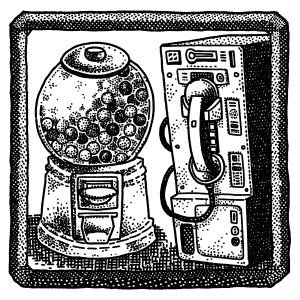

店主は、他人の激しい口調を聞かされたり、がんがんと何かを叩く音を聞かされるのは、本当に嫌いだった。うるさいのが嫌いなのではない。怒りとか、いらだちとか、他人が放った情動を受け取るのがストレスだった。


帽子の学生が帰って、急に静けさを感じたので、店主はラジオをつけた。天井のスピーカーから店内に、道路情報を読み上げる声が流れた。交通渋滞はなく、490号道路の工事が続いているとのこと。面白みのない文章が読み上げられる。聴く人の感情を何も刺激しない心地よさを受け取ることができた。
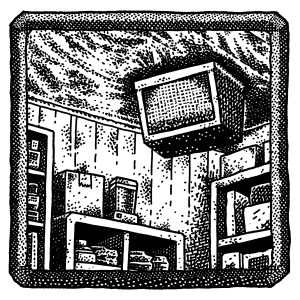

短い音楽が流れ、天気予報のコーナーに移った。自分たち、スノードームの面々も、ラジオを聴けるのはありがたかった。この店に来る、傘と帽子の学生2人以外に、大寒波を意識している人間がどれほどいるのかが気になっていたからだ。

しかしその日、ラジオで大寒波の話題は流れなかった。天気予報も落ち着いていたし、去年や一昨年と変わらない様子だった。実際、店の外は曇っていて、ほとんど風は無いようだった。