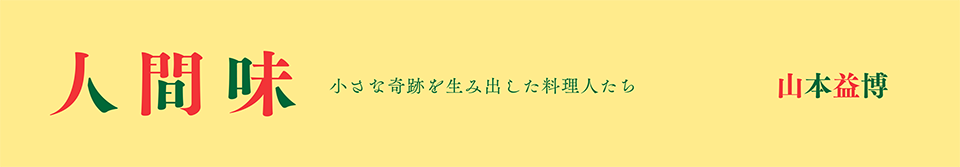パリでの出会い
1990年代末、フランス料理のグランシェフ、ジョエル・ロブションの本を作るため、パリへ足繁く通った時期があった。仔牛、じゃがいも、トリュフといったフランス料理に欠かせない食材や生産者を訪ねる旅にも出た。
旅先では、当然、取材のあとロブションと一緒にその土地のレストランで夕食を食べに出かけた。ロブションを迎えるレストランのシェフは、ここ一番とばかりに腕によりをかけて、私たちをもてなしてくれた。ただし、どこのレストランでも、これでもかというほどのご馳走で、最後にシェフがテーブルに挨拶にやってくると、ロブションは料理を褒めちぎるのだが、店を一歩出ると、「料理がこんがらがっていて、なにを食べたのか分からない皿ばかりだった」と呟くことがほとんどだった。
2005年のことだったか、パリで一緒に食事しようということになり、珍しく私から、当時評判になっている「アストランス」でのデジュネ(昼食)を提案した。
すると、ロブションは「では、うちの秘書に予約を取らせよう」と即答してくれた。
「アストランス」は16区のセーヌ河に近いベートーヴェン通りにある小さなレストランで、パリを代表する名店「アルページュ」のアラン・パッサールの下で働いていたシェフ、パスカル・バルボが開いた店である。

「 アストランス」のシェフ、バルボ(右)と、メートル・ドテルのクリストフ(左)とともに
出かけて行った当日、セーヌ河岸でタクシーを降り、通りの坂道を歩いて上ってゆくと、店の前で、サービスの責任者が直立不動で出迎えてくれた。予約名が「ジョエル・ロブション」だったから、相当緊張していたに違いない。
パリの飛ぶ鳥を落とす勢いのレストランだけあって、簡潔で洗練された料理は、前菜から主菜、デザートまで申し分なかった。料理がこのように素晴らしかったとき、ロブションは自ら厨房に出向いていく。

「アストランス」のフォアグラとセップ
客席数が20席足らずの店で、厨房は狭く、ロブションはバルボシェフと挨拶を交わした後、横にいた若い日本の料理人に、私を指さしながら「この人、知っているかい?」と訊ねた。
「はい、もちろんです!」と答えた料理人が岸田周三さんだった。そのとき彼に私の名刺を差し出し、いつか日本に戻って店を開くときにはご連絡くださいと伝えておいた。
そして、2006年5月、白金台で「カンテサンス」が開店した。
本場と時差のないフランス料理
初めて店に出かけたのが7月半ばの昼、当時「カンテサンス」も岸田シェフも、雑誌などでまだ話題に上る前だったから、お客は私一人だった。
確か、食事の二皿目だったと思う。ガラスの皿に盛りつけられた温野菜の料理が出た。盛つけは繊細で美的感覚に優れ、その野菜たちはしみじみ美味しかった。食べ終えて、すぐに思い浮かんだフレーズが「パリと時差のないフランス料理」。
岸田シェフの料理の虜になった瞬間だった。それから「カンテサンス」通いが始まったのだった。(「カンテサンス」とは「真髄」と言った意味合いで、岸田シェフが働いていた「アストランス」の語呂に合わせているフシもあるが、その「真髄」はメニューにはっきりと示されていると言ってよい。)
さらなる挑戦をみすえて
「カンテサンス」ではパテ、テリーヌの類の料理は一切出てこない。加熱した後、冷やしてサービスする料理は、岸田シェフにとっては自分の料理哲学に沿わないし、レストランでサービスすべき皿ではないということなのだろう。すべては、厨房でその日に調理されて、お客のテーブルの前に運ばれ、何も残らず、冷蔵庫のいらないレストラン、これが彼にとって理想のレストランなのだ。

「カンテサンス」岸田シェフ
「従来の古典フランス料理とはスタイルが違っても、私の解釈したフランス料理の定義を覆す事はありません。『プロデュイ(素材)』『キュイソン(火の入れ方)』『アセゾネ(味付け)』この3つのプロセスが何より大切だと考えます」
こうした料理哲学を踏まえたうえで、コース料理13皿がテーブルに次々と登場する。

オリーブオイルの緑色が冴えるバヴァロワ
前菜の調味料の塩とオリーブオイルが主役となった山羊乳のバヴァロワは、開店以来の定番で「カンテサンス」を象徴するような清潔感溢れるシグネチャーディッシュである。バヴァロワにはマカデミアンナッツと百合根が添えてあり、その似た形状がユーモアを誘う。盛り付けの色味は白一色にオリーブオイルの薄黄緑が流してあるといった、極めてシンプルで品格のある一品。食べ進むうちにじわじわと感動が押し寄せてくる傑作と言ってよい。
デザートのメレンゲのアイスクリームは、手間をかけただけの甲斐がある出来たてのアイスクリームで、これを食べないと「カンテサンス」の食事が終わらないほどのスぺシャリテと言ってよい。

火入れの技が光る一皿
そして、岸田シェフの何よりの得意技は魚、肉の火入れではなかろうか。初めて訪れたときの鱸のキュイソン・ナクレ、螺鈿のような虹色の切り身からうま味がにじみ出てくるひと皿は、いまでも変わらないし、豚肉をはじめとする肉の火入れも比類がない。
こうした確固とした料理哲学は、ほとんど「アストランス」のパスカル・バルボシェフから学んだとのこと。
昨日より、今日。今日より、明日
2007年、次の時代を担うはずのこの若き料理人が、「ミシュラン」でいきなり最高点の3つ星を与えられ、フランス料理ファンはおろか、東京に君臨していた年上のシェフたちの包囲網で仕事をする苦労は、想像を絶するものがあると思う。食材探しでは新天地を見つけられても、赤いガイドはことのほか急激な変化を嫌うから、料理はどうしても保守的にならざるを得ない。
岸田シェフは1974年、東京町田市生まれ、47歳。
2013年、白金台から御殿山へレストランを移した。これを機に、開店以来の「カンテサンス」ファンは、新たな充実ぶりを見てみたいと贅沢な願いを抱いてしまう。このコロナ禍だからこそ、今一度、岸田シェフがいままで辿ってきた軌跡を振り返り、50歳代を目指して新たな冒険の旅に出るということなら、私達たちは是非ともお供したいと思う。
「昨日より、今日。今日より、明日」が岸田周三シェフの生活信条である。
*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。